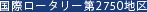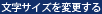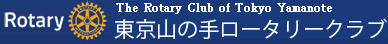Q&A
東京山の手ロータリー
を紹介
- 山の手RCのカラー
- みな平等
- 奉仕活動
- Togethers
- 土と遊ぶ
- ボッチャ
- その他
- 例会の様子
- 内容と流れ
- 卓話
- 親睦行事
- 親睦旅行・夜間例会(忘年、観桜会、周年)
- 二木会
- 同行会(ゴルフ、俳句、蕎麦、スキー)
Q&A
創立25周年記念版
卓話「村上開新堂 百五十周年を迎えて」
村上開新堂 代表取締役 山本道子さま
2024年4月18日

 只今ご紹介いただきました山本道子でございます。今日は私どもの店のお話をさせていただきます。村上開新堂は明治7年、1874年に麹町で洋菓子店を開業し、今年で創立150周年を迎えました。
私どもの150年の歩みということで、村上開新堂の歴史を少しお話いたします。私の曽祖父、村上光保が初代になります。曽祖父は武士として京都の方におりましたが、皇室の仕事をすることになり、明治2年に天皇が東京に移られるときに付き従って東京に参りました。お菓子のことを何も知らない状態で、明治3年に横浜でフランス人からお菓子作りを習い、明治6年頃まで横浜におりました。フランス語もわからないまったくの素人でしたから、とても苦労したと思います。その後、鹿鳴館などで供されるお菓子も作るようになりました。当時はオーブンも薪を使うオーブンで熱も安定せず、大変であったと思います。
明治38年の開新堂の店舗の写真を見るとティーサルーンというお茶を召し上がれる場所も写っています。店のショウウィンドウには飾り菓子を置き、とてもモダンであったと思います。明治43年に開催された英国博覧会に小田原城を模した城を飾り菓子で作って金牌を受賞しました。
二代目の村上一政は私の祖父の兄にあたります。フランス語で苦労した初代が暁星に入れてフランス語を学ばせました。二代目はフランスの料理書や料理雑誌を訳して二郎の菓子作りを支えました。その後、私の祖父村上二郎が三代目を継ぎました。三代目の二郎は職人としての能力にすぐれ、色々なことをやっておりました。戦時中に「ヒットB」という大変カロリーと栄養価の高いものを作りました。これは栄養補給用の携行食で、戦後は南極やマナスル登頂の非常食としても使われました。終戦後はお菓子づくりだけでは難しく、かといって祖父も父もお金に追われるのも嫌だということで、日本経済新聞社の社員食堂、特別食堂をやったこともありました。
昭和40年に現在の場所に住まいと共に店舗を移転し、四代目の母がレストランを始めました。今日にいたるまでレストランもご愛顧をいただいております。そして、私は主人のアメリカ駐在でニューヨークに5年間滞在し、1974年に帰ってきた後、「ドーカン」という食事ができる小さな店を半蔵門の新宿通沿いに開きました。その後、1990年の建て替えを機に、「山本道子の店」という名前の店を開新堂ビルの一角に開きました。
村上開新堂はご紹介制で、ご登録のあるお客様にご予約でお菓子をお譲りしております。私はもう少し街に扉が開いている店も必要だと思っていました。物づくりが継承したものだけを作ることの繰り返しになると、どこが美味しいのか、こうすれば美味しいのではないかといったことを考えなくなり、空洞化してしまうのが一番怖いことです。そういう意味で、自分たちで開発し、それをお譲りしてお客様の反響をうかがう形にしたいと思い、建て替えを機にどなたにもお買いいただける「山本道子の店」を開店しました。
開新堂のクッキーは0号缶から5号缶まであります。なぜ0号かというと、父が1号缶よりも軽くて少しお安いものがあれば皆さんが使いやすいのではないかということで作ったので0号になりました。
クッキーはすべて手でぎっちりと詰めておりますので、非常に重たいです。見た目よりは食べでがあると思います。3号缶で1200グラム、1.2キロの重さがあります。0号缶は470グラムです。
生菓子は、1個ずつくるんであったり、ケースに入ったりしています。戦前には皇族方が箱ごとお手元に置かれることもあり、直接お菓子に触らずに、お手でおつまみになれるような形にしたようです。お見せしているのは40個入りの生菓子です。普通のおうちでは食べきれませんが、楽屋見舞いなどに使われます。
今年の150周年の祝い菓子を皆様に召し上がっていただきました。このお菓子は元々大きい角形に焼き、小さく切って、銀紙に包んだ私どもの伝統的なダークフルーツケーキです。私どもはこれを「ウイデン」と呼んできました。この「ウイデン」をクグロフ型という型の真中にドーナツ状の穴があるもので焼き上げたのが、今回の記念菓子です。大きく焼くと、焼成に時間がかかり、重厚な仕上がりになります。クグロフ型で焼くと、同じ生地を使いながら、熱の抜けがよく、軽やかなお菓子になりました。
「ウイデン」は英語のウェディングがフランス語訛りでウイデンになったのか、今となっては、よくわかりません。ただ、こうしたフルーツケーキはイギリス発祥ですが、クリスマスをはじめ、いろいろな行事の時のお菓子のベースになっています。フランスに浸透したイギリス菓子も、初代がフランス人から習ったものです。イギリスのクリスマスケーキとクリスマスプディングは、スパイス・ドライフルーツ等の材料が殆ど同じです。前者はオーブンで焼き、後者は蒸して作ります。このプディングに添えて供されるソースがハードソース。バターと粉砂糖を練って、多くの場合はラムやブランデーを加えたものです。これをフランス語で言うと、ソースデュール。そしてこれは英国風なので、アングレーズ。昔からクッキーに挟むバターのクリームをうちでは「アングレーズ」と呼んできました。一般的に知られるアングレーズソースは卵黄・牛乳・砂糖などをしずかに熱したとろっとした、デザートソースです。開新堂では初代がクリスマスケーキとクリスマスプディングを習い、商品としてのプディングは残らず、ハードソースだけがアングレーズの名で、クッキーに挟むバタークリームとなったのでしょう。
古いものでも様々な見方をすれば、また違うものが紡ぎだせると思います。古くからつながってきたものは惰性になると、とたんに魅力がなくなってしまいます。私たちが持っているものをどうやっていけば、生きているお菓子、新鮮で脈打っているお菓子として皆様にお譲りできるのかなというのが、私にとっての長年のテーマの一つです。
焼き上げる熱がどう伝わるかで同じものがすごく違うということを別のお菓子を作る時に実感したので、今回の記念菓子では、熱の抜けの良い型で作ってみたのですが、大きな違いが生まれました。このようにして、祖父が残したたくさんのものの中で、自分が気になるところは一か所ずつ変えていけばよいと思っています。
そんなことで、今年は私たち、大変充実した150周年を迎えております。
ありがとうございました。
只今ご紹介いただきました山本道子でございます。今日は私どもの店のお話をさせていただきます。村上開新堂は明治7年、1874年に麹町で洋菓子店を開業し、今年で創立150周年を迎えました。
私どもの150年の歩みということで、村上開新堂の歴史を少しお話いたします。私の曽祖父、村上光保が初代になります。曽祖父は武士として京都の方におりましたが、皇室の仕事をすることになり、明治2年に天皇が東京に移られるときに付き従って東京に参りました。お菓子のことを何も知らない状態で、明治3年に横浜でフランス人からお菓子作りを習い、明治6年頃まで横浜におりました。フランス語もわからないまったくの素人でしたから、とても苦労したと思います。その後、鹿鳴館などで供されるお菓子も作るようになりました。当時はオーブンも薪を使うオーブンで熱も安定せず、大変であったと思います。
明治38年の開新堂の店舗の写真を見るとティーサルーンというお茶を召し上がれる場所も写っています。店のショウウィンドウには飾り菓子を置き、とてもモダンであったと思います。明治43年に開催された英国博覧会に小田原城を模した城を飾り菓子で作って金牌を受賞しました。
二代目の村上一政は私の祖父の兄にあたります。フランス語で苦労した初代が暁星に入れてフランス語を学ばせました。二代目はフランスの料理書や料理雑誌を訳して二郎の菓子作りを支えました。その後、私の祖父村上二郎が三代目を継ぎました。三代目の二郎は職人としての能力にすぐれ、色々なことをやっておりました。戦時中に「ヒットB」という大変カロリーと栄養価の高いものを作りました。これは栄養補給用の携行食で、戦後は南極やマナスル登頂の非常食としても使われました。終戦後はお菓子づくりだけでは難しく、かといって祖父も父もお金に追われるのも嫌だということで、日本経済新聞社の社員食堂、特別食堂をやったこともありました。
昭和40年に現在の場所に住まいと共に店舗を移転し、四代目の母がレストランを始めました。今日にいたるまでレストランもご愛顧をいただいております。そして、私は主人のアメリカ駐在でニューヨークに5年間滞在し、1974年に帰ってきた後、「ドーカン」という食事ができる小さな店を半蔵門の新宿通沿いに開きました。その後、1990年の建て替えを機に、「山本道子の店」という名前の店を開新堂ビルの一角に開きました。
村上開新堂はご紹介制で、ご登録のあるお客様にご予約でお菓子をお譲りしております。私はもう少し街に扉が開いている店も必要だと思っていました。物づくりが継承したものだけを作ることの繰り返しになると、どこが美味しいのか、こうすれば美味しいのではないかといったことを考えなくなり、空洞化してしまうのが一番怖いことです。そういう意味で、自分たちで開発し、それをお譲りしてお客様の反響をうかがう形にしたいと思い、建て替えを機にどなたにもお買いいただける「山本道子の店」を開店しました。
開新堂のクッキーは0号缶から5号缶まであります。なぜ0号かというと、父が1号缶よりも軽くて少しお安いものがあれば皆さんが使いやすいのではないかということで作ったので0号になりました。
クッキーはすべて手でぎっちりと詰めておりますので、非常に重たいです。見た目よりは食べでがあると思います。3号缶で1200グラム、1.2キロの重さがあります。0号缶は470グラムです。
生菓子は、1個ずつくるんであったり、ケースに入ったりしています。戦前には皇族方が箱ごとお手元に置かれることもあり、直接お菓子に触らずに、お手でおつまみになれるような形にしたようです。お見せしているのは40個入りの生菓子です。普通のおうちでは食べきれませんが、楽屋見舞いなどに使われます。
今年の150周年の祝い菓子を皆様に召し上がっていただきました。このお菓子は元々大きい角形に焼き、小さく切って、銀紙に包んだ私どもの伝統的なダークフルーツケーキです。私どもはこれを「ウイデン」と呼んできました。この「ウイデン」をクグロフ型という型の真中にドーナツ状の穴があるもので焼き上げたのが、今回の記念菓子です。大きく焼くと、焼成に時間がかかり、重厚な仕上がりになります。クグロフ型で焼くと、同じ生地を使いながら、熱の抜けがよく、軽やかなお菓子になりました。
「ウイデン」は英語のウェディングがフランス語訛りでウイデンになったのか、今となっては、よくわかりません。ただ、こうしたフルーツケーキはイギリス発祥ですが、クリスマスをはじめ、いろいろな行事の時のお菓子のベースになっています。フランスに浸透したイギリス菓子も、初代がフランス人から習ったものです。イギリスのクリスマスケーキとクリスマスプディングは、スパイス・ドライフルーツ等の材料が殆ど同じです。前者はオーブンで焼き、後者は蒸して作ります。このプディングに添えて供されるソースがハードソース。バターと粉砂糖を練って、多くの場合はラムやブランデーを加えたものです。これをフランス語で言うと、ソースデュール。そしてこれは英国風なので、アングレーズ。昔からクッキーに挟むバターのクリームをうちでは「アングレーズ」と呼んできました。一般的に知られるアングレーズソースは卵黄・牛乳・砂糖などをしずかに熱したとろっとした、デザートソースです。開新堂では初代がクリスマスケーキとクリスマスプディングを習い、商品としてのプディングは残らず、ハードソースだけがアングレーズの名で、クッキーに挟むバタークリームとなったのでしょう。
古いものでも様々な見方をすれば、また違うものが紡ぎだせると思います。古くからつながってきたものは惰性になると、とたんに魅力がなくなってしまいます。私たちが持っているものをどうやっていけば、生きているお菓子、新鮮で脈打っているお菓子として皆様にお譲りできるのかなというのが、私にとっての長年のテーマの一つです。
焼き上げる熱がどう伝わるかで同じものがすごく違うということを別のお菓子を作る時に実感したので、今回の記念菓子では、熱の抜けの良い型で作ってみたのですが、大きな違いが生まれました。このようにして、祖父が残したたくさんのものの中で、自分が気になるところは一か所ずつ変えていけばよいと思っています。
そんなことで、今年は私たち、大変充実した150周年を迎えております。
ありがとうございました。
卓話「野球を通じての人生経験談」
元阪神タイガース 川藤幸三さま
2024年4月11日

 みなさん、こんにちは。私はたまたま野球の世界でここまで来させてもらいました。この野球を通じて自分なりに感じたことは、やはり人のご縁です。人さまのご縁がなかったら、果たして今の自分はあるだろうかと思います。
18歳でプロ野球に入り、入った限りは何かをしなければいけないと思い、先輩たちから何か盗めるものはないだろうかと目で追いかけていました。ある先輩が夜9時になると毎日屋上でバットを1時間振っていました。どのような考え方を持っているのか尋ねようと風呂まで付いて行き、頭を下げて教えてほしいとお願いしましたが、答えてもらえませんでした。ただ、風呂の後で部屋に呼ばれて言われたのは、お前に教えてお前が上手くなったら自分が抜かれてしまう。悔しければ、目で物を盗んで相手を抜くのがこの世界の一番の基本だということでした。一つだけ教えてやると言って、一日は24時間だと言われました。その一言を考え直したときに、あの人は自分の野球のために夜9時からの1時間を作っているのだと気づきました。この世界では自分で創意工夫して時間を作り、使うのだということを、プロの第一歩として、頭を殴られたような感じで気づかされました。
入団当初は当然二軍でした。休みの日に大阪へ出かけて目新しいものを食べて腹を壊しました。しかし翌日は練習です。しかも朝食前にランニングがあります。今の体調ではランニングは無理だと思いました。当時の二軍監督は藤村富美男さんの弟の藤村隆男さんという方でした。この藤村監督に、体調を話して、朝のランニングは休ませてほしい、10時からの普通の練習には出ますからと言ったところ、いきなり荷物をまとめて福井に帰れと言われました。たかが朝のランニングなのに、帰れと言われてカチンと来たので、監督に食ってかかりました。そして、走ればいいんでしょと言って走りました。その日一日、納得できずに不貞腐れていたら、練習後に藤村監督に呼ばれました。そして、自分の体の管理もできないような甘い考えではプロ野球で通用しないということを目覚めさせられました。
そうこうしているうちに、私たちの時代のトップ、江夏豊、田淵幸一、藤田平が御三家と呼ばれる時代になりました。表面上の江夏豊の傲慢な姿は皆さんよくご存じだと思います。でも、その裏側を、江夏豊はどのような生きざまだったのかを少しお話いたします。
江夏さんは私より1歳年上です。寮で食事の後、後ろに座っていた江夏さんが私に煙草をくれと言いました。私が顔も見ずに煙草を渡したところ、その態度が悪いと喧嘩になりました。間に入った先輩から、私の態度が悪かったのだから謝れと言われ、確かにそうだと思って謝ったところ、江夏さんから自分も言い過ぎた、これからは一緒になってやっていこうと言われました。それから、私に対しては非常に気を使ってくれました。江夏さんが私の故郷の福井でのサイン会に行くとき、一緒に来いと言って連れていかれました。サイン会のギャラを聞かれて15万だと答えると、30分ほど席を外して戻ってきたときに、お前のギャラは30万でよいかと言われました。当時給料が7万だったので、15万のギャラでもありがたいのに30万と聞いて、とても驚きました。サイン会では当然江夏さんの方に人が集まるので、まず私のところへ来てから江夏さんのところへ行き連名のサインになるようにと気配りしてくれました。こういう気配りが周りに知られていないので、江夏さんに、いい加減その強面の江夏豊は外したらどうか言ったことがあります。江夏さんは、ここまで虚勢張って生きてきたから、今更この虚勢は外せない、死ぬまでこの姿で生きていくと言っていました。
田淵幸一が頭にデッドボールを受けて入院した時、私も二軍戦で頭にデッドボールが当たり、同じ病院に入院していました。急にうるさくなってきて何があったのかと看護師に尋ねたら、田淵さんが頭にデッドボールが当たって運ばれてきたと言われました。次の日から球団の偉い方々やトップの方々が、田淵さんのところへ大丈夫かと次々見舞いに訪れました。3歩先に私の病室がありますが、誰も来ません。ただ一人、田淵さんのお母さんが「川藤さん、大丈夫?」と心配してくれました。そのお母さんのやさしさに触れて、田淵幸一のあのおおらかな素晴らしいホームラン打者はこのお母さんがあってのことだと思いました。
藤村富美男さんから、阪神タイガースというチームで生きることを教わったのは昭和60年、21年ぶりの優勝を経験した時です。監督のやり方に納得いかない時にガンガンと文句をつける私に対して、それで良いと言ってくれました。目先の一打席よりも、先輩として後輩の掛布や岡田、真弓や佐野を引っ張っていくのがお前の務めだ。阪神タイガースの歴史を後輩に教えていくのがお前の仕事だと言われました。この時初めて、私はタイガースの一員になれた、良いチームに入らせてもらったと感じました。確かに、その時々で色々と感じるものはあります。しかし中心になるのは、助言を下さる方々とのご縁です。自分自身の考えを真正面からぶつけて、先輩たちからもそれを跳ね返していただく、そういう世界が必要だと思います。
昨年の阪神タイガースの18年ぶりのリーグ優勝、38年ぶりの日本一は嬉しかったです。ファンの方々にも喜んでいただきました。この優勝の喜びは主力選手だけの喜びか、そうではありません。私も18年目で優勝を経験しました。その前の17年間の自分の考え方と18年目の優勝の瞬間の考え方がどれほど違うかを最後にお話しさせていただきます。
10月16日だったと思います。練習の終わり近くに後輩のピッチャー伊藤が、話があると言ってきました。聞くと、前半に4勝したがその後勝てずに二軍落ちしている。ところが一軍の若いピッチャーのアメリカ留学の員数合わせに彼も加えられたが面白くない。今日優勝してもどう喜んだら良いかわからないというのです。私は伊藤に、彼の4勝が無ければ今日という日は無い。それだけでもどれほどこの優勝に貢献しているかわかるだろう。私はヒット2本しかないのに、首脳陣と選手の間でギャーコラと言っている。こんなものはプロ野球選手ではない。でも、なぜ自分の心を殺したかというと、それは優勝したいからだ。優勝の瞬間にどんな姿で私が喜ぶか、隣で見ろと言いました。そして、その瞬間が来ました。ピッチャー中西が投げる瞬間に私は駆け出していました。ゲームセットになってからでは乗り遅れるからです。あの瞬間、マウンドめがけて一斉にみんなが走っていく。周りをみれば選手がワイワイと喜び、スタンドではファンが泣いている、裏方さんも一緒になって泣いてくれている。優勝の瞬間の思いはこれだったんだ。団体で、みんなで一つのものを勝ち取るためには、皆それぞれの立場で力を尽くす。これが、ファンの皆さんにあそこまでの感動を与えるのではないか、私は本当にその瞬間、肌で感じました。ですから、自分の浅はかな考えや個人の喜びなどはたかが知れていると思いました。
ロータリークラブの皆さんが世間のために良い方向で活動されているのは、まさしく、優勝を目指しているのと一緒です。今後皆様の気持ちが一つになって、どんどんと前へ進んでいくことを祈念して、話を終わります。ありがとうございました。
みなさん、こんにちは。私はたまたま野球の世界でここまで来させてもらいました。この野球を通じて自分なりに感じたことは、やはり人のご縁です。人さまのご縁がなかったら、果たして今の自分はあるだろうかと思います。
18歳でプロ野球に入り、入った限りは何かをしなければいけないと思い、先輩たちから何か盗めるものはないだろうかと目で追いかけていました。ある先輩が夜9時になると毎日屋上でバットを1時間振っていました。どのような考え方を持っているのか尋ねようと風呂まで付いて行き、頭を下げて教えてほしいとお願いしましたが、答えてもらえませんでした。ただ、風呂の後で部屋に呼ばれて言われたのは、お前に教えてお前が上手くなったら自分が抜かれてしまう。悔しければ、目で物を盗んで相手を抜くのがこの世界の一番の基本だということでした。一つだけ教えてやると言って、一日は24時間だと言われました。その一言を考え直したときに、あの人は自分の野球のために夜9時からの1時間を作っているのだと気づきました。この世界では自分で創意工夫して時間を作り、使うのだということを、プロの第一歩として、頭を殴られたような感じで気づかされました。
入団当初は当然二軍でした。休みの日に大阪へ出かけて目新しいものを食べて腹を壊しました。しかし翌日は練習です。しかも朝食前にランニングがあります。今の体調ではランニングは無理だと思いました。当時の二軍監督は藤村富美男さんの弟の藤村隆男さんという方でした。この藤村監督に、体調を話して、朝のランニングは休ませてほしい、10時からの普通の練習には出ますからと言ったところ、いきなり荷物をまとめて福井に帰れと言われました。たかが朝のランニングなのに、帰れと言われてカチンと来たので、監督に食ってかかりました。そして、走ればいいんでしょと言って走りました。その日一日、納得できずに不貞腐れていたら、練習後に藤村監督に呼ばれました。そして、自分の体の管理もできないような甘い考えではプロ野球で通用しないということを目覚めさせられました。
そうこうしているうちに、私たちの時代のトップ、江夏豊、田淵幸一、藤田平が御三家と呼ばれる時代になりました。表面上の江夏豊の傲慢な姿は皆さんよくご存じだと思います。でも、その裏側を、江夏豊はどのような生きざまだったのかを少しお話いたします。
江夏さんは私より1歳年上です。寮で食事の後、後ろに座っていた江夏さんが私に煙草をくれと言いました。私が顔も見ずに煙草を渡したところ、その態度が悪いと喧嘩になりました。間に入った先輩から、私の態度が悪かったのだから謝れと言われ、確かにそうだと思って謝ったところ、江夏さんから自分も言い過ぎた、これからは一緒になってやっていこうと言われました。それから、私に対しては非常に気を使ってくれました。江夏さんが私の故郷の福井でのサイン会に行くとき、一緒に来いと言って連れていかれました。サイン会のギャラを聞かれて15万だと答えると、30分ほど席を外して戻ってきたときに、お前のギャラは30万でよいかと言われました。当時給料が7万だったので、15万のギャラでもありがたいのに30万と聞いて、とても驚きました。サイン会では当然江夏さんの方に人が集まるので、まず私のところへ来てから江夏さんのところへ行き連名のサインになるようにと気配りしてくれました。こういう気配りが周りに知られていないので、江夏さんに、いい加減その強面の江夏豊は外したらどうか言ったことがあります。江夏さんは、ここまで虚勢張って生きてきたから、今更この虚勢は外せない、死ぬまでこの姿で生きていくと言っていました。
田淵幸一が頭にデッドボールを受けて入院した時、私も二軍戦で頭にデッドボールが当たり、同じ病院に入院していました。急にうるさくなってきて何があったのかと看護師に尋ねたら、田淵さんが頭にデッドボールが当たって運ばれてきたと言われました。次の日から球団の偉い方々やトップの方々が、田淵さんのところへ大丈夫かと次々見舞いに訪れました。3歩先に私の病室がありますが、誰も来ません。ただ一人、田淵さんのお母さんが「川藤さん、大丈夫?」と心配してくれました。そのお母さんのやさしさに触れて、田淵幸一のあのおおらかな素晴らしいホームラン打者はこのお母さんがあってのことだと思いました。
藤村富美男さんから、阪神タイガースというチームで生きることを教わったのは昭和60年、21年ぶりの優勝を経験した時です。監督のやり方に納得いかない時にガンガンと文句をつける私に対して、それで良いと言ってくれました。目先の一打席よりも、先輩として後輩の掛布や岡田、真弓や佐野を引っ張っていくのがお前の務めだ。阪神タイガースの歴史を後輩に教えていくのがお前の仕事だと言われました。この時初めて、私はタイガースの一員になれた、良いチームに入らせてもらったと感じました。確かに、その時々で色々と感じるものはあります。しかし中心になるのは、助言を下さる方々とのご縁です。自分自身の考えを真正面からぶつけて、先輩たちからもそれを跳ね返していただく、そういう世界が必要だと思います。
昨年の阪神タイガースの18年ぶりのリーグ優勝、38年ぶりの日本一は嬉しかったです。ファンの方々にも喜んでいただきました。この優勝の喜びは主力選手だけの喜びか、そうではありません。私も18年目で優勝を経験しました。その前の17年間の自分の考え方と18年目の優勝の瞬間の考え方がどれほど違うかを最後にお話しさせていただきます。
10月16日だったと思います。練習の終わり近くに後輩のピッチャー伊藤が、話があると言ってきました。聞くと、前半に4勝したがその後勝てずに二軍落ちしている。ところが一軍の若いピッチャーのアメリカ留学の員数合わせに彼も加えられたが面白くない。今日優勝してもどう喜んだら良いかわからないというのです。私は伊藤に、彼の4勝が無ければ今日という日は無い。それだけでもどれほどこの優勝に貢献しているかわかるだろう。私はヒット2本しかないのに、首脳陣と選手の間でギャーコラと言っている。こんなものはプロ野球選手ではない。でも、なぜ自分の心を殺したかというと、それは優勝したいからだ。優勝の瞬間にどんな姿で私が喜ぶか、隣で見ろと言いました。そして、その瞬間が来ました。ピッチャー中西が投げる瞬間に私は駆け出していました。ゲームセットになってからでは乗り遅れるからです。あの瞬間、マウンドめがけて一斉にみんなが走っていく。周りをみれば選手がワイワイと喜び、スタンドではファンが泣いている、裏方さんも一緒になって泣いてくれている。優勝の瞬間の思いはこれだったんだ。団体で、みんなで一つのものを勝ち取るためには、皆それぞれの立場で力を尽くす。これが、ファンの皆さんにあそこまでの感動を与えるのではないか、私は本当にその瞬間、肌で感じました。ですから、自分の浅はかな考えや個人の喜びなどはたかが知れていると思いました。
ロータリークラブの皆さんが世間のために良い方向で活動されているのは、まさしく、優勝を目指しているのと一緒です。今後皆様の気持ちが一つになって、どんどんと前へ進んでいくことを祈念して、話を終わります。ありがとうございました。
卓話「工場野菜のご紹介と今後について」
株式会社RYODEN グリーンシステム事業本部長 執行役員 清水則之さま
2024年3月21日

 皆さんこんにちは。ご紹介いただきました株式会社RYODENの清水と申します。工場野菜のご紹介と今後について、私どもの会社、株式会社RYODENが取り組んでいるスマートアグリ事業についてご説明いたします。
株式会社RYODENは1947年設立、事業社数は国内39,海外21、従業員数1242名、売り上げ2600億円の東証一部プライム上場している会社です。売り上げ2600億円のうち、一番大きいのは7割を占めるエレクトロニクス分野、そしてファクトリーオートメーション分野、そして冷熱ビルシステムの分野となり、今日ご紹介するアグリカルチャーは新規事業として始めて、まだ会社の事業の柱にはなっておりません。
世界の食料需要増加のグラフを見ると、世界の人口は2010年頃70億人だったのが2050年には97億人に増え、一人当たりの消費カロリーも増えています。一方で、一人当たりの耕作面積は減っています。異常気象の影響も受けております。こうしたことで年々経済損失が増えている状況です。
日本の農業の現状を見ると、野菜生産が2010年43万トンから2020年27万トンに4割も減り、野菜作付面積も43万ヘクタールから39万ヘクタールに減少しています。農家の高齢化も進み、2010年に61%であった高齢化率が2020年には70%に増加し、新規の就農者数は55,000人から54,000人に減少しています。
国内外で持続可能な食糧生産システムの必要性が高まっており、さまざまな企業や大学がこの課題に向けて取り組んでいます。その一つが、私どもが運営している植物工場です。閉鎖的または半閉鎖的な場所で野菜などの植物を安定的に生産する工場です。二つ目は細胞培養で、動物の食べられる部分の細胞を培養して肉などを作るというものです。日本では培養肉の販売はまだ認められていませんが、アメリカやシンガポールでは普通に販売されています。三つ目は陸上養殖で、陸上の水槽で魚や海藻を養殖するというものです。また、植物性代替肉として、大豆の代替肉といった植物由来の細胞で肉を作るということも進んでおります。そして昆虫食。パナソニックが自社のLEDで昆虫を作ってドッグフードに使うという記事が出ていましたが、この食の危機、持続可能な食の世界を維持するために、いろんな研究が進んでいます。
私どもが運営している植物工場は、世界的に必要性が高まる食糧生産システムの一つとして期待されています。2021年には5805億円くらいの市場規模でしたが、2030年には4.5兆円になると期待されています。
植物工場は、閉鎖された清潔な室内で農薬を使わずに、光合成をLEDの光、空気、水、温度や湿度と風量を人工的にコントロールした水耕栽培で安心、安全な野菜を育てています。栽培棚は10段あり、同じ面積でも10倍の広さを使えるという非常に面積効率が高い栽培方法です。天候に左右されないので、安定的に1年中収穫できる栽培で安心、安全な野菜です。昨年、夏の高温の影響で葉物野菜の収穫が減ったため、葉物野菜の値段が非常に上がりましたが、工場野菜は同じ量が収穫できるので、ずっと同じ値段で販売しています。
元々RYODENは、こうした植物工場に向けてエアコンや冷熱システム、省エネを実現するためのファクトリーオートメーションのシステム、温度や湿度、風量を監視しコントロールするデバイスを販売していました。IoTのシステムの開発や、植物工場を作る企画、設計、請負も行っていました。その結果として、植物工場向けに色々な製品を販売しています。LEDの自社開発や、専用資材として、種を入れる成形品の制作販売などです。
今、農業とは関係のない異業種の会社が参入しています。西濃運輸や三菱ガス化学が野菜の工場を作ったり、東電エナジーパートナーが協賛する「彩菜生活」や東芝の「ベジノーバ」など、様々な企業が新規事業としてこの分野に参入しています。
私どもも2022年に、沼津にBlockFARMという植物工場を作りました。今、日本で最大の生産量の工場となっています。この工場の屋根には太陽光パネルを設置し、太陽光で電気代をまかなっています。そして、RYODENグループのFARMSHIPという販売大手が工場野菜の販売を行っています。このように、植物工場のインフラから、研究開発、生産、販売、流通、ブランディングまで、すべてをRYODENグループで行っています。
この工場野菜は1パック160円くらいですが、長所と短所があります。長所は露地ものに比べて、野菜を腐らせる菌が少なく、非常に長持ちすることです。冷蔵庫で保存しても2週間くらいはシャキッとしています。さらに、工場で作っている野菜はストレスを感じないので露地もののような苦みがありません。そして、工場から冷蔵車でスーパーに直接送っているので、短時間でお客様に届けられるという長所があります。逆に短所は、すべての野菜がこの水耕栽培に適しているわけではないので、品種が限定されていること。そして、人工的に自然環境を作っているためエネルギーコストがかかり、商品単価は一定ですが露地もの野菜よりは値段が高くなることが弱点です。
現在、この工場野菜を販売しているお店ですが、サミットでは関東全域で扱っていただいています。コストコは最初西日本だけでしたが、今は全国でルッコラやケール、スイートバジルをコストコブランドで販売しています。そのほか、いなげや、九州屋でも販売しています。
RYODENの植物工場は従来の植物工場とは一線を画し、作る、栽培する、販売する、のすべてを網羅しています。この次世代植物工場を通じてさらに蓄積されていくナレッジでサステナブルな社会の実現に貢献する新たな仕組みを提供し続けます。
どうもありがとうございました。
質疑応答
Q: 工場野菜は香りや歯ごたえが自然のものとは違うのではないですか。
A: 確かに、さまざまな自然環境の中で出る風味や苦みなどは露地ものとは若干違うかもしれませんが、鮮度や菌が少ないことでのおいしさを訴えていこうと思っています。栄養価も露地ものと変わりません。
Q: 農業は9時から5時の会社の仕事とは違うと思うのですが。
A: 社員の中には9時から5時の人もいますが、工場野菜は24時間稼働しているので、収穫は随時行っています。また、パートで来ていただいている地元の方には工場野菜を安く供給させていただいています。
皆さんこんにちは。ご紹介いただきました株式会社RYODENの清水と申します。工場野菜のご紹介と今後について、私どもの会社、株式会社RYODENが取り組んでいるスマートアグリ事業についてご説明いたします。
株式会社RYODENは1947年設立、事業社数は国内39,海外21、従業員数1242名、売り上げ2600億円の東証一部プライム上場している会社です。売り上げ2600億円のうち、一番大きいのは7割を占めるエレクトロニクス分野、そしてファクトリーオートメーション分野、そして冷熱ビルシステムの分野となり、今日ご紹介するアグリカルチャーは新規事業として始めて、まだ会社の事業の柱にはなっておりません。
世界の食料需要増加のグラフを見ると、世界の人口は2010年頃70億人だったのが2050年には97億人に増え、一人当たりの消費カロリーも増えています。一方で、一人当たりの耕作面積は減っています。異常気象の影響も受けております。こうしたことで年々経済損失が増えている状況です。
日本の農業の現状を見ると、野菜生産が2010年43万トンから2020年27万トンに4割も減り、野菜作付面積も43万ヘクタールから39万ヘクタールに減少しています。農家の高齢化も進み、2010年に61%であった高齢化率が2020年には70%に増加し、新規の就農者数は55,000人から54,000人に減少しています。
国内外で持続可能な食糧生産システムの必要性が高まっており、さまざまな企業や大学がこの課題に向けて取り組んでいます。その一つが、私どもが運営している植物工場です。閉鎖的または半閉鎖的な場所で野菜などの植物を安定的に生産する工場です。二つ目は細胞培養で、動物の食べられる部分の細胞を培養して肉などを作るというものです。日本では培養肉の販売はまだ認められていませんが、アメリカやシンガポールでは普通に販売されています。三つ目は陸上養殖で、陸上の水槽で魚や海藻を養殖するというものです。また、植物性代替肉として、大豆の代替肉といった植物由来の細胞で肉を作るということも進んでおります。そして昆虫食。パナソニックが自社のLEDで昆虫を作ってドッグフードに使うという記事が出ていましたが、この食の危機、持続可能な食の世界を維持するために、いろんな研究が進んでいます。
私どもが運営している植物工場は、世界的に必要性が高まる食糧生産システムの一つとして期待されています。2021年には5805億円くらいの市場規模でしたが、2030年には4.5兆円になると期待されています。
植物工場は、閉鎖された清潔な室内で農薬を使わずに、光合成をLEDの光、空気、水、温度や湿度と風量を人工的にコントロールした水耕栽培で安心、安全な野菜を育てています。栽培棚は10段あり、同じ面積でも10倍の広さを使えるという非常に面積効率が高い栽培方法です。天候に左右されないので、安定的に1年中収穫できる栽培で安心、安全な野菜です。昨年、夏の高温の影響で葉物野菜の収穫が減ったため、葉物野菜の値段が非常に上がりましたが、工場野菜は同じ量が収穫できるので、ずっと同じ値段で販売しています。
元々RYODENは、こうした植物工場に向けてエアコンや冷熱システム、省エネを実現するためのファクトリーオートメーションのシステム、温度や湿度、風量を監視しコントロールするデバイスを販売していました。IoTのシステムの開発や、植物工場を作る企画、設計、請負も行っていました。その結果として、植物工場向けに色々な製品を販売しています。LEDの自社開発や、専用資材として、種を入れる成形品の制作販売などです。
今、農業とは関係のない異業種の会社が参入しています。西濃運輸や三菱ガス化学が野菜の工場を作ったり、東電エナジーパートナーが協賛する「彩菜生活」や東芝の「ベジノーバ」など、様々な企業が新規事業としてこの分野に参入しています。
私どもも2022年に、沼津にBlockFARMという植物工場を作りました。今、日本で最大の生産量の工場となっています。この工場の屋根には太陽光パネルを設置し、太陽光で電気代をまかなっています。そして、RYODENグループのFARMSHIPという販売大手が工場野菜の販売を行っています。このように、植物工場のインフラから、研究開発、生産、販売、流通、ブランディングまで、すべてをRYODENグループで行っています。
この工場野菜は1パック160円くらいですが、長所と短所があります。長所は露地ものに比べて、野菜を腐らせる菌が少なく、非常に長持ちすることです。冷蔵庫で保存しても2週間くらいはシャキッとしています。さらに、工場で作っている野菜はストレスを感じないので露地もののような苦みがありません。そして、工場から冷蔵車でスーパーに直接送っているので、短時間でお客様に届けられるという長所があります。逆に短所は、すべての野菜がこの水耕栽培に適しているわけではないので、品種が限定されていること。そして、人工的に自然環境を作っているためエネルギーコストがかかり、商品単価は一定ですが露地もの野菜よりは値段が高くなることが弱点です。
現在、この工場野菜を販売しているお店ですが、サミットでは関東全域で扱っていただいています。コストコは最初西日本だけでしたが、今は全国でルッコラやケール、スイートバジルをコストコブランドで販売しています。そのほか、いなげや、九州屋でも販売しています。
RYODENの植物工場は従来の植物工場とは一線を画し、作る、栽培する、販売する、のすべてを網羅しています。この次世代植物工場を通じてさらに蓄積されていくナレッジでサステナブルな社会の実現に貢献する新たな仕組みを提供し続けます。
どうもありがとうございました。
質疑応答
Q: 工場野菜は香りや歯ごたえが自然のものとは違うのではないですか。
A: 確かに、さまざまな自然環境の中で出る風味や苦みなどは露地ものとは若干違うかもしれませんが、鮮度や菌が少ないことでのおいしさを訴えていこうと思っています。栄養価も露地ものと変わりません。
Q: 農業は9時から5時の会社の仕事とは違うと思うのですが。
A: 社員の中には9時から5時の人もいますが、工場野菜は24時間稼働しているので、収穫は随時行っています。また、パートで来ていただいている地元の方には工場野菜を安く供給させていただいています。
卓話「人手不足解消の新たな取組み」
株式会社クリエイト 代表取締役社長 井崎貴之さま
株式会社アドミューズ 木下明彦さま
2024年3月7日

 こんにちは。改めまして井崎です。よろしくお願いいたします。高齢化社会と人口減少によって、労働力の採用が非常に難しくなっている中、求職者がどのように変化してきているかを、木下さんと一緒にお話しできればと思います。
まず最初に、当社のグループは、主にHR事業、求人の広告会社として56年目になるクリエイト、そのほか、IT派遣のクリエイト・マンパワーサービス、高校生の新卒採用事業のハリアー研究所、ネットメディアのコンサル、ホームページの制作の会社、システム関係のシンク・クリエイト、金融業界のシステム開発を請け負っているテクノミスト、その他すべて合わせて9社のグループになります。このあと、木下さんにバトンタッチして説明していただきます。
木下です。よろしくお願いいたします。採用に関してよくお聞きするのが、採用したくても以前のように採用できないとか、媒体を使っても応募が少ない、仕事はあるが人手不足で売り上げが伸びないといった課題です。このような採用の課題をどのように解決していけばよいかをご紹介いたします。
まず、人材紹介会社を使っての採用。採用したい人材を獲得するのに一番良いサービスだと思います。採用単価が高いのですが、ハイスキル層や幹部層の採用には良いサービスです。次に、転職サイトを使っての採用。一定の応募数が獲得できるので、費用対効果が一番高い採用方法かと思われます。ただ、最近の人手不足の影響で、転職サイトを使っても応募者を獲得できないという話も聞かれます。もう一つの方法が、自社の採用ホームページを使っての採用です。ただ、一般的に知名度がない会社だと、採用ホームページから応募を獲得するのは難しいのが現状です。ただ、転職サイトを通じて会社のことを知り、グーグル検索で会社のホームページに来るということがあるので、ホームページの出来栄えは応募の数に影響を与えます。会社のホームページだけでは効果がなくても、色々なサービスと組み合わせることで応募数を増やすことができます。
最近の採用トレンドをご紹介します。まず、業界特化型の採用サービスが増えています。医療介護分野のジョブメドレー、運送業界のドライバー、製造業の工場求人ナビといったサイトがあります。特徴としては、ジョブメドレーの場合、転職サイトへの掲載料を支払うのではなく、採用が決まったら成果報酬を支払うというサービスがあります。業界特化型なので、業界の経験者が集まりやすいのも特徴です。二つ目のトレンドとして、Indeedのような求人情報の検索エンジンが盛り上がりを見せています。最近は掲載数が多いので、有料の広告を出さないとなかなか表示されないようですが、うまく使いこなせば応募者獲得につながるサービスだと思います。三つ目はSNS、オウンドメディアです。新卒や若手はSNSで情報収集するので、企業も6割が採用にSNSを使っていると言われており、必須の取り組みになっています。
ご紹介した採用手法の効果が気になるかと思います。コストを比較すると、人材紹介サービスは一人採用するのに140万から150万円かかります。転職サイトの場合はプランにもよりますが、50万から60万円くらいです。自社のホームページの場合、サイトを作成するのに大体100万円くらいから、費用をかけると300万、400万円ぐらいかかります。Indeedの場合は月額20万から30万円出せば効果が出ると言われています。最後のSNSは自社で制作・運用すれば費用はかかりません。
どの採用手法を使うべきかは、ケースバイケースで変わってきますが、お勧めの採用手法をご紹介いたします。まず、現場の作業スタッフとして経験者を1、2名採用したい場合は、転職サイトが良いと思います。業界専門サイトであれば、より経験者を採りやすくなると思います。転職サイトを使っても応募が少ない場合に、自社のホームページをきれいにして、実際に応募者が1.5倍や3倍に増えたという例もあります。次に、幹部候補生やハイスキル層の採用には人材紹介会社が確実です。最近CMで目にするビズリーチは、人材データベースから欲しい人材に直接連絡するというサービスです。手間がかかるサービスですが、熱意を伝えれば獲得しやすいという点があります。もうひとつ、工場や建設現場、飲食店などで、高卒を採用したいというニーズがあります。大卒よりも高卒の方が素直で教育しやすいという話も聞きます。ただ、高卒採用には気を付けなければいけないルールがあります。採用活動はハローワークや高校を必ず通すこと、面接で親の職業や好きな作家を聞いてはいけないといったルールがあり、守らないと罰則規定があります。高卒採用を本格的に取り組むのであれば、専門のコンサル会社に相談するのが良いと思います。また、毎年5人以上の若手社員を採用したい場合は、SNSや採用のホームページを使うのがお勧めです。
SNSや、ホームページ、ブログがなぜ良いかというと、バズると中小企業でもかなり注目されやすいというメリットがあるからです。また、給与条件だけでなく、自社に興味を持つモチベーションが高い人材からの応募を獲得しやすいというメリットもあります。さらに、今の若い求職者が知りたい情報をしっかり伝えることができるというメリットもあります。求職者が知りたい情報のランキングを見ると、1位2位は仕事内容、福利厚生と当然のものですが、3位以下では、職場の人間関係や働き方、職場の雰囲気など、社風などを知りたいというニーズがあることがわかります。そこで、SNSやブログが、社内の雰囲気を伝えやすいメディアとして有効だと思います。タクシー運転手のおじさんが一生懸命踊る三和交通のTikTokは33万のいいね!を獲得しました。八百屋の採用ホームページでは、キャベツやバナナ、大根を持つ姿が映画風になっており、八百屋のイメージを一新しつつ、どのようなスタッフが働いているかをしっかり伝えています。リサイクルの会社で、若い社長が自分の思いを伝えるTikTokを作り7万4千のいいね!を獲得したという事例もあります。
SNS、ホームページ、人材紹介、求人広告の役割の違いをみると、まずは人材紹介や求人広告でまず会社を知ってもらい、次にSNSやオウンドメディアで会社を好きになってもらい、自社のホームページで応募の意欲を湧かせるというように、応募に対するモチベーションを高めていくのに活用していくのが良いと思います。SNSやホームページは、すぐには成果が出ませんが、時間をかければ必ず成果が出てくるので、数年後を見据えてじっくり取り組んでいただければ良いと思います。
本日はありがとうございました。
こんにちは。改めまして井崎です。よろしくお願いいたします。高齢化社会と人口減少によって、労働力の採用が非常に難しくなっている中、求職者がどのように変化してきているかを、木下さんと一緒にお話しできればと思います。
まず最初に、当社のグループは、主にHR事業、求人の広告会社として56年目になるクリエイト、そのほか、IT派遣のクリエイト・マンパワーサービス、高校生の新卒採用事業のハリアー研究所、ネットメディアのコンサル、ホームページの制作の会社、システム関係のシンク・クリエイト、金融業界のシステム開発を請け負っているテクノミスト、その他すべて合わせて9社のグループになります。このあと、木下さんにバトンタッチして説明していただきます。
木下です。よろしくお願いいたします。採用に関してよくお聞きするのが、採用したくても以前のように採用できないとか、媒体を使っても応募が少ない、仕事はあるが人手不足で売り上げが伸びないといった課題です。このような採用の課題をどのように解決していけばよいかをご紹介いたします。
まず、人材紹介会社を使っての採用。採用したい人材を獲得するのに一番良いサービスだと思います。採用単価が高いのですが、ハイスキル層や幹部層の採用には良いサービスです。次に、転職サイトを使っての採用。一定の応募数が獲得できるので、費用対効果が一番高い採用方法かと思われます。ただ、最近の人手不足の影響で、転職サイトを使っても応募者を獲得できないという話も聞かれます。もう一つの方法が、自社の採用ホームページを使っての採用です。ただ、一般的に知名度がない会社だと、採用ホームページから応募を獲得するのは難しいのが現状です。ただ、転職サイトを通じて会社のことを知り、グーグル検索で会社のホームページに来るということがあるので、ホームページの出来栄えは応募の数に影響を与えます。会社のホームページだけでは効果がなくても、色々なサービスと組み合わせることで応募数を増やすことができます。
最近の採用トレンドをご紹介します。まず、業界特化型の採用サービスが増えています。医療介護分野のジョブメドレー、運送業界のドライバー、製造業の工場求人ナビといったサイトがあります。特徴としては、ジョブメドレーの場合、転職サイトへの掲載料を支払うのではなく、採用が決まったら成果報酬を支払うというサービスがあります。業界特化型なので、業界の経験者が集まりやすいのも特徴です。二つ目のトレンドとして、Indeedのような求人情報の検索エンジンが盛り上がりを見せています。最近は掲載数が多いので、有料の広告を出さないとなかなか表示されないようですが、うまく使いこなせば応募者獲得につながるサービスだと思います。三つ目はSNS、オウンドメディアです。新卒や若手はSNSで情報収集するので、企業も6割が採用にSNSを使っていると言われており、必須の取り組みになっています。
ご紹介した採用手法の効果が気になるかと思います。コストを比較すると、人材紹介サービスは一人採用するのに140万から150万円かかります。転職サイトの場合はプランにもよりますが、50万から60万円くらいです。自社のホームページの場合、サイトを作成するのに大体100万円くらいから、費用をかけると300万、400万円ぐらいかかります。Indeedの場合は月額20万から30万円出せば効果が出ると言われています。最後のSNSは自社で制作・運用すれば費用はかかりません。
どの採用手法を使うべきかは、ケースバイケースで変わってきますが、お勧めの採用手法をご紹介いたします。まず、現場の作業スタッフとして経験者を1、2名採用したい場合は、転職サイトが良いと思います。業界専門サイトであれば、より経験者を採りやすくなると思います。転職サイトを使っても応募が少ない場合に、自社のホームページをきれいにして、実際に応募者が1.5倍や3倍に増えたという例もあります。次に、幹部候補生やハイスキル層の採用には人材紹介会社が確実です。最近CMで目にするビズリーチは、人材データベースから欲しい人材に直接連絡するというサービスです。手間がかかるサービスですが、熱意を伝えれば獲得しやすいという点があります。もうひとつ、工場や建設現場、飲食店などで、高卒を採用したいというニーズがあります。大卒よりも高卒の方が素直で教育しやすいという話も聞きます。ただ、高卒採用には気を付けなければいけないルールがあります。採用活動はハローワークや高校を必ず通すこと、面接で親の職業や好きな作家を聞いてはいけないといったルールがあり、守らないと罰則規定があります。高卒採用を本格的に取り組むのであれば、専門のコンサル会社に相談するのが良いと思います。また、毎年5人以上の若手社員を採用したい場合は、SNSや採用のホームページを使うのがお勧めです。
SNSや、ホームページ、ブログがなぜ良いかというと、バズると中小企業でもかなり注目されやすいというメリットがあるからです。また、給与条件だけでなく、自社に興味を持つモチベーションが高い人材からの応募を獲得しやすいというメリットもあります。さらに、今の若い求職者が知りたい情報をしっかり伝えることができるというメリットもあります。求職者が知りたい情報のランキングを見ると、1位2位は仕事内容、福利厚生と当然のものですが、3位以下では、職場の人間関係や働き方、職場の雰囲気など、社風などを知りたいというニーズがあることがわかります。そこで、SNSやブログが、社内の雰囲気を伝えやすいメディアとして有効だと思います。タクシー運転手のおじさんが一生懸命踊る三和交通のTikTokは33万のいいね!を獲得しました。八百屋の採用ホームページでは、キャベツやバナナ、大根を持つ姿が映画風になっており、八百屋のイメージを一新しつつ、どのようなスタッフが働いているかをしっかり伝えています。リサイクルの会社で、若い社長が自分の思いを伝えるTikTokを作り7万4千のいいね!を獲得したという事例もあります。
SNS、ホームページ、人材紹介、求人広告の役割の違いをみると、まずは人材紹介や求人広告でまず会社を知ってもらい、次にSNSやオウンドメディアで会社を好きになってもらい、自社のホームページで応募の意欲を湧かせるというように、応募に対するモチベーションを高めていくのに活用していくのが良いと思います。SNSやホームページは、すぐには成果が出ませんが、時間をかければ必ず成果が出てくるので、数年後を見据えてじっくり取り組んでいただければ良いと思います。
本日はありがとうございました。
卓話「鍛えること、育てること」
株式会社金子プロモーション・金子ボクシングジム 代表取締役社長
金子健太郎さま
2024年2月22日
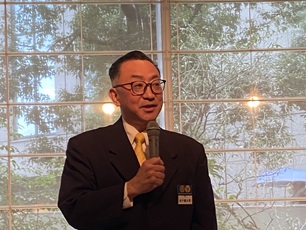 皆様こんにちは。只今ご紹介に預かりました金子ボクシングジムの金子健太郎と申します。
金子ボクシングジムは父が創立者ですので、父の話をさせていただきます。父は戦後日本人として初めて国際タイトルを獲った東洋チャンピオンです。当時、フライ級世界チャンピオンの白井義男さんと父とが国際タイトルを持ち、ボクシング界を牽引していました。後のファイティング原田を育てた笹崎拳闘会の笹崎先生が父のボクシングの師匠でした。リングを降りると、父はまじめで敬虔なクリスチャンで、碑文谷教会の大石牧師が父の心の師匠でした。私もその大石先生から洗礼を受けて、二代目クリスチャンとして、教会学校の校長をボランティアで務めています。
父は、いざ世界戦を挑むという時に、ボクサーにとっては致命的な網膜剥離になってしまい、泣く泣く引退しました。そして自分が果たせなかった夢を、自分の後継者に託そうと、昭和40年に下北沢に金子ボクシングジムを設立しました。
私は大学のボクシングでアマチュアボクサーとして10戦ほど戦いましたが、目を悪くしてしまい、大学4年で引退しました。その後、金子ジムのアマチュア部のコーチからスタートして、プロのトレーナーライセンスを取得し、最終的に、世界チャンピオン一人、東洋太平洋チャンピオンを5人、日本チャンピオン7人、全日本新人王3人を育てることができました。一番の出世頭は、世界チャンピオンを獲得した清水智信選手です。
私は、33歳で入会した東京青年会議所を40歳で卒業すると同時に、保護司を拝命しました。やんちゃ坊主をボクシングの力で更生できるのなら協力したいという気持ちで保護司になりました。42歳でボクシングジムの会長、東日本ボクシング協会の事務局長になり、48歳でボクシングの興行などをプロモートする会社、金子プロモーションの代表取締役になりました。ジムの会長として強い選手を鍛えて、育てる。保護司として対象者を鍛えて、育てる。教会学校の校長として子供たちの信仰心を育てています。
清水智信は世界タイトルを簡単に獲ったわけではありません。初の世界戦では7ラウンドでTKO負け。その2年後の内藤大助チャンピオンとの試合では、10ラウンドまでポイントでは勝っていたのですが、KO負けしています。その3年後に1階級上のスーパーフライ級で、判定で勝利して世界チャンピオンになりました。チャンピオンは奪い取るものではなく与えられるものなのだという父の恩師の大石牧師の言葉がありますが、チャンピオンにふさわしい選手になっていれば、自然と与えられると信じて頑張り、頂点を捉えることができました。
今日は「鍛えること、育てること」というテーマでお話させていただきますが、5つのポイントがあります。
一つ目は「怒ると叱るの違い」です。怒るとは、一時の感情であり、教え諭すことではない。叱るとは、相手の立場になり己を顧みることなり。怒ると叱るを使い分けることが大事です。
二つ目は「謙虚さが大事」。「誰でも初めは子供だった。しかしそのことを大人になっても忘れない大人はいくらもいない」という米国の言語学者の言葉があります。これは、謙虚であれということです。初心忘るべからずという言葉がありますが、それが大切です。
三つめは「よく聞くこと」。私は選手や社員、生徒、保護司の対象者の方々の話をよく聞きます。彼らの目標や希望、将来の夢などをしっかり共有するようにしています。
四つ目は「よく褒めること」。褒められれば、人は嬉しいですから頑張ると思うので、よく褒めます。
五つ目は「妥協しないこと」。この子はこの辺で良いかとか、この子はこんなもんだろうなどと親が子供の限界を決めてしまったり、指導者が選手や従業員の限界を決めてしまったら、限界を突破することができません。スポーツで全国一になる、優勝するのは並大抵のことではありません。きっと監督は選手の良さを引き出すために、妥協しない厳しさをもって送り出すのだと思います。
そして最後にこれらを「コツコツと行うこと」。これが「鍛えること、育てること」だと思っています。コツコツ努力する人にはかないません。「コツコツは勝つコツ」が私の好きな言葉です。
私が保護観察の青少年に初めての面接の時にする小話をひとつ。お坊さんが弟子と旅をしている時、弟子が落ちている包みを拾うと良い匂いがするので弟子はしまっておきました。しばらく歩くときれいな紐が落ちているので拾うと臭いので弟子は捨てようとします。するとお坊さんが弟子に、良い匂いがする包みは良い匂いのものを包んでいたからで、臭い紐は臭いものを結わえていたからではないか、もともと良い匂いや臭い匂いだったわけではないだろうと言いました。これは、私たち人間も、臭いもの、悪いものの中で育つと悪くなる、良い人たちと出会い、良い人たちの本を読み、良い行いをすること。良い人間になりたいもんだね、という話です。犯罪に手を染めてしまった人も、生まれた時は普通の赤ん坊として生まれます。ただ、育った環境や付き合う仲間によって、犯罪を犯してしまう人がいるのです。私が保護司として対象としているのは、特殊詐欺、オレオレ詐欺の受け子や出し子をしてしまった子たちです。犯罪という意識がなく、先輩から頼まれたからやってしまった子たちです。特殊詐欺は重い罪ということで、犯した青少年は一回で少年院送致になってしまいます。そのバックにいる大人の犯罪者が一番悪いのですが、警察ではその犯罪組織にまでなかなか手が回っていません。かわいそうだと思います。
私たちは、純粋無垢な赤ちゃんとして生まれた翌日から、死に向かって生きていきます。必ず訪れるのは生まれることと死ぬことですから、いかに充実した人生を歩んでいくかが大切なのではないかと思います。
このような私の生きざまのようなものが、皆様の心にとまり、皆様のお仕事や人生のちょっとした励みになればと感じる次第です。
ご清聴ありがとうございました。
皆様こんにちは。只今ご紹介に預かりました金子ボクシングジムの金子健太郎と申します。
金子ボクシングジムは父が創立者ですので、父の話をさせていただきます。父は戦後日本人として初めて国際タイトルを獲った東洋チャンピオンです。当時、フライ級世界チャンピオンの白井義男さんと父とが国際タイトルを持ち、ボクシング界を牽引していました。後のファイティング原田を育てた笹崎拳闘会の笹崎先生が父のボクシングの師匠でした。リングを降りると、父はまじめで敬虔なクリスチャンで、碑文谷教会の大石牧師が父の心の師匠でした。私もその大石先生から洗礼を受けて、二代目クリスチャンとして、教会学校の校長をボランティアで務めています。
父は、いざ世界戦を挑むという時に、ボクサーにとっては致命的な網膜剥離になってしまい、泣く泣く引退しました。そして自分が果たせなかった夢を、自分の後継者に託そうと、昭和40年に下北沢に金子ボクシングジムを設立しました。
私は大学のボクシングでアマチュアボクサーとして10戦ほど戦いましたが、目を悪くしてしまい、大学4年で引退しました。その後、金子ジムのアマチュア部のコーチからスタートして、プロのトレーナーライセンスを取得し、最終的に、世界チャンピオン一人、東洋太平洋チャンピオンを5人、日本チャンピオン7人、全日本新人王3人を育てることができました。一番の出世頭は、世界チャンピオンを獲得した清水智信選手です。
私は、33歳で入会した東京青年会議所を40歳で卒業すると同時に、保護司を拝命しました。やんちゃ坊主をボクシングの力で更生できるのなら協力したいという気持ちで保護司になりました。42歳でボクシングジムの会長、東日本ボクシング協会の事務局長になり、48歳でボクシングの興行などをプロモートする会社、金子プロモーションの代表取締役になりました。ジムの会長として強い選手を鍛えて、育てる。保護司として対象者を鍛えて、育てる。教会学校の校長として子供たちの信仰心を育てています。
清水智信は世界タイトルを簡単に獲ったわけではありません。初の世界戦では7ラウンドでTKO負け。その2年後の内藤大助チャンピオンとの試合では、10ラウンドまでポイントでは勝っていたのですが、KO負けしています。その3年後に1階級上のスーパーフライ級で、判定で勝利して世界チャンピオンになりました。チャンピオンは奪い取るものではなく与えられるものなのだという父の恩師の大石牧師の言葉がありますが、チャンピオンにふさわしい選手になっていれば、自然と与えられると信じて頑張り、頂点を捉えることができました。
今日は「鍛えること、育てること」というテーマでお話させていただきますが、5つのポイントがあります。
一つ目は「怒ると叱るの違い」です。怒るとは、一時の感情であり、教え諭すことではない。叱るとは、相手の立場になり己を顧みることなり。怒ると叱るを使い分けることが大事です。
二つ目は「謙虚さが大事」。「誰でも初めは子供だった。しかしそのことを大人になっても忘れない大人はいくらもいない」という米国の言語学者の言葉があります。これは、謙虚であれということです。初心忘るべからずという言葉がありますが、それが大切です。
三つめは「よく聞くこと」。私は選手や社員、生徒、保護司の対象者の方々の話をよく聞きます。彼らの目標や希望、将来の夢などをしっかり共有するようにしています。
四つ目は「よく褒めること」。褒められれば、人は嬉しいですから頑張ると思うので、よく褒めます。
五つ目は「妥協しないこと」。この子はこの辺で良いかとか、この子はこんなもんだろうなどと親が子供の限界を決めてしまったり、指導者が選手や従業員の限界を決めてしまったら、限界を突破することができません。スポーツで全国一になる、優勝するのは並大抵のことではありません。きっと監督は選手の良さを引き出すために、妥協しない厳しさをもって送り出すのだと思います。
そして最後にこれらを「コツコツと行うこと」。これが「鍛えること、育てること」だと思っています。コツコツ努力する人にはかないません。「コツコツは勝つコツ」が私の好きな言葉です。
私が保護観察の青少年に初めての面接の時にする小話をひとつ。お坊さんが弟子と旅をしている時、弟子が落ちている包みを拾うと良い匂いがするので弟子はしまっておきました。しばらく歩くときれいな紐が落ちているので拾うと臭いので弟子は捨てようとします。するとお坊さんが弟子に、良い匂いがする包みは良い匂いのものを包んでいたからで、臭い紐は臭いものを結わえていたからではないか、もともと良い匂いや臭い匂いだったわけではないだろうと言いました。これは、私たち人間も、臭いもの、悪いものの中で育つと悪くなる、良い人たちと出会い、良い人たちの本を読み、良い行いをすること。良い人間になりたいもんだね、という話です。犯罪に手を染めてしまった人も、生まれた時は普通の赤ん坊として生まれます。ただ、育った環境や付き合う仲間によって、犯罪を犯してしまう人がいるのです。私が保護司として対象としているのは、特殊詐欺、オレオレ詐欺の受け子や出し子をしてしまった子たちです。犯罪という意識がなく、先輩から頼まれたからやってしまった子たちです。特殊詐欺は重い罪ということで、犯した青少年は一回で少年院送致になってしまいます。そのバックにいる大人の犯罪者が一番悪いのですが、警察ではその犯罪組織にまでなかなか手が回っていません。かわいそうだと思います。
私たちは、純粋無垢な赤ちゃんとして生まれた翌日から、死に向かって生きていきます。必ず訪れるのは生まれることと死ぬことですから、いかに充実した人生を歩んでいくかが大切なのではないかと思います。
このような私の生きざまのようなものが、皆様の心にとまり、皆様のお仕事や人生のちょっとした励みになればと感じる次第です。
ご清聴ありがとうございました。
卓話「『NPO法人イランの障害者を支援するミントの会』の現地活動について」
NPO法人イランの障害者を支援するミントの会 理事 作業療法士・公認心理師
秋山佳世子さま
2024年2月8日

 今日はお招きいただきありがとうございます。「NPO法人イランの障害者を支援するミントの会」の秋山と申します。私の職業は作業療法士で、おととし公認心理師の資格を取りました。精神科の病院に作業療法士として15年間勤務した後、現在は、主に横浜で精神科の訪問看護ステーションで、精神疾患を抱えた方の自宅に訪問するなどの仕事を行っています。
私とミントの会との出会いは、日本だけでなく世界の人たちの暮らしに対する興味から国際協力のイベントに行ったときに、リハビリの支援も必要だと聞いて参加したのがきっかけです。
ミントの会は、代表のパシャイが日本で働いている時に不慮の事故で下半身不随の障害者となってしまい、日本でリハビリを受けて、障害があっても家で生活できるようになったという体験から、祖国イランでも同じ障害を持つ人たちのために何かしたいという思いで立ち上げたのが出発点です。
ミントの会の活動内容は、主に3つあります。1つはバリアフリー事業です。現地は、車いすの方や障害を持つ方々が外出するには不便な土地柄です。そこで、障害者が外出しやすくなるにはどうすればよいかということを行政と協力しあって行っています。さらに、リハビリ、ホームケア支援を行っています。どうすれば障害者が外出できるか、家でよりよく暮らせるかということを支援しております。そして、障害教育です。子どもの頃から障害を理解し、どうすれば車いすの人が動きやすいかといった視点を持てるような教育を行っています。
現地の様子を写真でご覧いただきたいと思います。
まず、イランの住環境ですが、家はほとんど石やレンガで出来ています。住居が2階で1階が駐車場となっていると、階段で上り下りする生活になり、車いすの人は介助する人がいないと外出できません。外の歩道もでこぼこしており、高さや幅が違うために目の不自由な方は歩きづらい街になっています。そして食事はペルシャじゅうたんの上に座って食事するという生活様式ですので、体が不自由な方はベッドに座ったままか車いすに乗ったまま食事することになります。
バリアフリー事業の一つとして実施したバリアフリー研修では、障害を持つ当事者と、行政や一般市民の方も一緒に街歩きをして不便な場所を体験してもらい、どのように解決すればよいか、日本の技術で伝えられるものはあるかといった積極的なコミュニケーションを図りながら街づくりを行っています。
リハビリテーション研修では、神奈川県立リハビリテーションセンターの理学療法士等の先生方に一緒に渡航して頂き、現地で研修を行いました。(写真は)ボッチャをみんなで楽しんだり、自宅に訪問して体の動かし方やご家族に介助の仕方を指導しています。
イランでは、脊髄損傷の患者であっても入院期間は長くても1か月程度です。そのため、病院でリハビリをほとんど受けられず、身体の感覚もなく自分で動かすこともできない状態で家に帰されてしまいます。金銭的に余裕のある方はリハビリを受け、中にはアメリカやカナダでリハビリを行ったという話も聞き、その差が大きいのが特徴かと思います。そこで、日本の理学療法士の先生からリハビリの指導を受け、身体の動かし方を教わると非常に驚かれたりします。体を起こすところから始めて、色々なことができるのを実感するように指導しています。
2019年に現地の障害児のデイサービス施設の代表の方と交流を持ち、見学に行きました。つい最近もZoomを通じて、この施設と日本の特別支援校の教員の方とで意見交換を行うなど、今も交流を続けています。
コロナ禍を経て、昨年9月に4年ぶりにイランに2週間ほど行ってきました。滞在したのは市役所の研修棟です。ミントの会代表のパシャイがバリアフリー研修で市の建築土木の職員と協力体制を組んでいるので、市役所の配慮で建物を貸していただきました。ゆうちょ財団からの助成金で行った活動の一つは名刺づくりです。障害を負って仕事もできず、アイデンティティが障害者という人生から、さらに何か目指すものを作るきっかけになればと思い、自分の名刺をつくる活動を実施しました。
ミントセンターでは、リハビリやトレーニングだけでなく、ここに来れば仲間がいて情報交換ができる、そういうつながりをたくさん作りたいと思い、ミントデーというイベントを行いました。カレーや焼きそばを作ってみんなで食事をしたり、日本の紹介や一緒に踊ったりして楽しい時間を過ごしました。
貼り絵をしたり、新聞紙で兜を作ったり、自転車こぎでトレーニングしたり、ボッチャをしたりしています。また、日本から持って行ったwiiでバランス訓練やボウリングして盛り上がったりして過ごしてもらっています。
ただ、ミントセンターに通えるのは、移動手段が確保できる一部の人たちだけです。通所が難しい障害者の方たちにも行き届くような活動をさらに進めていければと思っております。今後もイランの方々との交流を大切にしながら、またイランに行って活動しようと考えています。皆様からご協力をいただければと思います。
ありがとうございました。
Q&A
Q: リハビリの施設は現地には多いのでしょうか、それとも数が足りないのでしょうか。
A: 施設は全く足りていません。キャラジシティにはミントセンター以外に1か所だけです。
Q: イランは紛争があったというイメージがありますが、実際はどのような感じでしょうか。
A: イランはイラク等と離接していますが、国境沿いを除けば、基本的にイラン国内は外務省からも安全な地域と認識されています。追記 イラクへ仕事で行き来する方や、宗教行事でたくさんの市民の方が巡礼にイラクに行かれており、日本人のもつイメージと実際は違います。
Q: 現地でボッチャをやる人がいるのでしょうか、試合や大会について教えてください。
A: ミントセンターはキャラジ市が拠点となって行っています。初めて見たという方がほとんどです。大きな大会はありますので、障害者のスポーツ競技として行われているようです。
今日はお招きいただきありがとうございます。「NPO法人イランの障害者を支援するミントの会」の秋山と申します。私の職業は作業療法士で、おととし公認心理師の資格を取りました。精神科の病院に作業療法士として15年間勤務した後、現在は、主に横浜で精神科の訪問看護ステーションで、精神疾患を抱えた方の自宅に訪問するなどの仕事を行っています。
私とミントの会との出会いは、日本だけでなく世界の人たちの暮らしに対する興味から国際協力のイベントに行ったときに、リハビリの支援も必要だと聞いて参加したのがきっかけです。
ミントの会は、代表のパシャイが日本で働いている時に不慮の事故で下半身不随の障害者となってしまい、日本でリハビリを受けて、障害があっても家で生活できるようになったという体験から、祖国イランでも同じ障害を持つ人たちのために何かしたいという思いで立ち上げたのが出発点です。
ミントの会の活動内容は、主に3つあります。1つはバリアフリー事業です。現地は、車いすの方や障害を持つ方々が外出するには不便な土地柄です。そこで、障害者が外出しやすくなるにはどうすればよいかということを行政と協力しあって行っています。さらに、リハビリ、ホームケア支援を行っています。どうすれば障害者が外出できるか、家でよりよく暮らせるかということを支援しております。そして、障害教育です。子どもの頃から障害を理解し、どうすれば車いすの人が動きやすいかといった視点を持てるような教育を行っています。
現地の様子を写真でご覧いただきたいと思います。
まず、イランの住環境ですが、家はほとんど石やレンガで出来ています。住居が2階で1階が駐車場となっていると、階段で上り下りする生活になり、車いすの人は介助する人がいないと外出できません。外の歩道もでこぼこしており、高さや幅が違うために目の不自由な方は歩きづらい街になっています。そして食事はペルシャじゅうたんの上に座って食事するという生活様式ですので、体が不自由な方はベッドに座ったままか車いすに乗ったまま食事することになります。
バリアフリー事業の一つとして実施したバリアフリー研修では、障害を持つ当事者と、行政や一般市民の方も一緒に街歩きをして不便な場所を体験してもらい、どのように解決すればよいか、日本の技術で伝えられるものはあるかといった積極的なコミュニケーションを図りながら街づくりを行っています。
リハビリテーション研修では、神奈川県立リハビリテーションセンターの理学療法士等の先生方に一緒に渡航して頂き、現地で研修を行いました。(写真は)ボッチャをみんなで楽しんだり、自宅に訪問して体の動かし方やご家族に介助の仕方を指導しています。
イランでは、脊髄損傷の患者であっても入院期間は長くても1か月程度です。そのため、病院でリハビリをほとんど受けられず、身体の感覚もなく自分で動かすこともできない状態で家に帰されてしまいます。金銭的に余裕のある方はリハビリを受け、中にはアメリカやカナダでリハビリを行ったという話も聞き、その差が大きいのが特徴かと思います。そこで、日本の理学療法士の先生からリハビリの指導を受け、身体の動かし方を教わると非常に驚かれたりします。体を起こすところから始めて、色々なことができるのを実感するように指導しています。
2019年に現地の障害児のデイサービス施設の代表の方と交流を持ち、見学に行きました。つい最近もZoomを通じて、この施設と日本の特別支援校の教員の方とで意見交換を行うなど、今も交流を続けています。
コロナ禍を経て、昨年9月に4年ぶりにイランに2週間ほど行ってきました。滞在したのは市役所の研修棟です。ミントの会代表のパシャイがバリアフリー研修で市の建築土木の職員と協力体制を組んでいるので、市役所の配慮で建物を貸していただきました。ゆうちょ財団からの助成金で行った活動の一つは名刺づくりです。障害を負って仕事もできず、アイデンティティが障害者という人生から、さらに何か目指すものを作るきっかけになればと思い、自分の名刺をつくる活動を実施しました。
ミントセンターでは、リハビリやトレーニングだけでなく、ここに来れば仲間がいて情報交換ができる、そういうつながりをたくさん作りたいと思い、ミントデーというイベントを行いました。カレーや焼きそばを作ってみんなで食事をしたり、日本の紹介や一緒に踊ったりして楽しい時間を過ごしました。
貼り絵をしたり、新聞紙で兜を作ったり、自転車こぎでトレーニングしたり、ボッチャをしたりしています。また、日本から持って行ったwiiでバランス訓練やボウリングして盛り上がったりして過ごしてもらっています。
ただ、ミントセンターに通えるのは、移動手段が確保できる一部の人たちだけです。通所が難しい障害者の方たちにも行き届くような活動をさらに進めていければと思っております。今後もイランの方々との交流を大切にしながら、またイランに行って活動しようと考えています。皆様からご協力をいただければと思います。
ありがとうございました。
Q&A
Q: リハビリの施設は現地には多いのでしょうか、それとも数が足りないのでしょうか。
A: 施設は全く足りていません。キャラジシティにはミントセンター以外に1か所だけです。
Q: イランは紛争があったというイメージがありますが、実際はどのような感じでしょうか。
A: イランはイラク等と離接していますが、国境沿いを除けば、基本的にイラン国内は外務省からも安全な地域と認識されています。追記 イラクへ仕事で行き来する方や、宗教行事でたくさんの市民の方が巡礼にイラクに行かれており、日本人のもつイメージと実際は違います。
Q: 現地でボッチャをやる人がいるのでしょうか、試合や大会について教えてください。
A: ミントセンターはキャラジ市が拠点となって行っています。初めて見たという方がほとんどです。大きな大会はありますので、障害者のスポーツ競技として行われているようです。
卓話「世田谷区内の子ども食堂について」
世田谷区社会福祉協議会 地域社協課 係長 尾﨑 一美さま
2024年1月25日

 本日はこのような席にお呼びいただきありがとうございます。世田谷区社会福祉協議会、地域社協課調整係の係長をしております尾﨑と申します。世田谷区内の子ども食堂について説明をさせていただきます。
子ども食堂の数は全国で9,131か所あります。最も多いのが東京都の1,009か所、次いで大阪府、兵庫県です。もっとも少ない県は秋田県で、次いで福井県、長崎県です。但し、これは子ども食堂の数だけです。充足率が一番高いのは沖縄県です。次いで、世田谷区より人口が少ない鳥取県、その次が東京都になります。
現在、世田谷区内には子ども食堂が77か所あります。東京都の中で世田谷区が一番多いと思います。子ども食堂の定義は、「共働き家庭やひとり親家庭などで遅くまでひとりで過ごす子どもたちの「孤食」、経済的理由による「欠食」などを少しでも減らすため、無料または安価な料金で食事(会食)の提供等を地域住民の方々が行なう地域・地区の活動団体等をいう」となります。
コロナ禍以前の世田谷区内の子ども食堂は、どちらかというと地域の中で楽しんで食事をする場でした。しかし、コロナ禍が明け、世田谷区内でも欠食や孤食のお子さんが急増しています。子ども食堂は月に1回か2回しかできないため、それ以外の食事をどうすればよいのかという相談が寄せられるようになりました。このため、子ども食堂の中に「相談支援機能」が加わり、孤食や欠食への対応を行政や社会福祉協議会の関係機関につなげていくというように変化してきています。
世田谷区内で子ども食堂という名前が出てくるようになったのは平成27年度頃で、社会福祉協議会が把握していた子ども食堂の数は4団体程度でした。その後、爆発的に子ども食堂の数は増えています。昨年までは62団体でしたが現在は77団体です。数が急増した理由には、保険会社等の有料老人ホームが子ども食堂を始めていることが挙げられます。
社会福祉協議会が支援していること、まず、子ども食堂の人材の確保です。次に大変なのが、場所の確保です。月の決まった日に安定的に活動でき、調理ができて子どもがご飯を食べられる場所の確保です。世田谷区社会福祉協議会は区の行政財産使用許可を得て、区内に22か所の拠点を案内しています。そして、食材を購入するお金。これは東京都と世田谷区で半分ずつ財源を持つ、子ども食堂推進補助金が始まりました。しかし補助金もたくさん出るわけではないので、今回東京山の手ロータリークラブからいただけるお米の寄贈などがとても重要になっています。さらに、全国に先駆けて世田谷区独自の取り組みとして、安心して活動できるための保険加入を無料で行っています。買い物に出たスタッフの怪我、子供の怪我、万一の食中毒にも保険対応できるような保険に加入しています。そして、一番大切なのは食材の提供です。寄贈していただけるもので一番うれしいのはお米です。多くの企業からいただく牛乳やパスタソースなどの食材を上手に活用しながら運営資金と合わせて、子ども食堂は活動しています。
平成27年に子ども食堂が始まった当時は、小学校の先生方も子ども食堂をご存じありませんでした。そこで、子ども食堂のPRチラシを小学校に持って行ったのですが、受け付けられないと返されることが多くありました。今はこれだけ子ども食堂が周知されたので、先生たちもPRのチラシや「子ども食堂情報」などを持っていくと学校側で配布に協力してくださっています。また、子ども食堂も変化してきているので、スタッフ向けに年1回か2回の研修を開催しています。
コロナ禍の第一波の時、学校は臨時休校になりました。その時に、子ども食堂に参加していたお子さんが、スタッフのところに来て、「僕、給食がないと困るんだよね」と話されました。子ども食堂の方が慌てて、社会福祉協議会に、コロナ禍だが何とかお弁当を子どもたちに配布できないかと話に来られました。世田谷区長が子ども食堂に寛大な考えを持っていたので、2週間で子ども食堂が再開されました。すると、両親が共にコロナで失職した家庭のお子さんがお弁当を何個ももらうために子ども食堂を渡り歩くということも起こりました。そこで、お弁当だけでなく、様々な企業から提供された食材をお弁当と一緒に渡すということもこの数年行なってきました。
現在はコロナ禍が明けて会食が戻ってきました。ひとり親家庭や経済的な事情で季節行事にまったく触れないというお子さんが、世田谷区内にも多くいます。そうしたお子さんのために、昨年5月の鯉のぼりの時期には鯉のぼりの形をしたお稲荷さんを作ったり、地域の野菜をたっぷり使ったシチューを提供したりしています。ただ、まだ半分くらいの団体では、会食に戻れず、お弁当の配布を続けています。コロナ禍の3年間お弁当が続き、お母さんたちも子どもたちもお弁当をもらい、家に帰って食べるのが楽だということもあります。また、コロナが明けたら子ども食堂が必要な子どもの数が爆発的に増えたために会食ができないという団体もあります。
社会福祉協議会では、寄贈していただく食料品として、お米以外に生鮮食品も受け付けています。但し、冷蔵庫や冷凍庫がたくさんあるわけではないので、ご提供いただける場合は事前にご連絡をいただければ助かります。
今後の課題としては、まず、会食に戻れない団体への対応が挙げられます。場所の提供や人員の確保を区と調整しながら行っています。次に、子ども食堂の数は増えてきていますが、子どもだけではなく、収入が低い高齢者や一人暮らしの方、少し障害を抱えた方が子どもたちと一緒に食事する地域食堂、多世代食堂への支援も行う必要があると考えています。そして、子ども食堂のスタッフは大学生から80歳まで多岐にわたる年代の方々がいます。こうしたスタッフへの研修強化もこれから先進めていきます。
本当に世田谷区内に子ども食堂が必要なのかという話を色々な方から尋ねられたりします。今年も夏休みが終わった後に小学校から連絡がありました。中長期の休み明けに痩せてしまうお子さんが学校に数名いるのです。経済的な理由で痩せてしまうお子さんやさまざまな理由で欠食になるお子さんがいらっしゃいます。世田谷区内でも様々な理由を抱えて、子ども食堂に参加しているお子さんがいることを、頭の隅に置いて覚えていただければと思います。
ありがとうございました。
Q&A
Q: PRチラシを学校で最初受け取らなかったのは何故でしょうか。
A: 支援が必要な子にチラシを渡してほしいとお願いしましたが、学校としては、全員に渡すことはできるが、この子が支援が必要だからとチラシを渡すことはできないと言われました。地域の団体は500枚も600枚もチラシを印刷することができなかったので、そういう点がうまくつながらなかったのだと思います。
Q: 私たちが子ども食堂で何かお手伝いできることはあるのでしょうか。
A: あります。三角巾とエプロンを持ってきていただいて食事の提供をしていただくとか、子どもの学習支援で宿題を見ていただくことなどご協力いただければと思います。
Q: 畑で余った野菜を処分していることがある。行政に働きかけてそうした野菜を活用できないか。
A: 世田谷区や目黒にも畑があり、JAから余った野菜を子ども食堂に提供していただいています。
本日はこのような席にお呼びいただきありがとうございます。世田谷区社会福祉協議会、地域社協課調整係の係長をしております尾﨑と申します。世田谷区内の子ども食堂について説明をさせていただきます。
子ども食堂の数は全国で9,131か所あります。最も多いのが東京都の1,009か所、次いで大阪府、兵庫県です。もっとも少ない県は秋田県で、次いで福井県、長崎県です。但し、これは子ども食堂の数だけです。充足率が一番高いのは沖縄県です。次いで、世田谷区より人口が少ない鳥取県、その次が東京都になります。
現在、世田谷区内には子ども食堂が77か所あります。東京都の中で世田谷区が一番多いと思います。子ども食堂の定義は、「共働き家庭やひとり親家庭などで遅くまでひとりで過ごす子どもたちの「孤食」、経済的理由による「欠食」などを少しでも減らすため、無料または安価な料金で食事(会食)の提供等を地域住民の方々が行なう地域・地区の活動団体等をいう」となります。
コロナ禍以前の世田谷区内の子ども食堂は、どちらかというと地域の中で楽しんで食事をする場でした。しかし、コロナ禍が明け、世田谷区内でも欠食や孤食のお子さんが急増しています。子ども食堂は月に1回か2回しかできないため、それ以外の食事をどうすればよいのかという相談が寄せられるようになりました。このため、子ども食堂の中に「相談支援機能」が加わり、孤食や欠食への対応を行政や社会福祉協議会の関係機関につなげていくというように変化してきています。
世田谷区内で子ども食堂という名前が出てくるようになったのは平成27年度頃で、社会福祉協議会が把握していた子ども食堂の数は4団体程度でした。その後、爆発的に子ども食堂の数は増えています。昨年までは62団体でしたが現在は77団体です。数が急増した理由には、保険会社等の有料老人ホームが子ども食堂を始めていることが挙げられます。
社会福祉協議会が支援していること、まず、子ども食堂の人材の確保です。次に大変なのが、場所の確保です。月の決まった日に安定的に活動でき、調理ができて子どもがご飯を食べられる場所の確保です。世田谷区社会福祉協議会は区の行政財産使用許可を得て、区内に22か所の拠点を案内しています。そして、食材を購入するお金。これは東京都と世田谷区で半分ずつ財源を持つ、子ども食堂推進補助金が始まりました。しかし補助金もたくさん出るわけではないので、今回東京山の手ロータリークラブからいただけるお米の寄贈などがとても重要になっています。さらに、全国に先駆けて世田谷区独自の取り組みとして、安心して活動できるための保険加入を無料で行っています。買い物に出たスタッフの怪我、子供の怪我、万一の食中毒にも保険対応できるような保険に加入しています。そして、一番大切なのは食材の提供です。寄贈していただけるもので一番うれしいのはお米です。多くの企業からいただく牛乳やパスタソースなどの食材を上手に活用しながら運営資金と合わせて、子ども食堂は活動しています。
平成27年に子ども食堂が始まった当時は、小学校の先生方も子ども食堂をご存じありませんでした。そこで、子ども食堂のPRチラシを小学校に持って行ったのですが、受け付けられないと返されることが多くありました。今はこれだけ子ども食堂が周知されたので、先生たちもPRのチラシや「子ども食堂情報」などを持っていくと学校側で配布に協力してくださっています。また、子ども食堂も変化してきているので、スタッフ向けに年1回か2回の研修を開催しています。
コロナ禍の第一波の時、学校は臨時休校になりました。その時に、子ども食堂に参加していたお子さんが、スタッフのところに来て、「僕、給食がないと困るんだよね」と話されました。子ども食堂の方が慌てて、社会福祉協議会に、コロナ禍だが何とかお弁当を子どもたちに配布できないかと話に来られました。世田谷区長が子ども食堂に寛大な考えを持っていたので、2週間で子ども食堂が再開されました。すると、両親が共にコロナで失職した家庭のお子さんがお弁当を何個ももらうために子ども食堂を渡り歩くということも起こりました。そこで、お弁当だけでなく、様々な企業から提供された食材をお弁当と一緒に渡すということもこの数年行なってきました。
現在はコロナ禍が明けて会食が戻ってきました。ひとり親家庭や経済的な事情で季節行事にまったく触れないというお子さんが、世田谷区内にも多くいます。そうしたお子さんのために、昨年5月の鯉のぼりの時期には鯉のぼりの形をしたお稲荷さんを作ったり、地域の野菜をたっぷり使ったシチューを提供したりしています。ただ、まだ半分くらいの団体では、会食に戻れず、お弁当の配布を続けています。コロナ禍の3年間お弁当が続き、お母さんたちも子どもたちもお弁当をもらい、家に帰って食べるのが楽だということもあります。また、コロナが明けたら子ども食堂が必要な子どもの数が爆発的に増えたために会食ができないという団体もあります。
社会福祉協議会では、寄贈していただく食料品として、お米以外に生鮮食品も受け付けています。但し、冷蔵庫や冷凍庫がたくさんあるわけではないので、ご提供いただける場合は事前にご連絡をいただければ助かります。
今後の課題としては、まず、会食に戻れない団体への対応が挙げられます。場所の提供や人員の確保を区と調整しながら行っています。次に、子ども食堂の数は増えてきていますが、子どもだけではなく、収入が低い高齢者や一人暮らしの方、少し障害を抱えた方が子どもたちと一緒に食事する地域食堂、多世代食堂への支援も行う必要があると考えています。そして、子ども食堂のスタッフは大学生から80歳まで多岐にわたる年代の方々がいます。こうしたスタッフへの研修強化もこれから先進めていきます。
本当に世田谷区内に子ども食堂が必要なのかという話を色々な方から尋ねられたりします。今年も夏休みが終わった後に小学校から連絡がありました。中長期の休み明けに痩せてしまうお子さんが学校に数名いるのです。経済的な理由で痩せてしまうお子さんやさまざまな理由で欠食になるお子さんがいらっしゃいます。世田谷区内でも様々な理由を抱えて、子ども食堂に参加しているお子さんがいることを、頭の隅に置いて覚えていただければと思います。
ありがとうございました。
Q&A
Q: PRチラシを学校で最初受け取らなかったのは何故でしょうか。
A: 支援が必要な子にチラシを渡してほしいとお願いしましたが、学校としては、全員に渡すことはできるが、この子が支援が必要だからとチラシを渡すことはできないと言われました。地域の団体は500枚も600枚もチラシを印刷することができなかったので、そういう点がうまくつながらなかったのだと思います。
Q: 私たちが子ども食堂で何かお手伝いできることはあるのでしょうか。
A: あります。三角巾とエプロンを持ってきていただいて食事の提供をしていただくとか、子どもの学習支援で宿題を見ていただくことなどご協力いただければと思います。
Q: 畑で余った野菜を処分していることがある。行政に働きかけてそうした野菜を活用できないか。
A: 世田谷区や目黒にも畑があり、JAから余った野菜を子ども食堂に提供していただいています。
卓話「世界を走る」
ミズノ株式会社 ミズノトラッククラブ所属 リオオリンピック銀メダリスト
飯塚翔太さま
2023年12月14日

 みなさん、こんにちは。ミズノ株式会社ミズノトラッククラブに所属しております飯塚翔太と申します。
現役選手として今回のオリンピックの話も出ましたが、7年前のリオオリンピックで銀メダルを取ることができました。今年はハンガリーで開催された世界選手権に出場して海外での自己ベストを更新することができました。32歳ですが、まだまだ速く走れると燃えております。
最初にリオオリンピックを振り返ろうと思います。入場の時のポーズは僕が考えました。もともと学生時代から中の良い4人で、非常に良いメンバーでした。日本は、アンダーハンドパスというバトンの渡し方を2000年から始めました。それまではフランスがやっていて、現在はフランスと日本しかやっていない非常に難しい技術です。これは走者のフォームが崩れにくいという良さがあり、バトンを受け取る側は速く加速できるというメリットがあります。渡した瞬間の手の長さで走らなくてよい距離を得ることができて、走りのフォームが崩れないハイブリッド・アンダーハンドパスをずっと練習しています。バトンパスにもう一つの難しい点があります。前の走者が通ったら自分が走り出すという位置にテープを貼っておくのですが、その通りにスタートを切るというのが一番難しいところです。
リオオリンピックの時は、予選でバトンが近いと感じたので、その差を埋めるために僕が少し早めにスタートを切ろうということになりました。そこで、スタートを切る位置を足で測って7センチ広げました。もし、これよりも広げたらバトンが渡らなかった可能性もあったので、ギリギリで勝負を分けた7センチになりました。
リオオリンピック100メートル決勝の一歩目の写真を見ると選手の走り方がみんな違っています。正解がないのです。世界のトップ中のトップでも走り方はバラバラです。それが走ることの楽しさで、自分で色々な走りを真似したり模索するのがとても楽しいです。
リオのオリンピックの選手村には30階建てくらいのタワーマンションがたくさん建っていました。公園の中の非常に広い敷地にあり、中で練習もできるようになっていました。部屋は基本3LDKで、2名一部屋で6人で過ごす形になっていました。ベッドはシングルベッドで、身長186センチの僕でもかかとが出るくらいなので、球技の2メートルを超える選手にとっては相当狭かったと思います。食堂は24時間営業で食べ放題でした。色んな国から来るのでみんなそれぞれが選べるように対応していました。
私は毎年11月に色々な海外の国へ行って陸上を教えています。走り方を教えたり、競走しに行ったりしています。先月は東アフリカのルワンダに行きました。ルワンダの近くにはエチオピア、ケニアなどマラソンに非常に強い国があり、オリンピックメダリストがたくさん出ている国の近くです。しかし、ルワンダはメダリストが一人もおらず、選手としても行ったことがないような国です。ところが子供たちと一緒に走ってみると能力が非常に高い子がたくさんいます。そうした人を発掘して、コーチングして、国を背負って頑張る選手が出て、メダルを取って国に貢献するようにできればと思って活動しています。
リオオリンピックでメダルを取った時の入場シーンでのポーズの話になりますが、大会側から決勝に残ったらポーズをするようにと言われていました。僕らは決勝直前の確認する時間にそれを思い出して、急いで相談して30秒くらいであのポーズをすることに決めました。結果的にポーズをしたチームは日本とジャマイカとカナダの3チームだけでした。メダルを取った3チームです。これは、一つの目標に向かっていくための決め事のような一つの瞬間を作る大切さだと思います。僕たちは、ウォーミングアップは個々にバラバラに行いますが、それ以外は一緒に過ごすことが多いのです。こうして一緒に過ごして気持ちを一つにする時間を作ることが大切だと感じました。
陸上は30歳を超えるとほとんどの人が引退してしまって、自分の同世代が誰もいなくなり寂しい気持ちになります。それでも自分が長く競技を続けていられる理由は、色々な方々からの力を借り続けていることだと思います。赤羽にあるナショナルトレーニングセンターの中に掲げられているスローガンに「人間力なくして競技力向上なし」という言葉があります。自分が競技をやる上で、指導してくれる人がいたり、しんどい時に顔を思い浮かべると頑張れるライバルがいたり、自分の活躍を世の中に報じてくれるメディアの方や、普段から応援してくださる方など、常に人に囲まれている人生で、結果が出なかったときにもこうした周りの方々の言葉に支えられたりします。自分が優勝したときに、他のライバルを貶めるような発言をしないといったことなど、良いときこそ良いふるまいをしてきたからこそ、長く競技を続けることができた、支えられているという実感があります。
遠い目標ですが100歳で世界記録更新という目標があります。30歳からマスターズ陸上というスプリンターの大会があります。日本人の高齢の選手が記録を持っていたりして世界でも活躍していますが、なかなか試合が盛り上がっていません。自分が入って盛り上げたいと思っています。
走りは歩幅と回転数という二つの要素に分けられます。回転数は子供から大人までさほど変わらず1秒間で4回転くらいです。でも、歩幅は違います。科学的にはアスリートは身長の1.2倍くらいの歩幅が出ると言われています。子供の場合は身長と同じくらいの歩幅で走るのが基準だと言われています。これを掛け算して足の速さが出てきます。走っている時に足が地面に着く時間は0.1秒ありません。0.08~0.09秒くらいです。人間は走るとき、小指から入ってかかとが落ち込んで離れるというのがメカニズムです。速い人はかかとがあまり落ちずに足が抜けます。遅い人はかかとから入ってベタっと地面に着いて離れます。これが速い人と遅い人の差です。なぜ速いか、かかとが落ちないかというと、足首が硬いのです。陸上競技用のトラックやコンクリートの上ではねたりしているとどんどん硬くなっていきます。速く走るのと健康は相反するものなのです。競技特性として、僕も体がすごく硬くなってしまっています。膝、足首、股関節が一つの硬い棒になっていていることで、地面から力をもらって弾むことができるのです。その代わり、怪我をしやすいというリスクがあります。また、腕を振る時は手の力を抜いていないと速く振ることができません。速く走るために、フォームはバラバラでも共通しているのは手の平がリラックスしていることです。そして首が長くて肩が落ちていることも共通しています。
来年はパリオリンピックが開催されます。4月から6月にかけて日本で大きな試合が行われ、オリンピックの2か月前の予選会で代表が決まります。それに加えて、世界で種目ごとに決まっている人数があり、200メートルは48人という出場枠があります。僕は現在42番くらいです。来年6月まで48位以内をキープして代表選考会で3位以内に入るとオリンピック選手に選ばれます。オリンピックに4回出場したのは朝原選手だけですが、僕もそこに並び、その次のオリンピックにも出て歴史上誰も達成していない5回連続出場達成を目指します。引き続き、応援をいただければ嬉しく思います。
ありがとうございます。
みなさん、こんにちは。ミズノ株式会社ミズノトラッククラブに所属しております飯塚翔太と申します。
現役選手として今回のオリンピックの話も出ましたが、7年前のリオオリンピックで銀メダルを取ることができました。今年はハンガリーで開催された世界選手権に出場して海外での自己ベストを更新することができました。32歳ですが、まだまだ速く走れると燃えております。
最初にリオオリンピックを振り返ろうと思います。入場の時のポーズは僕が考えました。もともと学生時代から中の良い4人で、非常に良いメンバーでした。日本は、アンダーハンドパスというバトンの渡し方を2000年から始めました。それまではフランスがやっていて、現在はフランスと日本しかやっていない非常に難しい技術です。これは走者のフォームが崩れにくいという良さがあり、バトンを受け取る側は速く加速できるというメリットがあります。渡した瞬間の手の長さで走らなくてよい距離を得ることができて、走りのフォームが崩れないハイブリッド・アンダーハンドパスをずっと練習しています。バトンパスにもう一つの難しい点があります。前の走者が通ったら自分が走り出すという位置にテープを貼っておくのですが、その通りにスタートを切るというのが一番難しいところです。
リオオリンピックの時は、予選でバトンが近いと感じたので、その差を埋めるために僕が少し早めにスタートを切ろうということになりました。そこで、スタートを切る位置を足で測って7センチ広げました。もし、これよりも広げたらバトンが渡らなかった可能性もあったので、ギリギリで勝負を分けた7センチになりました。
リオオリンピック100メートル決勝の一歩目の写真を見ると選手の走り方がみんな違っています。正解がないのです。世界のトップ中のトップでも走り方はバラバラです。それが走ることの楽しさで、自分で色々な走りを真似したり模索するのがとても楽しいです。
リオのオリンピックの選手村には30階建てくらいのタワーマンションがたくさん建っていました。公園の中の非常に広い敷地にあり、中で練習もできるようになっていました。部屋は基本3LDKで、2名一部屋で6人で過ごす形になっていました。ベッドはシングルベッドで、身長186センチの僕でもかかとが出るくらいなので、球技の2メートルを超える選手にとっては相当狭かったと思います。食堂は24時間営業で食べ放題でした。色んな国から来るのでみんなそれぞれが選べるように対応していました。
私は毎年11月に色々な海外の国へ行って陸上を教えています。走り方を教えたり、競走しに行ったりしています。先月は東アフリカのルワンダに行きました。ルワンダの近くにはエチオピア、ケニアなどマラソンに非常に強い国があり、オリンピックメダリストがたくさん出ている国の近くです。しかし、ルワンダはメダリストが一人もおらず、選手としても行ったことがないような国です。ところが子供たちと一緒に走ってみると能力が非常に高い子がたくさんいます。そうした人を発掘して、コーチングして、国を背負って頑張る選手が出て、メダルを取って国に貢献するようにできればと思って活動しています。
リオオリンピックでメダルを取った時の入場シーンでのポーズの話になりますが、大会側から決勝に残ったらポーズをするようにと言われていました。僕らは決勝直前の確認する時間にそれを思い出して、急いで相談して30秒くらいであのポーズをすることに決めました。結果的にポーズをしたチームは日本とジャマイカとカナダの3チームだけでした。メダルを取った3チームです。これは、一つの目標に向かっていくための決め事のような一つの瞬間を作る大切さだと思います。僕たちは、ウォーミングアップは個々にバラバラに行いますが、それ以外は一緒に過ごすことが多いのです。こうして一緒に過ごして気持ちを一つにする時間を作ることが大切だと感じました。
陸上は30歳を超えるとほとんどの人が引退してしまって、自分の同世代が誰もいなくなり寂しい気持ちになります。それでも自分が長く競技を続けていられる理由は、色々な方々からの力を借り続けていることだと思います。赤羽にあるナショナルトレーニングセンターの中に掲げられているスローガンに「人間力なくして競技力向上なし」という言葉があります。自分が競技をやる上で、指導してくれる人がいたり、しんどい時に顔を思い浮かべると頑張れるライバルがいたり、自分の活躍を世の中に報じてくれるメディアの方や、普段から応援してくださる方など、常に人に囲まれている人生で、結果が出なかったときにもこうした周りの方々の言葉に支えられたりします。自分が優勝したときに、他のライバルを貶めるような発言をしないといったことなど、良いときこそ良いふるまいをしてきたからこそ、長く競技を続けることができた、支えられているという実感があります。
遠い目標ですが100歳で世界記録更新という目標があります。30歳からマスターズ陸上というスプリンターの大会があります。日本人の高齢の選手が記録を持っていたりして世界でも活躍していますが、なかなか試合が盛り上がっていません。自分が入って盛り上げたいと思っています。
走りは歩幅と回転数という二つの要素に分けられます。回転数は子供から大人までさほど変わらず1秒間で4回転くらいです。でも、歩幅は違います。科学的にはアスリートは身長の1.2倍くらいの歩幅が出ると言われています。子供の場合は身長と同じくらいの歩幅で走るのが基準だと言われています。これを掛け算して足の速さが出てきます。走っている時に足が地面に着く時間は0.1秒ありません。0.08~0.09秒くらいです。人間は走るとき、小指から入ってかかとが落ち込んで離れるというのがメカニズムです。速い人はかかとがあまり落ちずに足が抜けます。遅い人はかかとから入ってベタっと地面に着いて離れます。これが速い人と遅い人の差です。なぜ速いか、かかとが落ちないかというと、足首が硬いのです。陸上競技用のトラックやコンクリートの上ではねたりしているとどんどん硬くなっていきます。速く走るのと健康は相反するものなのです。競技特性として、僕も体がすごく硬くなってしまっています。膝、足首、股関節が一つの硬い棒になっていていることで、地面から力をもらって弾むことができるのです。その代わり、怪我をしやすいというリスクがあります。また、腕を振る時は手の力を抜いていないと速く振ることができません。速く走るために、フォームはバラバラでも共通しているのは手の平がリラックスしていることです。そして首が長くて肩が落ちていることも共通しています。
来年はパリオリンピックが開催されます。4月から6月にかけて日本で大きな試合が行われ、オリンピックの2か月前の予選会で代表が決まります。それに加えて、世界で種目ごとに決まっている人数があり、200メートルは48人という出場枠があります。僕は現在42番くらいです。来年6月まで48位以内をキープして代表選考会で3位以内に入るとオリンピック選手に選ばれます。オリンピックに4回出場したのは朝原選手だけですが、僕もそこに並び、その次のオリンピックにも出て歴史上誰も達成していない5回連続出場達成を目指します。引き続き、応援をいただければ嬉しく思います。
ありがとうございます。
卓話「長寿菌がいのちを守る-100歳長寿をめざして」
一般財団法人 辨野腸内フローラ研究所 辨野義己さま
2023年11月2日

 ただいま紹介いただきました辨野腸内フローラ研究所の辨野と申します。
これまで、理化学研究所に48年間(1973年から2021年まで)、お世話になっておりました。2009年に理研より定年退職後、企業からの研究資金提供と研究者の派遣していただいて、特別研究室を主宰する特別招聘研究員として、引き続き研究活動を12年間させて頂きました。その期間終了後、社会のため、人々のために貢献する目的で、財団法人を設立させて頂いて、研究・啓発活動する事を続行しなさいという形で、今現在に至っております。
生まれは昭和23年ですので、只今75歳。後期高齢者でございます。今なお、研究に対する意欲、ま、生涯、腸内細菌研究を続けていこうという決意と共に、次の若い世代をいかに育成していくかということを中心に、仕事を進めさせていただいております。
理研に在職中は様々なサポートしていただき、大好きな腸内細菌の分類と生態に関する研究に夢中になって過ごさせていただいてまいりました。理研を卒業して財団法人を立ち上げてみますと、いかに娑婆が厳しいかということを身の肌に感じております。財団法人という研究所運営に必要な資金確保ために収益事業や公益事業も展開せざるを得ず、日々休むことなく、ま、今日に至っております。
今日もこういう会に呼んでいただきまして、ほんと、あの、食事中で、どういう設定なのか、私も苦しみましたが・・(笑い)。もう、名前が辨野(べんの)という名前で、皆さん、「えっ!」と思われるでしょう?実は本名でございまして、大阪は枚方というところで生まれて、育ちました。辨野という姓の人口は、120人くらいだそうです。たぶん半数近くは私の親戚ですが、あと半数はまったく親戚じゃない辨野さんもいらっしゃるそうです。
本日の講演内容はすでに単行本として多数、上梓しております。どれか1冊買っていただければ、内容もさらにご理解が深まるものと期待しております。実は最近、幻冬舎から上梓しました『大便革命』が中国語版で出版されるようです。中国語で発刊されば、さらなる展開も望まれと切望しております。
卓話の内容は、健康長寿、どうのようにすれば健康で長生きできる、できるっていうか、していこうとする姿勢にどのようにつなげていけばいいかという事をご理解していただこうという試みです。準備させていだきましたレジメに書かせていただきました。
以下についてお話させていただけたらと思います。
健康長寿を目指す最高の腸活
1)女はたまる。男はくだる。
2)大腸は病気の発生源。
3)あなたの腸は何歳ですか?
4)カラダを強くする最高の腸活実践
実は腸活という言葉ですが、これ90年代後半に腸内フローラ、腸年齢、菌活、腸活という言葉を私どもの研究室から発した言葉でございまして。なじみのある言葉と思います。なぜ腸活と言うかというと、いかに良い腸内環境に保つかが健康長寿に結びつくのです。
本日は食事中ですが、大便や腸内細菌の内容ですので、本当に、この内容でいいのかと悩みました。つまり、食べたものがいつ排便されるかという「うんちくの話」なのです。そういう話をさせていただきますけど、なるべく臭い話はしないように、心がけますけれども、つい日ごろからそういう言葉を使っているので、ぽろぽろと出てしまうような、少し心配ですが・・。
唐突ですが、便秘について説明しますと、医学的に3日以上出ないことを便秘あるいは便秘症と定義づけられております。そこで、健康とされる女性約2000名に排便に関する調査しますと、48%半数の方が便秘!その内の65%、5日に1回しか出さないのです。つまり、月曜から金曜日出さなくて、土日を使って出しているという結果を得ることができました。これを名付けて、「週末トイレ症候群」という表現にいたしました。どういう方が多いかというと、ほとんど若い女性たち、20代の女性たちが2人に1人は便秘です。また、10代ですら10名中3名は便秘なのです。小さい頃から便秘で、もう諦めきっている女性たちの姿というのが見えてきますよ。
その要因は何かというと、なんといっても偏った食事。肉が大好きだから肉だけを食べている。野菜を摂らないようなライフスタイルが日本人の女性たちの腸内環境を悪くしていると言えます(直腸性便秘)。あるいは運動不足から来る便秘です。出したけれどもまだ出し切れていない気がする状況です(弛緩性便秘)。
さらに、ストレスからくる便秘、これは、なんとなく、トイレ見るとパラパラ分かれたようなうんちが出てる状態を、ウサギのような糞、兎糞(とふん)と言われます。これはストレスからくる便秘で、痙攣(けいれん)性便秘です。
さらに、女性に多いのですが痩せていたい、スマートでいたいというので、ダイエットをしてしまうと。食べる量が少ないので出す量も少なくなっています。日本人女性の腸内環境を作っているということもよく知られています。
運動でもインナーマッスル(腸腰筋と腸骨筋)を鍛えるのは、やっぱり筋力、運動の活力なのです。ですから、これも排便に大きな影響与えますということも理解していただければ、運動も、非常に重要な働きがあるのです。
ところで、30代40代の女性500名に腸内環境調査をしますと、なんと95%の人たちは、腸の調子が悪いと答えておられます。どういうことかでいうと、便秘じゃありませんよ、おなかが張り、ポッコリするとか、お通じが不規則で出にくいとか、臭いガスが出るとか、おなかに不快感、違和感を有しているとか、下痢をしやすい、あるいは、食後おなかの調子がとても悪いと答えています。これらは現代女性の腸内環境の実態がよくないということです。
誰もが経験しているような内容をこのような形で女性たちは、実際に自分たちのものにしてしまっているのです。さらに、あまり腸内環境は良くないと実感されている方はなんと全体の70%でした。悪いと認識の要因は、なんといっても肌の調子が悪いのです。つまり、内側を守る鎧の腸、そして外側を守る肌というのは、表裏一体の関係がありますので、腸の調子が悪くなると、肌の調子が悪くなるという訳です。
女性の場合は生理が始まるとどうしても便秘気味になり、あるいは、肌の調子が悪いということも経験あると思います。そういう状態が生まれてきますよということも知られていますし、もっとも、体重が増える、太ることにも腸内環境の悪さがあると感じられています。やっぱり食生活の悪さの結果は腸内環境を悪くしているかもしれないという状況がこういう段階で現れてきています。
また、生活が楽しくない、ストレスがたまるとか、病気の原因、つまり生活習慣病である様々な腸の疾患、全身の病気を含めて、原因を作ってしまっているという認識があるようです。
さらに、免疫力の低下。これは基本的には風邪を引きやすい、引いても治りにくいとか、疲れやすい。この免疫というのは非常に重要なキーワードであることを実感された3年間ではなかったでしょうか。腸内環境の悪化が、免疫力の低下、なぜかというと、腸が我々の免疫担当細胞の60~70%は腸に集約されています。ですから、腸の状態が悪いということは、免疫担当細胞の働きが低下してしまっているという事です。
さらに冷え性・血行障害にも影響あります。調査ですので、実際、実態はよくわからない部分もあると思いますけれども、基本的には腸内環境の悪化というのは、ご自分の健康状態を悪くしているという認識は皆さん持っていらっしゃるのです。
一方、ちょっと、リアルな話になりますけれど、でも、軟便あるいは下痢で苦しんでいるのが、なんと40代の男性たちです。
これは鬱とか、上からノルマ達成を言われて、下から突き上げられ、同時に家に帰っても疎まれている中間管理職の男性たち。ストレスと偏った食事、寝不足・運動不足が一番の原因です。やはり、軟便気味で出さなきゃ気が済まない「過敏性腸症候群」がという症状が出ています。
つまり、トイレがある場所を確認できないと安心して歩けない。ですから、どこのホテルのトイレがきれいか、落ち着くかということも罹患されている方々は実感されています。山手線内におけるどの駅のトイレがいいかということの認識も、今は実はアプリもありますので、そういうものを扱って、トイレという確認をするという状況です。
私はトイレがなければおちおち歩けないというので、トイレのない急行電車に乗れないというので、「各駅停車症候群」という名称を提唱いたしております。
ですから、男性は「各駅停車症候群」、女性は「週末トイレ症候群」、つまり、何を言いたいかというと、現在の日本人のそれこそトイレ事情は、「女はたまる。男はくだる。」という言葉で表現いたしております。
さらに、ちょっと、食事中申し訳ないのですが、毎日出す大便は何からできていると思いますか。
大抵、皆さん食べカスとお思いでしょうが、本当はそうじゃありません。大便の成分のなんと80%は、実は水なのです。のこりの20%が固形成分です。ですから、この固形成分中に含まれる食べカスは1/3にすぎません。残りの2/3ははがれた腸の粘液・腸粘膜や生きた腸内細菌でできているのです。
ちょっと、私の専門になりますけれども、腸に住む腸内細菌は大便1グラムあたり1兆個。さらに1000種類以上にもなります。さらに大腸内にいる細菌の重さは1.5キロとされています。大腸の壁(粘膜)の表面に粘着しております。これらをかき集めると、約、推定で1.5キロの重さがあると言われています。口腔内にも700~800グラムの細菌がいて、皮膚にも棲む細菌。女性では膣内にも細菌がおり、女性では2.5キロの細菌、男性では2.2キロの細菌を体内に有しているのです。ですから、マイナス2.2~2.5キロがあなたの本当の体重ですよというと喜ばれる方がいらっしゃるかもしれません。
腸内細菌というと、小腸と大腸の腸内ですね、ほとんどの細菌が好んで住むところは大腸です。
腸内細菌というと、あ、大腸菌、腸球菌、乳酸菌は知っているわと、あっ、そうだ、ビフィズス菌もいたねと言えば腸内細菌通です。ビフィズス菌も大腸内に住む細菌です。大腸内に棲む細菌の特徴は何かというと、酸素を嫌う。つまり、酸素の無い条件を作らないと生育できないない細菌が腸内細菌の99.99%はとされています。ですから、大腸内というのは酸素のない「暗黒世界」です。こういうところに住む様々な腸内細菌がどんな有害物質をつくり、直接大腸に障害を与えて、大腸の病気を起こします。大腸というのは、我々の臓器の中でもっとも病気の種類の多い臓器と言えます。大腸がん、大腸ポリープ、潰瘍性大腸炎、クローン病、大腸憩室症、過敏性腸症候群などさまざまな疾患名がつくのも大腸の特徴です。そこにはこの腸内細菌が棲むことにより、こういう状況を作っているのです。さらにこういう腸内細菌が作った発がん物質、発がん促進物質有害物質が血中を介して全身に蔓延すると内臓に障害を与えるのです。肝臓がんや乳がんもそうですけども、様々な疾患を作り出すのも大腸の住む腸内細菌なのです。
さらに、免疫能低下、免疫不全にも関与しています。さらにとか肥満や糖尿病にも関係することが報告されました。肥満というとなんとなく、食べすぎといわれますが、腸内細菌が肥満を促進する物質を産生あるいは痩せを抑制することも知られるようになっています。また、「腸脳相関」といって、腸内細菌が脳の機能にも関与することが強調されています。これは、自閉症と腸内細菌という関係が報告され、現在、認知症、アルツハいま―症などと腸内細菌の関係について研究・報告されています。やはり、様々な脳疾患発症が、腸内細菌の大きな働きをしているのです。同時に、我々の健康な体を作る上でも、大腸内にどんな細菌を棲まわせるのかが大切なのです。つまり、腸活を、腸内環境を整えるというのが腸活の基本なのですが、どのような菌を持つべきかという答えを出すのも大切なポイントの、これが腸活の基本視点です。
じゃ、ご自分で、自分の腸内環境をチェックすることができないのかというので、腸年齢チェックシートを作りました。
これは、1990年代後半に、オレンジページという雑誌社と組みまして、実は400人の女性から大便サンプルいただいて、ビフィズス菌の構成解析を行い、10項目の点検チェックを作って、どういう状況かというのを調べました。
以下の項目です。
□ 便秘気味(または時々下痢をする)。
□ 便が硬くて気持ちよく出ない。
□ 便の色が茶褐色や黒っぽい。
□ おならや排便後の臭いがきつい。
□ 野菜が嫌い。あまり食べない。
□ 肉食や外食が多い。
□ 牛乳や乳製品が苦手。
□ 運動不足が気になる。
□ 顔色が悪く、老けて見られる。
□ ストレスをいつも感じる。
何項目があてはまりますか?
すると、0個がもっともベストですが、6個以上ある人はもう腸年齢がけっぷちですよ、転げ落ちる寸前ですねということで、腸内環境を改善するということも、とても大事なポイントではないかということを提案しております。
以下が腸年齢チェックの判定です。
腸年齢の判定基準
◯が0個の人:腸年齢は若くてバッチリ合格!
◯が1~2個の人:腸年齢は若いのですが、あてはまる項目を無くしましょう。
◯が3~5個の人:腸年齢=実年齢+10歳, 腸年齢は実年齢より少し上。気を抜かないで生活の見直しを。
◯が6~8個の人:腸年齢=実年齢+20歳,腸年齢はがけっぷち。転げ落ちる寸前です。
◯が9個以上の人:腸年齢=実年齢+30歳腸年齢は老人状態。即, 快腸になる生活を開始。
さらに、この腸内チェックシートを500名について調べてみると、なんといっても野菜不足、肉が大好き、あるいはまた、運動不足とかストレスをいつも感じる、排便の時間が不規則とか、便が緩くなるということも出てきます。
さらに腸年齢が若いと肌のトラブルが少ない、同時に、脳や肌の衰えを感じないとか、あるいは脳の老化現象も顕在化しにくいと。腸内環境と脳の衰えとの関係では、腸内環境が悪い方ですけれども、何をするために行ったか忘れる。記憶障害と物忘れは違いますが、例えば人の名前すぐ出てこないとか、昨日の夜何食べたかすぐ出てこないとか。そういう状況、物忘れ的なものはないかどうか。あるいは会話に、「アレ、ソレ」の指示語ばかりで中身が全然伝わってないとか、ものをあちこちに置き忘れるとか、何を言ったか忘れるとか、簡単な計算ができないということが、やはり腸年齢が高ければ高いほど、その傾向は強いですという結果でした。
では、脳の機能を活性化するために大事なことは、よく話をする。よく、あの、べらべら自分のことばっかり話す人いますけれども、そうではなくて、よく話を聞くという、聞いて、聞いて、ちょっとだけ意見を言う。この状態がもっともベストです。相手の意見をよく聞いて、平行線、あるいは通じないとチェックするということで、脳の活性が保たれるのです。
よく歩く、日野原先生は75歳以上を新老人として定義して、75歳以上の人のクラブ、これには、7~8000人くらい会員がおられますが、その中で、400名を10年間フォローアップして、調べたところ、歩くスピードが速いと、毎日どこか出かけて、約30,40%の人は毎日どこか出かけて、徘徊じゃないですよ、きちんとこういう会ができて、いろんな意見を聞いてまとめていらっしゃる、そしてその運動の結果、よく眠れるということと、やはり、皆様と同じように夢を持つということもとても大事な脳の活性化でしっかり繋がっています。
さらにエイジングと関係があるのは、なんといっても体力・気力が若い傾向にあるとか、あるいは、腸年齢若いとプロバイオティクスと言われる健康に良い働きをする生きた微生物、あるいは野菜、食物繊維を多く摂っているということも特徴的です。
いいウンチをデザインするには、プロバイオティクスと食物繊維、これは実際には、一番大事なのは毎日、トイレで「どのようなウンチを出してますか」です。その観察の基本ですが、その色やにおいを観察すると、大体ビフィズス菌や酪酸産生菌の活性化がありますよと。この二つの菌はとても大事なポイントで、2018年に私はこの二つを「長寿菌」と提唱いたしました。これは、全国の長寿地域に入って、実際に高齢老人たちの食生活の調査および大便をいただいて腸内細菌を調べた結果、長寿菌がとても多かったのです。ですから、食物繊維を豊富に摂る食生活と運動(農作業)のライフスタイルが長寿菌の多い腸内環境を作り出されて、元気な営みをされているのです。
最近では、プロバイオティクスという健康に良い働きする生きた微生物の機能として、大腸がんの低減、アレルギー、アトピー性皮膚炎や花粉症症状の軽減、コレステロール低下作用、あるいは口腔内疾患、胃内ピロリ菌を防ぐ作用、インフルエンザ感染予防効果ということも実際に報告されてきました。可能な限り健康にいい働きをする生きた微生物を含む食品を摂っていただくのも一つの手かと思います。
さらに、食物繊維は腸内の酪酸産生菌の酪酸産生能を活性化させる働きを有しております。そして、大腸がんの予防、水分保持ということで、なるべく早く排泄されるという意味においても肥満予防や大腸憩室の予防効果、あるいはコレステロールの吸収抑制という働きを持っているということもよく知られています。ですから、食物繊維を多く摂るということ、野菜や、キノコ類、豆類、あるいは海藻類ということもとても大事なことです。
そして、体に優しい腸活促進の理由は、免疫が高まり、アレルギーや風邪をブロックします。短鎖脂肪酸これは酪酸ですが、ストレスに強くなること、あるいは代謝が促進されて太りにくい美ボディができます。あるいは肌、メンタル、脳も若々しく、アンチエイジングに大きな効果があるのです。さらに皮膚の機能もアップして肌荒れが起こりにくくすることも期待できます。このように腸活促進効果が様々な病気を起こさせないことに繋がると思います。
さらに、その実践するにはどうしたらいいかというと、三食ごとに食物繊維を含む野菜、海藻、発酵食品を摂ることも大事ですよと。また、便意を感じたらすぐトイレに行ってお通じをチェックしましょう。1日1.5リットルの、ま、目安、水ですね、こまめに水分を摂ろうということも大事です。1日30~60分のウォーキング。30分で大体3000歩、60分で6000歩、健康日本では9000歩以上のウォーキングを勧めています。家庭・職場で大体3000歩くらい歩いておられます。あと30分くらいご自分で意識的に歩いていくことによって、そのウォーキングタイムの取り入れが可能です。
あるいはリラックスが勝るものはありません。趣味の時間を大切にすること。そして最後になんといっても平均的な睡眠時間7時間を、ま、睡眠を理想。やはり睡眠をとることによって疲れが取れるということもありますので、睡眠環境を整えて、腸活生活を進めてほしいということもあります。
理想的なウンチを得るためには、3つのウンチ力の実践です。まずうんちをつくる力、何を食べればよく出るだろうか、今日は調子いいなと思うと、前日何を食べたのかということを調べると、あの食品を摂ると私にとってはいいんだという、一つの方程式を自ら立ち上げてくこともとても大事ではないでしょうか。次はうんちを育てる力。これは腸内のいわば長寿菌といわれるビフィズス菌や酪酸産生菌を活性化するということで、実際に健康の源はそこにあるです。最後に一番大事なのはうんちを出す力は運動です。腸腰筋・腸骨筋と呼ばれるインナーマッスルをどう鍛えるかということもとても大事なポイントです。
そして最後に、どのようなものを出せばいいのかという一つの話で。硬さ、これはほどよい硬さというのはトイレで座ると気持ちよく、ストーンストーンと出るうんちの成分の80%が水なのがもっとも理想的なものです。たとえ便秘をしても70~75%は水分含んでいますから、そういう点においても頑張って出していただければ良いでしょう。そしてあんまり臭くない。トイレの後、臭いというのは、あるいはおならが臭いというのは危険信号です。ですから、実際にはあまり臭わない、赤ん坊のうんちの匂いというのは、いわゆる酸っぱいです。なぜかというと、赤ん坊のうんちの中の腸内細菌はビフィズス菌が80%を占めているからです。ビフィズス菌は酢酸と乳酸を産生しますから、いわゆる酸っぱい匂いがするのです。あるいは、色は、だまされたと思ってヨーグルトを300グラム以上摂ってみてください。そうすると、黄色から黄褐色、そこには腸内のビフィズス菌が多数住んでいることは事実です。
男性で250~300グラム、女性では、200~250グラムの大便、一日の排便量があればもっとも理想的です。どうやって測るかというと、体重計をね、トイレ前に置くのです。行く前と行った後を引けば、大体風袋の重さ見えますから、そういう点において、今日は花丸マーク、今日は二重丸、今日は〇、今日は三角、バッテンと。1週間に何キロ出したのか、私たちは年間で1トン出しますので、80年間で80トンの排便、うんち出していますが、そういう意味においてトイレで出したものをチェックする習慣が大切です。毎日お世話になっている便所とは便器のあるところを便所と言いますが、本当は便所とは体からのお便りを受け取る「お便り所」なのです。
で、自分の体の健康を知る、トイレこそ、まさに、自分の、ご自分でチェックできる基本だということをよく認識をもってもらえればいいと思います。私自身も2万名以上の腸内細菌を調べてきましたけれども、日本人、全国の日本人の腸内細菌調べていると、やはりこういうことを言えることは、逆に言えば、日ごろから自分が出したものをチェックする習慣があるかどうかということも大事なポイントです。
まとめますと、大腸を健康の、病気の発生源でなしに、健康の発信源に変えましょうと。私たちの臓器の中で一番コントロールできるのは大腸しかありません。ですから、そこをどのような食物残渣物を送り込むのか、どのような運動すれば、うまく出るのかということも振り返ってみることも大事なのです。
腸年齢の老化、つまり健康寿命の短命化というのは、偏った食事、ストレス、運動不足が原因ですよと。長寿菌が健康長寿に貢献していることをよーく認識持っていただければいいと思います。カラダを強くする腸活生活の実践そのものが、ご自分の健康長寿を目指す大きな力になることも間違いないでしょう。つまり、大腸をどのようにコントロールするか、ここが大きなポイントです。
そして、最後に、トイレに出したものを見ないで流してしまうのはもったいないと。毎日うんちチェック、つまり見返り美人が腸美人ですという風に言われているように、やはり見返ったときに、初めてご自分の、あるいはトイレ見てみたいけども勝手に流れてしまうわという方いらっしゃいます。大丈夫です。右手に使用したティッシュを左手で便座を押さえれば流れません。ですから、ますます、顔が近づくと観察できる、あるいは観察しようとする心が生まれてくるのではないでしょうか。そういう意味で、トイレで出るものもの情報はとても大事なポイントです。つまり長寿菌が教えてくれる健康長寿、そして、健康長寿の100歳を目指す腸活生活の実践と。このことはやはり、健康の源の今日の話の中心にならざるを得ないと思います。そして、最後は何といっても、「腸を制することは健康を制する」ことですよということをお伝えして、卓話を終わりたいと思います。
どうもご清聴ありがとうございました。
Q&A
Q: 辨野先生本日はお話ありがとうございました。 あの、前々からちょっと気になっていたんですけれども、ヨーグルトを食べると腸の動きがよくなるということで、食べていましたが、実は胃酸などで死滅するのでヨーグルトはあまり効果がないと話聞いたことがあるんですけど、その点についてどのように。
A: ありがとうございます。 それはまったく嘘です。ヨーグルトに使われた菌は耐酸性、耐胆汁性をもった菌株が選ばれています。だから、それを知らないので胃酸で全部死んでしまいます、だから、だめなんですと言われる方もおられますが、実態をご存じないのだ思います。
さらにヨーグルトや乳酸菌飲料は乳等省令といって法律で決められていて、賞味期限2週間以内に、商品中にきちんとした菌株がいるということと、投与された菌株が、たとえばトクホ食品では、投与した菌が大腸に達しますということを証明しないとトクホ取れないんですよ。
僕はトクホのときに言ったのは、入れたとき、便性改善とそれから腸内のビフィズス菌が増えるということ、有害物質が減るということを調べなさい。そしてそれを飲んだ時に、その菌が大腸にすべてでなくても達しますということを証明しないと、この4点を出さないとトクホ取れませんという制度を僕は作りました。ま、メーカーにとっては非常に厳しい条件でしたが、トクホマークがついている商品に関しては、それはもう全然問題ないと思いますし、
あるいはA社の食べてダメだったら、次はB社に、C社になると、あなたの相性のある商品がありますよということを言う先生がいるんですが、実は私もそう言ってたんだけども、ある先生に言ったら、君がそう言ってたんだろと怒られましたが、そんな試験、誰もしたことありません。
僕が森永を食べて、次、明治を食べて、そして変わったかという試験は誰もしないんですよ、したことないんですよね。
だから、そういうことは、相性があるということは当然考えられません。
確かに、効果は、むしろヨーグルトじゃなしに、食物繊維を多く摂る。
言いましたように、50%は運動です。40%は食物繊維です。あと10%は発酵食品、ヨーグルトや乳酸菌飲料、あるいは納豆とか麹があるかもしれません。そういう発酵食品を摂る。この5対4対1の割合で摂っていただけると、良い腸内環境、つまり健康長寿に向かう腸活の基本の食生活ができるのではないでしょうか。
ま、基本的にライフスタイル全体で考えたときに、食事の摂り方、運動の実践が大切です。本日、最初に、体操されたときにびっくりしたんですが、非常に良い体操だったので、実は、10月の初めに、福岡で吉本さんという「筋肉は裏切らない」という、今、順天堂大学の准教授ですけども、彼とちょっとコラボありました。そこでも腸腰筋をいかに鍛えるかということで、新しい手法も彼が考えてくれて、非常に日本人の健康のありかたにしても運動というのは大事なんですね。
できれば、ウォーキングというのは、1日に60分くらいしていただけると、より良い腸内環境になるだろうと。
だけど、同時にどんなものを出しているか、出そうとしているか、うんちをデザインするんですよ。デザインすることがとても大事なポイントだということで、健康の源、まさに腸を制するものは健康を制すると申しましたけれども、結局的には大腸の状態をどうコントロールするか、一番コントロールしやすい場所ですのでそれを実行していただければいいなと思います。
ちょっと尾ひれがついて長くなりましたけれども申し訳ありません。
以上です。
ただいま紹介いただきました辨野腸内フローラ研究所の辨野と申します。
これまで、理化学研究所に48年間(1973年から2021年まで)、お世話になっておりました。2009年に理研より定年退職後、企業からの研究資金提供と研究者の派遣していただいて、特別研究室を主宰する特別招聘研究員として、引き続き研究活動を12年間させて頂きました。その期間終了後、社会のため、人々のために貢献する目的で、財団法人を設立させて頂いて、研究・啓発活動する事を続行しなさいという形で、今現在に至っております。
生まれは昭和23年ですので、只今75歳。後期高齢者でございます。今なお、研究に対する意欲、ま、生涯、腸内細菌研究を続けていこうという決意と共に、次の若い世代をいかに育成していくかということを中心に、仕事を進めさせていただいております。
理研に在職中は様々なサポートしていただき、大好きな腸内細菌の分類と生態に関する研究に夢中になって過ごさせていただいてまいりました。理研を卒業して財団法人を立ち上げてみますと、いかに娑婆が厳しいかということを身の肌に感じております。財団法人という研究所運営に必要な資金確保ために収益事業や公益事業も展開せざるを得ず、日々休むことなく、ま、今日に至っております。
今日もこういう会に呼んでいただきまして、ほんと、あの、食事中で、どういう設定なのか、私も苦しみましたが・・(笑い)。もう、名前が辨野(べんの)という名前で、皆さん、「えっ!」と思われるでしょう?実は本名でございまして、大阪は枚方というところで生まれて、育ちました。辨野という姓の人口は、120人くらいだそうです。たぶん半数近くは私の親戚ですが、あと半数はまったく親戚じゃない辨野さんもいらっしゃるそうです。
本日の講演内容はすでに単行本として多数、上梓しております。どれか1冊買っていただければ、内容もさらにご理解が深まるものと期待しております。実は最近、幻冬舎から上梓しました『大便革命』が中国語版で出版されるようです。中国語で発刊されば、さらなる展開も望まれと切望しております。
卓話の内容は、健康長寿、どうのようにすれば健康で長生きできる、できるっていうか、していこうとする姿勢にどのようにつなげていけばいいかという事をご理解していただこうという試みです。準備させていだきましたレジメに書かせていただきました。
以下についてお話させていただけたらと思います。
健康長寿を目指す最高の腸活
1)女はたまる。男はくだる。
2)大腸は病気の発生源。
3)あなたの腸は何歳ですか?
4)カラダを強くする最高の腸活実践
実は腸活という言葉ですが、これ90年代後半に腸内フローラ、腸年齢、菌活、腸活という言葉を私どもの研究室から発した言葉でございまして。なじみのある言葉と思います。なぜ腸活と言うかというと、いかに良い腸内環境に保つかが健康長寿に結びつくのです。
本日は食事中ですが、大便や腸内細菌の内容ですので、本当に、この内容でいいのかと悩みました。つまり、食べたものがいつ排便されるかという「うんちくの話」なのです。そういう話をさせていただきますけど、なるべく臭い話はしないように、心がけますけれども、つい日ごろからそういう言葉を使っているので、ぽろぽろと出てしまうような、少し心配ですが・・。
唐突ですが、便秘について説明しますと、医学的に3日以上出ないことを便秘あるいは便秘症と定義づけられております。そこで、健康とされる女性約2000名に排便に関する調査しますと、48%半数の方が便秘!その内の65%、5日に1回しか出さないのです。つまり、月曜から金曜日出さなくて、土日を使って出しているという結果を得ることができました。これを名付けて、「週末トイレ症候群」という表現にいたしました。どういう方が多いかというと、ほとんど若い女性たち、20代の女性たちが2人に1人は便秘です。また、10代ですら10名中3名は便秘なのです。小さい頃から便秘で、もう諦めきっている女性たちの姿というのが見えてきますよ。
その要因は何かというと、なんといっても偏った食事。肉が大好きだから肉だけを食べている。野菜を摂らないようなライフスタイルが日本人の女性たちの腸内環境を悪くしていると言えます(直腸性便秘)。あるいは運動不足から来る便秘です。出したけれどもまだ出し切れていない気がする状況です(弛緩性便秘)。
さらに、ストレスからくる便秘、これは、なんとなく、トイレ見るとパラパラ分かれたようなうんちが出てる状態を、ウサギのような糞、兎糞(とふん)と言われます。これはストレスからくる便秘で、痙攣(けいれん)性便秘です。
さらに、女性に多いのですが痩せていたい、スマートでいたいというので、ダイエットをしてしまうと。食べる量が少ないので出す量も少なくなっています。日本人女性の腸内環境を作っているということもよく知られています。
運動でもインナーマッスル(腸腰筋と腸骨筋)を鍛えるのは、やっぱり筋力、運動の活力なのです。ですから、これも排便に大きな影響与えますということも理解していただければ、運動も、非常に重要な働きがあるのです。
ところで、30代40代の女性500名に腸内環境調査をしますと、なんと95%の人たちは、腸の調子が悪いと答えておられます。どういうことかでいうと、便秘じゃありませんよ、おなかが張り、ポッコリするとか、お通じが不規則で出にくいとか、臭いガスが出るとか、おなかに不快感、違和感を有しているとか、下痢をしやすい、あるいは、食後おなかの調子がとても悪いと答えています。これらは現代女性の腸内環境の実態がよくないということです。
誰もが経験しているような内容をこのような形で女性たちは、実際に自分たちのものにしてしまっているのです。さらに、あまり腸内環境は良くないと実感されている方はなんと全体の70%でした。悪いと認識の要因は、なんといっても肌の調子が悪いのです。つまり、内側を守る鎧の腸、そして外側を守る肌というのは、表裏一体の関係がありますので、腸の調子が悪くなると、肌の調子が悪くなるという訳です。
女性の場合は生理が始まるとどうしても便秘気味になり、あるいは、肌の調子が悪いということも経験あると思います。そういう状態が生まれてきますよということも知られていますし、もっとも、体重が増える、太ることにも腸内環境の悪さがあると感じられています。やっぱり食生活の悪さの結果は腸内環境を悪くしているかもしれないという状況がこういう段階で現れてきています。
また、生活が楽しくない、ストレスがたまるとか、病気の原因、つまり生活習慣病である様々な腸の疾患、全身の病気を含めて、原因を作ってしまっているという認識があるようです。
さらに、免疫力の低下。これは基本的には風邪を引きやすい、引いても治りにくいとか、疲れやすい。この免疫というのは非常に重要なキーワードであることを実感された3年間ではなかったでしょうか。腸内環境の悪化が、免疫力の低下、なぜかというと、腸が我々の免疫担当細胞の60~70%は腸に集約されています。ですから、腸の状態が悪いということは、免疫担当細胞の働きが低下してしまっているという事です。
さらに冷え性・血行障害にも影響あります。調査ですので、実際、実態はよくわからない部分もあると思いますけれども、基本的には腸内環境の悪化というのは、ご自分の健康状態を悪くしているという認識は皆さん持っていらっしゃるのです。
一方、ちょっと、リアルな話になりますけれど、でも、軟便あるいは下痢で苦しんでいるのが、なんと40代の男性たちです。
これは鬱とか、上からノルマ達成を言われて、下から突き上げられ、同時に家に帰っても疎まれている中間管理職の男性たち。ストレスと偏った食事、寝不足・運動不足が一番の原因です。やはり、軟便気味で出さなきゃ気が済まない「過敏性腸症候群」がという症状が出ています。
つまり、トイレがある場所を確認できないと安心して歩けない。ですから、どこのホテルのトイレがきれいか、落ち着くかということも罹患されている方々は実感されています。山手線内におけるどの駅のトイレがいいかということの認識も、今は実はアプリもありますので、そういうものを扱って、トイレという確認をするという状況です。
私はトイレがなければおちおち歩けないというので、トイレのない急行電車に乗れないというので、「各駅停車症候群」という名称を提唱いたしております。
ですから、男性は「各駅停車症候群」、女性は「週末トイレ症候群」、つまり、何を言いたいかというと、現在の日本人のそれこそトイレ事情は、「女はたまる。男はくだる。」という言葉で表現いたしております。
さらに、ちょっと、食事中申し訳ないのですが、毎日出す大便は何からできていると思いますか。
大抵、皆さん食べカスとお思いでしょうが、本当はそうじゃありません。大便の成分のなんと80%は、実は水なのです。のこりの20%が固形成分です。ですから、この固形成分中に含まれる食べカスは1/3にすぎません。残りの2/3ははがれた腸の粘液・腸粘膜や生きた腸内細菌でできているのです。
ちょっと、私の専門になりますけれども、腸に住む腸内細菌は大便1グラムあたり1兆個。さらに1000種類以上にもなります。さらに大腸内にいる細菌の重さは1.5キロとされています。大腸の壁(粘膜)の表面に粘着しております。これらをかき集めると、約、推定で1.5キロの重さがあると言われています。口腔内にも700~800グラムの細菌がいて、皮膚にも棲む細菌。女性では膣内にも細菌がおり、女性では2.5キロの細菌、男性では2.2キロの細菌を体内に有しているのです。ですから、マイナス2.2~2.5キロがあなたの本当の体重ですよというと喜ばれる方がいらっしゃるかもしれません。
腸内細菌というと、小腸と大腸の腸内ですね、ほとんどの細菌が好んで住むところは大腸です。
腸内細菌というと、あ、大腸菌、腸球菌、乳酸菌は知っているわと、あっ、そうだ、ビフィズス菌もいたねと言えば腸内細菌通です。ビフィズス菌も大腸内に住む細菌です。大腸内に棲む細菌の特徴は何かというと、酸素を嫌う。つまり、酸素の無い条件を作らないと生育できないない細菌が腸内細菌の99.99%はとされています。ですから、大腸内というのは酸素のない「暗黒世界」です。こういうところに住む様々な腸内細菌がどんな有害物質をつくり、直接大腸に障害を与えて、大腸の病気を起こします。大腸というのは、我々の臓器の中でもっとも病気の種類の多い臓器と言えます。大腸がん、大腸ポリープ、潰瘍性大腸炎、クローン病、大腸憩室症、過敏性腸症候群などさまざまな疾患名がつくのも大腸の特徴です。そこにはこの腸内細菌が棲むことにより、こういう状況を作っているのです。さらにこういう腸内細菌が作った発がん物質、発がん促進物質有害物質が血中を介して全身に蔓延すると内臓に障害を与えるのです。肝臓がんや乳がんもそうですけども、様々な疾患を作り出すのも大腸の住む腸内細菌なのです。
さらに、免疫能低下、免疫不全にも関与しています。さらにとか肥満や糖尿病にも関係することが報告されました。肥満というとなんとなく、食べすぎといわれますが、腸内細菌が肥満を促進する物質を産生あるいは痩せを抑制することも知られるようになっています。また、「腸脳相関」といって、腸内細菌が脳の機能にも関与することが強調されています。これは、自閉症と腸内細菌という関係が報告され、現在、認知症、アルツハいま―症などと腸内細菌の関係について研究・報告されています。やはり、様々な脳疾患発症が、腸内細菌の大きな働きをしているのです。同時に、我々の健康な体を作る上でも、大腸内にどんな細菌を棲まわせるのかが大切なのです。つまり、腸活を、腸内環境を整えるというのが腸活の基本なのですが、どのような菌を持つべきかという答えを出すのも大切なポイントの、これが腸活の基本視点です。
じゃ、ご自分で、自分の腸内環境をチェックすることができないのかというので、腸年齢チェックシートを作りました。
これは、1990年代後半に、オレンジページという雑誌社と組みまして、実は400人の女性から大便サンプルいただいて、ビフィズス菌の構成解析を行い、10項目の点検チェックを作って、どういう状況かというのを調べました。
以下の項目です。
□ 便秘気味(または時々下痢をする)。
□ 便が硬くて気持ちよく出ない。
□ 便の色が茶褐色や黒っぽい。
□ おならや排便後の臭いがきつい。
□ 野菜が嫌い。あまり食べない。
□ 肉食や外食が多い。
□ 牛乳や乳製品が苦手。
□ 運動不足が気になる。
□ 顔色が悪く、老けて見られる。
□ ストレスをいつも感じる。
何項目があてはまりますか?
すると、0個がもっともベストですが、6個以上ある人はもう腸年齢がけっぷちですよ、転げ落ちる寸前ですねということで、腸内環境を改善するということも、とても大事なポイントではないかということを提案しております。
以下が腸年齢チェックの判定です。
腸年齢の判定基準
◯が0個の人:腸年齢は若くてバッチリ合格!
◯が1~2個の人:腸年齢は若いのですが、あてはまる項目を無くしましょう。
◯が3~5個の人:腸年齢=実年齢+10歳, 腸年齢は実年齢より少し上。気を抜かないで生活の見直しを。
◯が6~8個の人:腸年齢=実年齢+20歳,腸年齢はがけっぷち。転げ落ちる寸前です。
◯が9個以上の人:腸年齢=実年齢+30歳腸年齢は老人状態。即, 快腸になる生活を開始。
さらに、この腸内チェックシートを500名について調べてみると、なんといっても野菜不足、肉が大好き、あるいはまた、運動不足とかストレスをいつも感じる、排便の時間が不規則とか、便が緩くなるということも出てきます。
さらに腸年齢が若いと肌のトラブルが少ない、同時に、脳や肌の衰えを感じないとか、あるいは脳の老化現象も顕在化しにくいと。腸内環境と脳の衰えとの関係では、腸内環境が悪い方ですけれども、何をするために行ったか忘れる。記憶障害と物忘れは違いますが、例えば人の名前すぐ出てこないとか、昨日の夜何食べたかすぐ出てこないとか。そういう状況、物忘れ的なものはないかどうか。あるいは会話に、「アレ、ソレ」の指示語ばかりで中身が全然伝わってないとか、ものをあちこちに置き忘れるとか、何を言ったか忘れるとか、簡単な計算ができないということが、やはり腸年齢が高ければ高いほど、その傾向は強いですという結果でした。
では、脳の機能を活性化するために大事なことは、よく話をする。よく、あの、べらべら自分のことばっかり話す人いますけれども、そうではなくて、よく話を聞くという、聞いて、聞いて、ちょっとだけ意見を言う。この状態がもっともベストです。相手の意見をよく聞いて、平行線、あるいは通じないとチェックするということで、脳の活性が保たれるのです。
よく歩く、日野原先生は75歳以上を新老人として定義して、75歳以上の人のクラブ、これには、7~8000人くらい会員がおられますが、その中で、400名を10年間フォローアップして、調べたところ、歩くスピードが速いと、毎日どこか出かけて、約30,40%の人は毎日どこか出かけて、徘徊じゃないですよ、きちんとこういう会ができて、いろんな意見を聞いてまとめていらっしゃる、そしてその運動の結果、よく眠れるということと、やはり、皆様と同じように夢を持つということもとても大事な脳の活性化でしっかり繋がっています。
さらにエイジングと関係があるのは、なんといっても体力・気力が若い傾向にあるとか、あるいは、腸年齢若いとプロバイオティクスと言われる健康に良い働きをする生きた微生物、あるいは野菜、食物繊維を多く摂っているということも特徴的です。
いいウンチをデザインするには、プロバイオティクスと食物繊維、これは実際には、一番大事なのは毎日、トイレで「どのようなウンチを出してますか」です。その観察の基本ですが、その色やにおいを観察すると、大体ビフィズス菌や酪酸産生菌の活性化がありますよと。この二つの菌はとても大事なポイントで、2018年に私はこの二つを「長寿菌」と提唱いたしました。これは、全国の長寿地域に入って、実際に高齢老人たちの食生活の調査および大便をいただいて腸内細菌を調べた結果、長寿菌がとても多かったのです。ですから、食物繊維を豊富に摂る食生活と運動(農作業)のライフスタイルが長寿菌の多い腸内環境を作り出されて、元気な営みをされているのです。
最近では、プロバイオティクスという健康に良い働きする生きた微生物の機能として、大腸がんの低減、アレルギー、アトピー性皮膚炎や花粉症症状の軽減、コレステロール低下作用、あるいは口腔内疾患、胃内ピロリ菌を防ぐ作用、インフルエンザ感染予防効果ということも実際に報告されてきました。可能な限り健康にいい働きをする生きた微生物を含む食品を摂っていただくのも一つの手かと思います。
さらに、食物繊維は腸内の酪酸産生菌の酪酸産生能を活性化させる働きを有しております。そして、大腸がんの予防、水分保持ということで、なるべく早く排泄されるという意味においても肥満予防や大腸憩室の予防効果、あるいはコレステロールの吸収抑制という働きを持っているということもよく知られています。ですから、食物繊維を多く摂るということ、野菜や、キノコ類、豆類、あるいは海藻類ということもとても大事なことです。
そして、体に優しい腸活促進の理由は、免疫が高まり、アレルギーや風邪をブロックします。短鎖脂肪酸これは酪酸ですが、ストレスに強くなること、あるいは代謝が促進されて太りにくい美ボディができます。あるいは肌、メンタル、脳も若々しく、アンチエイジングに大きな効果があるのです。さらに皮膚の機能もアップして肌荒れが起こりにくくすることも期待できます。このように腸活促進効果が様々な病気を起こさせないことに繋がると思います。
さらに、その実践するにはどうしたらいいかというと、三食ごとに食物繊維を含む野菜、海藻、発酵食品を摂ることも大事ですよと。また、便意を感じたらすぐトイレに行ってお通じをチェックしましょう。1日1.5リットルの、ま、目安、水ですね、こまめに水分を摂ろうということも大事です。1日30~60分のウォーキング。30分で大体3000歩、60分で6000歩、健康日本では9000歩以上のウォーキングを勧めています。家庭・職場で大体3000歩くらい歩いておられます。あと30分くらいご自分で意識的に歩いていくことによって、そのウォーキングタイムの取り入れが可能です。
あるいはリラックスが勝るものはありません。趣味の時間を大切にすること。そして最後になんといっても平均的な睡眠時間7時間を、ま、睡眠を理想。やはり睡眠をとることによって疲れが取れるということもありますので、睡眠環境を整えて、腸活生活を進めてほしいということもあります。
理想的なウンチを得るためには、3つのウンチ力の実践です。まずうんちをつくる力、何を食べればよく出るだろうか、今日は調子いいなと思うと、前日何を食べたのかということを調べると、あの食品を摂ると私にとってはいいんだという、一つの方程式を自ら立ち上げてくこともとても大事ではないでしょうか。次はうんちを育てる力。これは腸内のいわば長寿菌といわれるビフィズス菌や酪酸産生菌を活性化するということで、実際に健康の源はそこにあるです。最後に一番大事なのはうんちを出す力は運動です。腸腰筋・腸骨筋と呼ばれるインナーマッスルをどう鍛えるかということもとても大事なポイントです。
そして最後に、どのようなものを出せばいいのかという一つの話で。硬さ、これはほどよい硬さというのはトイレで座ると気持ちよく、ストーンストーンと出るうんちの成分の80%が水なのがもっとも理想的なものです。たとえ便秘をしても70~75%は水分含んでいますから、そういう点においても頑張って出していただければ良いでしょう。そしてあんまり臭くない。トイレの後、臭いというのは、あるいはおならが臭いというのは危険信号です。ですから、実際にはあまり臭わない、赤ん坊のうんちの匂いというのは、いわゆる酸っぱいです。なぜかというと、赤ん坊のうんちの中の腸内細菌はビフィズス菌が80%を占めているからです。ビフィズス菌は酢酸と乳酸を産生しますから、いわゆる酸っぱい匂いがするのです。あるいは、色は、だまされたと思ってヨーグルトを300グラム以上摂ってみてください。そうすると、黄色から黄褐色、そこには腸内のビフィズス菌が多数住んでいることは事実です。
男性で250~300グラム、女性では、200~250グラムの大便、一日の排便量があればもっとも理想的です。どうやって測るかというと、体重計をね、トイレ前に置くのです。行く前と行った後を引けば、大体風袋の重さ見えますから、そういう点において、今日は花丸マーク、今日は二重丸、今日は〇、今日は三角、バッテンと。1週間に何キロ出したのか、私たちは年間で1トン出しますので、80年間で80トンの排便、うんち出していますが、そういう意味においてトイレで出したものをチェックする習慣が大切です。毎日お世話になっている便所とは便器のあるところを便所と言いますが、本当は便所とは体からのお便りを受け取る「お便り所」なのです。
で、自分の体の健康を知る、トイレこそ、まさに、自分の、ご自分でチェックできる基本だということをよく認識をもってもらえればいいと思います。私自身も2万名以上の腸内細菌を調べてきましたけれども、日本人、全国の日本人の腸内細菌調べていると、やはりこういうことを言えることは、逆に言えば、日ごろから自分が出したものをチェックする習慣があるかどうかということも大事なポイントです。
まとめますと、大腸を健康の、病気の発生源でなしに、健康の発信源に変えましょうと。私たちの臓器の中で一番コントロールできるのは大腸しかありません。ですから、そこをどのような食物残渣物を送り込むのか、どのような運動すれば、うまく出るのかということも振り返ってみることも大事なのです。
腸年齢の老化、つまり健康寿命の短命化というのは、偏った食事、ストレス、運動不足が原因ですよと。長寿菌が健康長寿に貢献していることをよーく認識持っていただければいいと思います。カラダを強くする腸活生活の実践そのものが、ご自分の健康長寿を目指す大きな力になることも間違いないでしょう。つまり、大腸をどのようにコントロールするか、ここが大きなポイントです。
そして、最後に、トイレに出したものを見ないで流してしまうのはもったいないと。毎日うんちチェック、つまり見返り美人が腸美人ですという風に言われているように、やはり見返ったときに、初めてご自分の、あるいはトイレ見てみたいけども勝手に流れてしまうわという方いらっしゃいます。大丈夫です。右手に使用したティッシュを左手で便座を押さえれば流れません。ですから、ますます、顔が近づくと観察できる、あるいは観察しようとする心が生まれてくるのではないでしょうか。そういう意味で、トイレで出るものもの情報はとても大事なポイントです。つまり長寿菌が教えてくれる健康長寿、そして、健康長寿の100歳を目指す腸活生活の実践と。このことはやはり、健康の源の今日の話の中心にならざるを得ないと思います。そして、最後は何といっても、「腸を制することは健康を制する」ことですよということをお伝えして、卓話を終わりたいと思います。
どうもご清聴ありがとうございました。
Q&A
Q: 辨野先生本日はお話ありがとうございました。 あの、前々からちょっと気になっていたんですけれども、ヨーグルトを食べると腸の動きがよくなるということで、食べていましたが、実は胃酸などで死滅するのでヨーグルトはあまり効果がないと話聞いたことがあるんですけど、その点についてどのように。
A: ありがとうございます。 それはまったく嘘です。ヨーグルトに使われた菌は耐酸性、耐胆汁性をもった菌株が選ばれています。だから、それを知らないので胃酸で全部死んでしまいます、だから、だめなんですと言われる方もおられますが、実態をご存じないのだ思います。
さらにヨーグルトや乳酸菌飲料は乳等省令といって法律で決められていて、賞味期限2週間以内に、商品中にきちんとした菌株がいるということと、投与された菌株が、たとえばトクホ食品では、投与した菌が大腸に達しますということを証明しないとトクホ取れないんですよ。
僕はトクホのときに言ったのは、入れたとき、便性改善とそれから腸内のビフィズス菌が増えるということ、有害物質が減るということを調べなさい。そしてそれを飲んだ時に、その菌が大腸にすべてでなくても達しますということを証明しないと、この4点を出さないとトクホ取れませんという制度を僕は作りました。ま、メーカーにとっては非常に厳しい条件でしたが、トクホマークがついている商品に関しては、それはもう全然問題ないと思いますし、
あるいはA社の食べてダメだったら、次はB社に、C社になると、あなたの相性のある商品がありますよということを言う先生がいるんですが、実は私もそう言ってたんだけども、ある先生に言ったら、君がそう言ってたんだろと怒られましたが、そんな試験、誰もしたことありません。
僕が森永を食べて、次、明治を食べて、そして変わったかという試験は誰もしないんですよ、したことないんですよね。
だから、そういうことは、相性があるということは当然考えられません。
確かに、効果は、むしろヨーグルトじゃなしに、食物繊維を多く摂る。
言いましたように、50%は運動です。40%は食物繊維です。あと10%は発酵食品、ヨーグルトや乳酸菌飲料、あるいは納豆とか麹があるかもしれません。そういう発酵食品を摂る。この5対4対1の割合で摂っていただけると、良い腸内環境、つまり健康長寿に向かう腸活の基本の食生活ができるのではないでしょうか。
ま、基本的にライフスタイル全体で考えたときに、食事の摂り方、運動の実践が大切です。本日、最初に、体操されたときにびっくりしたんですが、非常に良い体操だったので、実は、10月の初めに、福岡で吉本さんという「筋肉は裏切らない」という、今、順天堂大学の准教授ですけども、彼とちょっとコラボありました。そこでも腸腰筋をいかに鍛えるかということで、新しい手法も彼が考えてくれて、非常に日本人の健康のありかたにしても運動というのは大事なんですね。
できれば、ウォーキングというのは、1日に60分くらいしていただけると、より良い腸内環境になるだろうと。
だけど、同時にどんなものを出しているか、出そうとしているか、うんちをデザインするんですよ。デザインすることがとても大事なポイントだということで、健康の源、まさに腸を制するものは健康を制すると申しましたけれども、結局的には大腸の状態をどうコントロールするか、一番コントロールしやすい場所ですのでそれを実行していただければいいなと思います。
ちょっと尾ひれがついて長くなりましたけれども申し訳ありません。
以上です。
卓話「どくとるマンボウ家のてんやわんや―イキイキと健康に生きるコツ」
エッセイスト/サントリー社員 斎藤由香さま
2023年10月12日

 ご紹介いただきましてありがとうございます。サントリーの斎藤由香でございます。
皆様、作家の家というと素敵なおうちと勘違いされると思いますが、実は父が躁病、うつ病になり、一家破産、夫婦別居、大貧困生活という大変な騒動がありました。私の祖父歌人の斎藤茂吉の家も夫婦別居12年間という大変な家でしたので、今日は不幸の話をたくさん持ってきました。皆様のお家ででも大変なことがあるかもしれませんが、斎藤さんの家の方が大変だよねと笑っていただければと思います。
まず、父の母斎藤輝子の人生からお話いたします。輝子は東京の表参道にある4500坪の大きな精神病院、斎藤病院の娘として生まれました。当時はまだ精神病に理解がない時代で、精神を病んだ方は病院に閉じ込められたり、家で監禁されるような時代でしたが、輝子の父、精神科医の斎藤紀一は、どんなお金持ちでも心を患うことはある、閉じ込めるのではなく、太陽の下で運動してしっかり食べることが大事だという考えでこのような大きな病院を建てました。父の作品『楡家の人びと』の舞台にもなった病院です。
輝子の姉である長女が生後すぐに亡くなっていたので、次女の輝子が生まれると同時に跡継ぎ探しが始まりました。山形県上山にいた15歳の非常に優秀な少年守谷茂吉が斎藤病院の書生の一人として東京に呼ばれ、0歳の輝子と出会ったことが、一つ目の不幸です。茂吉は優秀で将来の跡継ぎにふさわしいということで輝子が9歳の時に二人は婚約させられます。これが二つ目の不幸です。輝子が18歳の時に二人は結婚します。茂吉がヨーロッパに留学して3年経った頃、好奇心旺盛な輝子はヨーロッパに行きたいと言い出し、一人で茂吉の元へ行きました。しかし、二人の夫婦仲は最悪の状態で帰国しました。出迎えの病院関係者からの「斎藤病院が火事で焼けた」という知らせが三つ目の不幸です。さらに、火災保険が1週間前に切れていたという四つ目の不幸が襲いました。茂吉は金策に走り回り、精神病院建設反対にあいながら、病院を建設するという苦難のスタートを切りました。茂吉は精神科医でありながら、歌人として次々と歌集を作り、4人の子供に恵まれましたが、夫婦仲は非常に悪く、昭和8年から12年間別居生活を送ります。しかし、茂吉が高齢になり弱っていた晩年は夫婦仲良く暮らしたそうです。
茂吉が亡くなった後、輝子の第二の人生が始まります。好奇心旺盛な輝子は、まだ日本人が海外旅行に行けない時代に64歳で訪れたアラビア半島を皮切りに、サハラ砂漠、80歳で南極、エベレスト、85歳でガラパゴス、87歳でセイシェルと世界108カ国を旅行しました。
輝子は大病院で生まれたお嬢様ですが、戦争で家を失い、四畳半一間の借家で食べるものにも困るような生活になっても、一番輝いていたのが輝子だったそうです。二人の娘を失い、戦争の困難や苦労、お金の苦労と、うつ病になってもおかしくないと思いますが、人の目を気にせず、ゴーイングマイウェイ、そして好奇心旺盛であったことが輝子の元気の秘訣だったと思います。
父北杜夫は、茂吉から絶対医者になるように言われて、旧制松本高校から東北大医学部に進学し、精神科医になりました。慶応の医局で無給で働いていたときに、三日後に出航する水産庁のマグロ漁船が医者を探していると聞き、その船の医者として横浜港を出て各地を回り、ドイツのハンブルクで三菱商事の支店長の家に行きました。そこでたまたまお茶を出したお嬢さんが、私の母です。帰国後に再会したのがきっかけで昭和36年に両親は結婚しました。
父は純文学の作家になる夢を抱いていましたが、なかなか原稿が書けずに苦労している時に中央公論の編集者から、「マグロ漁船のエピソードを書いてはどうか」というアドバイスを受けて書いたのが、『どくとるマンボウ航海記』です。商社マンの家で生まれた母は、結婚したら幸せになれるという夢を抱いていました。家の庭には薔薇の花が咲き乱れ、夕食の時は周りに刺繍が施されたテーブルクロスで、グラタン、ラザニア、ドリア、ビーフシチューといった母の手作りの料理が並びました。しかし、母の幸せはここまでです。なんと、父が躁うつ病を発症し、急に、「チャーリー・チャップリンのような映画を作りたい」と言い出し、その映画の製作費を作るために株の売買を始め、毎日の売り買いで家のお金を全て失いました。父は友人である佐藤愛子先生、遠藤周作先生、阿川弘之先生に借金しようとしますが、母はそれを嫌がり、二人の間で壮絶な夫婦喧嘩になりました。ついには夫婦別居、一家破産ということもありました。そういうわけで、私は家族旅行や海水浴、遊園地にも行ったことがないまま育ちました。
私は大学4年の就職を考えた時、父からひどい目に合っていたので、作家なんて最低だ、人間がまともに生きるのにはサラリーマンが一番だと思い、サントリーに入社しました。15年間広報部におりましたが、部長から斎藤さんは風邪もひかず元気だからということで、当時無名の健康食品事業部に飛ばされました。広報出身ですので、健康食品のセサミンが良いとPRしたのですが、誰にも見向きしてもらえませんでした。たまたま、スポーツ新聞の方に、マカが夫婦生活にオススメですとお話したところ、2001年12月11日のスポーツ新聞に非常にえげつない記事が出ました。この記事を見て真面目な研究員たちは絶句し、私も会社をクビになるかと思いました。ところがその日から、マカを買い求める電話が鳴り続け、12月20日で品切れになり、前年比6000%の伸びを記録するほどになりました。マカの効果が男性の心を捉えるのだと思い、あちらこちらでこの新聞のコピーを配っていたところ、「週刊新潮から精力剤コラムを書いてほしい」と依頼されました。上司に相談したところ、サントリーの「やってみなはれ」という社風のおかげでOKが出て、それがきっかけでコラムを書くようになりました。当時のコラムが何冊かの新潮文庫になっております。
ここで、皆様にイキイキと健康に生きるための大切なコツ7つをお伝えしたいと思います。まず、当たり前ですが、バランスのよい食生活と適度な運動がとても大切です。そして、質の高い睡眠。次に、今より10分多く歩く、運動+10(プラス・テン)。歯医者で歯石を取ったり、歯をチェックすること。駅ではエスカレーターを使わずに階段を使う。日本人は真面目なのでうつ病になりがちですが、そんな時に80%で満足するコツを身につけるのが大切です。そして最後にユーモアを身につけること。今年の暑い夏で、身体にもストレスがかかりダメージを受けていると思います。是非、この7つのコツを覚えていただき、体調を整えて、元気にお過ごしいただきたいと思います。
今日は誠に有難うございました。
ご紹介いただきましてありがとうございます。サントリーの斎藤由香でございます。
皆様、作家の家というと素敵なおうちと勘違いされると思いますが、実は父が躁病、うつ病になり、一家破産、夫婦別居、大貧困生活という大変な騒動がありました。私の祖父歌人の斎藤茂吉の家も夫婦別居12年間という大変な家でしたので、今日は不幸の話をたくさん持ってきました。皆様のお家ででも大変なことがあるかもしれませんが、斎藤さんの家の方が大変だよねと笑っていただければと思います。
まず、父の母斎藤輝子の人生からお話いたします。輝子は東京の表参道にある4500坪の大きな精神病院、斎藤病院の娘として生まれました。当時はまだ精神病に理解がない時代で、精神を病んだ方は病院に閉じ込められたり、家で監禁されるような時代でしたが、輝子の父、精神科医の斎藤紀一は、どんなお金持ちでも心を患うことはある、閉じ込めるのではなく、太陽の下で運動してしっかり食べることが大事だという考えでこのような大きな病院を建てました。父の作品『楡家の人びと』の舞台にもなった病院です。
輝子の姉である長女が生後すぐに亡くなっていたので、次女の輝子が生まれると同時に跡継ぎ探しが始まりました。山形県上山にいた15歳の非常に優秀な少年守谷茂吉が斎藤病院の書生の一人として東京に呼ばれ、0歳の輝子と出会ったことが、一つ目の不幸です。茂吉は優秀で将来の跡継ぎにふさわしいということで輝子が9歳の時に二人は婚約させられます。これが二つ目の不幸です。輝子が18歳の時に二人は結婚します。茂吉がヨーロッパに留学して3年経った頃、好奇心旺盛な輝子はヨーロッパに行きたいと言い出し、一人で茂吉の元へ行きました。しかし、二人の夫婦仲は最悪の状態で帰国しました。出迎えの病院関係者からの「斎藤病院が火事で焼けた」という知らせが三つ目の不幸です。さらに、火災保険が1週間前に切れていたという四つ目の不幸が襲いました。茂吉は金策に走り回り、精神病院建設反対にあいながら、病院を建設するという苦難のスタートを切りました。茂吉は精神科医でありながら、歌人として次々と歌集を作り、4人の子供に恵まれましたが、夫婦仲は非常に悪く、昭和8年から12年間別居生活を送ります。しかし、茂吉が高齢になり弱っていた晩年は夫婦仲良く暮らしたそうです。
茂吉が亡くなった後、輝子の第二の人生が始まります。好奇心旺盛な輝子は、まだ日本人が海外旅行に行けない時代に64歳で訪れたアラビア半島を皮切りに、サハラ砂漠、80歳で南極、エベレスト、85歳でガラパゴス、87歳でセイシェルと世界108カ国を旅行しました。
輝子は大病院で生まれたお嬢様ですが、戦争で家を失い、四畳半一間の借家で食べるものにも困るような生活になっても、一番輝いていたのが輝子だったそうです。二人の娘を失い、戦争の困難や苦労、お金の苦労と、うつ病になってもおかしくないと思いますが、人の目を気にせず、ゴーイングマイウェイ、そして好奇心旺盛であったことが輝子の元気の秘訣だったと思います。
父北杜夫は、茂吉から絶対医者になるように言われて、旧制松本高校から東北大医学部に進学し、精神科医になりました。慶応の医局で無給で働いていたときに、三日後に出航する水産庁のマグロ漁船が医者を探していると聞き、その船の医者として横浜港を出て各地を回り、ドイツのハンブルクで三菱商事の支店長の家に行きました。そこでたまたまお茶を出したお嬢さんが、私の母です。帰国後に再会したのがきっかけで昭和36年に両親は結婚しました。
父は純文学の作家になる夢を抱いていましたが、なかなか原稿が書けずに苦労している時に中央公論の編集者から、「マグロ漁船のエピソードを書いてはどうか」というアドバイスを受けて書いたのが、『どくとるマンボウ航海記』です。商社マンの家で生まれた母は、結婚したら幸せになれるという夢を抱いていました。家の庭には薔薇の花が咲き乱れ、夕食の時は周りに刺繍が施されたテーブルクロスで、グラタン、ラザニア、ドリア、ビーフシチューといった母の手作りの料理が並びました。しかし、母の幸せはここまでです。なんと、父が躁うつ病を発症し、急に、「チャーリー・チャップリンのような映画を作りたい」と言い出し、その映画の製作費を作るために株の売買を始め、毎日の売り買いで家のお金を全て失いました。父は友人である佐藤愛子先生、遠藤周作先生、阿川弘之先生に借金しようとしますが、母はそれを嫌がり、二人の間で壮絶な夫婦喧嘩になりました。ついには夫婦別居、一家破産ということもありました。そういうわけで、私は家族旅行や海水浴、遊園地にも行ったことがないまま育ちました。
私は大学4年の就職を考えた時、父からひどい目に合っていたので、作家なんて最低だ、人間がまともに生きるのにはサラリーマンが一番だと思い、サントリーに入社しました。15年間広報部におりましたが、部長から斎藤さんは風邪もひかず元気だからということで、当時無名の健康食品事業部に飛ばされました。広報出身ですので、健康食品のセサミンが良いとPRしたのですが、誰にも見向きしてもらえませんでした。たまたま、スポーツ新聞の方に、マカが夫婦生活にオススメですとお話したところ、2001年12月11日のスポーツ新聞に非常にえげつない記事が出ました。この記事を見て真面目な研究員たちは絶句し、私も会社をクビになるかと思いました。ところがその日から、マカを買い求める電話が鳴り続け、12月20日で品切れになり、前年比6000%の伸びを記録するほどになりました。マカの効果が男性の心を捉えるのだと思い、あちらこちらでこの新聞のコピーを配っていたところ、「週刊新潮から精力剤コラムを書いてほしい」と依頼されました。上司に相談したところ、サントリーの「やってみなはれ」という社風のおかげでOKが出て、それがきっかけでコラムを書くようになりました。当時のコラムが何冊かの新潮文庫になっております。
ここで、皆様にイキイキと健康に生きるための大切なコツ7つをお伝えしたいと思います。まず、当たり前ですが、バランスのよい食生活と適度な運動がとても大切です。そして、質の高い睡眠。次に、今より10分多く歩く、運動+10(プラス・テン)。歯医者で歯石を取ったり、歯をチェックすること。駅ではエスカレーターを使わずに階段を使う。日本人は真面目なのでうつ病になりがちですが、そんな時に80%で満足するコツを身につけるのが大切です。そして最後にユーモアを身につけること。今年の暑い夏で、身体にもストレスがかかりダメージを受けていると思います。是非、この7つのコツを覚えていただき、体調を整えて、元気にお過ごしいただきたいと思います。
今日は誠に有難うございました。
卓話「有職組紐 道明の歴史と技術・未来への展望」
株式会社道明 代表取締役 道明葵一郎さま
2023年9月28日

 株式会社道明の代表取締役、道明葵一郎と申します。本日はこのような素晴らしい場でお話の機会を頂戴いたしまして、誠にありがとうございます。
組紐に馴染みのない方も多いかと思いますので、簡単に組紐についてご紹介させていただきます。
まず、真っ白なシルクの糸を染料で染めて色をつけるところからスタートします。この染めた糸を手作業で、組紐を組むための下準備をしていきます。組紐を組むための道具の一つ、高台という台を使って、鉛の重りの入った玉に糸を取り付けて、一定の手順で動かしていくと、どんどん組紐が組まれていきます。丸台という台では一定の手順で糸を動かしていくと、台の下の方に組紐が出来ていきます。
手作りの組紐は力の加減を調整しながら組むと非常に伸縮性に富んだ組紐が出来上がります。カランコロンという音を奏でながら組むと心が癒されて、とても楽しいものです。
組紐という工芸は世界中にありますが、日本の組紐は世界でも類を見ないほど非常に精緻で、日本独自の工芸と呼べるものだと思います。
6世紀に中国から伝来した組紐は長い歴史を持っています。飛鳥・奈良時代は仏教の法具などに多くの組紐が使われました。奈良の正倉院には当時使われた組紐が多く残っております。平安時代の貴族社会では貴族の装束に使われました。今でも皇室の重要な行事で着用される衣冠束帯に使われる平緒という組紐は1本製作するのに丸1年かかるという大変な労力を要する組紐です。平安末期から鎌倉・室町時代の武士の時代になると、武具に組紐が使われるようになりました。鎧の縅(おどし)と呼ばれる部分はすべて組紐でできています。刀の下緒(さげお)も組紐で作られる代表的なものです。武士の時代が終わり、近現代になると、女性の帯の上に締める帯締めが主要な用途になりました。現代では、道明が作るものの9割5分は帯締めとなっています。
私ども道明は、会社の仕事として組紐の製品を作るだけではなく、古い組紐の調査研究とそれを復元する分野にも力を入れております。法隆寺の幡垂飾(ばんすいしょく)と呼ばれる仏教行事に使用される幡の調査を行い、糸の作り方、撚りの加減、糸の立体的な動き方すべてを再現したものを作りました。また、厳島神社にある平家納経という巻物を留める組紐部分を復元模造したものも作成しました。東北の中尊寺の藤原秀衡の棺のミイラの胸の上に置かれていた組紐は、長年どのように組まれたものかが謎でしたが、二代前と三代前の道明の当主が試行錯誤の末に復元いたしました。
組紐にはさまざまな構造の美しさがあります。織物は自由に横糸を入れることによって絵画のような絵を描くことができますが、組紐は構造がそのまま柄になっています。中国から伝来した当初は非常にシンプルな構造でしたが、時代を経るにつれて日本で独自の発展を遂げて組紐の構造がどんどん複雑になっていきました。これはやはり、日本人の繊細さや目の細かさが生かされているからだと思います。伝統工芸というと昔と同じものをずっと作り続けていると思われるかもしれませんが、技術はどんどんレベルアップしており、一番新しい組紐が一番複雑なものであったりします。
道明では色々と新しい試みも行っています。東京大学の位相幾何学の先生とのコラボレーションによる立体的な組紐の作成や、ファッションデザイナーとのコラボレーションでは、19世紀のヨーロッパの衣服を解体して、組紐とコットンの材料を用いて再構成して衣服の作成を行いました。着物の帯締めに代わる現代版の帯締めとして、ベルトシリーズを作成しております。また、アクセサリーやネクタイなど、世界中の人々に日本の組紐の良さを知っていただくために、さまざまな製品を開発しております。
さらには、新素材の光る糸やビニールチューブを使ったり、シルク以外の強度のある繊維で作った組紐など、新しい素材を使った組紐にも今後力を入れていきたいと思っています。
伝統的なスタイルだけではなく現代的なスタイルでの展示会も行っています。ロサンゼルス、サンパウロ、ロンドンにある外務省のジャパン・ハウスという館でそれぞれ約3か月間、『KUMIHIMO: The Art of Japanese Silk Braiding by DOMYO』という組紐展を巡回展として実施いたしました。
また、道明の取り組みとして、組紐の教室を全国各地で開催しております。今年でちょうど50周年になります。産業として組紐を作るだけなく、出来るだけ多くの方に組紐を楽しんでもらい、技術を知ってもらうことによって、技術が絶えることなく裾野が広がっていくと考えております。神楽坂に、気軽に組紐体験をできる新たな施設を作りました。日本の方だけでなく、海外から来日された方にも組紐の魅力を伝えておもてなしできる施設として考えております。
道明は1652年、承応元年に開業し、創業371年目となります。伝統工芸として持続可能性を成し遂げていると思っています。手仕事で作っている伝統工芸ですので、動力を使わない、二酸化炭素を排出しない低炭素の産業です。近年大量に衣服を作って大量に破棄するという問題が起こっていますが、組紐は手作りなので沢山作ることができません。適量を作って適量を出荷しています。伝統工芸では、職人がいなくなったとか技術が途絶えたというような話を聞きますが、道明では毎年できるだけ多くの職人を育成して持続可能な産業としてのシステムを作っていこうとしております。
また組紐教室や組紐体験にも力を入れており、モノ消費ではなくコト消費として楽しんでいただくことも考えています。カランコロンという音を聞きながら組紐を組んでいると心が落ち着きます。ちょっとした精神修養やマインドフルネスになるのではないかと思います。
道明は非常に小さな組織で、沢山のものを作ることはできませんが、組紐自体も小さなものですし、家族で代々続けるファミリービジネスの適度の小ささが、仕事や組織にちょうど合っているのではないかと思っております。
本日はどうもありがとうございました。
株式会社道明の代表取締役、道明葵一郎と申します。本日はこのような素晴らしい場でお話の機会を頂戴いたしまして、誠にありがとうございます。
組紐に馴染みのない方も多いかと思いますので、簡単に組紐についてご紹介させていただきます。
まず、真っ白なシルクの糸を染料で染めて色をつけるところからスタートします。この染めた糸を手作業で、組紐を組むための下準備をしていきます。組紐を組むための道具の一つ、高台という台を使って、鉛の重りの入った玉に糸を取り付けて、一定の手順で動かしていくと、どんどん組紐が組まれていきます。丸台という台では一定の手順で糸を動かしていくと、台の下の方に組紐が出来ていきます。
手作りの組紐は力の加減を調整しながら組むと非常に伸縮性に富んだ組紐が出来上がります。カランコロンという音を奏でながら組むと心が癒されて、とても楽しいものです。
組紐という工芸は世界中にありますが、日本の組紐は世界でも類を見ないほど非常に精緻で、日本独自の工芸と呼べるものだと思います。
6世紀に中国から伝来した組紐は長い歴史を持っています。飛鳥・奈良時代は仏教の法具などに多くの組紐が使われました。奈良の正倉院には当時使われた組紐が多く残っております。平安時代の貴族社会では貴族の装束に使われました。今でも皇室の重要な行事で着用される衣冠束帯に使われる平緒という組紐は1本製作するのに丸1年かかるという大変な労力を要する組紐です。平安末期から鎌倉・室町時代の武士の時代になると、武具に組紐が使われるようになりました。鎧の縅(おどし)と呼ばれる部分はすべて組紐でできています。刀の下緒(さげお)も組紐で作られる代表的なものです。武士の時代が終わり、近現代になると、女性の帯の上に締める帯締めが主要な用途になりました。現代では、道明が作るものの9割5分は帯締めとなっています。
私ども道明は、会社の仕事として組紐の製品を作るだけではなく、古い組紐の調査研究とそれを復元する分野にも力を入れております。法隆寺の幡垂飾(ばんすいしょく)と呼ばれる仏教行事に使用される幡の調査を行い、糸の作り方、撚りの加減、糸の立体的な動き方すべてを再現したものを作りました。また、厳島神社にある平家納経という巻物を留める組紐部分を復元模造したものも作成しました。東北の中尊寺の藤原秀衡の棺のミイラの胸の上に置かれていた組紐は、長年どのように組まれたものかが謎でしたが、二代前と三代前の道明の当主が試行錯誤の末に復元いたしました。
組紐にはさまざまな構造の美しさがあります。織物は自由に横糸を入れることによって絵画のような絵を描くことができますが、組紐は構造がそのまま柄になっています。中国から伝来した当初は非常にシンプルな構造でしたが、時代を経るにつれて日本で独自の発展を遂げて組紐の構造がどんどん複雑になっていきました。これはやはり、日本人の繊細さや目の細かさが生かされているからだと思います。伝統工芸というと昔と同じものをずっと作り続けていると思われるかもしれませんが、技術はどんどんレベルアップしており、一番新しい組紐が一番複雑なものであったりします。
道明では色々と新しい試みも行っています。東京大学の位相幾何学の先生とのコラボレーションによる立体的な組紐の作成や、ファッションデザイナーとのコラボレーションでは、19世紀のヨーロッパの衣服を解体して、組紐とコットンの材料を用いて再構成して衣服の作成を行いました。着物の帯締めに代わる現代版の帯締めとして、ベルトシリーズを作成しております。また、アクセサリーやネクタイなど、世界中の人々に日本の組紐の良さを知っていただくために、さまざまな製品を開発しております。
さらには、新素材の光る糸やビニールチューブを使ったり、シルク以外の強度のある繊維で作った組紐など、新しい素材を使った組紐にも今後力を入れていきたいと思っています。
伝統的なスタイルだけではなく現代的なスタイルでの展示会も行っています。ロサンゼルス、サンパウロ、ロンドンにある外務省のジャパン・ハウスという館でそれぞれ約3か月間、『KUMIHIMO: The Art of Japanese Silk Braiding by DOMYO』という組紐展を巡回展として実施いたしました。
また、道明の取り組みとして、組紐の教室を全国各地で開催しております。今年でちょうど50周年になります。産業として組紐を作るだけなく、出来るだけ多くの方に組紐を楽しんでもらい、技術を知ってもらうことによって、技術が絶えることなく裾野が広がっていくと考えております。神楽坂に、気軽に組紐体験をできる新たな施設を作りました。日本の方だけでなく、海外から来日された方にも組紐の魅力を伝えておもてなしできる施設として考えております。
道明は1652年、承応元年に開業し、創業371年目となります。伝統工芸として持続可能性を成し遂げていると思っています。手仕事で作っている伝統工芸ですので、動力を使わない、二酸化炭素を排出しない低炭素の産業です。近年大量に衣服を作って大量に破棄するという問題が起こっていますが、組紐は手作りなので沢山作ることができません。適量を作って適量を出荷しています。伝統工芸では、職人がいなくなったとか技術が途絶えたというような話を聞きますが、道明では毎年できるだけ多くの職人を育成して持続可能な産業としてのシステムを作っていこうとしております。
また組紐教室や組紐体験にも力を入れており、モノ消費ではなくコト消費として楽しんでいただくことも考えています。カランコロンという音を聞きながら組紐を組んでいると心が落ち着きます。ちょっとした精神修養やマインドフルネスになるのではないかと思います。
道明は非常に小さな組織で、沢山のものを作ることはできませんが、組紐自体も小さなものですし、家族で代々続けるファミリービジネスの適度の小ささが、仕事や組織にちょうど合っているのではないかと思っております。
本日はどうもありがとうございました。


卓話「七代目が語る二宮金次郎」
親子をつなぐ学びのスペース「リレイト」代表 中桐万里子さま
2023年9月14日

 皆様こんにちは。只今ご紹介いただきました中桐と申します。
私自身は二宮金次郎の七代目にあたります。幼い頃、祖母から繰り返し金次郎の話を聞いて、すっかり金次郎オタクとして育ちました。私にとって二宮金次郎は、家の中で聞いて育った遠いおじいちゃんといった存在です。皆様にとっては、二宮金次郎のイメージは、小学校の校庭などでお馴染みの、薪を背負って本を読んでいる像でしょうか。私たち家族が金次郎の像を見る時に注目してきたのは、手に持っている本や背負っている薪よりも、小さく一歩前に出ている足でした。この像のメッセージはどんな時もくじけず、あきらめず、小さな一歩を大事にすることを伝える像なのだと言われてきました。
二宮金次郎は、今から200年ほど前の幕末を生きた人物です。今の神奈川県小田原市で生まれ、明治維新を見ることなく栃木県で亡くなっています。農民として生まれ農業人として人生を送りました。当時は異常気象や自然災害が続き、農業、つまり経済にダメージを与えたことで政治が動乱に向かっていったと言われる時代でした。その中で金次郎が取り組んだのは被災地の復興、再建でした。生涯で600以上の村の再建に関わるという実績を残しています。ちなみに、大人になった金次郎は身長182センチ、体重94キロという大男でした。
当時の小田原は、金次郎が生まれる少し前の富士山噴火による火山灰の影響に悩まされていました。火山灰のために土地が荒れて、今までの作物が作れなくなっていました。さらに冷夏が追い打ちをかけて、主産業の米が実らなくなっていました。誰もが火山灰や時代、自然、冷夏、身分、状況が悪いからうまく行かないのだと言って、足を止めていた時代でした。しかし金次郎は、それは全てに目をつぶって現実から逃げていることだから何の意味もない、大切なのは目を開けて現実と向かうことだと言い、火山灰や冷夏を活かそうとする考えが大切だと言いました。のちに小田原周辺では、火山灰の土質を活かして煙草や落花生の栽培で有名になっていきます。目の前の現状を活かし、実践して、幸せに生きることに徹底的にこだわったのが金次郎でした。
金次郎は、仲間たちから、様々な困難の中で何故前向きに一歩を踏み出そうとするのか、そのモチベーションはどこから来るのかと尋ねられました。彼は目の前をよく見ることからなのだと答えたそうです。ただ見るだけでは智恵は浮かばないし、道は見えてこないし、モチベーションも湧かない。重要なのはよく見ること、単純な事実を見落とさないことだと言いました。例えば、立派な大木も、小さな木の実から長い時間をかけて今の姿へ育ってきています。その時間の中にはさまざまな出来事があったであろう。つまり、よく見るということはプロセスを知ること、そこに宿るドラマに思いをはせることであり、時間軸でものを見ること、時間が流れているという単純な事実に気づくことが大事なのだと金次郎は考えていました。
身体の眼だけを使うのではなく、心の眼を開いて見ること、「心眼」と言う言葉を金次郎は好んで使っていました。それは難しい話ではなく、まさに想像力、イメージする力です。心の眼を開いて何気ない日常を見れば、頑張っているのは自分だけではなく、沢山の仲間の働きでこの社会が成り立っていることに気づくのではないか。そうしたドラマが見えるからこそ、もう一歩先へと踏み出すモチベーションへとつながっているのです。
金次郎は時間軸のことを「徳」と呼びました。すべてのものが「徳」を持っていると考えました。リアリストであった金次郎は「徳」を良いところという意味では使っていません。良いところに見えるか、悪いところに見えるかは好み次第、相性次第、価値観次第だからです。火山灰は米との相性は最低ですが、煙草や落花生にとっての相性は最高です。では、良いとか悪いとかではなく、大事なことは何かと問われた時、金次郎は今ここに存在している事実、現実が大事なのだと言いました。なぜ存在しているのか、それは諦めなかったから、くじけなかったから、逃げ出さなかったからです。つまり、あらゆるものが「徳」を持っているとは、あらゆるものに傷や壁を超える力を持ち、その実践の証としてここに存在している、大変価値があるものだという意味なのです。そういう「徳」を発掘しながら一歩進むことを、金次郎は「報徳」と呼びました。報徳というと、頑張れば報われるという風に考える方が多いようですが、実際には、頑張って報いようという意味の言葉です。
まずはよく見ることから始めよう。何もできない赤ん坊だった自分が、途方もなく多くの人に育てられ、教えられ、サポートを受けて、今ここにいる。では、今度は自分に何ができるだろうと発想していくこと、しっかりと「徳」を受けて、その上で報いていこう、恩返しをしよう、そのように動き出せばモチベーションを高く持ってやっていけるのではないかと金次郎は言いました。多くの人たちのおかげでここまでやれた、その幸せを確かに受け止めて、その上で自分なりの実践を考える、そんな実践スタイルを金次郎は提唱していました。それがまさに、まずは心の眼を開いて色々なものとのつながりに気づくこと、自らの心の田を耕すことで仲間とのつながりを感じ、前に進もうと思える原動力だったのです。
金次郎は、世のため、人のために頑張るというよりは、むしろ仕事を与えてくれた殿さまや、支えてくれる家族、仲間やお弟子さんたちに報いたいと思っていました。こうした確かなつながりが大事なモチベーションになっていたと語っています。受けた「徳」に報いていこうとする恩返しの思想が金次郎の実践のモデルでした。それが時間軸を持っていることから、単なる恩返しではなく、「恩送り」と呼ばれる構造ではないかと言われています。江戸時代に「おんくり」と呼ばれ、これが未来を作る方法だったと言われています。
実はこのロータリーとも金次郎は深いつながりがあります。日本にロータリークラブを設立した米山梅吉さんは、かつて金融界の二宮金次郎と呼ばれていました。また、ロータリー発祥の頃に、国際大会で「ロータリアン以前のロータリアン二宮金次郎」という講演をされた大阪の方がいらっしゃったと聞いています。ロータリーにおける友愛と奉仕の考え方が、二宮金次郎の根っことも何かつながるような感じもしています。
よく見ること、目を開けることが大切だとお話しましたが、よく見ることの達人になった時に生まれる言葉が「ありがとう」です。「ありがとう」の反対語はきっと「当たり前」でしょう。ただ見ているだけだと、全てが普通や当たり前にしか見えません。でもよく見ると、尊さや奇跡などに出会い、一歩を踏み出す力になるのではないでしょうか。「ありがとう」探しの達人になることが、次の「ありがとう」を生み出す創造の原点なのかもしれません。
ご清聴ありがとうございました。
皆様こんにちは。只今ご紹介いただきました中桐と申します。
私自身は二宮金次郎の七代目にあたります。幼い頃、祖母から繰り返し金次郎の話を聞いて、すっかり金次郎オタクとして育ちました。私にとって二宮金次郎は、家の中で聞いて育った遠いおじいちゃんといった存在です。皆様にとっては、二宮金次郎のイメージは、小学校の校庭などでお馴染みの、薪を背負って本を読んでいる像でしょうか。私たち家族が金次郎の像を見る時に注目してきたのは、手に持っている本や背負っている薪よりも、小さく一歩前に出ている足でした。この像のメッセージはどんな時もくじけず、あきらめず、小さな一歩を大事にすることを伝える像なのだと言われてきました。
二宮金次郎は、今から200年ほど前の幕末を生きた人物です。今の神奈川県小田原市で生まれ、明治維新を見ることなく栃木県で亡くなっています。農民として生まれ農業人として人生を送りました。当時は異常気象や自然災害が続き、農業、つまり経済にダメージを与えたことで政治が動乱に向かっていったと言われる時代でした。その中で金次郎が取り組んだのは被災地の復興、再建でした。生涯で600以上の村の再建に関わるという実績を残しています。ちなみに、大人になった金次郎は身長182センチ、体重94キロという大男でした。
当時の小田原は、金次郎が生まれる少し前の富士山噴火による火山灰の影響に悩まされていました。火山灰のために土地が荒れて、今までの作物が作れなくなっていました。さらに冷夏が追い打ちをかけて、主産業の米が実らなくなっていました。誰もが火山灰や時代、自然、冷夏、身分、状況が悪いからうまく行かないのだと言って、足を止めていた時代でした。しかし金次郎は、それは全てに目をつぶって現実から逃げていることだから何の意味もない、大切なのは目を開けて現実と向かうことだと言い、火山灰や冷夏を活かそうとする考えが大切だと言いました。のちに小田原周辺では、火山灰の土質を活かして煙草や落花生の栽培で有名になっていきます。目の前の現状を活かし、実践して、幸せに生きることに徹底的にこだわったのが金次郎でした。
金次郎は、仲間たちから、様々な困難の中で何故前向きに一歩を踏み出そうとするのか、そのモチベーションはどこから来るのかと尋ねられました。彼は目の前をよく見ることからなのだと答えたそうです。ただ見るだけでは智恵は浮かばないし、道は見えてこないし、モチベーションも湧かない。重要なのはよく見ること、単純な事実を見落とさないことだと言いました。例えば、立派な大木も、小さな木の実から長い時間をかけて今の姿へ育ってきています。その時間の中にはさまざまな出来事があったであろう。つまり、よく見るということはプロセスを知ること、そこに宿るドラマに思いをはせることであり、時間軸でものを見ること、時間が流れているという単純な事実に気づくことが大事なのだと金次郎は考えていました。
身体の眼だけを使うのではなく、心の眼を開いて見ること、「心眼」と言う言葉を金次郎は好んで使っていました。それは難しい話ではなく、まさに想像力、イメージする力です。心の眼を開いて何気ない日常を見れば、頑張っているのは自分だけではなく、沢山の仲間の働きでこの社会が成り立っていることに気づくのではないか。そうしたドラマが見えるからこそ、もう一歩先へと踏み出すモチベーションへとつながっているのです。
金次郎は時間軸のことを「徳」と呼びました。すべてのものが「徳」を持っていると考えました。リアリストであった金次郎は「徳」を良いところという意味では使っていません。良いところに見えるか、悪いところに見えるかは好み次第、相性次第、価値観次第だからです。火山灰は米との相性は最低ですが、煙草や落花生にとっての相性は最高です。では、良いとか悪いとかではなく、大事なことは何かと問われた時、金次郎は今ここに存在している事実、現実が大事なのだと言いました。なぜ存在しているのか、それは諦めなかったから、くじけなかったから、逃げ出さなかったからです。つまり、あらゆるものが「徳」を持っているとは、あらゆるものに傷や壁を超える力を持ち、その実践の証としてここに存在している、大変価値があるものだという意味なのです。そういう「徳」を発掘しながら一歩進むことを、金次郎は「報徳」と呼びました。報徳というと、頑張れば報われるという風に考える方が多いようですが、実際には、頑張って報いようという意味の言葉です。
まずはよく見ることから始めよう。何もできない赤ん坊だった自分が、途方もなく多くの人に育てられ、教えられ、サポートを受けて、今ここにいる。では、今度は自分に何ができるだろうと発想していくこと、しっかりと「徳」を受けて、その上で報いていこう、恩返しをしよう、そのように動き出せばモチベーションを高く持ってやっていけるのではないかと金次郎は言いました。多くの人たちのおかげでここまでやれた、その幸せを確かに受け止めて、その上で自分なりの実践を考える、そんな実践スタイルを金次郎は提唱していました。それがまさに、まずは心の眼を開いて色々なものとのつながりに気づくこと、自らの心の田を耕すことで仲間とのつながりを感じ、前に進もうと思える原動力だったのです。
金次郎は、世のため、人のために頑張るというよりは、むしろ仕事を与えてくれた殿さまや、支えてくれる家族、仲間やお弟子さんたちに報いたいと思っていました。こうした確かなつながりが大事なモチベーションになっていたと語っています。受けた「徳」に報いていこうとする恩返しの思想が金次郎の実践のモデルでした。それが時間軸を持っていることから、単なる恩返しではなく、「恩送り」と呼ばれる構造ではないかと言われています。江戸時代に「おんくり」と呼ばれ、これが未来を作る方法だったと言われています。
実はこのロータリーとも金次郎は深いつながりがあります。日本にロータリークラブを設立した米山梅吉さんは、かつて金融界の二宮金次郎と呼ばれていました。また、ロータリー発祥の頃に、国際大会で「ロータリアン以前のロータリアン二宮金次郎」という講演をされた大阪の方がいらっしゃったと聞いています。ロータリーにおける友愛と奉仕の考え方が、二宮金次郎の根っことも何かつながるような感じもしています。
よく見ること、目を開けることが大切だとお話しましたが、よく見ることの達人になった時に生まれる言葉が「ありがとう」です。「ありがとう」の反対語はきっと「当たり前」でしょう。ただ見ているだけだと、全てが普通や当たり前にしか見えません。でもよく見ると、尊さや奇跡などに出会い、一歩を踏み出す力になるのではないでしょうか。「ありがとう」探しの達人になることが、次の「ありがとう」を生み出す創造の原点なのかもしれません。
ご清聴ありがとうございました。
卓話「すべての人が好きなスポーツに関わる社会へ」
NPO法人STAND代表理事 伊藤数子さま
2023年8月31日

 皆さん、こんにちは。
今日は「すべての人が好きなスポーツに関わる社会へ」というタイトルでお話しいたします。障害がある人も含めてすべての人がチャレンジしたいことにチャレンジできる社会をつくっていこうじゃないかという思いでつけたタイトルです。ロータリークラブ様の奉仕活動にも通ずるところがあるかなと思いながらお話いたします。
私が最初にパラスポーツと出会ったのは、電動車椅子サッカーという競技でした。パラリンピックの競技ではないので、見たことがある人は少ないかもしれませんが、私は2003年に当時住んでいた金沢での大会を見に行きました。金沢の地区大会で優勝したチームが大阪での全国大会へ進みましたが、選手の中に主治医から大阪へ行くことを止められた方がいたので、その選手に見てもらおうとインターネットで試合を中継しました。ところが、大会会場のロビーでこのインターネットのサイトを展示していたところ、ある男性から「障害者をさらし者にしてどうするつもりだ」と怒鳴られて大変驚きました。プロ野球の試合中継で映る選手は「さらし者」とは言われないのに、なぜ、選手が車いすに乗っていると「さらし者」と言われるのか。大きな違和感が私の中に湧いてきました。障害のある人がスポーツをやっていることを知らせよう、そうすれば少しでも社会が変わるかもしれない、変わってほしいという思いからNPO法人STANDを設立しました。
オリンピック・パラリンピックは、なぜ費用をかけて大々的に国を挙げて行うのか。もちろん規模が大きいというのもありますが、それだけではありません。近代オリンピックの精神は「平和で、より良い世界の実現に貢献すること」です。パラリンピックにも同じように精神が掲げられています。パラリンピックムーブメントというものがあり、これはより良い社会を作るための社会変革を起こそうとするあらゆる活動を指し、ゴールとしてインクルーシブな社会を創出すると掲げられています。
2020年の大会の三つの基本コンセプトは、「全員が自己ベスト」「多様性と調和」「未来への継承」でした。競技をどうするとか、誰を表彰するとか、メダルの数などということは書かれていません。つまり、オリンピック・パラリンピックは社会を変えるために開催する社会変革活動なのです。ですから大々的に国を挙げて開催するのです。
1964年の東京オリンピックの後、パラリンピックも開催されました。このオリンピックの後、社会変革活動のレガシーとして、新幹線や高速道路ができ、冷凍食品や電卓などが生まれ、それがその後の社会を変えていきました。パラリンピックは障害者の自立をレガシーとして残しました。実際にその後、さまざまな施策が実施されました。
2020年の大会のレガシーの一つは「共生社会」です。でも、パラリンピックの後、社会が変わって共生社会になったと実感できるでしょうか。パラリンピックを見て、カッコ良かった、興奮した、感動したという感想が聞かれます。障害のある人のスポーツが、これほど競技性が高くてカッコ良いという印象が残ったのは大きな財産だと思います。ただ、大会はきっかけをつくりましたが、開催後に国・自治体・企業・団体のオリパラ系の組織は全て解散しました。その後は私たち一人ひとりがやっていくしかありません。
日本では人口の約1割が障害のある人たちです。世界では15%が障害のある人たちです。このような状況で私たちがスポーツを通して何ができるでしょうか。
スポーツには「する」、「みる」、「ささえる」という関わり方があります。「スポーツをする。」私が2003年にNPO法人STANDを設立し、スポーツメーカーやスポーツショップへの営業活動をしていた時、障害がある人も同じラケットやボールを使うということが知られていませんでした。今は、段々理解されてきています。「スポーツをみる。」すなわちスポーツ観戦は、会場で臨場感やその場の空気や一緒に応援するのを楽しむのが大事です。国際パラリンピック委員会が推奨するスタジアムガイドでは、会場に設置する車いす席の数の基準が示されています。日本で車いす席が一番多いのは広島のMAZDAスタジアムです。車いす席の割合が0.44%で、1塁側、3塁側、内野、外野にも設置されています。これはとても大事なことです。色々な会場で、色んな人たちが見たいゲームを観戦できるようにすること。ここにも社会変革のきっかけがあると思います。「スポーツをささえる」という関わり方のために、ボランティアアカデミーという事業を始めました。パラリンピックの選手が講師となってパラスポーツの大会やイベントのボランティア希望者向けの講座を行っています。参加者のアンケートに「視覚障害の人の誘導の実習をした2日後、街中で白杖を持った人を見かけました。私は生まれて初めて障害のある人にお声がけをして近くの目的地までご案内をしました」という声があり、とても嬉しく思いました。私たちはパラスポーツの大会やイベントを通して社会を変えることを目指していくべきだと気づきました。
障害のある人にどうやって声を掛けたら良いのですかとよく講座の時にも参加者から尋ねられます。普段通りに声をかけてください。10年ほど前に私の全盲の友人が駅のホームから転落して電車にひかれて亡くなりました。ホームには人がたくさんいたのに、同じく全盲の奥様と二人でゆっくり歩いていたのに、ホームから転落してしまいました。こういう時には、どういう風に声をかけるかなどと考えている場合ではありません。危ない、止まれと声をかけるか、しがみついて止めてください。困っていそうな障害者の方がいたら、お手伝いしましょうかと声をかけるだけで良いのです。そうすることで、社会はどんどん変わっていくと思います。
慣れるということについてもお話させてください。初めて車いすの人と会うと、車いすがその人を象徴していると思えるかもしれません。でも、さまざまな障害のある人たちと触れ合っていくと、車いすに乗っていることがその人を象徴する特徴ではなくなります。慣れていくと、優しくて、英語が堪能で、映画を見に行くのが好き、ゴルフも上手く、そして車椅子を使っていると、障害はその人を象徴する特徴ではなくなります。こうして共生社会は広がっていくと思います。
階段を前にしている車いすの人を見て、障害はどこにあると思いますか。階段を登れない足にあると思いますか。スロープを付けて登れるようになると、障害は階段にあることがわかります。障害は人にあるのではなく、私たちの心も含めた社会にあります。道路や建物だけではなく、社会のさまざまな仕組みの中に障害があると考えると、色々なところを変えていけるのではないかと思います。
これからもスポーツからのアプローチで共生社会を目指してまいります。
今日はありがとうございました。
皆さん、こんにちは。
今日は「すべての人が好きなスポーツに関わる社会へ」というタイトルでお話しいたします。障害がある人も含めてすべての人がチャレンジしたいことにチャレンジできる社会をつくっていこうじゃないかという思いでつけたタイトルです。ロータリークラブ様の奉仕活動にも通ずるところがあるかなと思いながらお話いたします。
私が最初にパラスポーツと出会ったのは、電動車椅子サッカーという競技でした。パラリンピックの競技ではないので、見たことがある人は少ないかもしれませんが、私は2003年に当時住んでいた金沢での大会を見に行きました。金沢の地区大会で優勝したチームが大阪での全国大会へ進みましたが、選手の中に主治医から大阪へ行くことを止められた方がいたので、その選手に見てもらおうとインターネットで試合を中継しました。ところが、大会会場のロビーでこのインターネットのサイトを展示していたところ、ある男性から「障害者をさらし者にしてどうするつもりだ」と怒鳴られて大変驚きました。プロ野球の試合中継で映る選手は「さらし者」とは言われないのに、なぜ、選手が車いすに乗っていると「さらし者」と言われるのか。大きな違和感が私の中に湧いてきました。障害のある人がスポーツをやっていることを知らせよう、そうすれば少しでも社会が変わるかもしれない、変わってほしいという思いからNPO法人STANDを設立しました。
オリンピック・パラリンピックは、なぜ費用をかけて大々的に国を挙げて行うのか。もちろん規模が大きいというのもありますが、それだけではありません。近代オリンピックの精神は「平和で、より良い世界の実現に貢献すること」です。パラリンピックにも同じように精神が掲げられています。パラリンピックムーブメントというものがあり、これはより良い社会を作るための社会変革を起こそうとするあらゆる活動を指し、ゴールとしてインクルーシブな社会を創出すると掲げられています。
2020年の大会の三つの基本コンセプトは、「全員が自己ベスト」「多様性と調和」「未来への継承」でした。競技をどうするとか、誰を表彰するとか、メダルの数などということは書かれていません。つまり、オリンピック・パラリンピックは社会を変えるために開催する社会変革活動なのです。ですから大々的に国を挙げて開催するのです。
1964年の東京オリンピックの後、パラリンピックも開催されました。このオリンピックの後、社会変革活動のレガシーとして、新幹線や高速道路ができ、冷凍食品や電卓などが生まれ、それがその後の社会を変えていきました。パラリンピックは障害者の自立をレガシーとして残しました。実際にその後、さまざまな施策が実施されました。
2020年の大会のレガシーの一つは「共生社会」です。でも、パラリンピックの後、社会が変わって共生社会になったと実感できるでしょうか。パラリンピックを見て、カッコ良かった、興奮した、感動したという感想が聞かれます。障害のある人のスポーツが、これほど競技性が高くてカッコ良いという印象が残ったのは大きな財産だと思います。ただ、大会はきっかけをつくりましたが、開催後に国・自治体・企業・団体のオリパラ系の組織は全て解散しました。その後は私たち一人ひとりがやっていくしかありません。
日本では人口の約1割が障害のある人たちです。世界では15%が障害のある人たちです。このような状況で私たちがスポーツを通して何ができるでしょうか。
スポーツには「する」、「みる」、「ささえる」という関わり方があります。「スポーツをする。」私が2003年にNPO法人STANDを設立し、スポーツメーカーやスポーツショップへの営業活動をしていた時、障害がある人も同じラケットやボールを使うということが知られていませんでした。今は、段々理解されてきています。「スポーツをみる。」すなわちスポーツ観戦は、会場で臨場感やその場の空気や一緒に応援するのを楽しむのが大事です。国際パラリンピック委員会が推奨するスタジアムガイドでは、会場に設置する車いす席の数の基準が示されています。日本で車いす席が一番多いのは広島のMAZDAスタジアムです。車いす席の割合が0.44%で、1塁側、3塁側、内野、外野にも設置されています。これはとても大事なことです。色々な会場で、色んな人たちが見たいゲームを観戦できるようにすること。ここにも社会変革のきっかけがあると思います。「スポーツをささえる」という関わり方のために、ボランティアアカデミーという事業を始めました。パラリンピックの選手が講師となってパラスポーツの大会やイベントのボランティア希望者向けの講座を行っています。参加者のアンケートに「視覚障害の人の誘導の実習をした2日後、街中で白杖を持った人を見かけました。私は生まれて初めて障害のある人にお声がけをして近くの目的地までご案内をしました」という声があり、とても嬉しく思いました。私たちはパラスポーツの大会やイベントを通して社会を変えることを目指していくべきだと気づきました。
障害のある人にどうやって声を掛けたら良いのですかとよく講座の時にも参加者から尋ねられます。普段通りに声をかけてください。10年ほど前に私の全盲の友人が駅のホームから転落して電車にひかれて亡くなりました。ホームには人がたくさんいたのに、同じく全盲の奥様と二人でゆっくり歩いていたのに、ホームから転落してしまいました。こういう時には、どういう風に声をかけるかなどと考えている場合ではありません。危ない、止まれと声をかけるか、しがみついて止めてください。困っていそうな障害者の方がいたら、お手伝いしましょうかと声をかけるだけで良いのです。そうすることで、社会はどんどん変わっていくと思います。
慣れるということについてもお話させてください。初めて車いすの人と会うと、車いすがその人を象徴していると思えるかもしれません。でも、さまざまな障害のある人たちと触れ合っていくと、車いすに乗っていることがその人を象徴する特徴ではなくなります。慣れていくと、優しくて、英語が堪能で、映画を見に行くのが好き、ゴルフも上手く、そして車椅子を使っていると、障害はその人を象徴する特徴ではなくなります。こうして共生社会は広がっていくと思います。
階段を前にしている車いすの人を見て、障害はどこにあると思いますか。階段を登れない足にあると思いますか。スロープを付けて登れるようになると、障害は階段にあることがわかります。障害は人にあるのではなく、私たちの心も含めた社会にあります。道路や建物だけではなく、社会のさまざまな仕組みの中に障害があると考えると、色々なところを変えていけるのではないかと思います。
これからもスポーツからのアプローチで共生社会を目指してまいります。
今日はありがとうございました。
卓話「父・山本直純のこと、ミャンマーのこと」
チェリスト・指揮者 山本祐ノ介さま
2023年8月24日

 皆さんこんにちは。今日は、私の父、山本直純の話と、私がミャンマーでオーケストラの指導をしていることなどをお話したいと思います。
父、山本直純は1932年生まれで、12月16日というベートーベンと同じ誕生日であることが自慢でした。2002年に69歳で亡くなり、昨年2022年は生誕90年、没後20年ということで、コンサートなどで取り上げていただく機会が少し増えました。
コマーシャルやテレビ番組で大きな声で豪快に笑う父の姿が印象的だったせいか、私が子供の頃は、父が家ではどんな人なのかとよく尋ねられました。父直純がどのような人だったかは色々な切り口があると思いますが、一つ特徴的なことはなんでも混ぜこぜにするのが好きな人でした。食べ物でもトーストに納豆とバターとチーズを乗せて混ぜて食べたり、カレーにおでんを入れて食べたり、外食に行っても色々なものを混ぜて食べたり、他の人にも美味しいぞといって押し付けたりしていました。よく言えば創意工夫かもしれませんが、それを無理やり押し付けるというのが父の真骨頂だったと思います。
こういう部分は父の音楽にも表れているところがあります。父が編曲した「8時だヨ!全員集合」のオープニングテーマは、北海盆唄をアレンジしたものです。「オーケストラがやってきた」のテーマソングもヨハン・シュトラウスの曲をアレンジしたものです。あまり知られていませんが、父の交響曲「宿命」はベートーベンの交響曲1番から9番の良い所を繋ぎ合わせたものですし、有名なピアノ協奏曲を繋げた「ヘンペラー」という作品もありました。作曲というより編曲、いえ、「変曲」作品です。普通は自分で作曲したオリジナル作品を世に残したいと思うのですが、父はみんなが知っているメロディーを使った方が楽しいだろうと考えていたようです。
父が作曲した曲をご存知ない方もいらっしゃると思いますが、映画の「男はつらいよ」では49作の音楽をすべて作曲しています。ドラマでは大河ドラマの「風と雲と虹と」、「武田信玄」の音楽も書いております。歌番組の「シオノギ・ミュージックフェア」のテーマソングは、アレンジは現代風に変わりましたが、今でも演奏されています。童謡では「1年生になったら」や「こぶたぬきつねこ」を書いています。このように父直純は、たくさんの曲を書いていましたが、「作曲へのモチベーションは何ですか」と質問されたときに、はっきりと「締め切りです」と答えていました。本当に締め切り間近にならないと仕事が出来ない人でした。毎晩のように飲み歩いて、ギリギリまで面白いことを探してため込んで、最後の瞬間に楽譜に書き出すというのが父の流儀だったのかなと思います。
1979年と1980年の2年間、父は夏のオフシーズンに開催されるボストン・ポップスに指揮者として参加しました。この時代のボストンポップスのプログラムの面白いところはインターミッションが2回あることです。ボストンシンフォニーホールという素晴らしいシューボックス型のホールの座席を全部取外し、テーブルを置き、観客はそこでビールやワインを飲み、合間には食事をするというもので、これには父も驚いていました。ホールが社交の場でもあり、コンサートの合間のインターミッションもコンサートの重要な一部だったのです。こういうゆったりとした音楽の楽しみ方を日本でもやりたいとずっと思っていますが、時々チャンスはあるものの、なかなか続けてやることは出来ずにいます。
このボストン・ポップスのようなことをやりたいという話を私はいろいろな人にしていました。2012年当時ですが、どこかに何かうまい話はないかと話したところ、友人からミャンマーが民主化している、クラシックなどは全くないと思うので今行けば面白いことができるかもしれないと言われました。1985年に公開された市川崑監督の映画「ビルマの竪琴」は父直純が音楽を担当したこともあり、何かしらのつながりを感じて2013年にミャンマーに飛びました。
当時のミャンマーは、こんなところにオーケストラなどあるのかと思うほどの状況でした。首都ヤンゴンにある音楽院を訪ねましたが、音楽院と呼べるような学校ではありませんでした。しかし、オーケストラはあると聞いたので、実際に見に行ったところ、どうしようもないほど下手でした。これは大変だからもう日本に帰ろうと思っていたら、指揮者なら指揮をして欲しいと言われてその場で指揮をすることになりました。楽譜は何があるかと尋ねたらシューベルトの「未完成」を持ってきました。「未完成」にはトロンボーンも入っているので、トロンボーンはどこにあるのかと尋ねると、うちのオーケストラにトロンボーン奏者は居ないと平気で答えるのです。楽器も揃わず、楽譜もコピーばかりで譜面台からパラパラ落ちるのを拾いながら演奏するような状態でしたが、そのオーケストラの中に非常に熱心な担当者がいて、見捨てないでほしいとすがるような目で、どうしたらこれから上手になれるのかと尋ねられました。ミャンマーはこれから民主化されて色んな事が出来るはずだから教えてほしいと頼まれました。そこで私は手弁当でミャンマーに通い始めるようになりました。
ミャンマーの国営テレビ局に何か放送番組を作ってほしい、そうすれば私が来る意味ややりがいがあるからと頼んだところ、2013年に番組を作ってくれました。下手ながらも1週間ほどレッスンして演奏しました。そのうちコンサートをやろうという話になり、ミャンマーの国家プロジェクトとして承認を得るという話になりました。国家プロジェクトにはなりましたが資金が国からは出てきません。そこであちこちに相談したところ、日本の国際交流基金が資金を出してくれることになり、そこからどんどんと広がっていきました。アウン・サン・スーチーさんからも、これからも頑張ってほしいと言われましたが、その後彼女は軟禁されてしまいました。ミャンマーでの活動は非常に面白かったのですが、コロナとその後のクーデターのため、今は私が現地で活動することは難しい状態になっています。
そのような状態の中で、父がやっていたようなイメージのオーケストラのコンサートをやりたいと思い、映画音楽のコンサートや子供のオーケストラなどを一生懸命やっております。先日、シンガポールで子供たちのオーケストラのフェスティバルがあるというので、見に行ってきました。シンガポールは国立のナショナル・ユース・オーケストラがあり、子供たちのオーケストラが国家プロジェクトのようになっています。シンガポールだけでなく、台湾、マカオ、香港、マレーシアなどの子供たちが参加しているのですが、日本だけが蚊帳の外に置かれています。日本の子供たちをシンガポールなどに連れて行って、一緒にフェスティバルにも参加できるようにするのが今の私の課題となっています。今、私たちがミャンマーに行くのは難しいので、いずれはミャンマーの子供たちもこのようなプロジェクトに呼んで一緒に参加できるような方法があれば良いなと考えています。
この辺で今日のお話は終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
希望の音を再び ミャンマーのオーケストラで演奏した日々が育むもの(朝日新聞デジタル)
皆さんこんにちは。今日は、私の父、山本直純の話と、私がミャンマーでオーケストラの指導をしていることなどをお話したいと思います。
父、山本直純は1932年生まれで、12月16日というベートーベンと同じ誕生日であることが自慢でした。2002年に69歳で亡くなり、昨年2022年は生誕90年、没後20年ということで、コンサートなどで取り上げていただく機会が少し増えました。
コマーシャルやテレビ番組で大きな声で豪快に笑う父の姿が印象的だったせいか、私が子供の頃は、父が家ではどんな人なのかとよく尋ねられました。父直純がどのような人だったかは色々な切り口があると思いますが、一つ特徴的なことはなんでも混ぜこぜにするのが好きな人でした。食べ物でもトーストに納豆とバターとチーズを乗せて混ぜて食べたり、カレーにおでんを入れて食べたり、外食に行っても色々なものを混ぜて食べたり、他の人にも美味しいぞといって押し付けたりしていました。よく言えば創意工夫かもしれませんが、それを無理やり押し付けるというのが父の真骨頂だったと思います。
こういう部分は父の音楽にも表れているところがあります。父が編曲した「8時だヨ!全員集合」のオープニングテーマは、北海盆唄をアレンジしたものです。「オーケストラがやってきた」のテーマソングもヨハン・シュトラウスの曲をアレンジしたものです。あまり知られていませんが、父の交響曲「宿命」はベートーベンの交響曲1番から9番の良い所を繋ぎ合わせたものですし、有名なピアノ協奏曲を繋げた「ヘンペラー」という作品もありました。作曲というより編曲、いえ、「変曲」作品です。普通は自分で作曲したオリジナル作品を世に残したいと思うのですが、父はみんなが知っているメロディーを使った方が楽しいだろうと考えていたようです。
父が作曲した曲をご存知ない方もいらっしゃると思いますが、映画の「男はつらいよ」では49作の音楽をすべて作曲しています。ドラマでは大河ドラマの「風と雲と虹と」、「武田信玄」の音楽も書いております。歌番組の「シオノギ・ミュージックフェア」のテーマソングは、アレンジは現代風に変わりましたが、今でも演奏されています。童謡では「1年生になったら」や「こぶたぬきつねこ」を書いています。このように父直純は、たくさんの曲を書いていましたが、「作曲へのモチベーションは何ですか」と質問されたときに、はっきりと「締め切りです」と答えていました。本当に締め切り間近にならないと仕事が出来ない人でした。毎晩のように飲み歩いて、ギリギリまで面白いことを探してため込んで、最後の瞬間に楽譜に書き出すというのが父の流儀だったのかなと思います。
1979年と1980年の2年間、父は夏のオフシーズンに開催されるボストン・ポップスに指揮者として参加しました。この時代のボストンポップスのプログラムの面白いところはインターミッションが2回あることです。ボストンシンフォニーホールという素晴らしいシューボックス型のホールの座席を全部取外し、テーブルを置き、観客はそこでビールやワインを飲み、合間には食事をするというもので、これには父も驚いていました。ホールが社交の場でもあり、コンサートの合間のインターミッションもコンサートの重要な一部だったのです。こういうゆったりとした音楽の楽しみ方を日本でもやりたいとずっと思っていますが、時々チャンスはあるものの、なかなか続けてやることは出来ずにいます。
このボストン・ポップスのようなことをやりたいという話を私はいろいろな人にしていました。2012年当時ですが、どこかに何かうまい話はないかと話したところ、友人からミャンマーが民主化している、クラシックなどは全くないと思うので今行けば面白いことができるかもしれないと言われました。1985年に公開された市川崑監督の映画「ビルマの竪琴」は父直純が音楽を担当したこともあり、何かしらのつながりを感じて2013年にミャンマーに飛びました。
当時のミャンマーは、こんなところにオーケストラなどあるのかと思うほどの状況でした。首都ヤンゴンにある音楽院を訪ねましたが、音楽院と呼べるような学校ではありませんでした。しかし、オーケストラはあると聞いたので、実際に見に行ったところ、どうしようもないほど下手でした。これは大変だからもう日本に帰ろうと思っていたら、指揮者なら指揮をして欲しいと言われてその場で指揮をすることになりました。楽譜は何があるかと尋ねたらシューベルトの「未完成」を持ってきました。「未完成」にはトロンボーンも入っているので、トロンボーンはどこにあるのかと尋ねると、うちのオーケストラにトロンボーン奏者は居ないと平気で答えるのです。楽器も揃わず、楽譜もコピーばかりで譜面台からパラパラ落ちるのを拾いながら演奏するような状態でしたが、そのオーケストラの中に非常に熱心な担当者がいて、見捨てないでほしいとすがるような目で、どうしたらこれから上手になれるのかと尋ねられました。ミャンマーはこれから民主化されて色んな事が出来るはずだから教えてほしいと頼まれました。そこで私は手弁当でミャンマーに通い始めるようになりました。
ミャンマーの国営テレビ局に何か放送番組を作ってほしい、そうすれば私が来る意味ややりがいがあるからと頼んだところ、2013年に番組を作ってくれました。下手ながらも1週間ほどレッスンして演奏しました。そのうちコンサートをやろうという話になり、ミャンマーの国家プロジェクトとして承認を得るという話になりました。国家プロジェクトにはなりましたが資金が国からは出てきません。そこであちこちに相談したところ、日本の国際交流基金が資金を出してくれることになり、そこからどんどんと広がっていきました。アウン・サン・スーチーさんからも、これからも頑張ってほしいと言われましたが、その後彼女は軟禁されてしまいました。ミャンマーでの活動は非常に面白かったのですが、コロナとその後のクーデターのため、今は私が現地で活動することは難しい状態になっています。
そのような状態の中で、父がやっていたようなイメージのオーケストラのコンサートをやりたいと思い、映画音楽のコンサートや子供のオーケストラなどを一生懸命やっております。先日、シンガポールで子供たちのオーケストラのフェスティバルがあるというので、見に行ってきました。シンガポールは国立のナショナル・ユース・オーケストラがあり、子供たちのオーケストラが国家プロジェクトのようになっています。シンガポールだけでなく、台湾、マカオ、香港、マレーシアなどの子供たちが参加しているのですが、日本だけが蚊帳の外に置かれています。日本の子供たちをシンガポールなどに連れて行って、一緒にフェスティバルにも参加できるようにするのが今の私の課題となっています。今、私たちがミャンマーに行くのは難しいので、いずれはミャンマーの子供たちもこのようなプロジェクトに呼んで一緒に参加できるような方法があれば良いなと考えています。
この辺で今日のお話は終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
希望の音を再び ミャンマーのオーケストラで演奏した日々が育むもの(朝日新聞デジタル)
卓話「木で出来た薔薇で日本の魅力を内外に~五十歳からの転身~」
株式会社Lino Lino代表取締役 専務 木下元介さま
2023年8月17日

 皆様、只今ご紹介に預かりました株式会社Lino Linoの木下でございます。
今皆様にお配りした削り木は青森県のヒバを昨日私が削ったばかりの物です。是非香りをお試しください。この削り木を用いて1枚1枚を花びらにして薔薇を制作し販売しております。
まず、この木の薔薇と事業のご説明の後、私が丸紅を早期退職して転身した時の心境や経緯をお話したいと思います。
この薔薇には4つの特徴があります。一つ目は、鉋という日本古来の道具を用いて美しい曲線美を表現している点です。非常に壊れやすくて扱いが難しいのですが、熟達した技巧で、手で折って麻ひもで縛って造っております。
二つ目は香りです。アロマオイルを垂らしてディフューザーとしてお使いいただけます。お風呂に浮かべて何十回も優雅に香りを楽しんでいただけます。
三つ目は普遍性です。大きな衝撃さえ与えなければ、形が崩れることはありません。ヒバの防水、抗菌、防虫作用といったものも合わせて楽しんでいただけるかと思います。
四つ目がSDGsアートという点です。特定の商品を除いては製材所で廃材をもらってきて使えるところを用いて造っております。最近ではアップサイクルと呼ばれるものになると思います。
こうした商品には大きく分けて3つのコンセプトがあります。一つ目が日本の魅力です。自然や鉋、繊細な手仕事といった日本の魅力を感じていただきたいと考えています。
二つ目は、敢えて壊れやすい素材を使い、不揃いでも丁寧に接すればきれいな花になるというメッセージを込めて造っております。昨年3月に個展を行いましたが折しもロシアのウクライナ侵攻が始まった時期で、個展のテーマは自然や平和を大切にというものでした。
そして三つ目のコンセプトがLino Linoという私どもの社名ですが、ハワイ語で結ぶ、輝くという意味です。私どもの作品に思いを込めて贈っていただき、贈った方と贈られた方を結び、さらに輝くような笑顔になっていただきたい。そういったコンセプトを込めて造っております。
次に、私が50歳で大きな決断をして会社を辞め、この事業にチャレンジした経緯をお話させていただきます。
きっかけは大きな大きな危機感でした。その危機感は4年間のシンガポール駐在時に感じたものですが、振り返れば私の人生はいつも何かしらの危機感に押されて変化してきました。
私は昭和45年、一億総中流家庭の時代に、サラリーマンの父と専業主婦の母の間に生まれました。幼い頃、母が夜な夜な家計簿を前にお金が無いとうなっている姿を見て、何かしらの経済的な危機感が私に覆いかぶさっていました。父は転勤族でした。引っ越しの度に父の会社の同僚が集まって荷物を運ぶのですが、腰を痛めたり怪我をする姿を見て、子供心に会社は非常に厳しいところだと感じ、父と同じ会社だけには入っちゃいけないと思いました。そこで、良い会社に入るためには良い大学、良い高校、良い中学に入る必要があると考えました。危機感に押されて必死に勉強して名古屋の東海中学を受験して合格しました。しかし、父が東京に転勤することになり、芝学園に、なぜか面接だけで編入が決まりました。編入生は正規の編入試験を受けて入ってきていますが、私は受けていません。もし非正規の入学だと問題提起をされたら、この学校に居られなくなるのではないかという危機感を抱えて6年間必死に勉強して、高校の卒業式では総代として答辞を読ませていただきました。大学時代も経済的な危機感から学生起業していたことを評価されてか商社を志して入社いたしました。普通はポジティブな要因で頑張るのかもしれませんが、私はいつも大きな危機感が原動力になっていました。
丸紅に入り39歳の時にシンガポールに赴任しました。シンガポールでは、労働者がトラックの荷台に乗せられて運ばれる姿や、私たちが住むコンドミニアムのベランダに設置された狭くて貧相なメイド部屋を見て、貧困や格差の意味合いを思い知らされました。欧米による植民地の統治とはどういうものかをまざまざと理解しました。一方で、シンガポールは、給与格差はあるものの国の政策が行き渡っており、国民一人当たりのGDPも2007年には日本を追い越しています。国全体が国民の資産を大切に守り、国の成長イコール個人の豊かさに直結する政策を行っています。そうしたシンガポールを見て4年後に私は帰国しました。日本は失われた30年の間に、消費税は10%に上がり、社会保険料、医療費、年金を見ても、不動産や教育費の暴騰で、気づかぬ内にどんどん貧しくなり、豊かさが失われて非常に暮らしにくい国になっており、今までにない危機感に襲われました。
そこで私は世界に誇れる日本の歴史や伝統、観光資源を輸出、もしくは外国の方に売ることをやりたいと思い、数々の和文化発信のイベントを始めました。2019年に原宿の東郷神社でナイトタイムエコノミーとしてイベントを開催しましたが、その直後にコロナ危機に襲われました。これで5年くらいは人が集まるイベントはできないだろうと考え、イベントに集まった大工の棟梁とハンドメイド作家から生まれたのがこの木の薔薇です。色々と紆余曲折もありましたが、最後はコロナ危機が私にとっての契機となって、この木で出来た薔薇を通じて日本の魅力を伝えたいという思いで、現在はスーツを脱いで上野桜木の店頭で日々鉋を削る生活をしております。
この仕事を始めて思いがけず得たことがあります。お客さまが木の薔薇を買って下さった時に伺った話などから、相手を思う気持ちを伝えるのは、照れもあり、なかなか難しいことかもしれないと思いました。でも、この木の薔薇がその気持ちを伝えるお手伝いをしてくれるなら、この仕事を始めて良かったと思います。働くということは人の役に立ち、喜んでもらいそれがお金という経済的価値に変わっていく。辛いことばかりではなく、尊くて喜ばしいことなのではないかと、この転身をはかってから日々感じているところです。これからまだまだ努力が必要ですが、引き続き頑張ってまいりたいと思っております。
最後までご清聴ありがとうございました。
皆様、只今ご紹介に預かりました株式会社Lino Linoの木下でございます。
今皆様にお配りした削り木は青森県のヒバを昨日私が削ったばかりの物です。是非香りをお試しください。この削り木を用いて1枚1枚を花びらにして薔薇を制作し販売しております。
まず、この木の薔薇と事業のご説明の後、私が丸紅を早期退職して転身した時の心境や経緯をお話したいと思います。
この薔薇には4つの特徴があります。一つ目は、鉋という日本古来の道具を用いて美しい曲線美を表現している点です。非常に壊れやすくて扱いが難しいのですが、熟達した技巧で、手で折って麻ひもで縛って造っております。
二つ目は香りです。アロマオイルを垂らしてディフューザーとしてお使いいただけます。お風呂に浮かべて何十回も優雅に香りを楽しんでいただけます。
三つ目は普遍性です。大きな衝撃さえ与えなければ、形が崩れることはありません。ヒバの防水、抗菌、防虫作用といったものも合わせて楽しんでいただけるかと思います。
四つ目がSDGsアートという点です。特定の商品を除いては製材所で廃材をもらってきて使えるところを用いて造っております。最近ではアップサイクルと呼ばれるものになると思います。
こうした商品には大きく分けて3つのコンセプトがあります。一つ目が日本の魅力です。自然や鉋、繊細な手仕事といった日本の魅力を感じていただきたいと考えています。
二つ目は、敢えて壊れやすい素材を使い、不揃いでも丁寧に接すればきれいな花になるというメッセージを込めて造っております。昨年3月に個展を行いましたが折しもロシアのウクライナ侵攻が始まった時期で、個展のテーマは自然や平和を大切にというものでした。
そして三つ目のコンセプトがLino Linoという私どもの社名ですが、ハワイ語で結ぶ、輝くという意味です。私どもの作品に思いを込めて贈っていただき、贈った方と贈られた方を結び、さらに輝くような笑顔になっていただきたい。そういったコンセプトを込めて造っております。
次に、私が50歳で大きな決断をして会社を辞め、この事業にチャレンジした経緯をお話させていただきます。
きっかけは大きな大きな危機感でした。その危機感は4年間のシンガポール駐在時に感じたものですが、振り返れば私の人生はいつも何かしらの危機感に押されて変化してきました。
私は昭和45年、一億総中流家庭の時代に、サラリーマンの父と専業主婦の母の間に生まれました。幼い頃、母が夜な夜な家計簿を前にお金が無いとうなっている姿を見て、何かしらの経済的な危機感が私に覆いかぶさっていました。父は転勤族でした。引っ越しの度に父の会社の同僚が集まって荷物を運ぶのですが、腰を痛めたり怪我をする姿を見て、子供心に会社は非常に厳しいところだと感じ、父と同じ会社だけには入っちゃいけないと思いました。そこで、良い会社に入るためには良い大学、良い高校、良い中学に入る必要があると考えました。危機感に押されて必死に勉強して名古屋の東海中学を受験して合格しました。しかし、父が東京に転勤することになり、芝学園に、なぜか面接だけで編入が決まりました。編入生は正規の編入試験を受けて入ってきていますが、私は受けていません。もし非正規の入学だと問題提起をされたら、この学校に居られなくなるのではないかという危機感を抱えて6年間必死に勉強して、高校の卒業式では総代として答辞を読ませていただきました。大学時代も経済的な危機感から学生起業していたことを評価されてか商社を志して入社いたしました。普通はポジティブな要因で頑張るのかもしれませんが、私はいつも大きな危機感が原動力になっていました。
丸紅に入り39歳の時にシンガポールに赴任しました。シンガポールでは、労働者がトラックの荷台に乗せられて運ばれる姿や、私たちが住むコンドミニアムのベランダに設置された狭くて貧相なメイド部屋を見て、貧困や格差の意味合いを思い知らされました。欧米による植民地の統治とはどういうものかをまざまざと理解しました。一方で、シンガポールは、給与格差はあるものの国の政策が行き渡っており、国民一人当たりのGDPも2007年には日本を追い越しています。国全体が国民の資産を大切に守り、国の成長イコール個人の豊かさに直結する政策を行っています。そうしたシンガポールを見て4年後に私は帰国しました。日本は失われた30年の間に、消費税は10%に上がり、社会保険料、医療費、年金を見ても、不動産や教育費の暴騰で、気づかぬ内にどんどん貧しくなり、豊かさが失われて非常に暮らしにくい国になっており、今までにない危機感に襲われました。
そこで私は世界に誇れる日本の歴史や伝統、観光資源を輸出、もしくは外国の方に売ることをやりたいと思い、数々の和文化発信のイベントを始めました。2019年に原宿の東郷神社でナイトタイムエコノミーとしてイベントを開催しましたが、その直後にコロナ危機に襲われました。これで5年くらいは人が集まるイベントはできないだろうと考え、イベントに集まった大工の棟梁とハンドメイド作家から生まれたのがこの木の薔薇です。色々と紆余曲折もありましたが、最後はコロナ危機が私にとっての契機となって、この木で出来た薔薇を通じて日本の魅力を伝えたいという思いで、現在はスーツを脱いで上野桜木の店頭で日々鉋を削る生活をしております。
この仕事を始めて思いがけず得たことがあります。お客さまが木の薔薇を買って下さった時に伺った話などから、相手を思う気持ちを伝えるのは、照れもあり、なかなか難しいことかもしれないと思いました。でも、この木の薔薇がその気持ちを伝えるお手伝いをしてくれるなら、この仕事を始めて良かったと思います。働くということは人の役に立ち、喜んでもらいそれがお金という経済的価値に変わっていく。辛いことばかりではなく、尊くて喜ばしいことなのではないかと、この転身をはかってから日々感じているところです。これからまだまだ努力が必要ですが、引き続き頑張ってまいりたいと思っております。
最後までご清聴ありがとうございました。


卓話「経営者×格闘技 これまでにない格闘技 イベントにかける夢」
元ISKAオリエンタル世界スーパーウェルター級チャンピオン 小比類巻貴之さま
2023年7月27日

 皆さんこんにちは。小比類巻貴之と申します。皆さんの前でお話させていただく機会をいただきまして誠に有難うございます。
私は青森県三沢市生まれ、現在45歳です。18歳まで青森県三沢市にいました。1997年19歳でプロデビューし、プロ2戦目でK-1チャンピオンにもなっている魔裟斗選手にKO勝ちしました。1999年21歳の時にK-1初参戦し、2004年、2005年、2009年にK-1ジャパントーナメントで優勝し、2010年に現役を引退しました。
現役時代の夢は、強くなりたいという一言です。13歳の時に強くなりたいと思い、テレビでボクシングの試合をテレビで見たときにこれが強いということかと知りました。しかし、三沢市にはボクシングジムが無かったので、空手の道場に通い始めました。13歳の誕生日プレゼントで父からもらったサンドバッグを吊るす部屋を父と作り、格闘家としての意識が目覚めていきました。
2010年32歳で現役を引退し、そこから第二の人生が始まりました。第二の人生の夢は、経営者への格闘技指導と経営者による新しい格闘技イベントです。イベントの収益をチャリティに充てる経営者格闘技イベントは2017年12月に始まりました。本物の強さとは何かを伝えるために、名前をEXECUTIVE FIGHT-武士道として、2020年9月に第1回目を開催しました。この大会は、コロナ禍でもなんとかやってきて、3年後の2023年9月に第9回が開催することができます。
経営者たちは試合が決まると、試合に出ない人と一緒に合宿を行います。そこで試合経験がある人を含めて交流し、スパーリング、減量を行います。過去には試合が決まって50日で15キロやせた方もいます。記者会見も行い、緊張で試合当日を迎え、打ち上げも行います。
憎くもない相手と闘うので、試合の後は感謝の気持ちが生まれ、苦楽を共にした相手と本当の仲間になります。まだまだやれるという自信がつき、リングで殴り合った相手、試合をサポートしてくれた人、一緒に合宿した仲間、全ての人に対して感謝の心が生まれます。この感謝の心が一番の強さを作ります。
私は2004年、2005年2年連続でK-1トーナメントのチャンピオンになりました。トーナメントなので1日に3回試合します。2004年のトーナメントでは、試合中に鼻を骨折し、肩を脱臼し、足を骨折しながらもなんとかリングに立って勝ちました。
2005年もチャンピオンベルトを獲得しましたが、2006年、2007年、2008年はチャンピオンになれませんでした。それは、どんな相手でも受けようと思って、前の世界チャンピオンといった選手たちと闘っているうちに、身体だけでなく心もボロボロになったからです。何かおかしいと思いましたが、当時は自分を見つめずに周りの環境などのせいだと考えてしまいました。すると、チームの中や家族との関係も悪くなり、負けの負のオーラを発するようになったのだと思います。
ある時サンドバッグを蹴っていたら、突然膝からカクンと落ちるようになってしまいました。病院で診てもらいましたが結局原因がわからず、私は地元の青森に帰りました。地元の小さなボクシングジムに行って、サンドバッグをパンチだけで殴る練習をさせてもらいました。あるとき、そのジムのトイレの壁に書いてある「ストレスがあるのは感謝が足りないからだ」という言葉が心に突き刺さりました。そこで、もう一度東京で試合をしようと思い、東京に戻りました。
東京では少し環境を変えて、20代の若い選手しかいない道場に頭を下げて一からスタートしました。すると3カ月後に2009年の日本トーナメント代表決定戦があるので出場して欲しいと言われ、出ますと答えました。なんで小比類巻さんがこんなところにいるんですかと言われるような環境の中で若い子たちとやっていたら、どんどん復活していき、久しぶりの試合でしたが2009年のK-1でチャンピオンになることができました。
この「ストレスがあるのは感謝が足りないからだ」という言葉。この出会った感謝という言葉、これが子供の頃から2010年32歳までやってきた格闘技で自分を一番強くするものだと気づきました。
プロの場合、試合の準備は50日前から始まります。50日前に対戦相手が決まったという連絡が来ます。それを受けると契約書が送られてきてサインをして試合が決まります。対戦相手が決まるとその相手の試合の映像をトレーナーと見て、細かいデータを調べていきます。
40日前くらいになるとどんな練習をするかを決めます。そして普段の私生活、交友関係や食事会などをほとんどシャットアウトします。私の場合、現役のときは試合の40日前の体重は83キロありました。試合の時は体重を70キロにするために40日間で13キロ落とさなければなりません。練習メニューをこなすと試合の1週間前には残り3キロくらいになります。試合の前日午前11時に計量があります。一番苦しいのはその1日前です。1週間前の残り3キロの調整がとても難しく、水抜きということをやります。走ったり動いたりして汗をかいても水を取りません。カラッカラの状態になっているのが、計量の前日の夜です。計量当日に300グラムオーバーしていると、最後の手段としてガムを噛んでつばを吐いて減量します。そして計量で合格となると、翌日の試合に備えて3リットルの常温の水を飲み、5食くらい食べます。最初は胃袋にやさしいおかゆやうどんから始めて、最後にちゃんこ鍋を食べます。翌日の試合前の夜は、朝70キロだった体重が寝る前には78キロくらいになっています。
明日は試合だと思うと夜は緊張して寝られなくなります。そういう時は、トレーナーと戦略を練ったこと、一緒にトレーニングしてくれた仲間たち、練習した場所を思い出します。携帯には応援のメッセージがたくさん入っています。そうすると、自分の中に感謝の気持ちがどんどん生まれてきます。練習で100%になった自分が、この感謝の気持ちでもう20%増えて、120%の気持ちが出来上がります。この120%で闘った試合はすべてチャンピオンベルトを獲得しています。
私の夢のお話をさせていただきました。その夢を通して伝えたいのは、本物の強さとは感謝の心だということです。最近は相手を挑発したり格闘技なのか暴力なのかわからないものも出てきています。一般的には、格闘技は感謝とは真逆の世界だと思う方もいるかもしれません。
しかし、格闘技で自分を強くするのは感謝の心です。これから経営者やビジネスで活躍している皆さんと、このイベントを通して一番伝えていきたいことが、この感謝の心です。
本日は聞いていただき有難うございました。
皆さんこんにちは。小比類巻貴之と申します。皆さんの前でお話させていただく機会をいただきまして誠に有難うございます。
私は青森県三沢市生まれ、現在45歳です。18歳まで青森県三沢市にいました。1997年19歳でプロデビューし、プロ2戦目でK-1チャンピオンにもなっている魔裟斗選手にKO勝ちしました。1999年21歳の時にK-1初参戦し、2004年、2005年、2009年にK-1ジャパントーナメントで優勝し、2010年に現役を引退しました。
現役時代の夢は、強くなりたいという一言です。13歳の時に強くなりたいと思い、テレビでボクシングの試合をテレビで見たときにこれが強いということかと知りました。しかし、三沢市にはボクシングジムが無かったので、空手の道場に通い始めました。13歳の誕生日プレゼントで父からもらったサンドバッグを吊るす部屋を父と作り、格闘家としての意識が目覚めていきました。
2010年32歳で現役を引退し、そこから第二の人生が始まりました。第二の人生の夢は、経営者への格闘技指導と経営者による新しい格闘技イベントです。イベントの収益をチャリティに充てる経営者格闘技イベントは2017年12月に始まりました。本物の強さとは何かを伝えるために、名前をEXECUTIVE FIGHT-武士道として、2020年9月に第1回目を開催しました。この大会は、コロナ禍でもなんとかやってきて、3年後の2023年9月に第9回が開催することができます。
経営者たちは試合が決まると、試合に出ない人と一緒に合宿を行います。そこで試合経験がある人を含めて交流し、スパーリング、減量を行います。過去には試合が決まって50日で15キロやせた方もいます。記者会見も行い、緊張で試合当日を迎え、打ち上げも行います。
憎くもない相手と闘うので、試合の後は感謝の気持ちが生まれ、苦楽を共にした相手と本当の仲間になります。まだまだやれるという自信がつき、リングで殴り合った相手、試合をサポートしてくれた人、一緒に合宿した仲間、全ての人に対して感謝の心が生まれます。この感謝の心が一番の強さを作ります。
私は2004年、2005年2年連続でK-1トーナメントのチャンピオンになりました。トーナメントなので1日に3回試合します。2004年のトーナメントでは、試合中に鼻を骨折し、肩を脱臼し、足を骨折しながらもなんとかリングに立って勝ちました。
2005年もチャンピオンベルトを獲得しましたが、2006年、2007年、2008年はチャンピオンになれませんでした。それは、どんな相手でも受けようと思って、前の世界チャンピオンといった選手たちと闘っているうちに、身体だけでなく心もボロボロになったからです。何かおかしいと思いましたが、当時は自分を見つめずに周りの環境などのせいだと考えてしまいました。すると、チームの中や家族との関係も悪くなり、負けの負のオーラを発するようになったのだと思います。
ある時サンドバッグを蹴っていたら、突然膝からカクンと落ちるようになってしまいました。病院で診てもらいましたが結局原因がわからず、私は地元の青森に帰りました。地元の小さなボクシングジムに行って、サンドバッグをパンチだけで殴る練習をさせてもらいました。あるとき、そのジムのトイレの壁に書いてある「ストレスがあるのは感謝が足りないからだ」という言葉が心に突き刺さりました。そこで、もう一度東京で試合をしようと思い、東京に戻りました。
東京では少し環境を変えて、20代の若い選手しかいない道場に頭を下げて一からスタートしました。すると3カ月後に2009年の日本トーナメント代表決定戦があるので出場して欲しいと言われ、出ますと答えました。なんで小比類巻さんがこんなところにいるんですかと言われるような環境の中で若い子たちとやっていたら、どんどん復活していき、久しぶりの試合でしたが2009年のK-1でチャンピオンになることができました。
この「ストレスがあるのは感謝が足りないからだ」という言葉。この出会った感謝という言葉、これが子供の頃から2010年32歳までやってきた格闘技で自分を一番強くするものだと気づきました。
プロの場合、試合の準備は50日前から始まります。50日前に対戦相手が決まったという連絡が来ます。それを受けると契約書が送られてきてサインをして試合が決まります。対戦相手が決まるとその相手の試合の映像をトレーナーと見て、細かいデータを調べていきます。
40日前くらいになるとどんな練習をするかを決めます。そして普段の私生活、交友関係や食事会などをほとんどシャットアウトします。私の場合、現役のときは試合の40日前の体重は83キロありました。試合の時は体重を70キロにするために40日間で13キロ落とさなければなりません。練習メニューをこなすと試合の1週間前には残り3キロくらいになります。試合の前日午前11時に計量があります。一番苦しいのはその1日前です。1週間前の残り3キロの調整がとても難しく、水抜きということをやります。走ったり動いたりして汗をかいても水を取りません。カラッカラの状態になっているのが、計量の前日の夜です。計量当日に300グラムオーバーしていると、最後の手段としてガムを噛んでつばを吐いて減量します。そして計量で合格となると、翌日の試合に備えて3リットルの常温の水を飲み、5食くらい食べます。最初は胃袋にやさしいおかゆやうどんから始めて、最後にちゃんこ鍋を食べます。翌日の試合前の夜は、朝70キロだった体重が寝る前には78キロくらいになっています。
明日は試合だと思うと夜は緊張して寝られなくなります。そういう時は、トレーナーと戦略を練ったこと、一緒にトレーニングしてくれた仲間たち、練習した場所を思い出します。携帯には応援のメッセージがたくさん入っています。そうすると、自分の中に感謝の気持ちがどんどん生まれてきます。練習で100%になった自分が、この感謝の気持ちでもう20%増えて、120%の気持ちが出来上がります。この120%で闘った試合はすべてチャンピオンベルトを獲得しています。
私の夢のお話をさせていただきました。その夢を通して伝えたいのは、本物の強さとは感謝の心だということです。最近は相手を挑発したり格闘技なのか暴力なのかわからないものも出てきています。一般的には、格闘技は感謝とは真逆の世界だと思う方もいるかもしれません。
しかし、格闘技で自分を強くするのは感謝の心です。これから経営者やビジネスで活躍している皆さんと、このイベントを通して一番伝えていきたいことが、この感謝の心です。
本日は聞いていただき有難うございました。
卓話「ウクライナ人道支援の現場」
認定NPO法人 難民を助ける会(AAR Japan)東京事務局広報兼関西担当 中坪央暁さま
2023年7月20日
 ロータリアンの皆様、こんにちは。ご紹介いただきましたAAR Japan難民を助ける会の中坪と申します。本日はウクライナ人道支援の現場ということでお話しいたします。私はつい先日、モルドバへの出張から帰ってきたばかりです。ウクライナのキーウを訪れた時には空襲警報が鳴って地下に退避するという経験もしております。
AAR Japan難民を助ける会は1979年に設立された40年以上の歴史があり、「日本生まれの国際NGO」としては最大規模の団体です。日本国内を含め、現在世界16カ国で難民支援、開発途上国の障がい者の自立支援、災害被災者の緊急支援などを行っております。創設者は既に故人ですが、明治生まれのバイリンガルのエネルギッシュな女性、相馬雪香です。明治から昭和にかけて活躍した政治家で「憲政の神様」と呼ばれた尾崎行雄の娘です。AARは日本国内、アジア、アフリカを中心に活動しており、昨年からウクライナとモルドバが加わりました。
ウクライナの人道危機のキーワードは「難民の9割は女性と子供たち」ということです。昨年2月24日にロシア軍のウクライナへの軍事侵攻が始まり、大量の難民が主にEU圏に逃れています。今、海外にいる難民が約800万人、国内避難民が約600万人にのぼり、第二次世界大戦以降で最大の人道危機と言われています。
ここでAAR のウクライナ人道支援の活動についてご紹介いたします。
いくつかの支援事業を行っておりますが、その一つが、ウクライナ国内にいる国内避難民に対する支援です。ポーランドのワルシャワに拠点を持つ修道会と連携して、ウクライナ西部のテルノピリ州にある修道院に身を寄せている避難民に対して、食料支援や医薬品、子供服などの衣料品を届ける支援を昨年3月から継続しています。また、AARのサポーターであるアウトドアグッズの企業モンベルから提供されたTシャツを現地に届けたほか、子供たちの通学や支援活動のために、ポーランドで中古車を調達して提供しております。ちなみにAARは特定の宗教を背景とする団体ではなく、修道会とはあくまで信頼できる現地協力団体として連携しています。
ウクライナの隣国モルドバの首都キシナウには私どもの現地事務所があり、日本人駐在員が常駐しております。
モルドバには、いわゆる難民キャンプは存在せず、大学の学生寮や公的な保養所などが難民を受け入れる滞在施設になっています。モルドバでの難民支援では、昨年3月以降、難民が身を寄せる大学の学生寮に食料を届けたり、現地のレストランと提携して温かい食事を提供したりする活動を行いました。
モルドバ北部では、現地のコミュニティから無償で家を提供されたウクライナ難民のために、現地の協力団体と連携して食料や生活用品、ストーブを焚くための一冬分の燃料を届けました。また、私どもがモルドバ現地の協力団体と共に運営する交流施設は、ウクライナとモルドバの子供たちが交流する場となっています。7月11日には、モルドバの首都キシナウに、難民が集うコミュニティセンターを新たに開設しました。
モルドバは非常に小さくて経済力も脆弱な国ですが、心の温かい人たちばかりで、ウクライナ難民をなんとか自分たちのコミュニティで支えようと奮闘しています。
大きな柱の一つである、ウクライナ国内の障がい者支援活動をご紹介します。ウクライナ国内には知的障がい者と身体障がい者を合わせて約270万人の障がい者がいます。もちろん、ウクライナには社会福祉制度がありますが、戦時下のため、政府や行政の障がい者対策は非常に滞っています。そこで私たちは、ウクライナの障がい者団体に資金や物資を提供する支援活動を行っています。障がい者施設では、ロシア軍による意図的な電力インフラへの攻撃による停電に悩まされていたため、この冬に発電機を調達して届けました。「日本の支援で発電機が届いた時には、みんなが涙を流した」と現地から報告を受けました。
もう一つの支援活動はウクライナの地雷対策です。ウクライナ国内にはロシア軍が埋設した地雷がたくさんあり、これが難民の帰還や復興の妨げになると予想されています。私たち自身が地雷除去の活動をしているわけではありませんが、イギリスのヘイロー・トラストという地雷除去を専門とするNGOと連携し、資金提供や情報共有を通じて、地雷の除去を進めております。
このウクライナ危機がいつまで続くのか。報道によるとプーチン大統領は非常に苦境に立たされており、軍の統制も効かなくなっているという話もありますが、プーチンとしては引くに引けない状況のようです。ウクライナ市民に話を聞くと、実はウクライナ側もこの戦争を辞められないという現実があります。ウクライナ国内の至る所に2014年以降の戦死者の遺影が張り出されています。私たちは昨年2月に戦争が始まったと認識していますが、現地ウクライナの人たちにとってロシアとの戦争は、2014年のクリミア併合、あるいは東部ドンバス地域の占拠から始まって8~9年続いていると受け止めています。多くの犠牲を払ってでも、奪われた領土を奪還するまで戦争を止めない、これはゼレンスキー大統領だけでなく、多くのウクライナ国民の考えだということを私は現地で色々な人の話を聞いて実感しました。
とはいえ、ウクライナの人たちはこの戦争が長引くことを望んでいるわけではありません。私がボロディアンカという町で出会った中年の女性は、「二人の息子のうち一人は2年前に東部戦線で戦死し、もう一人も今、ロシア軍と戦っている。愛する息子を二人とも失ったら私は生きていけない。この戦争は一体いつ終わるのでしょうか」と問わず語りに話しました。私は何も答えることができませんでした。奪われた領土を奪還するまで戦争を止めないというのが大きな世論であると同時に、一日も早く戦争が終わってほしいというのも、ウクライナ市民の偽らざる気持ちだと思います。
私たちの人道支援もいつまで続ければよいのか分かりませんが、仮に戦争が終わっても、難民が帰還し、国土を復興するには長い時間がかかります。長期的にこの支援活動を続けていく必要があると考えます。
皆様のお力添えをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ロータリアンの皆様、こんにちは。ご紹介いただきましたAAR Japan難民を助ける会の中坪と申します。本日はウクライナ人道支援の現場ということでお話しいたします。私はつい先日、モルドバへの出張から帰ってきたばかりです。ウクライナのキーウを訪れた時には空襲警報が鳴って地下に退避するという経験もしております。
AAR Japan難民を助ける会は1979年に設立された40年以上の歴史があり、「日本生まれの国際NGO」としては最大規模の団体です。日本国内を含め、現在世界16カ国で難民支援、開発途上国の障がい者の自立支援、災害被災者の緊急支援などを行っております。創設者は既に故人ですが、明治生まれのバイリンガルのエネルギッシュな女性、相馬雪香です。明治から昭和にかけて活躍した政治家で「憲政の神様」と呼ばれた尾崎行雄の娘です。AARは日本国内、アジア、アフリカを中心に活動しており、昨年からウクライナとモルドバが加わりました。
ウクライナの人道危機のキーワードは「難民の9割は女性と子供たち」ということです。昨年2月24日にロシア軍のウクライナへの軍事侵攻が始まり、大量の難民が主にEU圏に逃れています。今、海外にいる難民が約800万人、国内避難民が約600万人にのぼり、第二次世界大戦以降で最大の人道危機と言われています。
ここでAAR のウクライナ人道支援の活動についてご紹介いたします。
いくつかの支援事業を行っておりますが、その一つが、ウクライナ国内にいる国内避難民に対する支援です。ポーランドのワルシャワに拠点を持つ修道会と連携して、ウクライナ西部のテルノピリ州にある修道院に身を寄せている避難民に対して、食料支援や医薬品、子供服などの衣料品を届ける支援を昨年3月から継続しています。また、AARのサポーターであるアウトドアグッズの企業モンベルから提供されたTシャツを現地に届けたほか、子供たちの通学や支援活動のために、ポーランドで中古車を調達して提供しております。ちなみにAARは特定の宗教を背景とする団体ではなく、修道会とはあくまで信頼できる現地協力団体として連携しています。
ウクライナの隣国モルドバの首都キシナウには私どもの現地事務所があり、日本人駐在員が常駐しております。
モルドバには、いわゆる難民キャンプは存在せず、大学の学生寮や公的な保養所などが難民を受け入れる滞在施設になっています。モルドバでの難民支援では、昨年3月以降、難民が身を寄せる大学の学生寮に食料を届けたり、現地のレストランと提携して温かい食事を提供したりする活動を行いました。
モルドバ北部では、現地のコミュニティから無償で家を提供されたウクライナ難民のために、現地の協力団体と連携して食料や生活用品、ストーブを焚くための一冬分の燃料を届けました。また、私どもがモルドバ現地の協力団体と共に運営する交流施設は、ウクライナとモルドバの子供たちが交流する場となっています。7月11日には、モルドバの首都キシナウに、難民が集うコミュニティセンターを新たに開設しました。
モルドバは非常に小さくて経済力も脆弱な国ですが、心の温かい人たちばかりで、ウクライナ難民をなんとか自分たちのコミュニティで支えようと奮闘しています。
大きな柱の一つである、ウクライナ国内の障がい者支援活動をご紹介します。ウクライナ国内には知的障がい者と身体障がい者を合わせて約270万人の障がい者がいます。もちろん、ウクライナには社会福祉制度がありますが、戦時下のため、政府や行政の障がい者対策は非常に滞っています。そこで私たちは、ウクライナの障がい者団体に資金や物資を提供する支援活動を行っています。障がい者施設では、ロシア軍による意図的な電力インフラへの攻撃による停電に悩まされていたため、この冬に発電機を調達して届けました。「日本の支援で発電機が届いた時には、みんなが涙を流した」と現地から報告を受けました。
もう一つの支援活動はウクライナの地雷対策です。ウクライナ国内にはロシア軍が埋設した地雷がたくさんあり、これが難民の帰還や復興の妨げになると予想されています。私たち自身が地雷除去の活動をしているわけではありませんが、イギリスのヘイロー・トラストという地雷除去を専門とするNGOと連携し、資金提供や情報共有を通じて、地雷の除去を進めております。
このウクライナ危機がいつまで続くのか。報道によるとプーチン大統領は非常に苦境に立たされており、軍の統制も効かなくなっているという話もありますが、プーチンとしては引くに引けない状況のようです。ウクライナ市民に話を聞くと、実はウクライナ側もこの戦争を辞められないという現実があります。ウクライナ国内の至る所に2014年以降の戦死者の遺影が張り出されています。私たちは昨年2月に戦争が始まったと認識していますが、現地ウクライナの人たちにとってロシアとの戦争は、2014年のクリミア併合、あるいは東部ドンバス地域の占拠から始まって8~9年続いていると受け止めています。多くの犠牲を払ってでも、奪われた領土を奪還するまで戦争を止めない、これはゼレンスキー大統領だけでなく、多くのウクライナ国民の考えだということを私は現地で色々な人の話を聞いて実感しました。
とはいえ、ウクライナの人たちはこの戦争が長引くことを望んでいるわけではありません。私がボロディアンカという町で出会った中年の女性は、「二人の息子のうち一人は2年前に東部戦線で戦死し、もう一人も今、ロシア軍と戦っている。愛する息子を二人とも失ったら私は生きていけない。この戦争は一体いつ終わるのでしょうか」と問わず語りに話しました。私は何も答えることができませんでした。奪われた領土を奪還するまで戦争を止めないというのが大きな世論であると同時に、一日も早く戦争が終わってほしいというのも、ウクライナ市民の偽らざる気持ちだと思います。
私たちの人道支援もいつまで続ければよいのか分かりませんが、仮に戦争が終わっても、難民が帰還し、国土を復興するには長い時間がかかります。長期的にこの支援活動を続けていく必要があると考えます。
皆様のお力添えをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
卓話「訪日旅行の担い手として見る日本のポテンシャルと課題~持続的な観光立国に向けて~」
みちトラベルジャパン株式会社 代表取締役 茶田誠一さま
2023年6月15日
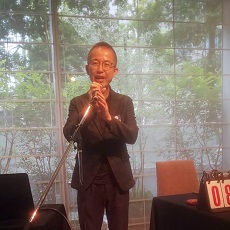
 皆さんこんにちは。ご紹介いただきました茶田と申します。
私は奈良県の出身で学生時代までは関西で過ごしておりました。社会人になって最初は政府系の金融機関で投融資をしていましたが、日本の魅力を世界の人に知ってほしい、そういう旅行会社をやりたいと思い、みちトラベルジャパンを創業したのが17年ほど前、35歳の時です。当時は日本への海外旅行者数は世界で31番目でしたが、その後旅行者数は右肩上がりで増加し、コロナ前の2019年には世界で12番目になりました。
私が創業した理由は、多岐に渡る日本の魅力を、もっと世界の人に旅を通じて知ってもらいたいと思ったからです。そして、魅力の幅があまりにも多様なので、パッケージツアーではなく、お客さまの希望や関心に合わせてコンシェルジュ的にテーラーメイドの旅行を提供したら喜ばれるだろうと思い、そういう会社に転職したいと思いましたが、見当たらなかったので自分で創業しました。
元々、奈良や京都に住んでいたので、海外の方々に歴史的な場所も見せたい、また東京のように都会的なところや自然も好きですので、日本の色々な場所を海外の方に案内したいと思ったのも創業に至った原体験の一つだったと思います。テーラーメイドのサービスを提供しているので、お客さまは欧米の方が過半数で、富裕層の知的好奇心の高く、こだわりの強い方に利用していただいています。
コロナ禍の期間は旅行業が低迷しておりましたので、我々の実業の経験を生かしたアドバイザリーや観光コンサルティング事業も新たに展開して参りました。
テーラーメイドの旅行サービスですので、最初に海外からのお客さまがどのようなことに関心があるかをヒヤリングすることから始めます。これまでに受けたリクエストの一部をご紹介いたします。典型的には、家族旅行で、家族みんなにとって日本は行ってみたい国なんだ、というのが旅の動機という方が多いです。また、結構マニアックな関心をお持ちの方も多いです。例えば、中山道や熊野古道を歩きたい(これはもはや有名ですが)、庭園が趣味なので日本でも庭園をひたすら見たい、北海道でバードウォッチングをしたい、地方の5つ星のsmall luxury hotelに宿泊したい、自分の家を作るためのインスピレーションを得るために有名建築家の建物をたくさん見たいなどです。総じて、与えられた情報に反応するというより、自分の中にやりたいことや関心が高いものをもともと持たれており、それを実現するために日本を旅したいと考えておられるという印象を受けております。旅は人生を豊かにするもの、という意識も強いように思います。日本人でもあまり日本国内を旅行されていない方がおられると思いますが、海外の観光客の中には日本が大好きになって何度も訪日される方が増えています。弊社の最近のお客さんが行った場所でも、新潟県十日町、宮崎県飫肥、小豆島の遍路札所など、皆さんも行かれたことが無い場所もあるかもしれません。日本は様々なテーマや関心に応えられる面白い国ですので、世界中のお客さまから注目されているのではないかと思っています。
これまでは「顧客の期待、顧客の体験」についてお話しましたが、少しこの業界の経済的な側面やビジネスとしての切り口をお話したいと思います。私が創業のビジネスプランを立てていた2004年~2005年頃は、海外からの訪日旅行客は600万人程度でした。その後、観光客が訪日旅行者数をけん引する形で、コロナ前には3000万人に達しました。なぜこれほど増加したかというと、世界の人びとの所得が拡大して海外旅行できる余裕が出てきたことがひとつの理由だと言えるでしょう。日本の成長率は主要国の中でも一番低く人口も減少しているのに比べ、海外での経済成長により拡大する世界の富を日本に取り込む一つの手段として、インバウンドが注目されていると思います。もう一つは日本の観光地の人気が高いことです。東京、京都、大阪ばかりでなく、四国でのお遍路や瀬戸内海での高級クルーズ船が注目されるなど、新たなマーケットや需要が作り出されているのです。
今、コロナ後のインバウンドが戻ってきていますが、昔と同じままの観光に戻るのではなく、国全体としてはサービスの質を向上させなければいけないと考えています。特に、日本が本当に好きなリピーターの訪日が増えています。かつて流行った爆買いのようなことではなく、我々日本人が行ったことのないような地域でその土地の人々と交流していただいて、日本をもっと好きになってもらったり、彼らの自己実現や知的好奇心に応えていくような旅行を増やしていきたいと思っています。
観光産業は低収益で、人手不足という問題も抱えていますが、これからは富裕層向けのコンテンツを増やして、高付加価値、高単価で生産性を高めていく必要もあると思います。日本の観光資源の多様性や深みを考えると、今後もリピーターが増えて、世界中から日本に憧れを抱いて来日される可能性はかなりあると、明るい見通しを持っています。
私がよく財界の方々から言われることに、「円安だから増えてるんでしょ。良かったね」とがあります。もちろん、為替によって消費額は左右されますが、日本が行きたい国であることのほうがずっと重要だと考えています。バードウォッチングをしたい方や庭園ツアーに来日される方は、為替を日々見て日本に行こうと決めているわけではありません。2025年の大阪・関西万博の際には我が地域にも誘客してほしいとの声も良く聞きますが、毎年3000万人も海外から来ているのに、その方々が何を期待して来日しているかの理解を深めずに万博のような一過性のイベントに安易に乗っかろうとするのかと思ったりもします。それ以外にも、日本人は、「人気の観光地はどこ」とか「世界遺産だから旅行する」といった、人気とかお墨付きを求めますが、海外からの弊社の利用客は、本当に自分が行きたい場所、関心がある場所に行き、結果として日本人が知らない日本を感じて、消費をしているということをもう少し知っていただきたいなと思います。
訪日旅行業の経済規模は、コロナ前は5兆円という市場規模で、相応のインパクトもある産業になってきました。また成長の可能性が大きい業界です。しかし、海外の人がなぜ日本に何度も来るのかを理解しなければなりません。日本には心に刺さるような素敵な文化がたくさんあります。こうした本物をきちんと見せていけば、更に訪日観光客は増えていくでしょう。また、ただの異文化というだけではなく、快適なホテルや美味しい食事も重要でして、それらが組み合わさって、また日本に来たいと思わせる強みになっていると思っています。
従来の観光業のビジネスモデルは、定番のパッケージツアーを廉価で提供するのが主流でした。その発想から抜け出して、高付加価値で一人一人のお客さまの満足度を高め、高単価に見合ったサービスを提供することが鍵になると思います。
本日お話させていただいたように、来日される動機が日本の様々な文化や魅力に関連しているので、インバウンドは、観光業だけではなく、日本の総合的な文化力が問われる産業だと思います。また、日々の日本の世界でのふるまいなどで日本が尊敬される国であれば、海外から来て下さる国であり続けると考えております。
ご清聴ありがとうございました。以上で今日のお話を終えたいと思います。
皆さんこんにちは。ご紹介いただきました茶田と申します。
私は奈良県の出身で学生時代までは関西で過ごしておりました。社会人になって最初は政府系の金融機関で投融資をしていましたが、日本の魅力を世界の人に知ってほしい、そういう旅行会社をやりたいと思い、みちトラベルジャパンを創業したのが17年ほど前、35歳の時です。当時は日本への海外旅行者数は世界で31番目でしたが、その後旅行者数は右肩上がりで増加し、コロナ前の2019年には世界で12番目になりました。
私が創業した理由は、多岐に渡る日本の魅力を、もっと世界の人に旅を通じて知ってもらいたいと思ったからです。そして、魅力の幅があまりにも多様なので、パッケージツアーではなく、お客さまの希望や関心に合わせてコンシェルジュ的にテーラーメイドの旅行を提供したら喜ばれるだろうと思い、そういう会社に転職したいと思いましたが、見当たらなかったので自分で創業しました。
元々、奈良や京都に住んでいたので、海外の方々に歴史的な場所も見せたい、また東京のように都会的なところや自然も好きですので、日本の色々な場所を海外の方に案内したいと思ったのも創業に至った原体験の一つだったと思います。テーラーメイドのサービスを提供しているので、お客さまは欧米の方が過半数で、富裕層の知的好奇心の高く、こだわりの強い方に利用していただいています。
コロナ禍の期間は旅行業が低迷しておりましたので、我々の実業の経験を生かしたアドバイザリーや観光コンサルティング事業も新たに展開して参りました。
テーラーメイドの旅行サービスですので、最初に海外からのお客さまがどのようなことに関心があるかをヒヤリングすることから始めます。これまでに受けたリクエストの一部をご紹介いたします。典型的には、家族旅行で、家族みんなにとって日本は行ってみたい国なんだ、というのが旅の動機という方が多いです。また、結構マニアックな関心をお持ちの方も多いです。例えば、中山道や熊野古道を歩きたい(これはもはや有名ですが)、庭園が趣味なので日本でも庭園をひたすら見たい、北海道でバードウォッチングをしたい、地方の5つ星のsmall luxury hotelに宿泊したい、自分の家を作るためのインスピレーションを得るために有名建築家の建物をたくさん見たいなどです。総じて、与えられた情報に反応するというより、自分の中にやりたいことや関心が高いものをもともと持たれており、それを実現するために日本を旅したいと考えておられるという印象を受けております。旅は人生を豊かにするもの、という意識も強いように思います。日本人でもあまり日本国内を旅行されていない方がおられると思いますが、海外の観光客の中には日本が大好きになって何度も訪日される方が増えています。弊社の最近のお客さんが行った場所でも、新潟県十日町、宮崎県飫肥、小豆島の遍路札所など、皆さんも行かれたことが無い場所もあるかもしれません。日本は様々なテーマや関心に応えられる面白い国ですので、世界中のお客さまから注目されているのではないかと思っています。
これまでは「顧客の期待、顧客の体験」についてお話しましたが、少しこの業界の経済的な側面やビジネスとしての切り口をお話したいと思います。私が創業のビジネスプランを立てていた2004年~2005年頃は、海外からの訪日旅行客は600万人程度でした。その後、観光客が訪日旅行者数をけん引する形で、コロナ前には3000万人に達しました。なぜこれほど増加したかというと、世界の人びとの所得が拡大して海外旅行できる余裕が出てきたことがひとつの理由だと言えるでしょう。日本の成長率は主要国の中でも一番低く人口も減少しているのに比べ、海外での経済成長により拡大する世界の富を日本に取り込む一つの手段として、インバウンドが注目されていると思います。もう一つは日本の観光地の人気が高いことです。東京、京都、大阪ばかりでなく、四国でのお遍路や瀬戸内海での高級クルーズ船が注目されるなど、新たなマーケットや需要が作り出されているのです。
今、コロナ後のインバウンドが戻ってきていますが、昔と同じままの観光に戻るのではなく、国全体としてはサービスの質を向上させなければいけないと考えています。特に、日本が本当に好きなリピーターの訪日が増えています。かつて流行った爆買いのようなことではなく、我々日本人が行ったことのないような地域でその土地の人々と交流していただいて、日本をもっと好きになってもらったり、彼らの自己実現や知的好奇心に応えていくような旅行を増やしていきたいと思っています。
観光産業は低収益で、人手不足という問題も抱えていますが、これからは富裕層向けのコンテンツを増やして、高付加価値、高単価で生産性を高めていく必要もあると思います。日本の観光資源の多様性や深みを考えると、今後もリピーターが増えて、世界中から日本に憧れを抱いて来日される可能性はかなりあると、明るい見通しを持っています。
私がよく財界の方々から言われることに、「円安だから増えてるんでしょ。良かったね」とがあります。もちろん、為替によって消費額は左右されますが、日本が行きたい国であることのほうがずっと重要だと考えています。バードウォッチングをしたい方や庭園ツアーに来日される方は、為替を日々見て日本に行こうと決めているわけではありません。2025年の大阪・関西万博の際には我が地域にも誘客してほしいとの声も良く聞きますが、毎年3000万人も海外から来ているのに、その方々が何を期待して来日しているかの理解を深めずに万博のような一過性のイベントに安易に乗っかろうとするのかと思ったりもします。それ以外にも、日本人は、「人気の観光地はどこ」とか「世界遺産だから旅行する」といった、人気とかお墨付きを求めますが、海外からの弊社の利用客は、本当に自分が行きたい場所、関心がある場所に行き、結果として日本人が知らない日本を感じて、消費をしているということをもう少し知っていただきたいなと思います。
訪日旅行業の経済規模は、コロナ前は5兆円という市場規模で、相応のインパクトもある産業になってきました。また成長の可能性が大きい業界です。しかし、海外の人がなぜ日本に何度も来るのかを理解しなければなりません。日本には心に刺さるような素敵な文化がたくさんあります。こうした本物をきちんと見せていけば、更に訪日観光客は増えていくでしょう。また、ただの異文化というだけではなく、快適なホテルや美味しい食事も重要でして、それらが組み合わさって、また日本に来たいと思わせる強みになっていると思っています。
従来の観光業のビジネスモデルは、定番のパッケージツアーを廉価で提供するのが主流でした。その発想から抜け出して、高付加価値で一人一人のお客さまの満足度を高め、高単価に見合ったサービスを提供することが鍵になると思います。
本日お話させていただいたように、来日される動機が日本の様々な文化や魅力に関連しているので、インバウンドは、観光業だけではなく、日本の総合的な文化力が問われる産業だと思います。また、日々の日本の世界でのふるまいなどで日本が尊敬される国であれば、海外から来て下さる国であり続けると考えております。
ご清聴ありがとうございました。以上で今日のお話を終えたいと思います。
卓話「DXの経営へのインパクト」
ベイヒルズ株式会社 代表取締役 程 近智さま
2023年6月8日

 皆さんこんにちは。
DX、デジタルトランスフォーメーションという言葉は最近少し下火になってきましたが、デジタル、ITの力を使って、様々な業界、個人も世界も加速度的に変わらなければいけない状況になってきているのではないかと思います。
今はITとかデジタルと言いますが、元々コンピュータは、第二次大戦時にミサイルの弾道計算に使用した防衛産業から普及が始まりました。戦後1950年頃からコンピュータがビジネスに使われるようになり、諸説ありますが、GEが人事領域、特に給与計算にコンピュータを使用して今までの手作業のペーパーワークから機械化したのが出発点でした。アーサー・アンダーセンという会計事務所で、会計士が給与計算などの経理の領域でコンピュータをうまく利用していこうとしたのが1950年の大きな商用という意味での始まりでした。当初はビジネスでこうしたいというニーズがあって、ITをツールとして使ってビジネスを変えていくというサイクルで回り始めました。
この様相が少し変わってきたのが2000年頃からです。インターネットは、元々アメリカの国防省の内輪のネットワークだったものが開放されて、民生用に転用されたものです。このインターネットの出現によって、ITがビジネスを規定するというインパクトが増えてきました。さらに恐ろしいことに、ITがビジネスを壊してしまうような力になってきました。その象徴的な例がAmazonです。本屋の流通システムが非常に非効率的だということで、ITが本の業界というビジネスを壊し始めたのです。そのインパクトで本屋の数は少なくなっています。ITがビジネスを壊す、または新しいビジネスを創造するということも可能なのです。
今は、ITがビジネスを可能にしたり、壊したり、作ったりする以上に、ITがビジネスの中核を占める、Digital at the coreという状態になっています。コンピュータやデータといった仕組みが中心にあり、その周りに物を作ったり、サービスを提供したり、販売したりという発想の企業がたくさん出てきています。テスラはその代表例と言えます。開発コストの6~7割はソフトウェアです。以前は、車を買う時は販売店に行きましたが、テスラはネットで注文して、車が届くと自分でセットアップするというスマホと同じ感覚なのです。製薬会社でも生体情報をデータ化しシミュレーションを取り入れるなどDigital at the coreになりつつあります。
ビジネス以外の分野にもITのインパクトが進んでいます。例えば、東京都ではデジタル・スマート・シティということで、色々なインフラの情報をデジタルで得て、震災や大きな災害にどう対応すべきかをシミュレーションしていますし、街の物理的な情報もデジタルツインズというデジタルの空間で再現するなど、ITが急速に自治体の政策にも影響を与えています。
残念ながら、ウクライナの戦争にもITのインパクトが見られます。今戦場で欠かせないものはスマホとパソコンです。どちらが先に敵の情報を得て、ドローンやロボットで相手を駆逐するのか、というようにITにより戦争のやり方が変わってきています。
健康促進の領域でもITが医療の在り方を変えています。スタートアップ企業のCureApp社のホームページを見ると、ソフトウェアで高血圧を治療すると書かれています。アプリで生活習慣を変えて高血圧や糖尿病を治療するというのもDigital at the coreの発想です
デジタル発想で会社の組織や運営を作り上げ、顧客が望むものを効率的に安価に提供できるようなビジネスが組み立てられています。いくつかの例をお話ししましたが、このようなデジタル発想は全ての業界に当てはまりつつあります。自治体も国もそういった発想を取り入れならなければならないと思います。
ITにはソフトウェアだけではなく、それを可能とする裏にある基本要素技術というものがあります。一つ目は半導体です。半導体はコンピュータの処理能力の源泉ですので、半導体がどういうスピードで進化していくかを見なければなりません。二つ目は通信です。いくらコンピュータがあってもつながらなければ意味がありません。今は5Gで、次6Gになりますが、つながる時差やタイムラグができるだけなくなっていくことが必要になります。三つめはセンサーのデバイスです。そして四つ目はAIです。これら四つの要素技術と共に、集められる大量のデータも資源だと言われています。
もうひとつはエネルギーです。最近の動きとしては、世界的にグリーンエネルギー、つまり石油由来ではなく再生エネルギーを使った電力の使用が求められています。Appleのような先端企業は納品する会社に対して再生エネルギーで操業している工場の製品でなければ部品を買わないという要求を突き付けています。
もう一つの大きな流れとして、日本が誇る領域ですがNTTのIOWNという仕組みがあります。光の技術を使って電力を省力化しようという動きです。Intelなどの海外企業も入ってきて、電送のインフラを省力化し、かつ、グリーンで対応するという動きが盛んになっています。
国もSociety5.0という構想を打ち出して、すべての業界がITと掛け合わさって変わっていくとしています。
大きな流れとして2045年にAIが人類の知の総和を超えるという技術的変異点が起こると未来予想学者のカーツワイルが10年くらい前に予言しています。AIが人間より賢くなるという予言が現実的になっていると思います。2011年にマーク・アンドリーセンという起業家が、「ソフトウェアが世界を食べている」と述べています。これもソフトウェアが重要になってきているという流れの一環だと思います。
どういう業界に一番インパクトがあるかという議論をよくするのですが、AIの自動化の余地がとても大きいのは金融業です。一番少ないのは、天然資源や化学、運輸業など、物理的にやらなければならないことが多い分野にはさほどインパクトがないと考えられています。平均的にみると私たちがやっている仕事の40%はAIにやってもらうということになってくるのではないかと思います。
結論としては、AIが我々に取って代わる部分と一緒に補完しながらやっていく仕事が増えていくことになると思います。AIは我々一人一人の生活をかならず変えていきます。AIをどのように味方につけてきちんとした使い方をできるかを考えていかなければいけません。その裏には倫理の問題もあります。またどの国が素晴らしいAIを作れるかという国家間の競争が激しくなれば国家安全保障的な課題も出てくることになるでしょう
以上とさせていただきます。ありがとうございました。
皆さんこんにちは。
DX、デジタルトランスフォーメーションという言葉は最近少し下火になってきましたが、デジタル、ITの力を使って、様々な業界、個人も世界も加速度的に変わらなければいけない状況になってきているのではないかと思います。
今はITとかデジタルと言いますが、元々コンピュータは、第二次大戦時にミサイルの弾道計算に使用した防衛産業から普及が始まりました。戦後1950年頃からコンピュータがビジネスに使われるようになり、諸説ありますが、GEが人事領域、特に給与計算にコンピュータを使用して今までの手作業のペーパーワークから機械化したのが出発点でした。アーサー・アンダーセンという会計事務所で、会計士が給与計算などの経理の領域でコンピュータをうまく利用していこうとしたのが1950年の大きな商用という意味での始まりでした。当初はビジネスでこうしたいというニーズがあって、ITをツールとして使ってビジネスを変えていくというサイクルで回り始めました。
この様相が少し変わってきたのが2000年頃からです。インターネットは、元々アメリカの国防省の内輪のネットワークだったものが開放されて、民生用に転用されたものです。このインターネットの出現によって、ITがビジネスを規定するというインパクトが増えてきました。さらに恐ろしいことに、ITがビジネスを壊してしまうような力になってきました。その象徴的な例がAmazonです。本屋の流通システムが非常に非効率的だということで、ITが本の業界というビジネスを壊し始めたのです。そのインパクトで本屋の数は少なくなっています。ITがビジネスを壊す、または新しいビジネスを創造するということも可能なのです。
今は、ITがビジネスを可能にしたり、壊したり、作ったりする以上に、ITがビジネスの中核を占める、Digital at the coreという状態になっています。コンピュータやデータといった仕組みが中心にあり、その周りに物を作ったり、サービスを提供したり、販売したりという発想の企業がたくさん出てきています。テスラはその代表例と言えます。開発コストの6~7割はソフトウェアです。以前は、車を買う時は販売店に行きましたが、テスラはネットで注文して、車が届くと自分でセットアップするというスマホと同じ感覚なのです。製薬会社でも生体情報をデータ化しシミュレーションを取り入れるなどDigital at the coreになりつつあります。
ビジネス以外の分野にもITのインパクトが進んでいます。例えば、東京都ではデジタル・スマート・シティということで、色々なインフラの情報をデジタルで得て、震災や大きな災害にどう対応すべきかをシミュレーションしていますし、街の物理的な情報もデジタルツインズというデジタルの空間で再現するなど、ITが急速に自治体の政策にも影響を与えています。
残念ながら、ウクライナの戦争にもITのインパクトが見られます。今戦場で欠かせないものはスマホとパソコンです。どちらが先に敵の情報を得て、ドローンやロボットで相手を駆逐するのか、というようにITにより戦争のやり方が変わってきています。
健康促進の領域でもITが医療の在り方を変えています。スタートアップ企業のCureApp社のホームページを見ると、ソフトウェアで高血圧を治療すると書かれています。アプリで生活習慣を変えて高血圧や糖尿病を治療するというのもDigital at the coreの発想です
デジタル発想で会社の組織や運営を作り上げ、顧客が望むものを効率的に安価に提供できるようなビジネスが組み立てられています。いくつかの例をお話ししましたが、このようなデジタル発想は全ての業界に当てはまりつつあります。自治体も国もそういった発想を取り入れならなければならないと思います。
ITにはソフトウェアだけではなく、それを可能とする裏にある基本要素技術というものがあります。一つ目は半導体です。半導体はコンピュータの処理能力の源泉ですので、半導体がどういうスピードで進化していくかを見なければなりません。二つ目は通信です。いくらコンピュータがあってもつながらなければ意味がありません。今は5Gで、次6Gになりますが、つながる時差やタイムラグができるだけなくなっていくことが必要になります。三つめはセンサーのデバイスです。そして四つ目はAIです。これら四つの要素技術と共に、集められる大量のデータも資源だと言われています。
もうひとつはエネルギーです。最近の動きとしては、世界的にグリーンエネルギー、つまり石油由来ではなく再生エネルギーを使った電力の使用が求められています。Appleのような先端企業は納品する会社に対して再生エネルギーで操業している工場の製品でなければ部品を買わないという要求を突き付けています。
もう一つの大きな流れとして、日本が誇る領域ですがNTTのIOWNという仕組みがあります。光の技術を使って電力を省力化しようという動きです。Intelなどの海外企業も入ってきて、電送のインフラを省力化し、かつ、グリーンで対応するという動きが盛んになっています。
国もSociety5.0という構想を打ち出して、すべての業界がITと掛け合わさって変わっていくとしています。
大きな流れとして2045年にAIが人類の知の総和を超えるという技術的変異点が起こると未来予想学者のカーツワイルが10年くらい前に予言しています。AIが人間より賢くなるという予言が現実的になっていると思います。2011年にマーク・アンドリーセンという起業家が、「ソフトウェアが世界を食べている」と述べています。これもソフトウェアが重要になってきているという流れの一環だと思います。
どういう業界に一番インパクトがあるかという議論をよくするのですが、AIの自動化の余地がとても大きいのは金融業です。一番少ないのは、天然資源や化学、運輸業など、物理的にやらなければならないことが多い分野にはさほどインパクトがないと考えられています。平均的にみると私たちがやっている仕事の40%はAIにやってもらうということになってくるのではないかと思います。
結論としては、AIが我々に取って代わる部分と一緒に補完しながらやっていく仕事が増えていくことになると思います。AIは我々一人一人の生活をかならず変えていきます。AIをどのように味方につけてきちんとした使い方をできるかを考えていかなければいけません。その裏には倫理の問題もあります。またどの国が素晴らしいAIを作れるかという国家間の競争が激しくなれば国家安全保障的な課題も出てくることになるでしょう
以上とさせていただきます。ありがとうございました。
卓話「東京パラリンピックで金メダルを獲るまで」
東京パラリンピック水泳金メダリスト・IPCアスリート委員 鈴木孝幸さま
2023年5月25日

 皆さんこんにちは。本日はお招きいただきありがとうございます。パラ水泳をしております鈴木孝幸と申します。
今日は「東京パラリンピックで金メダルを獲るまで」というテーマでお話しいたします。私がパラ水泳でデビューし、強化指定選手に入り、初めて国際大会に出場したのが2003年です。今年が2023年ですので20年間活動しておりますが、全てをお話しする時間はありませんので、どのようなことを考えてパラ水泳に取り組んできたのかを東京パラリンピックまで時系列でお話ししたいと思います。
私は、水泳選手でありますが、スポーツアパレルメーカーの株式会社ゴールドウインに社員として所属しています。現在は、公益財団法人日本パラスポーツ協会及び日本パラリンピック委員会(JPC)にも出向しております。そして、東京パラリンピック期間中の選挙でIPCアスリート委員にも選出され、その活動も行っています。パラリンピックはアテネから東京まで5大会に出場し、現在はパリパラリンピック出場に向けて頑張っています。
多くの方は東京パラリンピックで金メダルを獲得したことで私のことを知って下さったと思いますが、2008年の北京パラリンピックでも金メダルを獲得したことを覚えていただければと思います。東京パラリンピックでは100メートル自由形の金メダルを含め、出場した5種目全てでメダルを獲得しました。
国際大会に初出場した翌年2004年にアテネパラリンピックに出場し4×50メートルのメドレーリレーの平泳ぎで銀メダルを獲得しました。この時の記憶として鮮明に残っているのが帰国した空港での出来事です。到着ゲートの手前でメダリストはメダルをかけて前方に出るように言われたので、きっと多くの報道陣が駆けつけているのだろうと思ったら、ゲートの先に報道陣はわずかしかいませんでした。パラリンピックはこんなに人気がないのかと愕然とし、悔しく思ったことを覚えています。そこでパラリンピックに注目を集めるために考えたのが「オリンピック選手よりもオリンピック選手らしく」ということです。高い意識を持ってトレーニングに励もうと思いました。早稲田大学に入学して水泳部に所属し、日本のトップスイマーから身体が小さいと言われたので、身体を大きくするために4年間必死にトレーニングしました。その甲斐もあって2008年の北京パラリンピックで金メダルを獲得しました。
翌2009年に自分にとって転機となる「100%理論」というものに出会いました。最大限のパフォーマンスを発揮するためには、練習の成果や実力を100%出し切るという考え方です。水泳選手の調整方法で「超回復」というものがあります。大会当日に合わせて負荷をかける練習を積んでいくと、身体の回復と脳の回復との時差によって実力以上の力(120%の力)が発揮できると考えることが多かったので、この「100%理論」という考え方が印象に残りました。
2012年のロンドンパラリンピックの時はスランプに陥り銅メダルこそ獲得したものの、自分の水泳人生の中では一番辛いシーズンでした。この状況を打破するために英国のノーザンブリア大学に留学し、トレーニングを続けました。しかし、2016年のリオパラリンピックではメダルを獲得できず、選手としては潮時かと思いました。ただ、奨学金で2018年までは水泳を続けなければならなかったので、残りの2年間に新たなことに取り組み、結果が出たら東京パラリンピックを目指そうと考えました。肉体改造に着手して体幹強化に努めました。泳ぎのフォームを変えました。さらに自分では必要ないと思っていた心理カウンセリングを受け、そこで得たものへの理解を深めて咀嚼していくうちに、「世の中には変えられるものと変えられないものがある」という考えにたどり着きました。これは水泳を続けていく上で大切なキーワードになりました。それまではライバルのことばかり考えていましたが、自分をどのように変えていけば良いのかを考えるようになり、自分に出来るトレーニングで鍛えた結果、2018年にはアジア大会で5冠を達成し、東京パラリンピックを目指そうという覚悟が決まりました。2020年の東京パラリンピック延期が決まった時も「変えられるものと変えられないものがある」という考え方で、自分ができるものに色々と挑戦して有意義に過ごせました。年齢的には2020年に開催されたらベストだったかもしれませんが、延期になった1年間に可能なことはやれたと感じています。そして、東京パラリンピックでは5つのメダルを獲得することができました。
水泳を通して得た行動面で意識していることが四つあります。一つ目は「習慣化させる」ということです。トレーニングの効果が出るのに最低でも数ヶ月かかります。楽しくもない練習をやり続けるためには習慣化させていくことが必要だと思います。二つ目は「自分に優しく」ということです。苦しい練習をすることは変えられません。そこでなるべく苦しく感じないように、準備運動を入念に行い、疲労を残さないように寝る前にストレッチをして、疲れが早く抜けるようにサプリメントをしっかり摂っています。三つ目は「練習は本番のように、本番は練習のように」ということです。反復練習の中で、本番を意識してトレーニングすることがとても大事だと思っています。四つ目は「後悔の無い状態でスタート台に立つ」ということです。サプリメントを飲み忘れたことを考えながらスタート台に立ったら絶対良いタイムは出ません。絶対に忘れないようにします。国際大会では思い通りに行かないアクシデントがよく起こります。その場合も、アクシデントが起こった状態からの最善をしっかり尽くし、最善を尽くしたから大丈夫だと思ってスタート台に立つことを心がけています。
最後に皆さんにパラスポーツを応援していただきたい、パラ水泳あるいは鈴木孝幸を応援していただきたいということで、皆さんが応援できる三つの方法をご紹介いたします。一つは会場やメディアを通して応援することです。最近は競技団体や選手自身がYouTubeやソーシャルメディアを通じて情報発信しています。私もオフィシャルウェブサイト、Instagram、Facebook、Twitterをやっておりますので、よろしければフォローして「いいね!」をいただければ大変励みになります。二つ目は選手やチーム、競技団体へのサポートです。金銭的なサポートや物品のサポートなど、大変ありがたいです。特に東京パラリンピックを終えてスポンサー離れという状況もありますので、サポートしていただけるとありがたく思います。最後の三つ目が共生社会について考えて行動することです。今一つぴんとこないかもしれませんが、IPCの目標の一つにパラリンピックやパラスポーツを通じて共生社会を実現するということがあります。日本では障害者差別基本法や、最近では合理的配慮という言葉も耳にするようになりました。これは障がい者が選択肢を持てるようにすることだと思っています。ハード面では段差を解消するスロープや低床バス、車いすの積み下ろしが楽なタクシーなどありますが、ハード面だけではだめなのです。タクシーに乗車拒否されたり、健常者が駅のエレベーターを使うため、エレベーターしか選択肢のない障がい者が待たされることがあります。他に選択肢がある人は選択肢の無い人に譲るというのも合理的配慮の一つの形だと思います。こうしたことを考えて行動していただくのもパラスポーツを応援することにつながると思いますので、是非よろしくお願いいたします。
ご清聴いただきまして、ありがとうございました。
皆さんこんにちは。本日はお招きいただきありがとうございます。パラ水泳をしております鈴木孝幸と申します。
今日は「東京パラリンピックで金メダルを獲るまで」というテーマでお話しいたします。私がパラ水泳でデビューし、強化指定選手に入り、初めて国際大会に出場したのが2003年です。今年が2023年ですので20年間活動しておりますが、全てをお話しする時間はありませんので、どのようなことを考えてパラ水泳に取り組んできたのかを東京パラリンピックまで時系列でお話ししたいと思います。
私は、水泳選手でありますが、スポーツアパレルメーカーの株式会社ゴールドウインに社員として所属しています。現在は、公益財団法人日本パラスポーツ協会及び日本パラリンピック委員会(JPC)にも出向しております。そして、東京パラリンピック期間中の選挙でIPCアスリート委員にも選出され、その活動も行っています。パラリンピックはアテネから東京まで5大会に出場し、現在はパリパラリンピック出場に向けて頑張っています。
多くの方は東京パラリンピックで金メダルを獲得したことで私のことを知って下さったと思いますが、2008年の北京パラリンピックでも金メダルを獲得したことを覚えていただければと思います。東京パラリンピックでは100メートル自由形の金メダルを含め、出場した5種目全てでメダルを獲得しました。
国際大会に初出場した翌年2004年にアテネパラリンピックに出場し4×50メートルのメドレーリレーの平泳ぎで銀メダルを獲得しました。この時の記憶として鮮明に残っているのが帰国した空港での出来事です。到着ゲートの手前でメダリストはメダルをかけて前方に出るように言われたので、きっと多くの報道陣が駆けつけているのだろうと思ったら、ゲートの先に報道陣はわずかしかいませんでした。パラリンピックはこんなに人気がないのかと愕然とし、悔しく思ったことを覚えています。そこでパラリンピックに注目を集めるために考えたのが「オリンピック選手よりもオリンピック選手らしく」ということです。高い意識を持ってトレーニングに励もうと思いました。早稲田大学に入学して水泳部に所属し、日本のトップスイマーから身体が小さいと言われたので、身体を大きくするために4年間必死にトレーニングしました。その甲斐もあって2008年の北京パラリンピックで金メダルを獲得しました。
翌2009年に自分にとって転機となる「100%理論」というものに出会いました。最大限のパフォーマンスを発揮するためには、練習の成果や実力を100%出し切るという考え方です。水泳選手の調整方法で「超回復」というものがあります。大会当日に合わせて負荷をかける練習を積んでいくと、身体の回復と脳の回復との時差によって実力以上の力(120%の力)が発揮できると考えることが多かったので、この「100%理論」という考え方が印象に残りました。
2012年のロンドンパラリンピックの時はスランプに陥り銅メダルこそ獲得したものの、自分の水泳人生の中では一番辛いシーズンでした。この状況を打破するために英国のノーザンブリア大学に留学し、トレーニングを続けました。しかし、2016年のリオパラリンピックではメダルを獲得できず、選手としては潮時かと思いました。ただ、奨学金で2018年までは水泳を続けなければならなかったので、残りの2年間に新たなことに取り組み、結果が出たら東京パラリンピックを目指そうと考えました。肉体改造に着手して体幹強化に努めました。泳ぎのフォームを変えました。さらに自分では必要ないと思っていた心理カウンセリングを受け、そこで得たものへの理解を深めて咀嚼していくうちに、「世の中には変えられるものと変えられないものがある」という考えにたどり着きました。これは水泳を続けていく上で大切なキーワードになりました。それまではライバルのことばかり考えていましたが、自分をどのように変えていけば良いのかを考えるようになり、自分に出来るトレーニングで鍛えた結果、2018年にはアジア大会で5冠を達成し、東京パラリンピックを目指そうという覚悟が決まりました。2020年の東京パラリンピック延期が決まった時も「変えられるものと変えられないものがある」という考え方で、自分ができるものに色々と挑戦して有意義に過ごせました。年齢的には2020年に開催されたらベストだったかもしれませんが、延期になった1年間に可能なことはやれたと感じています。そして、東京パラリンピックでは5つのメダルを獲得することができました。
水泳を通して得た行動面で意識していることが四つあります。一つ目は「習慣化させる」ということです。トレーニングの効果が出るのに最低でも数ヶ月かかります。楽しくもない練習をやり続けるためには習慣化させていくことが必要だと思います。二つ目は「自分に優しく」ということです。苦しい練習をすることは変えられません。そこでなるべく苦しく感じないように、準備運動を入念に行い、疲労を残さないように寝る前にストレッチをして、疲れが早く抜けるようにサプリメントをしっかり摂っています。三つ目は「練習は本番のように、本番は練習のように」ということです。反復練習の中で、本番を意識してトレーニングすることがとても大事だと思っています。四つ目は「後悔の無い状態でスタート台に立つ」ということです。サプリメントを飲み忘れたことを考えながらスタート台に立ったら絶対良いタイムは出ません。絶対に忘れないようにします。国際大会では思い通りに行かないアクシデントがよく起こります。その場合も、アクシデントが起こった状態からの最善をしっかり尽くし、最善を尽くしたから大丈夫だと思ってスタート台に立つことを心がけています。
最後に皆さんにパラスポーツを応援していただきたい、パラ水泳あるいは鈴木孝幸を応援していただきたいということで、皆さんが応援できる三つの方法をご紹介いたします。一つは会場やメディアを通して応援することです。最近は競技団体や選手自身がYouTubeやソーシャルメディアを通じて情報発信しています。私もオフィシャルウェブサイト、Instagram、Facebook、Twitterをやっておりますので、よろしければフォローして「いいね!」をいただければ大変励みになります。二つ目は選手やチーム、競技団体へのサポートです。金銭的なサポートや物品のサポートなど、大変ありがたいです。特に東京パラリンピックを終えてスポンサー離れという状況もありますので、サポートしていただけるとありがたく思います。最後の三つ目が共生社会について考えて行動することです。今一つぴんとこないかもしれませんが、IPCの目標の一つにパラリンピックやパラスポーツを通じて共生社会を実現するということがあります。日本では障害者差別基本法や、最近では合理的配慮という言葉も耳にするようになりました。これは障がい者が選択肢を持てるようにすることだと思っています。ハード面では段差を解消するスロープや低床バス、車いすの積み下ろしが楽なタクシーなどありますが、ハード面だけではだめなのです。タクシーに乗車拒否されたり、健常者が駅のエレベーターを使うため、エレベーターしか選択肢のない障がい者が待たされることがあります。他に選択肢がある人は選択肢の無い人に譲るというのも合理的配慮の一つの形だと思います。こうしたことを考えて行動していただくのもパラスポーツを応援することにつながると思いますので、是非よろしくお願いいたします。
ご清聴いただきまして、ありがとうございました。
卓話「世界に注目されるインド経済の現状と見通し」
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 代表取締役社長 佐藤輝幸さま
2023年5月11日

 只今ご紹介に預かりましたイーストスプリングの佐藤と申します。本日はこのような機会を頂戴いたしまして誠にありがとうございます。
私どもイーストスプリングは、創業175年の英国の保険会社プルーデンシャルの資産運用子会社として、アジアに特化した運用サービスを展開しております。日本には四半世紀前に参入し、アジアに強みのある運用会社として広く認識していただいております。インドに関しては、2004年に日本初のインド株式ファンドを設定し、パイオニア的な存在として知られております。本日はインドに関するお話をさせていただきます。
最近、中国を抜いて世界1位の人口になったインドは、人口のみならずGDPランキングでも存在感が高まっています。インドのGDPは既に英国を抜いて世界第5位、2027年には日本を抜いて世界第3位に、2050年には米国を抜いて世界第2位になると見込まれています。これほどの人口大国、経済大国ですので、米中対立の中、米国側でも中国側でもない第三の勢力として存在感が高まっているのがインドです。
OECDの統計では、今後10年で最も成長する国はインドだと予想されています。このインドを成長軌道に乗せたのが現政権のモディ首相です。モディ首相の進める経済改革、規制緩和の結果として、海外からインドへの直接投資が増加し、過去最高水準となっています。モディ首相が進める政策の柱の一つ、「メイク・イン・インディア」は、インド国内に製造業を誘致し、強化していき、雇用を創出し、輸出を促進し、税収を増加させ、高い経済成長につなげて、さらに消費を拡大させるという政策です。これまで世界の工場といえば中国でしたが、米中対立やコロナによる長期のロックダウンによって中国からインドへのサプライチェーンのシフトが見られるようになりました。
製造業を誘致しても、インフラは大丈夫なのかという質問が出るかと思います。モディ政権は、空港や地下鉄網など、強力にインフラ整備を推進しています。インフラ整備を進めて新たな投資を呼び込んでいますが、GDPの約60%は内需、個人消費です。平均年齢29歳、人口14億人、中間層の増加とさらなる消費拡大が期待できるマーケットです。このインドの消費に関してキーワードと共にお話いたします。
一つ目のキーワードは「プレミアム化」です。所得水準が向上するにつれてより上質なものを求めるようになっているのが今のインドです。自動車販売台数の増加と共にSUVの販売台数が一般乗用車を上回るようになっています。SUV新車は約200万円ですので、平均年収275万円のインドでは自動車購入は一大ライフイベントとなっています。
二つ目のキーワードは「コト消費」です。インドの消費は「モノ」から「コト」にシフトしています。映画はインドで最も人気のあるレジャーです。インドの映画産業の中心はムンバイでボリウッドと呼ばれています。年間の映画製作本数は2000本と米国ハリウッドを大きく引き離し、世界第1位の映画大国です。今インドでは、シネコンが成長しており、我々もシネコンの会社に投資しております。インドのスクリーン数は日本の約3倍の11,000、有料観客数は年間18億人と極めて大きなマーケットです。
三つ目のキーワードは「デジタル化」です。インドでは8億人がスマホ、携帯電話を保有していると言われています。この8億人が常時インターネットにつながるという巨大なプラットフォームが出来上がっています。QRコード決済も浸透し、日常使いの現金決済比率は1%未満というデジタル経済に一気に移行したのが今のインドの状況です。スマホでアクセスできる動画コンテンツの中でも特にインドで人気があるのが、クリケットです。インドのクリケットのプロリーグは人気が高く、選手の平均年俸は4億円、最高年俸は25億円にも達しています。このインド・プレミアリーグが昨年テレビ・ネットでの5年間の配信権を販売しました。新興の財閥企業リライアンスがネットでの配信権を3700億円で、ディズニー系の子会社がテレビでの配信権を同じく3700億円で獲得し、合計7400億円の配信権料をクリケットのプレミアリーグが得ています。今、インドのクリケットのプレミアリーグの1試合当たりの価値は、アメフトのNFLに次いで世界第2位となっています。第3位は英国のサッカーのプレミアリーグです。ちなみに、このクリケットのプロリーグの立ち上げから支援をしたのがナイキです。インドでナイキを知っている人は95%、買ったことがある人は50%ということで、ナイキはインドにおけるブランドづくりにクリケットを活用したと言われております。
最後に、経済のバロメーターであるインドの株式についてお話いたします。世界の株式を、2000年からの20数年をみると、最もリターンが良かったのはインド株です。現地通貨ベースで2000年以降約12倍に値上がりしています。ルピーが円に対して約3割下がっている分を考慮しても約8倍以上の上昇となっています。
今後の見通しについてご説明します。長期の経済成長予測の際に人口動態と人口構成が重要な要素として挙げられます。キーワードとして人口ボーナス期というものがあります。総人口の3分の2以上を生産年齢の人口が占めている期間で、生産性が高く、経済成長が加速しやすい期間です。日本は、高度成長期に入った1963年から2022年までが人口ボーナス期で、ピーク時には日本株は28.9倍になりました。期間終了時でも8.5倍という状況でした。中国は1996年から人口ボーナス期に入り、ピーク時には10.7倍になりました。インドが人口ボーナス期に突入したのは2019年、株価もまだ1.6倍です。ここからもインドが今後も非常に成長が期待できるマーケットであることがお分かりになっていただけると思います。
ご清聴いただき、ありがとうございました。
Q&A
Q: インド市場でどういう業種が今後伸びるのかお聞きしたいのですが。
A: 日本で三つの投資信託を運用しておりますが、一番人気があるのがインドの消費セクターに特化したファンドです。もう一つはインドのインフラに特化したもの、そして、インドのバリュー株という本源的価値から安く放置されている銘柄に投資するファンドがあります。人気のある消費のセクターの中味を見ていくと、非常にユニークなのは銀行株が成長産業であるという点です。投資の立場から、銀行株に非常に注目しているところです。
Q: インドの階級制度は未だに残っているのでしょうか。階級制度を打ち破るための経済発展が望めるのか、それとも階級制度で縛られている部分があるのでしょうか。
A: インドのカースト制度は職業を縛っていたものですので、以前はなかった職業に人気があるというのがインドの現状だと聞いています。特にITに関しては、インド工科大学や米国に留学してH1-Bビザを取得して、米国のIT企業で働くのが成功ストーリーだと言われています。そこにはカーストは一切介在しません。マイクロソフトやグーグルのCEOもインド出身ですが、GAFAと言われるテクノロジー企業ではインドの方々が多数働いています。こうした新しい業種では多様性が図られていると聞いています。ただ、人々の潜在意識の中では古い考え方が残っており、それが成長を阻害する要因だと考えられているのが現状だと思います。
只今ご紹介に預かりましたイーストスプリングの佐藤と申します。本日はこのような機会を頂戴いたしまして誠にありがとうございます。
私どもイーストスプリングは、創業175年の英国の保険会社プルーデンシャルの資産運用子会社として、アジアに特化した運用サービスを展開しております。日本には四半世紀前に参入し、アジアに強みのある運用会社として広く認識していただいております。インドに関しては、2004年に日本初のインド株式ファンドを設定し、パイオニア的な存在として知られております。本日はインドに関するお話をさせていただきます。
最近、中国を抜いて世界1位の人口になったインドは、人口のみならずGDPランキングでも存在感が高まっています。インドのGDPは既に英国を抜いて世界第5位、2027年には日本を抜いて世界第3位に、2050年には米国を抜いて世界第2位になると見込まれています。これほどの人口大国、経済大国ですので、米中対立の中、米国側でも中国側でもない第三の勢力として存在感が高まっているのがインドです。
OECDの統計では、今後10年で最も成長する国はインドだと予想されています。このインドを成長軌道に乗せたのが現政権のモディ首相です。モディ首相の進める経済改革、規制緩和の結果として、海外からインドへの直接投資が増加し、過去最高水準となっています。モディ首相が進める政策の柱の一つ、「メイク・イン・インディア」は、インド国内に製造業を誘致し、強化していき、雇用を創出し、輸出を促進し、税収を増加させ、高い経済成長につなげて、さらに消費を拡大させるという政策です。これまで世界の工場といえば中国でしたが、米中対立やコロナによる長期のロックダウンによって中国からインドへのサプライチェーンのシフトが見られるようになりました。
製造業を誘致しても、インフラは大丈夫なのかという質問が出るかと思います。モディ政権は、空港や地下鉄網など、強力にインフラ整備を推進しています。インフラ整備を進めて新たな投資を呼び込んでいますが、GDPの約60%は内需、個人消費です。平均年齢29歳、人口14億人、中間層の増加とさらなる消費拡大が期待できるマーケットです。このインドの消費に関してキーワードと共にお話いたします。
一つ目のキーワードは「プレミアム化」です。所得水準が向上するにつれてより上質なものを求めるようになっているのが今のインドです。自動車販売台数の増加と共にSUVの販売台数が一般乗用車を上回るようになっています。SUV新車は約200万円ですので、平均年収275万円のインドでは自動車購入は一大ライフイベントとなっています。
二つ目のキーワードは「コト消費」です。インドの消費は「モノ」から「コト」にシフトしています。映画はインドで最も人気のあるレジャーです。インドの映画産業の中心はムンバイでボリウッドと呼ばれています。年間の映画製作本数は2000本と米国ハリウッドを大きく引き離し、世界第1位の映画大国です。今インドでは、シネコンが成長しており、我々もシネコンの会社に投資しております。インドのスクリーン数は日本の約3倍の11,000、有料観客数は年間18億人と極めて大きなマーケットです。
三つ目のキーワードは「デジタル化」です。インドでは8億人がスマホ、携帯電話を保有していると言われています。この8億人が常時インターネットにつながるという巨大なプラットフォームが出来上がっています。QRコード決済も浸透し、日常使いの現金決済比率は1%未満というデジタル経済に一気に移行したのが今のインドの状況です。スマホでアクセスできる動画コンテンツの中でも特にインドで人気があるのが、クリケットです。インドのクリケットのプロリーグは人気が高く、選手の平均年俸は4億円、最高年俸は25億円にも達しています。このインド・プレミアリーグが昨年テレビ・ネットでの5年間の配信権を販売しました。新興の財閥企業リライアンスがネットでの配信権を3700億円で、ディズニー系の子会社がテレビでの配信権を同じく3700億円で獲得し、合計7400億円の配信権料をクリケットのプレミアリーグが得ています。今、インドのクリケットのプレミアリーグの1試合当たりの価値は、アメフトのNFLに次いで世界第2位となっています。第3位は英国のサッカーのプレミアリーグです。ちなみに、このクリケットのプロリーグの立ち上げから支援をしたのがナイキです。インドでナイキを知っている人は95%、買ったことがある人は50%ということで、ナイキはインドにおけるブランドづくりにクリケットを活用したと言われております。
最後に、経済のバロメーターであるインドの株式についてお話いたします。世界の株式を、2000年からの20数年をみると、最もリターンが良かったのはインド株です。現地通貨ベースで2000年以降約12倍に値上がりしています。ルピーが円に対して約3割下がっている分を考慮しても約8倍以上の上昇となっています。
今後の見通しについてご説明します。長期の経済成長予測の際に人口動態と人口構成が重要な要素として挙げられます。キーワードとして人口ボーナス期というものがあります。総人口の3分の2以上を生産年齢の人口が占めている期間で、生産性が高く、経済成長が加速しやすい期間です。日本は、高度成長期に入った1963年から2022年までが人口ボーナス期で、ピーク時には日本株は28.9倍になりました。期間終了時でも8.5倍という状況でした。中国は1996年から人口ボーナス期に入り、ピーク時には10.7倍になりました。インドが人口ボーナス期に突入したのは2019年、株価もまだ1.6倍です。ここからもインドが今後も非常に成長が期待できるマーケットであることがお分かりになっていただけると思います。
ご清聴いただき、ありがとうございました。
Q&A
Q: インド市場でどういう業種が今後伸びるのかお聞きしたいのですが。
A: 日本で三つの投資信託を運用しておりますが、一番人気があるのがインドの消費セクターに特化したファンドです。もう一つはインドのインフラに特化したもの、そして、インドのバリュー株という本源的価値から安く放置されている銘柄に投資するファンドがあります。人気のある消費のセクターの中味を見ていくと、非常にユニークなのは銀行株が成長産業であるという点です。投資の立場から、銀行株に非常に注目しているところです。
Q: インドの階級制度は未だに残っているのでしょうか。階級制度を打ち破るための経済発展が望めるのか、それとも階級制度で縛られている部分があるのでしょうか。
A: インドのカースト制度は職業を縛っていたものですので、以前はなかった職業に人気があるというのがインドの現状だと聞いています。特にITに関しては、インド工科大学や米国に留学してH1-Bビザを取得して、米国のIT企業で働くのが成功ストーリーだと言われています。そこにはカーストは一切介在しません。マイクロソフトやグーグルのCEOもインド出身ですが、GAFAと言われるテクノロジー企業ではインドの方々が多数働いています。こうした新しい業種では多様性が図られていると聞いています。ただ、人々の潜在意識の中では古い考え方が残っており、それが成長を阻害する要因だと考えられているのが現状だと思います。
卓話「嘱望される障がい者雇用のこれから」
株式会社JALサンライト 代表取締役社長 城田純子さま
2023年4月27日

 ただいまご紹介いただきましたJALサンライトの城田と申します。本日は貴重な機会をいただきありがとうございます。
「嘱望される障がい者雇用のこれから」というテーマでお話しさせていただきます。私の勤務するJALの特例子会社であるJALサンライトは、障がい者雇用を促進しながら、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)を推進しています。弊社の社員の活躍を皆さまに知っていただき、身近にいらっしゃる障がいのある方々の夢や希望の広がりに思いを馳せていただければ嬉しいなと思っております。
私は元々JALの客室乗務員として従事しておりました。その中で機内の現場や間接部門で長らく人財育成に携わっておりました。そして、今与えられたミッションの一つは、障がいのある方々の能力や可能性に光をあてて成長を促し、現在や将来の仕事にどのように参画し活躍してもらうかを共に考え進めていくことです。私のこれまでの経験を活かせるやりがいのある仕事だと思っております。
JALサンライトは、JALの特例子会社として障がいの有無にかかわらず、JALグループの業務を担い、JALの翼を支えている会社です。企業理念は「障がいを仕事の障害としない環境をもとに多様性を活かし、新たな価値を創造し続けます。」というもので、これは社員のプロジェクトチームを中心に社員自らが作り上げた企業理念です。現在423名の社員のうち半数以上、222名の障がいのある社員が在籍しております。障がいの種類も知的障がい、聴覚障がい、肢体障がい、視覚障がい、精神障がい、内部障がいと多岐にわたります。
その上で、請け負っている業務内容としては、まず本社から受託している基幹業務が三つあります。一つ目は航空輸送を支える業務として、航空券を審査する業務や、客室乗務員のスケジュール作成、通勤や就業時間管理等のサポート業務を行っています。二つ目は社員の仕事を支える業務として、出張渡航関連業務、名刺・IDカード作成業務、社内のメーリング業務などを担っています。三つ目は社員の日常を支える業務として、給与や福利厚生、退職手続きなどの総務関係の業務を担っています。それ以外の業務として、主に軽度の知的障がいのある社員が担う業務があります。知的障がいにもさまざまな特性がありますので、各人の特性に合った業務を担当してもらっています。宗教やアレルギー等が理由で特別食をご注文いただいたときに客室乗務員が機内で使用する作業用ラベルの作成や、お客さまが預ける荷物に付けるタグにゴム紐を取りつける作業、清掃作業、会議室への給茶、乗務員の訓練終了後の施設の消毒などの業務です。こうした従来からの業務に加えて新たな業務領域として、農作業、カフェ、マッサージルームの運営など、活躍の場を広げております。
現在では更に、新たな価値創造に力点をおいた事業運営をしております。具体的には、毎年社内で「新たな価値創造委員会」というビジネスコンテストを行っております。社員から出された案が事業化できるかを半年以上かけて検証し、新規事業化や社会への貢献を進めています。実際に事業化した事例として三つの事業をご紹介いたします。一つ目はチャレンジ手話です。聴覚障がいの社員の中には手話に長けた者が多くおりますので、最前線でサービスに当たる客室乗務員向けに手話講座を定期的に開催し、機内でのお客さまへのサービスの品質向上に貢献しようというのがチャレンジ手話です。二つ目はネイルルームです。2021年に始まり、現在は羽田整備地区と成田空港で営業しております。主な顧客は客室乗務員と空港の女性スタッフですが、最近は女性パイロットも利用しているようです。客室乗務員は身だしなみ基準が明確に決められているので、その基準に応じたネイルの色や施術を理解した障がいのある弊社の社員が、社員向けサービスの一つとして提供しています。三つ目はシューシャイン、靴磨きです。初代靴磨き世界大会のチャンピオンの方にコンサルティングしていただき、高い集中力を発揮し細かい作業が得意な社員に靴磨きの技術を習得してもらい社員向けにシューシャインサービスを提供しております。
また、JALサンライトではさまざまな障がいのある社員が円滑に活躍できるように、支援機器も数多く使用しています。聴覚障がいの社員に対しては音声を文字化するアプリを使ったり、筆談ボードを使うこともありますが、会議や研修の時には、社内の手話通訳士に通訳してもらうという情報保障をしております。聴覚障がいも人によって程度が異なります。人工内耳のみで会話ができる社員もいますが、ロジャーマイクなど補聴援助システムや機器を使用し円滑にコミュニケーションできるようにサポートもしています。視覚障がいもさまざまな障がいの種類がありますので、拡大読書器や音声読み上げソフトなどを使用しています。また、サポート機器だけではなく心身の健康サポートとして定期的なカウンセリングが重要だと考えております。社内に精神保健福祉士、臨床心理士、公認心理師、ジョブコーチなどが在籍し、日々の不安や心配ごとなど相談しやすい体制をとっています。
今後の更なる成長に向けて、私たちが今目指しているのは、基幹事業の品質を向上させつつ航空事業領域に関わるような仕事を増やしていくことです。もちろん、社会から求められているSDGsに関わる仕事も増やしていきたいと考えております。その一例として、国内線のクラスJで座席シートとして使用され、かつては廃棄されていた黒い本革を、コインケースやカップホルダーにアップサイクルし、社内やイベントで販売したりしております。
また昨年、新たな挑戦の一つとして、サステナブルチャーターフライトに聴覚障がいのある社員が参画いたしました。サステナブルフライトは、JALグループが2030年までにすべてのフライトをサステナブルなものとするというコンセプトのもと、持続可能な代替航空燃料SAF(Sustainable Aviation Fuel)を搭載してCO2削減に取り組んだフライトです。機内では脱プラスチックなど、よりサステナブルなアイテムを使ってサービスするという取り組みも行われました。その中でDE&Iの取り組みとして客室乗務員13名のうち6名の男性乗務員などを含む多様な人財と共に弊社の聴覚障がいのある社員が手話でコミュニケーションを取り合いながらお客さまに機内サービスをするという挑戦をしました。更に今月からチャレンジしている新たな事業領域としては、JALのグループ会社でグランドハンドリング業務を行っている会社に社員が出向し、協働を進めております。
また嬉しいニュースの一つとして、先日フランスで開催された国際アビリンピックの日本選手団30名の中にJALサンライトのネイリスト2名が参加しました。残念ながら金賞こそ逃したものの、銀賞と銅賞を受賞いたしました。アビリンピックは障がいのある方々の職業技能の向上と、社会の皆さまに障がいのある方々に対する理解と認識を深めてもらい、その雇用の促進を図るために開催されているものです。いろいろな競技があるので、今後もネイリストだけでなく他の競技にも参加してもらい、障がいのある方々に夢を描いてもらったり、より多くの選択肢を見出して自分らしく活躍してもらえるようにできればと思っております。
先ほどお話ししたサステナブルチャーターフライトに参画した聴覚障がいのある社員が客室乗務員と同じ制服を着て機内サービスを行ったことを、とあるろう学校の校長先生にお話ししたとき、校長先生は涙を流され「子どもたちに夢を本当にありがとうございます」と言っていただきました。以上ですが、本日は皆さまにJALサンライトの社員のさまざまな活躍を知っていただけて有難く思っております。これからも障がい者雇用を促進しつつ、さらにDE&Iを推進していきたいと思っております。
本日はありがとうございました。
ただいまご紹介いただきましたJALサンライトの城田と申します。本日は貴重な機会をいただきありがとうございます。
「嘱望される障がい者雇用のこれから」というテーマでお話しさせていただきます。私の勤務するJALの特例子会社であるJALサンライトは、障がい者雇用を促進しながら、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)を推進しています。弊社の社員の活躍を皆さまに知っていただき、身近にいらっしゃる障がいのある方々の夢や希望の広がりに思いを馳せていただければ嬉しいなと思っております。
私は元々JALの客室乗務員として従事しておりました。その中で機内の現場や間接部門で長らく人財育成に携わっておりました。そして、今与えられたミッションの一つは、障がいのある方々の能力や可能性に光をあてて成長を促し、現在や将来の仕事にどのように参画し活躍してもらうかを共に考え進めていくことです。私のこれまでの経験を活かせるやりがいのある仕事だと思っております。
JALサンライトは、JALの特例子会社として障がいの有無にかかわらず、JALグループの業務を担い、JALの翼を支えている会社です。企業理念は「障がいを仕事の障害としない環境をもとに多様性を活かし、新たな価値を創造し続けます。」というもので、これは社員のプロジェクトチームを中心に社員自らが作り上げた企業理念です。現在423名の社員のうち半数以上、222名の障がいのある社員が在籍しております。障がいの種類も知的障がい、聴覚障がい、肢体障がい、視覚障がい、精神障がい、内部障がいと多岐にわたります。
その上で、請け負っている業務内容としては、まず本社から受託している基幹業務が三つあります。一つ目は航空輸送を支える業務として、航空券を審査する業務や、客室乗務員のスケジュール作成、通勤や就業時間管理等のサポート業務を行っています。二つ目は社員の仕事を支える業務として、出張渡航関連業務、名刺・IDカード作成業務、社内のメーリング業務などを担っています。三つ目は社員の日常を支える業務として、給与や福利厚生、退職手続きなどの総務関係の業務を担っています。それ以外の業務として、主に軽度の知的障がいのある社員が担う業務があります。知的障がいにもさまざまな特性がありますので、各人の特性に合った業務を担当してもらっています。宗教やアレルギー等が理由で特別食をご注文いただいたときに客室乗務員が機内で使用する作業用ラベルの作成や、お客さまが預ける荷物に付けるタグにゴム紐を取りつける作業、清掃作業、会議室への給茶、乗務員の訓練終了後の施設の消毒などの業務です。こうした従来からの業務に加えて新たな業務領域として、農作業、カフェ、マッサージルームの運営など、活躍の場を広げております。
現在では更に、新たな価値創造に力点をおいた事業運営をしております。具体的には、毎年社内で「新たな価値創造委員会」というビジネスコンテストを行っております。社員から出された案が事業化できるかを半年以上かけて検証し、新規事業化や社会への貢献を進めています。実際に事業化した事例として三つの事業をご紹介いたします。一つ目はチャレンジ手話です。聴覚障がいの社員の中には手話に長けた者が多くおりますので、最前線でサービスに当たる客室乗務員向けに手話講座を定期的に開催し、機内でのお客さまへのサービスの品質向上に貢献しようというのがチャレンジ手話です。二つ目はネイルルームです。2021年に始まり、現在は羽田整備地区と成田空港で営業しております。主な顧客は客室乗務員と空港の女性スタッフですが、最近は女性パイロットも利用しているようです。客室乗務員は身だしなみ基準が明確に決められているので、その基準に応じたネイルの色や施術を理解した障がいのある弊社の社員が、社員向けサービスの一つとして提供しています。三つ目はシューシャイン、靴磨きです。初代靴磨き世界大会のチャンピオンの方にコンサルティングしていただき、高い集中力を発揮し細かい作業が得意な社員に靴磨きの技術を習得してもらい社員向けにシューシャインサービスを提供しております。
また、JALサンライトではさまざまな障がいのある社員が円滑に活躍できるように、支援機器も数多く使用しています。聴覚障がいの社員に対しては音声を文字化するアプリを使ったり、筆談ボードを使うこともありますが、会議や研修の時には、社内の手話通訳士に通訳してもらうという情報保障をしております。聴覚障がいも人によって程度が異なります。人工内耳のみで会話ができる社員もいますが、ロジャーマイクなど補聴援助システムや機器を使用し円滑にコミュニケーションできるようにサポートもしています。視覚障がいもさまざまな障がいの種類がありますので、拡大読書器や音声読み上げソフトなどを使用しています。また、サポート機器だけではなく心身の健康サポートとして定期的なカウンセリングが重要だと考えております。社内に精神保健福祉士、臨床心理士、公認心理師、ジョブコーチなどが在籍し、日々の不安や心配ごとなど相談しやすい体制をとっています。
今後の更なる成長に向けて、私たちが今目指しているのは、基幹事業の品質を向上させつつ航空事業領域に関わるような仕事を増やしていくことです。もちろん、社会から求められているSDGsに関わる仕事も増やしていきたいと考えております。その一例として、国内線のクラスJで座席シートとして使用され、かつては廃棄されていた黒い本革を、コインケースやカップホルダーにアップサイクルし、社内やイベントで販売したりしております。
また昨年、新たな挑戦の一つとして、サステナブルチャーターフライトに聴覚障がいのある社員が参画いたしました。サステナブルフライトは、JALグループが2030年までにすべてのフライトをサステナブルなものとするというコンセプトのもと、持続可能な代替航空燃料SAF(Sustainable Aviation Fuel)を搭載してCO2削減に取り組んだフライトです。機内では脱プラスチックなど、よりサステナブルなアイテムを使ってサービスするという取り組みも行われました。その中でDE&Iの取り組みとして客室乗務員13名のうち6名の男性乗務員などを含む多様な人財と共に弊社の聴覚障がいのある社員が手話でコミュニケーションを取り合いながらお客さまに機内サービスをするという挑戦をしました。更に今月からチャレンジしている新たな事業領域としては、JALのグループ会社でグランドハンドリング業務を行っている会社に社員が出向し、協働を進めております。
また嬉しいニュースの一つとして、先日フランスで開催された国際アビリンピックの日本選手団30名の中にJALサンライトのネイリスト2名が参加しました。残念ながら金賞こそ逃したものの、銀賞と銅賞を受賞いたしました。アビリンピックは障がいのある方々の職業技能の向上と、社会の皆さまに障がいのある方々に対する理解と認識を深めてもらい、その雇用の促進を図るために開催されているものです。いろいろな競技があるので、今後もネイリストだけでなく他の競技にも参加してもらい、障がいのある方々に夢を描いてもらったり、より多くの選択肢を見出して自分らしく活躍してもらえるようにできればと思っております。
先ほどお話ししたサステナブルチャーターフライトに参画した聴覚障がいのある社員が客室乗務員と同じ制服を着て機内サービスを行ったことを、とあるろう学校の校長先生にお話ししたとき、校長先生は涙を流され「子どもたちに夢を本当にありがとうございます」と言っていただきました。以上ですが、本日は皆さまにJALサンライトの社員のさまざまな活躍を知っていただけて有難く思っております。これからも障がい者雇用を促進しつつ、さらにDE&Iを推進していきたいと思っております。
本日はありがとうございました。
卓話「型染めって何?」
おかめ工房代表 (紅型染め物講師) 山本加代子さま
2023年4月20日

 はじめまして、新宿区の中井でモダン紅型工房をやっている山本加代子と申します。よろしくお願いいたします。
今日は私の保護者的立場で、新宿区のイベント「染めの小道」を13,4年やっている仲間の東さんと、生徒さんの上脇さんにも来ていただきました。
型染めとは、型紙を使って染める染め物です。型染めには、小紋、更紗染め、友禅の型友禅、そして私がやっている紅型があります。小紋は小さな柄の模様が上下の方向に関係なく細かい模様がついているものです。江戸小紋というと柄がもっと細かいものです。華美な柄を禁止した江戸時代に生まれた小紋で、無地のように見えるくらい柄を一色のみで染め上げたのが江戸小紋です。そして更紗はジャワ更紗やインド更紗といった派手な模様の型染めです。シックな柄の和更紗、江戸更紗というものもあります。染め方も手描きや木版に加え、「型染め」も出てきました。さらに友禅があります。京都の友禅斎という人が、扇子用の絵を着物に写して人気になり、それを着物の意匠に取り入れました。それを型紙を使って染めたのが型友禅です。紅型は沖縄の伝統工芸です。私は東京生まれですが、染め物がどういうものか分からない時に出会ったのが紅型でした。なんてきれいな色なのだろう、なんて素敵なのだろうと思って、夢中になりました。それから今までずっと続けています。
紅型は柿渋紙に模様を掘った型紙を使います。その型紙に紗張りをします。そうすると型紙が動かなくなるので、何回も使えます。ここに防染用の糊を置きます。糊が付いていないところに顔料で色を付けます。一度目の塗りは薄く配色する感じで薄く塗ります。二度目に同じ色を重ねます。違う色を重ねる場合もあります。発色をきれいにするために重ねるのです。最後に紅型の特徴である隈取りをすることでとても個性的な染め物になります。
紅型の良い点は自然のものを使っている点です。絹の布に置く糊は餅粉と糠から出来ています。色を付ける染料は化学染料ではなく顔料です。顔料は鉱物の土や動物から作られたものです。例えば、黄色は黄土の土、ベンガラはインドのベンガル地方の赤い土、宝石から出来たものもあります。今は使いませんが、昔は水銀も少し入っていた鉱物もありました。こういう顔料は化学染料と違い水や油に溶けません。そこで大豆の汁の豆汁で顔料を溶いて、鹿と馬の毛で出来た刷り込み刷毛で布に顔料をつけていきます。みんな自然のものです。そこに私はワクワクしたのです。
紅型の値段が高いのはこのような材料と共に工程が長くかかるからです。今の染め物は化学染料が中心になっています。化学染料の方が安く早く染め物が出来上がります。でも私は量産は出来ないし、一人でやっているので、顔料や糊など自然の物を使った紅型の染め物をずっと続けて伝えていきたいと思っています。
私が紅型に出会って夢中になり、やってみようと始めたころは、まだ会社に勤めていましたので、紅型は細々とやっていました。ただ、着物や帯の時代ではなくなってきたので、インテリアとして紅型を掛け軸や屏風にしたら素敵かなと思い、職業訓練校で半年間、表装を習いました。掛け軸というと床の間を思い浮かべるかもしれませんが、紅型の掛け軸は白い壁面にかけると家の中が華やぎます。そして、職業訓練校の卒業後に、カルチャースクールの講師募集に、紅型と表装で応募したところ、両方の講師をやってほしいと頼まれました。表装にはまだ自信がなかったのですが、たまたま近所の方から50本くらいの掛け軸の仕立てを頼まれ、その50本を仕立てたおかげで表装も上手になりました。動くと運がついてくるようです。その後、アメリカンクラブのロビーギャラリーで作品を展示した時に、新宿区の中井にある古い古民家の工房が月6万円で借りられるということで、ただやりたいという思いから工房を借りて今に至っています。生徒さんも20年以上続けている方もいます。
こうしてやってきましたけれど、私は沖縄出身ではないし、沖縄の伝統工芸士にはなれないし、自分なりにオリジナルなものを作っているので、沖縄の伝統工芸の「紅型」という名前を使うのは申し訳ないと思い、「モダン紅型」という名前にしました。深く考えたわけではないのですがこの「モダン紅型」という名前によって、新宿区のものづくりマイスターという称号をいただきました。だから、人生は面白いなと思っています。
今、教室では体験講座もやっています。アーティスト系の方が多いのですが、外国人の方も結構習いに来られています。夏休みに来て一週間くらい続けて通ってこられて、最初から最後まで自分でやりたいとおっしゃいます。それで、普段は私が材料屋から買っている糊も、餅粉と糠からつくって団子状に蒸かしてすりつぶすという糊の作り方で教えます。言葉の面ではなかなか難しいですけれど、何とか頑張ってやっています。日本人よりも海外の人の方が日本の文化に関心があるのかもしれないと思い、私も海外に行って日本の文化を広めたいというのが今の私の夢になっています。残念ながら、コロナの影響でまだいつ行けるか分からないのですが。
新宿区中井の町の図をご覧ください。真ん中に妙正寺川があり、西武線が走っています。そしてこの川の両側に染め物屋がたくさんあり隆盛を誇ったのです。この妙正寺川の水が染物を洗い流すにはちょうど良い成分だったのです。染物屋のほかには、湯のし屋、染み抜き屋、刺繍屋などがあります。染め物屋さんたちは皆さん新宿区の染色協議会に参加しています。
新宿区では、ふるさと納税で税金を他の地方にたくさん流出してしまうので、新宿もふるさと納税をやろうということになり、地場産業である染色も参加して良いということになりました。私も参加したいと手を挙げています。このほか新宿区では、新宿区の染色家が、恵まれない家庭の娘さんの成人式の着物を染めて、レンタルで着てもらおうということになりました。今の区長の任期があと3年あるので、3年間で少しずつ染ためていき、将来もずっとレンタルで着てもらおうということです。プリントではなく、手染めの本物の着物が着られるのですから、染色業界にとっても素晴らしいことだし、その手染めの作家の振り袖を着られる娘さん達にとっても素晴らしい体験だと思っています。
私が何も分からずにやってきた新宿区中井。そこが染色の町でした。京都、金沢、東京は日本の三大染色地です。その東京の新宿区が染色の町なのです。染物に付随する色々な業種の方がいらっしゃいます。今、染色業は衰退しています。一時は300軒くらいありましたが、今は50軒くらいに減少しています。それを盛り上げようというイベントが「染めの小道」です。昔は、妙正寺川の両側で友禅流し、糊を流す作業をしていました。しかし今は、護岸工事をして糊流しができないので、イベントでは、川の上に300メートルくらい反物を架け渡しています。各商店には工房や染め物屋で染めた暖簾がかかり、それは見ごたえのあるすごいイベントです。3日間のイベントに1万6千人が集まったことがあります。運営はすべてボランティアで行なっています。私もそこで染め物を披露でき、うちの生徒さんも出品します。それを皆さんが楽しみに来られて、それが染色の発展につながると良いなと思っています。
本日はどうもありがとうございました。
はじめまして、新宿区の中井でモダン紅型工房をやっている山本加代子と申します。よろしくお願いいたします。
今日は私の保護者的立場で、新宿区のイベント「染めの小道」を13,4年やっている仲間の東さんと、生徒さんの上脇さんにも来ていただきました。
型染めとは、型紙を使って染める染め物です。型染めには、小紋、更紗染め、友禅の型友禅、そして私がやっている紅型があります。小紋は小さな柄の模様が上下の方向に関係なく細かい模様がついているものです。江戸小紋というと柄がもっと細かいものです。華美な柄を禁止した江戸時代に生まれた小紋で、無地のように見えるくらい柄を一色のみで染め上げたのが江戸小紋です。そして更紗はジャワ更紗やインド更紗といった派手な模様の型染めです。シックな柄の和更紗、江戸更紗というものもあります。染め方も手描きや木版に加え、「型染め」も出てきました。さらに友禅があります。京都の友禅斎という人が、扇子用の絵を着物に写して人気になり、それを着物の意匠に取り入れました。それを型紙を使って染めたのが型友禅です。紅型は沖縄の伝統工芸です。私は東京生まれですが、染め物がどういうものか分からない時に出会ったのが紅型でした。なんてきれいな色なのだろう、なんて素敵なのだろうと思って、夢中になりました。それから今までずっと続けています。
紅型は柿渋紙に模様を掘った型紙を使います。その型紙に紗張りをします。そうすると型紙が動かなくなるので、何回も使えます。ここに防染用の糊を置きます。糊が付いていないところに顔料で色を付けます。一度目の塗りは薄く配色する感じで薄く塗ります。二度目に同じ色を重ねます。違う色を重ねる場合もあります。発色をきれいにするために重ねるのです。最後に紅型の特徴である隈取りをすることでとても個性的な染め物になります。
紅型の良い点は自然のものを使っている点です。絹の布に置く糊は餅粉と糠から出来ています。色を付ける染料は化学染料ではなく顔料です。顔料は鉱物の土や動物から作られたものです。例えば、黄色は黄土の土、ベンガラはインドのベンガル地方の赤い土、宝石から出来たものもあります。今は使いませんが、昔は水銀も少し入っていた鉱物もありました。こういう顔料は化学染料と違い水や油に溶けません。そこで大豆の汁の豆汁で顔料を溶いて、鹿と馬の毛で出来た刷り込み刷毛で布に顔料をつけていきます。みんな自然のものです。そこに私はワクワクしたのです。
紅型の値段が高いのはこのような材料と共に工程が長くかかるからです。今の染め物は化学染料が中心になっています。化学染料の方が安く早く染め物が出来上がります。でも私は量産は出来ないし、一人でやっているので、顔料や糊など自然の物を使った紅型の染め物をずっと続けて伝えていきたいと思っています。
私が紅型に出会って夢中になり、やってみようと始めたころは、まだ会社に勤めていましたので、紅型は細々とやっていました。ただ、着物や帯の時代ではなくなってきたので、インテリアとして紅型を掛け軸や屏風にしたら素敵かなと思い、職業訓練校で半年間、表装を習いました。掛け軸というと床の間を思い浮かべるかもしれませんが、紅型の掛け軸は白い壁面にかけると家の中が華やぎます。そして、職業訓練校の卒業後に、カルチャースクールの講師募集に、紅型と表装で応募したところ、両方の講師をやってほしいと頼まれました。表装にはまだ自信がなかったのですが、たまたま近所の方から50本くらいの掛け軸の仕立てを頼まれ、その50本を仕立てたおかげで表装も上手になりました。動くと運がついてくるようです。その後、アメリカンクラブのロビーギャラリーで作品を展示した時に、新宿区の中井にある古い古民家の工房が月6万円で借りられるということで、ただやりたいという思いから工房を借りて今に至っています。生徒さんも20年以上続けている方もいます。
こうしてやってきましたけれど、私は沖縄出身ではないし、沖縄の伝統工芸士にはなれないし、自分なりにオリジナルなものを作っているので、沖縄の伝統工芸の「紅型」という名前を使うのは申し訳ないと思い、「モダン紅型」という名前にしました。深く考えたわけではないのですがこの「モダン紅型」という名前によって、新宿区のものづくりマイスターという称号をいただきました。だから、人生は面白いなと思っています。
今、教室では体験講座もやっています。アーティスト系の方が多いのですが、外国人の方も結構習いに来られています。夏休みに来て一週間くらい続けて通ってこられて、最初から最後まで自分でやりたいとおっしゃいます。それで、普段は私が材料屋から買っている糊も、餅粉と糠からつくって団子状に蒸かしてすりつぶすという糊の作り方で教えます。言葉の面ではなかなか難しいですけれど、何とか頑張ってやっています。日本人よりも海外の人の方が日本の文化に関心があるのかもしれないと思い、私も海外に行って日本の文化を広めたいというのが今の私の夢になっています。残念ながら、コロナの影響でまだいつ行けるか分からないのですが。
新宿区中井の町の図をご覧ください。真ん中に妙正寺川があり、西武線が走っています。そしてこの川の両側に染め物屋がたくさんあり隆盛を誇ったのです。この妙正寺川の水が染物を洗い流すにはちょうど良い成分だったのです。染物屋のほかには、湯のし屋、染み抜き屋、刺繍屋などがあります。染め物屋さんたちは皆さん新宿区の染色協議会に参加しています。
新宿区では、ふるさと納税で税金を他の地方にたくさん流出してしまうので、新宿もふるさと納税をやろうということになり、地場産業である染色も参加して良いということになりました。私も参加したいと手を挙げています。このほか新宿区では、新宿区の染色家が、恵まれない家庭の娘さんの成人式の着物を染めて、レンタルで着てもらおうということになりました。今の区長の任期があと3年あるので、3年間で少しずつ染ためていき、将来もずっとレンタルで着てもらおうということです。プリントではなく、手染めの本物の着物が着られるのですから、染色業界にとっても素晴らしいことだし、その手染めの作家の振り袖を着られる娘さん達にとっても素晴らしい体験だと思っています。
私が何も分からずにやってきた新宿区中井。そこが染色の町でした。京都、金沢、東京は日本の三大染色地です。その東京の新宿区が染色の町なのです。染物に付随する色々な業種の方がいらっしゃいます。今、染色業は衰退しています。一時は300軒くらいありましたが、今は50軒くらいに減少しています。それを盛り上げようというイベントが「染めの小道」です。昔は、妙正寺川の両側で友禅流し、糊を流す作業をしていました。しかし今は、護岸工事をして糊流しができないので、イベントでは、川の上に300メートルくらい反物を架け渡しています。各商店には工房や染め物屋で染めた暖簾がかかり、それは見ごたえのあるすごいイベントです。3日間のイベントに1万6千人が集まったことがあります。運営はすべてボランティアで行なっています。私もそこで染め物を披露でき、うちの生徒さんも出品します。それを皆さんが楽しみに来られて、それが染色の発展につながると良いなと思っています。
本日はどうもありがとうございました。


卓話「国際奉仕について&PBG50周年について」
地区国際奉仕委員長 橘高薫子さま
2023年4月13日

 国際奉仕委員会より橘高委員長をお招きして卓話をして頂きました。
国際組織ならではの他クラブの国際奉仕活動や国際奉仕の方法などについてのお話しと、3月21日~22日にグアムにて開催された当地区のPBG50周年記念事業の様子をお伝えくださいました。山の手RCからも数名が参加しました。ビーチクリーニングや式典の様子をお話ししていただきました。
国際奉仕委員会より橘高委員長をお招きして卓話をして頂きました。
国際組織ならではの他クラブの国際奉仕活動や国際奉仕の方法などについてのお話しと、3月21日~22日にグアムにて開催された当地区のPBG50周年記念事業の様子をお伝えくださいました。山の手RCからも数名が参加しました。ビーチクリーニングや式典の様子をお話ししていただきました。
卓話「米中間選挙後の日米・米中関係」
元米国大統領府通商代表部通商代表補代理 グレン・S・フクシマさま
2023年3月16日

 3月16日(木)例会には、グレン・S・フクシマさまをお招きして「米中間選挙後の日米・米中関係」というタイムリーなテーマで卓話をしていただきました。7名のビジターゲストがお集まりくださり大変関心の高いお話を聞くことが出来ました。
3月16日(木)例会には、グレン・S・フクシマさまをお招きして「米中間選挙後の日米・米中関係」というタイムリーなテーマで卓話をしていただきました。7名のビジターゲストがお集まりくださり大変関心の高いお話を聞くことが出来ました。
卓話「小さな親善大使」
青少年交換留学生 ルーカス(Lucas Vincius ALLEIN)さま ブラジル
2023年3月9日

 皆さん、こんにちは。僕の名前はルーカス、16歳です。ブラジルから来ました。父と母は56歳、兄は21歳です。
留学するのが子供の頃からの夢でした。日本への留学は僕にとって大きなチャンスでした。日本の学校は教科がブラジルより多く、授業も難しいので、友だちと遊ぶ時間がありません。僕は写真のクラブとWSS(World School Society)という部活に入って日本人の友だちを作りました。僕のクラスにいるのは中国人、タイ人、ベトナム人など全員外国人です。でも日本人の友だちをたくさん作りたいと思ったので部活に入りました。
日本の料理はブラジルの料理とは大きく異なりますが、日本の料理は大好きです。ホストママと一緒にご飯を作るのは楽しいですし、日本語も学べます。好きな料理は寿司と天ぷらです。でも納豆は苦手です。
日本で初めて温泉に入りました。ブラジルには温泉がなく、知らない人と一緒にお風呂に入ることはありません。日本で何度も温泉に行き温泉好きになりました。
日本に来てすぐの頃、迷子になったことがありますが、学校の友だちが助けてくれたので不安にはなりませんでした。ホストファミリーとブラジルのレストランで待ち合わせた時は、途中でスマホのバッテリーが切れてしまい、大変なことになったと思いました。駅にある地図を見ても難しくて分からなかったので、見知らぬ人に日本語で尋ねました。とても優しい方で、レストランまで一緒に連れていってくれました。とても良い経験だったと思っています。
日本でのさまざまな経験をご紹介します。サマーキャンプでは16歳の誕生日を迎えました。富士急ハイランドでは怖いけれどジェットコースターが大好きになりました。ホストファミリーのホストシスターとその友だちと一緒にチームラボに行きました。苗場ではユーミンのコンサートに行きました。舞台のユーミンと目が合った時にユーミンが僕にウィンクをしてくれて、とても嬉しくてすっかりファンになりました。学校の旅行では勝浦に行き、友だちと同じ部屋に泊まりました。ロータリーのイベントで参加したお茶会やソーラン節、とても楽しかったです。ロータリーのクリスマスイベントでは沢山の留学生や日本人の方と会いました。
旅行では、白馬に行った時に、生れて初めて雪を見て、スキーをしました。ブラジルでも雪は降りますが、ずっと南の方で降るので僕にとっては初めて見る雪でした。ローテックスの方々と京都と奈良にも行きました。きれいな神社やかわいい鹿をみて楽しかったです。ローターアクトの方々と千葉に行った時は陶器を作りました。今日は僕の作った陶器を持ってきたのでご覧ください。
皆さんからのサポートをいただき、ありがとうございます。今日は僕の発表を聞いていただきありがとうございました。
Q&A
Q: アメリカ人や中国人のお友だちと一緒に出かける時も日本語で話すのですか。
A: はい、僕たち留学生は練習のために日本語で話します。僕の中国人の友だちは日本語が上手なので、僕の日本語の先生になってくれています。
Q: ブラジルに灰田という名前の移民がいるはずですが、お会いになったことはありますか。
A: 僕の住んでいた町にはドイツ系の移民はいますが、日本からの移民はいませんでした。
Q: 上着についているバッジが素敵ですね。どのようなバッジなのですか。
A: このバッジはブラジルの留学生にもらったものです。皆さんのためにもバッジを作って持ってきました。
Q: 青少年交換で日本に派遣されることを、ご自分で希望されたのですか。また、日本のどういうところがお好きなのですか。
A: 日本語を学びたいと思って希望しました。日本語はとてもきれいな言語だと思っています。日本の文化、神社や着物、サムライはブラジルに無いので興味があり、とても好きです。
Q: 卒業後はどのような仕事につきたいと考えていますか。
A: 国際ビジネスに関わりたいと思っています。
Q: 来日前に思い描いていた日本と、来てみてからの日本で、違うと思った点はありますか。
A: ブラジルにいる時は、日本人は冷たくてとても厳しい人たちだと言われていましたが、来てみると全く違って、とても楽しい人たちだと思っています。ブラジルに帰りたくないくらいです。
Q: 日本語はどのくらい前から勉強していたのですか。
A: 来日の1ヶ月前から日本語の勉強を始めましたが、6か月前に日本に来た当初は全く分からず大変でした。日本語で話せるようになりたいと思って一生懸命勉強しました。
皆さん、こんにちは。僕の名前はルーカス、16歳です。ブラジルから来ました。父と母は56歳、兄は21歳です。
留学するのが子供の頃からの夢でした。日本への留学は僕にとって大きなチャンスでした。日本の学校は教科がブラジルより多く、授業も難しいので、友だちと遊ぶ時間がありません。僕は写真のクラブとWSS(World School Society)という部活に入って日本人の友だちを作りました。僕のクラスにいるのは中国人、タイ人、ベトナム人など全員外国人です。でも日本人の友だちをたくさん作りたいと思ったので部活に入りました。
日本の料理はブラジルの料理とは大きく異なりますが、日本の料理は大好きです。ホストママと一緒にご飯を作るのは楽しいですし、日本語も学べます。好きな料理は寿司と天ぷらです。でも納豆は苦手です。
日本で初めて温泉に入りました。ブラジルには温泉がなく、知らない人と一緒にお風呂に入ることはありません。日本で何度も温泉に行き温泉好きになりました。
日本に来てすぐの頃、迷子になったことがありますが、学校の友だちが助けてくれたので不安にはなりませんでした。ホストファミリーとブラジルのレストランで待ち合わせた時は、途中でスマホのバッテリーが切れてしまい、大変なことになったと思いました。駅にある地図を見ても難しくて分からなかったので、見知らぬ人に日本語で尋ねました。とても優しい方で、レストランまで一緒に連れていってくれました。とても良い経験だったと思っています。
日本でのさまざまな経験をご紹介します。サマーキャンプでは16歳の誕生日を迎えました。富士急ハイランドでは怖いけれどジェットコースターが大好きになりました。ホストファミリーのホストシスターとその友だちと一緒にチームラボに行きました。苗場ではユーミンのコンサートに行きました。舞台のユーミンと目が合った時にユーミンが僕にウィンクをしてくれて、とても嬉しくてすっかりファンになりました。学校の旅行では勝浦に行き、友だちと同じ部屋に泊まりました。ロータリーのイベントで参加したお茶会やソーラン節、とても楽しかったです。ロータリーのクリスマスイベントでは沢山の留学生や日本人の方と会いました。
旅行では、白馬に行った時に、生れて初めて雪を見て、スキーをしました。ブラジルでも雪は降りますが、ずっと南の方で降るので僕にとっては初めて見る雪でした。ローテックスの方々と京都と奈良にも行きました。きれいな神社やかわいい鹿をみて楽しかったです。ローターアクトの方々と千葉に行った時は陶器を作りました。今日は僕の作った陶器を持ってきたのでご覧ください。
皆さんからのサポートをいただき、ありがとうございます。今日は僕の発表を聞いていただきありがとうございました。
Q&A
Q: アメリカ人や中国人のお友だちと一緒に出かける時も日本語で話すのですか。
A: はい、僕たち留学生は練習のために日本語で話します。僕の中国人の友だちは日本語が上手なので、僕の日本語の先生になってくれています。
Q: ブラジルに灰田という名前の移民がいるはずですが、お会いになったことはありますか。
A: 僕の住んでいた町にはドイツ系の移民はいますが、日本からの移民はいませんでした。
Q: 上着についているバッジが素敵ですね。どのようなバッジなのですか。
A: このバッジはブラジルの留学生にもらったものです。皆さんのためにもバッジを作って持ってきました。
Q: 青少年交換で日本に派遣されることを、ご自分で希望されたのですか。また、日本のどういうところがお好きなのですか。
A: 日本語を学びたいと思って希望しました。日本語はとてもきれいな言語だと思っています。日本の文化、神社や着物、サムライはブラジルに無いので興味があり、とても好きです。
Q: 卒業後はどのような仕事につきたいと考えていますか。
A: 国際ビジネスに関わりたいと思っています。
Q: 来日前に思い描いていた日本と、来てみてからの日本で、違うと思った点はありますか。
A: ブラジルにいる時は、日本人は冷たくてとても厳しい人たちだと言われていましたが、来てみると全く違って、とても楽しい人たちだと思っています。ブラジルに帰りたくないくらいです。
Q: 日本語はどのくらい前から勉強していたのですか。
A: 来日の1ヶ月前から日本語の勉強を始めましたが、6か月前に日本に来た当初は全く分からず大変でした。日本語で話せるようになりたいと思って一生懸命勉強しました。
卓話「課題先進国の日本で、労働人口不足をテクノロジーの力で解決し、持続可能な社会へ」
ファンファーレ株式会社 CEO 近藤志人さま
2023年3月2日

 こんにちは。ファンファーレ株式会社の近藤と申します。
本日は、廃棄物業界という生産性の向上がITによって得られにくく、かつその状態がじり貧で続くと社会自体が成り立たなくなるという業界に対して、弊社がIT企業としてどのように向き合っているかをお話させていただきます。
私は学生の頃から社会課題×ビジネスに取り組んできました。就活の時期はちょうどNPO法人の活動が活発になっていました。就職先の一つの選択肢として社会課題の解決というものがあった世代です。社会課題の解決が自己満足に終わらず、ビジネスとしてその業界全体を変えていけるようになりたいと考えて社会人経験を積み重ねてきました。最初の就職先は新規事業開発のコンサルティングを行う会社でした。そこでの新規事業を作る経験からは、会社自体がイノベーティブでないとイノベーションは起こせないと痛感しました。その後、リクルートホールディングスで組織開発を行い、事業面と組織面でイノベーティブなことをするためにどうすればよいかを経験した後に、今のファンファーレ株式会社を作りました。社会課題を本質的にスケーラブルなビジネスで解決することに今、私は挑戦しております。
弊社のビジネス組織は戦略コンサルティング出身の人間が支えております。AIを使う弊社の技術をけん引しているのは東大卒業後にNECのAI研究所でアルゴリズムの研究を行っていた研究者です。営業は、18年間産業廃棄物業界のシステム導入を行ってきた業界のインサイダーが担当しています。会社としてはこの業界のDXを担う企業として少しずつ注目を浴び、昨年は「すごいベンチャー100」にも選ばれてメディアにも取り上げていただいております。弊社は、外部資本によって会社を大きくするスタートアップというビジネスモデルで事業を行っています。産業廃棄物に特化し、高度なIT人材を集めて資金調達を行っている唯一のスタートアップであることが特徴です。
産業廃棄物業界は皆さまがイメージとしてお持ちの通り、大変、キツイ、汚いという業界で、労働人口不足にあえいでいます。この業界の経営者の課題第1位は5年連続で労働人口不足であり、人手不足によって経営がうまくいかないという状況です。産業廃棄物は家庭ごみとは異なり、建設業界や工場などのメーカーから出るものや、病院から出る感染性の廃棄物などです。産業廃棄物の量は、日本のGDPが大きく下がらない限り変わりません。過去20年間産業廃棄物の量は横ばいであるのに対し、業界の労働人口はどんどん減少しているという深刻な状況です。この状態が続くと、1960年代に経験したような公害問題や環境汚染が広がる時代に逆戻りする恐れがあります。また、資源に乏しい日本では産業廃棄物のリサイクル率は50%を超えているのですが、廃棄物処理のリサイクルが進まなくなると輸入に頼らざるを得なくなり、日本特有のこの業界が成り立たなくなるという社会課題があります。
この社会課題に対して弊社が提供しているのは、廃棄物の回収ルートをAIが自動的に作成するサービスです。これまで配車表の作成は廃棄物事業者の配車担当者が時間をかけて作るという属人化した業務でしたが、弊社のサービスでは、ボタンをぽちっと押すとAIが3分くらいで配車計画を立ててくれます。職人が作る配車表よりも配車効率が上がり、例えば10台導入されている事業者ではAIで作成することで月額400万円くらい売り上げがアップします。このサービスはリリースから2年ほどですが、北海道から鹿児島までお客さまに使っていただいております。今後の展開として産廃事業者の業務フローに対して、今までにないサービスを提供することで業界自体の変革を担い、日本における強靭な社会インフラ構築に寄与していきたいと考えております。
ちょっと小話のようになりますが、AIだから生じる不思議なことがあります。AIが出す配車表の違和感で気にしない方がよいことを資料としてお客さまに説明しています。例えば、遠回りしている車が1台ある場合は、そのおかげで他の車が回りやすくなるという効果があります。また、目の前を通っていても廃棄物を回収せずにスルーするのは、往復数が全体として少なくなる効果があります。中間処理施設で車一杯に廃棄物を乗せずに帰ってくるのは他の車が回収しやすくするためです。人間が直観的に理解できないところがどうしてもありますので、データとして配車効率がどれだけ上がるか、作業負荷がどれだけ下がるかを定量的に示してご理解いただきながら導入していただいております。
少し長めに質疑応答の時間を取った方が皆様の理解が深まるのではないかと思います。ありがとうございました。
Q&A
Q: 導入されているのは収集運搬の会社ですか。
A: はい、今は収集運搬と中間処理の両方をやっていらっしゃるお客様に導入されています。
Q: 廃棄物は地方自治体がやるものと思っていますが、御社が取り上げるものとの線引き区分を説明してください。
A: 廃棄物業界は一般廃棄物と産業廃棄物に分かれており、皆さんが想像される家庭ごみは一般廃棄物になります。年間0.4億トン排出される一般廃棄物は行政から委託されますが、その10倍の年間4億トン排出される産業廃棄物は100%民間で運営されており、民間企業が環境省などに適正に行政報告することで成り立っている業界です。廃棄物業界全体を救いたいと考えた場合、民間企業である私たちが入りやすいこと、そして廃棄物の量が多いという社会的なインパクトを考えて私たちは事業を展開しています。
Q: AIはどういうステージで働くのですか。
A: AIが働くポイントは結構たくさんあります。代表的なところでご説明すると、産廃事業者の配車のフローは、車庫で車と人をマッチングし、ごみの排出場で排出品目によって行先の処理場が変わるという流れです。例えば、ドライバーが60名、免許の種類が3種類、乗せるコンテナが8種類、車の種類が8種類、1日300か所に持って行き、その作業スペースが5種類、場所によっては10カ所くらい中間施設が変わる。この毎日変わるパターンの組み合わせを職人さんが一日中時間を使って考えているような業務を、AIはボタンをぽちっと押すだけで回答をすぐ出してくれるという点が一番大きなAIの使いどころになります。
こんにちは。ファンファーレ株式会社の近藤と申します。
本日は、廃棄物業界という生産性の向上がITによって得られにくく、かつその状態がじり貧で続くと社会自体が成り立たなくなるという業界に対して、弊社がIT企業としてどのように向き合っているかをお話させていただきます。
私は学生の頃から社会課題×ビジネスに取り組んできました。就活の時期はちょうどNPO法人の活動が活発になっていました。就職先の一つの選択肢として社会課題の解決というものがあった世代です。社会課題の解決が自己満足に終わらず、ビジネスとしてその業界全体を変えていけるようになりたいと考えて社会人経験を積み重ねてきました。最初の就職先は新規事業開発のコンサルティングを行う会社でした。そこでの新規事業を作る経験からは、会社自体がイノベーティブでないとイノベーションは起こせないと痛感しました。その後、リクルートホールディングスで組織開発を行い、事業面と組織面でイノベーティブなことをするためにどうすればよいかを経験した後に、今のファンファーレ株式会社を作りました。社会課題を本質的にスケーラブルなビジネスで解決することに今、私は挑戦しております。
弊社のビジネス組織は戦略コンサルティング出身の人間が支えております。AIを使う弊社の技術をけん引しているのは東大卒業後にNECのAI研究所でアルゴリズムの研究を行っていた研究者です。営業は、18年間産業廃棄物業界のシステム導入を行ってきた業界のインサイダーが担当しています。会社としてはこの業界のDXを担う企業として少しずつ注目を浴び、昨年は「すごいベンチャー100」にも選ばれてメディアにも取り上げていただいております。弊社は、外部資本によって会社を大きくするスタートアップというビジネスモデルで事業を行っています。産業廃棄物に特化し、高度なIT人材を集めて資金調達を行っている唯一のスタートアップであることが特徴です。
産業廃棄物業界は皆さまがイメージとしてお持ちの通り、大変、キツイ、汚いという業界で、労働人口不足にあえいでいます。この業界の経営者の課題第1位は5年連続で労働人口不足であり、人手不足によって経営がうまくいかないという状況です。産業廃棄物は家庭ごみとは異なり、建設業界や工場などのメーカーから出るものや、病院から出る感染性の廃棄物などです。産業廃棄物の量は、日本のGDPが大きく下がらない限り変わりません。過去20年間産業廃棄物の量は横ばいであるのに対し、業界の労働人口はどんどん減少しているという深刻な状況です。この状態が続くと、1960年代に経験したような公害問題や環境汚染が広がる時代に逆戻りする恐れがあります。また、資源に乏しい日本では産業廃棄物のリサイクル率は50%を超えているのですが、廃棄物処理のリサイクルが進まなくなると輸入に頼らざるを得なくなり、日本特有のこの業界が成り立たなくなるという社会課題があります。
この社会課題に対して弊社が提供しているのは、廃棄物の回収ルートをAIが自動的に作成するサービスです。これまで配車表の作成は廃棄物事業者の配車担当者が時間をかけて作るという属人化した業務でしたが、弊社のサービスでは、ボタンをぽちっと押すとAIが3分くらいで配車計画を立ててくれます。職人が作る配車表よりも配車効率が上がり、例えば10台導入されている事業者ではAIで作成することで月額400万円くらい売り上げがアップします。このサービスはリリースから2年ほどですが、北海道から鹿児島までお客さまに使っていただいております。今後の展開として産廃事業者の業務フローに対して、今までにないサービスを提供することで業界自体の変革を担い、日本における強靭な社会インフラ構築に寄与していきたいと考えております。
ちょっと小話のようになりますが、AIだから生じる不思議なことがあります。AIが出す配車表の違和感で気にしない方がよいことを資料としてお客さまに説明しています。例えば、遠回りしている車が1台ある場合は、そのおかげで他の車が回りやすくなるという効果があります。また、目の前を通っていても廃棄物を回収せずにスルーするのは、往復数が全体として少なくなる効果があります。中間処理施設で車一杯に廃棄物を乗せずに帰ってくるのは他の車が回収しやすくするためです。人間が直観的に理解できないところがどうしてもありますので、データとして配車効率がどれだけ上がるか、作業負荷がどれだけ下がるかを定量的に示してご理解いただきながら導入していただいております。
少し長めに質疑応答の時間を取った方が皆様の理解が深まるのではないかと思います。ありがとうございました。
Q&A
Q: 導入されているのは収集運搬の会社ですか。
A: はい、今は収集運搬と中間処理の両方をやっていらっしゃるお客様に導入されています。
Q: 廃棄物は地方自治体がやるものと思っていますが、御社が取り上げるものとの線引き区分を説明してください。
A: 廃棄物業界は一般廃棄物と産業廃棄物に分かれており、皆さんが想像される家庭ごみは一般廃棄物になります。年間0.4億トン排出される一般廃棄物は行政から委託されますが、その10倍の年間4億トン排出される産業廃棄物は100%民間で運営されており、民間企業が環境省などに適正に行政報告することで成り立っている業界です。廃棄物業界全体を救いたいと考えた場合、民間企業である私たちが入りやすいこと、そして廃棄物の量が多いという社会的なインパクトを考えて私たちは事業を展開しています。
Q: AIはどういうステージで働くのですか。
A: AIが働くポイントは結構たくさんあります。代表的なところでご説明すると、産廃事業者の配車のフローは、車庫で車と人をマッチングし、ごみの排出場で排出品目によって行先の処理場が変わるという流れです。例えば、ドライバーが60名、免許の種類が3種類、乗せるコンテナが8種類、車の種類が8種類、1日300か所に持って行き、その作業スペースが5種類、場所によっては10カ所くらい中間施設が変わる。この毎日変わるパターンの組み合わせを職人さんが一日中時間を使って考えているような業務を、AIはボタンをぽちっと押すだけで回答をすぐ出してくれるという点が一番大きなAIの使いどころになります。
卓話「幼少期の多様性教育について」
株式会社Mimmy 代表取締役CEO 関根謙太さま
2023年2月9日

 株式会社Mimmyの関根と申します。自己紹介も兼ねてお話させていただければと思っております。
私は、子供たちに毎日Zoomをつないで世界中を見せて、子供たちの興味を世界に広げていくという事業を行っています。今日のテーマは「幼少期の多様性教育について」です。幼い頃に世界を知り、色んなことを学ぶことが非常に大事だと考え、2019年に創業して以来、このサービスを展開しています。
私自身は大学卒業後に旭化成ホームズに入社し、住宅営業からスタートし、海外事業に携わり、主にM&Aの事業などをやっておりました。私自身は生まれも育ちも日本です。海外で事業をやることになったとき、言葉の壁はなんとかなりましたが、倫理観や宗教観などの相手の心の奥の部分で文化の違いを感じることが多くありました。こうした多様性は幼いころから培っていくこと、小さいころから世界を知ることが大事だと考えて今の事業をスタートしました。
会社のミッションは、「“こどものせかい”を地球規模にひろげる」ということです。コンシューマー向けのビジネスですが、メインの顧客は未就学生の5、6歳から7歳、8歳、9歳くらいまでの子供たちで、彼らを対象としたMimmyアドベンチャーというサービスを提供しています。これは世界とつながる双方向コミュニケーションとして、Zoomを使って、夕方5時から8時に15分刻みで世界各地とつないで、子供たちが外国の方たちとコミュニケーションをとる機会を作っています。今、子供には世界に羽ばたいていってもらいたいという親御さんが多く、昨年11月で累計参加者数が10万人を突破しました。
このサービスの特徴は、10分という短い時間、Zoomで世界各地とつないで双方向のコミュニケーションを子どもたちに提供している点です。例えば、子供たちが興味を持つ虫であれば、マレーシアにいる世界的に有名な虫のブリーダーとつないで、子供たちの世界を広げるといったことをしています。
実際のコンテンツの一部を皆様と共有させていただきます。森林や熱帯雨林の減少という問題については、インドネシアの方とZoomでつないで、食品用の油を作るためのパームツリーを取り上げて、子供たちに現状を知ってもらっています。皆さんご存知のボルネオ島は世界で一番生物多様性が豊かな場所だと言われていましたが、今、熱帯雨林の減少が顕著に表れている場所でもあります。パームツリーを栽培するために、森林を破壊して人工的に道を作っています。パームツリーはマネーツリーとも呼ばれるほど儲かるので、農園拡大の投資が進み森林破壊が止まらないという現象が起こっています。私たちはパームツリーの実そのものを見る機会は少ないでしょうが、普段食べるポテトチップスやチョコレートに含まれているという話を紹介してもらうと、日本の子供たちにとっても身近にある自分事として捉えることができ、非常に大きな経験知となっています。
森林伐採によって実際に起こっているのは、植物の栽培に化学物質を使うため土壌は元に戻すことが出来なくなり、森林が復活できないほど地球環境が壊されているという問題です。1950年以降、地球の森林は50%減少しています。こうした問題は日経新聞などでも報じられているはずですが、なかなか自分事として捉えられない問題だと思います。世界で何が起こっているかといった問題を、子供たちに小さいころから知らせておくのは非常に大事だと考えており、毎日ライブで子供たちに知ってもらえる環境設定をしています。
我々のメインのターゲットは、アルファー世代と呼ばれる小学校や中学校に上がる前の世代の子供たちです。この世代の子供たちに向けてコンテンツを提供していますが、もう一つ、ミレニアル世代と呼ばれる、37歳の私と同じかその前後の世代の方々、これからの社会をけん引していく方々の教育にも役立つサービスを提供しています。
世界中で様々な価値観を持つ人たちがいる中で、多様な価値観を持つ人たちのことを子供の時に知っておくのは非常に大事なことだと思っております。子供のうちにすべて学べることではありませんが、将来大人になった時に、世界中の人たちと円滑にコミュニケーションが取れるようにしていくことを目指しております。
ありがとうございました。
Q&A
Q: 世界の人たちが動画に登場する時、言葉は翻訳されるのでしょうか。
A: 基本的には英語です。Mimmyちゃんというパペット人形が部分的に通訳して、子供たちに分かるようにしています。
Q: 普段目にするのとは違う世界地図を見た気がしますが、意図されてのことですか。
A: 意図していません。普段子供たちには、日本が真ん中にある世界地図を使って、今日はこの国に行ってみようと案内しています。
Q: 世界とつながるときは、基本的に生放送ですか。
A: 基本的に全部生放送です。生放送であれば、子供たちが参加できます。それが大事だと思ってサービスを展開しています。
Q: 子供が質問することはありますか。
A: 驚かれるかもしれませんが、ほぼ全員が質問します。KPIとしてユーザー挙手率を取っているのですが、常に7割を超えるユーザー挙手率が我々の設定しているKPIです。それなりに意識が高い子供が多いのは確かですが、心理的な安全性が担保されると、子供たちは自分から積極的に参加するようになります。
Q: 親は関与しなくてよいのですか。子供だけで良いのですか。
A: 基本的には子供だけでできます。iPadとかですと子供たちは画面をタッチするだけで操作できるので、皆さん自分で操作しています。たまに3歳、4歳くらいのお子さんがいると、親が横にいて一緒に相談しているような感じです。親御さんには映らないようにと案内しています。たまに、質問したくなる親御さんがいますが、メッセージでご遠慮くださいというようなやり取りをしています。
Q: 以前インドネシアに住んでいたことがありお話に親近感を覚えましたが、環境汚染に焦点を当てたプログラムはあるのでしょうか。
A: インドネシア現地の子供が環境汚染をどの程度知っているかというと、先ほどのパームツリーの例でいえば、あの農園栽培のエリアでは平均寿命が短いというエビデンスがあり、子供たちは皆知っています。身体に悪いと分かりつつ働いているというのが現状です。Mimmyアドベンチャーというサービスでは、サステナビリティの観点で企業から発信してもらう取り組みをスタートしています。今年の4月からは各業界を代表する企業に入っていただき、金融リテラシーの向上や、地球環境やCO2削減への取り組みといったコンテンツを開始するところです。
株式会社Mimmyの関根と申します。自己紹介も兼ねてお話させていただければと思っております。
私は、子供たちに毎日Zoomをつないで世界中を見せて、子供たちの興味を世界に広げていくという事業を行っています。今日のテーマは「幼少期の多様性教育について」です。幼い頃に世界を知り、色んなことを学ぶことが非常に大事だと考え、2019年に創業して以来、このサービスを展開しています。
私自身は大学卒業後に旭化成ホームズに入社し、住宅営業からスタートし、海外事業に携わり、主にM&Aの事業などをやっておりました。私自身は生まれも育ちも日本です。海外で事業をやることになったとき、言葉の壁はなんとかなりましたが、倫理観や宗教観などの相手の心の奥の部分で文化の違いを感じることが多くありました。こうした多様性は幼いころから培っていくこと、小さいころから世界を知ることが大事だと考えて今の事業をスタートしました。
会社のミッションは、「“こどものせかい”を地球規模にひろげる」ということです。コンシューマー向けのビジネスですが、メインの顧客は未就学生の5、6歳から7歳、8歳、9歳くらいまでの子供たちで、彼らを対象としたMimmyアドベンチャーというサービスを提供しています。これは世界とつながる双方向コミュニケーションとして、Zoomを使って、夕方5時から8時に15分刻みで世界各地とつないで、子供たちが外国の方たちとコミュニケーションをとる機会を作っています。今、子供には世界に羽ばたいていってもらいたいという親御さんが多く、昨年11月で累計参加者数が10万人を突破しました。
このサービスの特徴は、10分という短い時間、Zoomで世界各地とつないで双方向のコミュニケーションを子どもたちに提供している点です。例えば、子供たちが興味を持つ虫であれば、マレーシアにいる世界的に有名な虫のブリーダーとつないで、子供たちの世界を広げるといったことをしています。
実際のコンテンツの一部を皆様と共有させていただきます。森林や熱帯雨林の減少という問題については、インドネシアの方とZoomでつないで、食品用の油を作るためのパームツリーを取り上げて、子供たちに現状を知ってもらっています。皆さんご存知のボルネオ島は世界で一番生物多様性が豊かな場所だと言われていましたが、今、熱帯雨林の減少が顕著に表れている場所でもあります。パームツリーを栽培するために、森林を破壊して人工的に道を作っています。パームツリーはマネーツリーとも呼ばれるほど儲かるので、農園拡大の投資が進み森林破壊が止まらないという現象が起こっています。私たちはパームツリーの実そのものを見る機会は少ないでしょうが、普段食べるポテトチップスやチョコレートに含まれているという話を紹介してもらうと、日本の子供たちにとっても身近にある自分事として捉えることができ、非常に大きな経験知となっています。
森林伐採によって実際に起こっているのは、植物の栽培に化学物質を使うため土壌は元に戻すことが出来なくなり、森林が復活できないほど地球環境が壊されているという問題です。1950年以降、地球の森林は50%減少しています。こうした問題は日経新聞などでも報じられているはずですが、なかなか自分事として捉えられない問題だと思います。世界で何が起こっているかといった問題を、子供たちに小さいころから知らせておくのは非常に大事だと考えており、毎日ライブで子供たちに知ってもらえる環境設定をしています。
我々のメインのターゲットは、アルファー世代と呼ばれる小学校や中学校に上がる前の世代の子供たちです。この世代の子供たちに向けてコンテンツを提供していますが、もう一つ、ミレニアル世代と呼ばれる、37歳の私と同じかその前後の世代の方々、これからの社会をけん引していく方々の教育にも役立つサービスを提供しています。
世界中で様々な価値観を持つ人たちがいる中で、多様な価値観を持つ人たちのことを子供の時に知っておくのは非常に大事なことだと思っております。子供のうちにすべて学べることではありませんが、将来大人になった時に、世界中の人たちと円滑にコミュニケーションが取れるようにしていくことを目指しております。
ありがとうございました。
Q&A
Q: 世界の人たちが動画に登場する時、言葉は翻訳されるのでしょうか。
A: 基本的には英語です。Mimmyちゃんというパペット人形が部分的に通訳して、子供たちに分かるようにしています。
Q: 普段目にするのとは違う世界地図を見た気がしますが、意図されてのことですか。
A: 意図していません。普段子供たちには、日本が真ん中にある世界地図を使って、今日はこの国に行ってみようと案内しています。
Q: 世界とつながるときは、基本的に生放送ですか。
A: 基本的に全部生放送です。生放送であれば、子供たちが参加できます。それが大事だと思ってサービスを展開しています。
Q: 子供が質問することはありますか。
A: 驚かれるかもしれませんが、ほぼ全員が質問します。KPIとしてユーザー挙手率を取っているのですが、常に7割を超えるユーザー挙手率が我々の設定しているKPIです。それなりに意識が高い子供が多いのは確かですが、心理的な安全性が担保されると、子供たちは自分から積極的に参加するようになります。
Q: 親は関与しなくてよいのですか。子供だけで良いのですか。
A: 基本的には子供だけでできます。iPadとかですと子供たちは画面をタッチするだけで操作できるので、皆さん自分で操作しています。たまに3歳、4歳くらいのお子さんがいると、親が横にいて一緒に相談しているような感じです。親御さんには映らないようにと案内しています。たまに、質問したくなる親御さんがいますが、メッセージでご遠慮くださいというようなやり取りをしています。
Q: 以前インドネシアに住んでいたことがありお話に親近感を覚えましたが、環境汚染に焦点を当てたプログラムはあるのでしょうか。
A: インドネシア現地の子供が環境汚染をどの程度知っているかというと、先ほどのパームツリーの例でいえば、あの農園栽培のエリアでは平均寿命が短いというエビデンスがあり、子供たちは皆知っています。身体に悪いと分かりつつ働いているというのが現状です。Mimmyアドベンチャーというサービスでは、サステナビリティの観点で企業から発信してもらう取り組みをスタートしています。今年の4月からは各業界を代表する企業に入っていただき、金融リテラシーの向上や、地球環境やCO2削減への取り組みといったコンテンツを開始するところです。
【Zoom】卓話「シリコンバレーから見る日本の医療」
スタンフォード大学 主任研究員 池野文昭さま
2023年2月2日

 ご紹介ありがとうございます。今日は「シリコンバレーから見る日本の医療」についてお話させていただきます。
この2年から3年、世界中がコロナで苦しんでいます。軍事だけでなく、医療も国家安全保障の重要な柱であることが一般的に認識されるようになりました。医療や介護、健康増進も含めたヘルスケアサービスの市場規模は今後大きくなっていきます。日本では、就労者数でみると医療福祉関係が2030年には最大の産業になります。
日本は、面積は小さな国ですが、世界192カ国中第11位という人口が非常に多い国です。そして、65歳以上が全人口に占める高齢化率が非常に高い国です。将来もっと高齢者が増えて2060年には40%近い高齢化率になると言われています。他の国々でも同様に高齢化は進行しています。日本は65歳以上の人口が世界第4位です。65歳以上の高齢者は病気になりやすく、がんの罹患率は一気に上がり、心臓病、脳血管障害、肺炎も同様です。年を取ると病気になるのは仕方ないのですが、何とかしなければいけません。
経済の視点でみると、高齢化によって成長率は右肩下がりになります。企業の平均年齢はどんどん上がり、年功序列でいけば給料も上がるということになります。どうすれば良いかを考えると、超高齢化社会の日本においては、ヘルステックによる予防医療と医療機器、医薬品、バイオで経済を成長させ、日本国民の身体的、精神的、経済的、社会的な健康を確立するために、私の専門である医療関係のビジネスで付加価値の高いイノベーションを起こすことができないかと考えています。自動車のようなコンシューマープロダクトは高齢化が進む日本では売り上げがどんどん伸びることは期待できませんが、医療関係のビジネスは伸びると予想されます。但し、付加価値の高いイノベーションを起こさなければなりません。
私自身は静岡県のへき地で地域医療に従事していましたが、2001年4月にアメリカに行き色々と驚きました。例えば、カリフォルニア州のGDPは世界第5位、州民一人当たりのGDPは日本の約2倍です。なぜ、カリフォルニア州がそれほど強いのか。その理由はスタートアップです。私が在籍しているスタンフォード大学はシリコンバレーの真ん中にあるのですが、スタートアップで有名になりました。1939年果樹園の畑の中にポツンとある三流大学であったスタンフォード大学の工学部長フレッド・ターマンが優秀な学生二人を見つけて、東海岸で就職せずにこの地で新しい会社を作れと言って出来たのがヒューレット・パッカード社でした。その後さまざまな人が新たな会社を起業したりサプライヤーが集まったりして、今のシリコンバレーになりました。シリコンバレーの一番の特徴は、アントレプレナー精神というマインドセットだと思います。
シリコンバレー以外でも、例えばアイルランドは国民一人当たりのGDPが世界第1位です。その理由の一つは、1980年代半ばから医療機器に産業をシフトさせたことです。工場誘致から始まり、農業やその他の産業に従事していた人が医療機器の工場に勤めるようになってある程度豊かになり、子供の教育にお金を使うようになり、優秀な大学で学力をつけた子供が新たな医療機器のスタートアップを作るようになりました。このように40年かかりましたが、高い教育を受けた若い人たちが挑戦するという仕組みでGDP世界第1位になったのです。
2007年に登場したiPhoneは評論家や専門家の前評判では売れない、特に日本では売れないと批判されていました。しかし実際には、日本でも発売日には長蛇の列ができました。この人たちは評論家の言うことを聞かない馬鹿者だと言われましたが、馬鹿者ではなく実は若者だったのです。私の郷里静岡出身の本田宗一郎は、今起きていることを、年寄りは過去の経験知識が邪魔して正面から受け取れないと言っています。終戦直後にソニーやホンダといった今の日本の大企業を当時起業した人たちは比較的若い人たちが多かったと言われています。
昨年岸田内閣もスタートアップ元年と位置付けていますが、スタートアップをやるのは人です。特に比較的若い人たちが斬新な考え方でチャレンジをしていきます。スタンフォード大学でも起業家精神育成講座がありますが、教育機関ですので商品を作るのではなく、イノベーティブな商品を作れるような優秀な人間を育てることに重きを置いています。教育はすぐに結果が出るわけではありません。計算すると損をしているコストセンターだと評価される可能性がありますが、人材育成を怠った国は過去の歴史を見ると全て滅びています。その意味で、我々日本人も、将来の日本を作っていけるリーダーシップのある人、イノベーションを起こせる人を育てることに軸足を置くのが長期的には非常に重要だと思っています。
日本はサッカーワールドカップの常連国になりましたが、1968年メキシコオリンピックで第3位になり、そこから「キャプテン翼」という漫画が登場し、それを読んだ少年、例えば三浦知良が15歳で単身ブラジルに行き、その後ドーハの悲劇や、ヨーロッパに行って挑戦する選手たちがいて、やっとワールドカップの常連になりました。ここまで来るのにやはり40年。50年とかかっているわけです。一朝一夕では世の中は変わりませんが、少なくとも人に対する投資は行わなければいけないと思います。私は医療が専門ですが同時に教育者でもありますので、人を作ることが将来の日本にとって非常に重要だと思っています。患者様のために、いつの時代もすべての中心は人であり、そして患者さんがいることを忘れずに行動していきたいと思っております。ご清聴ありがとうございました。
Q&A
Q: 以前安倍総理が5年で200社のスタートアップをシリコンバレーに送りこむと発表し、昨年萩生田経産大臣がバイオデザインを訪問して5年で1000人の起業家を派遣すると言いました。先生はどのような印象を受けられたでしょうか。
A: シリコンバレーに若い人を送ることに対して、アメリカかぶれの碌な人間ができないとか、たかだか1,2週間で人間が変わるわけない、税金の無駄遣いだと批判する人が多いです。私自身は少しアメリカに行っただけで人生が変わった人間です。実際に2015年から始まったジャパンバイオデザインも今8期生が来ていますが、1,2週間来るだけでもマインドセットは変わります。安倍総理の「始動」というプログラムでかれこれ数百名シリコンバレーに来ています。彼らを観察するとやはり皆チャレンジをしています。彼らは経験を積めば次世代の人を教育するかもしれないし、周りの人に良い刺激を与えるかもしれません。そういう意味で若い人に対して機会を与えることは無駄ではないと思うので、一朝一夕に結果は出なくても、人に対する投資は絶対に惜しんではいけないと思います。
Q: 先程の本田宗一郎さんの話は、うるさい上の衆がいないから楽に仕事が出来たという話ですが、アメリカにはうるさい年寄りはいないのでしょうか。いる場合はそれを克服できる文化はあるのでしょうか。
A: シリコンバレーにもうるさい年寄りはいっぱいいます。但し、うるささの種類が違います。彼らは若い時に成功したにせよ失敗したにせよ、少なくとも挑戦した人たちです。シリコンバレーは若い人だけでスタートアップが立ち上がり成功しているわけではありません。重要なのは、その挑戦者である若い人たちがイノベーションを起こせるように支えるメンターの存在です。メンターの共通点は若い時に挑戦していることです。彼らが若い人にイノベーションを起こせるようにしています。日本でなぜできないかというと、日本ではメンターのレベルで、スタートアップに挑戦した人がいないからだと思います。
Q: アメリカの男女差別の実情について教えてください。
A: 日本と比べるとアメリカの男女差別は10分の1以下だと思います。但し、シリコンバレーは男性が比較的マジョリティを占めていますが、やる気のある女性ならアメリカに来た方が生活しやすいかもしれません。
Q: 若者にとって憧れの場所シリコンバレーで挑戦できるルートにはどのようなものがあるのでしょうか。
A: 一番の問題はビザです。若い人が取りやすいのは学生ビザですので、手っ取り早いのは大学に入ることです。それ以外では、優秀な人であればアメリカの企業に雇ってもらう。もう一つは日本の企業のシリコンバレー支社に駐在員として赴任し、人脈を作り、日本への帰国命令がでたら辞めてアメリカの企業に就職するという方法が考えられます。もう一つの裏技として、永住権のくじ引きに応募するという方法もあります。実は私はこのくじ引きに当たって永住権を獲得しました。
ご紹介ありがとうございます。今日は「シリコンバレーから見る日本の医療」についてお話させていただきます。
この2年から3年、世界中がコロナで苦しんでいます。軍事だけでなく、医療も国家安全保障の重要な柱であることが一般的に認識されるようになりました。医療や介護、健康増進も含めたヘルスケアサービスの市場規模は今後大きくなっていきます。日本では、就労者数でみると医療福祉関係が2030年には最大の産業になります。
日本は、面積は小さな国ですが、世界192カ国中第11位という人口が非常に多い国です。そして、65歳以上が全人口に占める高齢化率が非常に高い国です。将来もっと高齢者が増えて2060年には40%近い高齢化率になると言われています。他の国々でも同様に高齢化は進行しています。日本は65歳以上の人口が世界第4位です。65歳以上の高齢者は病気になりやすく、がんの罹患率は一気に上がり、心臓病、脳血管障害、肺炎も同様です。年を取ると病気になるのは仕方ないのですが、何とかしなければいけません。
経済の視点でみると、高齢化によって成長率は右肩下がりになります。企業の平均年齢はどんどん上がり、年功序列でいけば給料も上がるということになります。どうすれば良いかを考えると、超高齢化社会の日本においては、ヘルステックによる予防医療と医療機器、医薬品、バイオで経済を成長させ、日本国民の身体的、精神的、経済的、社会的な健康を確立するために、私の専門である医療関係のビジネスで付加価値の高いイノベーションを起こすことができないかと考えています。自動車のようなコンシューマープロダクトは高齢化が進む日本では売り上げがどんどん伸びることは期待できませんが、医療関係のビジネスは伸びると予想されます。但し、付加価値の高いイノベーションを起こさなければなりません。
私自身は静岡県のへき地で地域医療に従事していましたが、2001年4月にアメリカに行き色々と驚きました。例えば、カリフォルニア州のGDPは世界第5位、州民一人当たりのGDPは日本の約2倍です。なぜ、カリフォルニア州がそれほど強いのか。その理由はスタートアップです。私が在籍しているスタンフォード大学はシリコンバレーの真ん中にあるのですが、スタートアップで有名になりました。1939年果樹園の畑の中にポツンとある三流大学であったスタンフォード大学の工学部長フレッド・ターマンが優秀な学生二人を見つけて、東海岸で就職せずにこの地で新しい会社を作れと言って出来たのがヒューレット・パッカード社でした。その後さまざまな人が新たな会社を起業したりサプライヤーが集まったりして、今のシリコンバレーになりました。シリコンバレーの一番の特徴は、アントレプレナー精神というマインドセットだと思います。
シリコンバレー以外でも、例えばアイルランドは国民一人当たりのGDPが世界第1位です。その理由の一つは、1980年代半ばから医療機器に産業をシフトさせたことです。工場誘致から始まり、農業やその他の産業に従事していた人が医療機器の工場に勤めるようになってある程度豊かになり、子供の教育にお金を使うようになり、優秀な大学で学力をつけた子供が新たな医療機器のスタートアップを作るようになりました。このように40年かかりましたが、高い教育を受けた若い人たちが挑戦するという仕組みでGDP世界第1位になったのです。
2007年に登場したiPhoneは評論家や専門家の前評判では売れない、特に日本では売れないと批判されていました。しかし実際には、日本でも発売日には長蛇の列ができました。この人たちは評論家の言うことを聞かない馬鹿者だと言われましたが、馬鹿者ではなく実は若者だったのです。私の郷里静岡出身の本田宗一郎は、今起きていることを、年寄りは過去の経験知識が邪魔して正面から受け取れないと言っています。終戦直後にソニーやホンダといった今の日本の大企業を当時起業した人たちは比較的若い人たちが多かったと言われています。
昨年岸田内閣もスタートアップ元年と位置付けていますが、スタートアップをやるのは人です。特に比較的若い人たちが斬新な考え方でチャレンジをしていきます。スタンフォード大学でも起業家精神育成講座がありますが、教育機関ですので商品を作るのではなく、イノベーティブな商品を作れるような優秀な人間を育てることに重きを置いています。教育はすぐに結果が出るわけではありません。計算すると損をしているコストセンターだと評価される可能性がありますが、人材育成を怠った国は過去の歴史を見ると全て滅びています。その意味で、我々日本人も、将来の日本を作っていけるリーダーシップのある人、イノベーションを起こせる人を育てることに軸足を置くのが長期的には非常に重要だと思っています。
日本はサッカーワールドカップの常連国になりましたが、1968年メキシコオリンピックで第3位になり、そこから「キャプテン翼」という漫画が登場し、それを読んだ少年、例えば三浦知良が15歳で単身ブラジルに行き、その後ドーハの悲劇や、ヨーロッパに行って挑戦する選手たちがいて、やっとワールドカップの常連になりました。ここまで来るのにやはり40年。50年とかかっているわけです。一朝一夕では世の中は変わりませんが、少なくとも人に対する投資は行わなければいけないと思います。私は医療が専門ですが同時に教育者でもありますので、人を作ることが将来の日本にとって非常に重要だと思っています。患者様のために、いつの時代もすべての中心は人であり、そして患者さんがいることを忘れずに行動していきたいと思っております。ご清聴ありがとうございました。
Q&A
Q: 以前安倍総理が5年で200社のスタートアップをシリコンバレーに送りこむと発表し、昨年萩生田経産大臣がバイオデザインを訪問して5年で1000人の起業家を派遣すると言いました。先生はどのような印象を受けられたでしょうか。
A: シリコンバレーに若い人を送ることに対して、アメリカかぶれの碌な人間ができないとか、たかだか1,2週間で人間が変わるわけない、税金の無駄遣いだと批判する人が多いです。私自身は少しアメリカに行っただけで人生が変わった人間です。実際に2015年から始まったジャパンバイオデザインも今8期生が来ていますが、1,2週間来るだけでもマインドセットは変わります。安倍総理の「始動」というプログラムでかれこれ数百名シリコンバレーに来ています。彼らを観察するとやはり皆チャレンジをしています。彼らは経験を積めば次世代の人を教育するかもしれないし、周りの人に良い刺激を与えるかもしれません。そういう意味で若い人に対して機会を与えることは無駄ではないと思うので、一朝一夕に結果は出なくても、人に対する投資は絶対に惜しんではいけないと思います。
Q: 先程の本田宗一郎さんの話は、うるさい上の衆がいないから楽に仕事が出来たという話ですが、アメリカにはうるさい年寄りはいないのでしょうか。いる場合はそれを克服できる文化はあるのでしょうか。
A: シリコンバレーにもうるさい年寄りはいっぱいいます。但し、うるささの種類が違います。彼らは若い時に成功したにせよ失敗したにせよ、少なくとも挑戦した人たちです。シリコンバレーは若い人だけでスタートアップが立ち上がり成功しているわけではありません。重要なのは、その挑戦者である若い人たちがイノベーションを起こせるように支えるメンターの存在です。メンターの共通点は若い時に挑戦していることです。彼らが若い人にイノベーションを起こせるようにしています。日本でなぜできないかというと、日本ではメンターのレベルで、スタートアップに挑戦した人がいないからだと思います。
Q: アメリカの男女差別の実情について教えてください。
A: 日本と比べるとアメリカの男女差別は10分の1以下だと思います。但し、シリコンバレーは男性が比較的マジョリティを占めていますが、やる気のある女性ならアメリカに来た方が生活しやすいかもしれません。
Q: 若者にとって憧れの場所シリコンバレーで挑戦できるルートにはどのようなものがあるのでしょうか。
A: 一番の問題はビザです。若い人が取りやすいのは学生ビザですので、手っ取り早いのは大学に入ることです。それ以外では、優秀な人であればアメリカの企業に雇ってもらう。もう一つは日本の企業のシリコンバレー支社に駐在員として赴任し、人脈を作り、日本への帰国命令がでたら辞めてアメリカの企業に就職するという方法が考えられます。もう一つの裏技として、永住権のくじ引きに応募するという方法もあります。実は私はこのくじ引きに当たって永住権を獲得しました。
卓話「諦めていた旅行を叶える 医師の作る旅行会社」
トラベルドクター株式会社 代表取締役 医師 伊藤玲哉さま
同行者 石部竜大さま
2023年1月26日

 皆様こんにちは。トラベルドクター株式会社代表取締役、医師の伊藤玲哉と申します。
まず、自己紹介ですが、平成元年生まれの33歳です。昭和大学を卒業して京都で研修したときの体験が今の自分につながっています。私が医師を目指したのは、幼い頃喘息で何度も入院しこのまま死んでしまうのではないかと怖い思いをする中で、病気が自分らしく生きるのを制限すると考えるようになったからです。また、うちは代々地域医療を担う医師の家でした。喘息が起きて父に息が苦しいから助けてと訴えると、父は吸入器を準備してそっと私の口元に当てて、喘息が治まるまで寄り添ってくれました。そんな父を見て、人が辛い時に寄りそう父のような医師になりたいと思うようになりました。そして、私が5歳の時に母が亡くなり、人には必ず最期がある、永遠に生きられない、そういう命の重みや大切さを幼い頃に認識したことも理由の一つです。
これは、病室の天井の写真です。今日本で亡くなる年間140万人の内の75%の方は医療機関で最期を迎えています。この病院の天井は年間100万人の方が人生最後に見ている景色です。私たちや皆様の大切な方が75%の確率で見るかもしれない景色です。人生100年時代、医療の発達は目覚ましいものがありますが、人には必ず最期があります。今の医療で治せない病気の方に何ができるかを考えていた時に、一人の余命わずかな患者さんに「旅行に行きたい」と言われました。その願いを叶えたいと思って他のドクターや旅行会社、航空会社、宿などを走り回りました。しかし、何かあったら危ない、辞めておいた方が良いと言われて時間だけが過ぎ、結局その患者さんは病室の天井を見上げながら、悔しいと言って亡くなりました。この体験から、他の患者さんにも尋ねてみると、温泉に入りたい、家族旅行に行きたい、お墓参りに行きたい、故郷に帰りたい、娘の結婚式に参加したいなど、病院や自宅で出来ない体験、つまり旅行がしたいと思っていることがわかりました。そこで、今の医療機関や在宅医療では出来ない、新たな医療の形として、病気で諦めていた旅行を叶える旅行医、トラベルドクターになろうと思いました。
ただ、多くの方は病気で旅行を諦めています。病気で不安があり、旅行に行くためには誰かの助けが必要だという医療介護の問題、独居や老々介護、子供が有給休暇を取りづらく旅行の同行者がいないという問題、さらに、どこに相談すれば良いのかなどの情報がないという問題があります。そして一番大きな問題は、病気が進行する中で時間だけが過ぎていくという時間の壁です。
先程の「何かあったら危ない」という漠然とした不安感が旅行の最大の壁だと考え、旅行に行けるように一つずつ解決して、医療と旅行の隙間を埋めて旅行を叶える立場の旅行医になろうと思いました。最初の数年間はボランティアとして土日に活動していたのですが、上司からそれは自己満足ではないかと言われました。私が叶えられる旅行者の数は週に1人、年間50人。日本で1日に亡くなる方は4,000人です。やはり、仕組みを作らないと世の中は変わらないと思い、大学病院を辞めて、経営をしっかり学び、2年前にトラベルドクター株式会社を立ち上げました。まだ始まったばかりですが、各地からお問い合わせをいただくようになり、おひとりおひとりの願いを叶えています。今は全ての旅行に私が同行していますが、全国から相談をいただくので、全国にトラベルドクターのチームをたくさん作っていきたいと考えています。
自宅から出られない寝たきりの方でも移動できるように、ストレッチャーが乗れるようなリフトがついた旅行専用の福祉車両を買い、私がプロドライバーの二種免許を取って実際に運転して沢山の方々の旅行を叶えています。
実際のご旅行の話をさせていただきます。
末期がんで余命2週間と主治医から宣告を受けた70代の男性は、生まれ育った熱海の海を見たい、そしてもう一度温泉に入りたいと願いを持っておられました。この方は鼻に酸素の管をつけて、眉毛が少し下がって、眉間にしわが寄り、どことなく寂しそうな、私が医療現場で出会ってきた多くの方々と同じような表情をされていました。ところが、熱海に行くために家を出た瞬間に表情が変わりました。酸素の管をつけているものの病気があるようには見えません。それまでは食欲もなかったのに、駅弁をほぼ完食に近いくらい召しあがりました。熱海に着いて車いすでビーチに行くと、帰ってきたという表情でじっと海を見ていました。気づくとシャツのボタンを外して海に入る気満々になっているほど、病気のことを忘れて童心に帰っていました。温泉に浸かったときも本当に気持ち良さそうにされていました。酸素の管を外してしまい、本当なら苦しいはずなのに、全然苦しそうではありません。これは旅行の不思議な力で、旅行中は痛みや辛さが和らぐようです。私は旅行処方という表現を使うのですが、痛み止めや抗がん剤は患者本人にしか効かず数時間しか効きませんが、旅行は家族や他の医療者にも効き、世代を超えて何十年とこの旅行が家族に受け継がれていく、それが旅行の持つ処方という形だと思っています。
旅行に行きたいという言葉の奥には、今を生きたいという願いが込められています。私は医療現場で患者さんからずっと、死にたい、死にたいと言われていましたが、初めて患者さんに「いきたい」と言われたのが、この「旅行に行きたい」という言葉でした。文字は違いますが、患者さんの生きる方法を医療の力で支えることができればと思っています。
今はまだ、病気になったら旅行はできないというのが社会の認識ですが、5年後10年後には旅行に行くのが当たり前になることを本気で目指して、一歩一歩取り組んでいます。
Q&A
Q: 先生と患者との最初のつながりはどうやってできるのですか。
A: 半分以上は在宅診療をしている主治医が、患者さんから旅行に行きたいという言葉を聞いてつなげていただいています。ご家族や患者ご本人から直接相談に来られることもあります。
Q: 旅行に行って元気になられると思いますが、その後の余命は伸びるのでしょうか。また地域医療を担われていたお父さんの医院は今どうなっているのでしょうか。
A: 奥様に会いたいと願われた方は危篤状態でしたが、願いを叶えた2日後に亡くなりました。やはり治らない病気の方が多いので、すぐに亡くなる方も多いのですが、余命1週間で娘さんの結婚式を叶えた方はその後数ヶ月間、ご飯も食べるようになり箱根旅行にも行かれるほど元気になりました。
父には医院を継ぎませんと宣言しましたが、親孝行したいという気持ちもあり、父が元気な内にこの仕組みを作って、父の病院を継承できるようにしたいと思っています。
Q: 費用はいくらぐらいかかるのでしょうか。
A: 多くのコストがかかるのが今の課題です。先ほどの熱海の旅行を叶えるとすると2泊3日で大体100万円くらいです。それでも赤字に近いくらいです。一部の富裕層だけのサービスにしたくないという思いがあり、規模が大きくなり拠点が増えれば今の費用の半分くらいは削減できると思っています。
Q: 素晴らしい活動をもっと広げていくためにどうすればよいとお考えでしょうか。
A: 一番のネックは人です。重度の病気を抱えた方の医療を旅行中も守るためには医師の存在は欠かせません。今は、私しか旅行に同行できる医師がいないのが一番の問題になっています。将来的にはオンラインで医師が見守る遠隔医療でサポートして旅行ができる仕組みを作りたいと思っています。
Q: 患者が旅行に行きたいと言っても医者は旅行はダメだということが多いようですが、是非患者の思いを叶えるようにしていただきたい。
A: 今旅行を叶える一番のネックは医師だと思います。医師が患者のことを思って旅行を辞めるように言ってしまい、そこで諦める方が多いです。医師を変えられるのは医師だと思うので、こういう旅行が叶えられると医師の背中を押してくれるような医療者を増やしていきたいと思っています。
皆様こんにちは。トラベルドクター株式会社代表取締役、医師の伊藤玲哉と申します。
まず、自己紹介ですが、平成元年生まれの33歳です。昭和大学を卒業して京都で研修したときの体験が今の自分につながっています。私が医師を目指したのは、幼い頃喘息で何度も入院しこのまま死んでしまうのではないかと怖い思いをする中で、病気が自分らしく生きるのを制限すると考えるようになったからです。また、うちは代々地域医療を担う医師の家でした。喘息が起きて父に息が苦しいから助けてと訴えると、父は吸入器を準備してそっと私の口元に当てて、喘息が治まるまで寄り添ってくれました。そんな父を見て、人が辛い時に寄りそう父のような医師になりたいと思うようになりました。そして、私が5歳の時に母が亡くなり、人には必ず最期がある、永遠に生きられない、そういう命の重みや大切さを幼い頃に認識したことも理由の一つです。
これは、病室の天井の写真です。今日本で亡くなる年間140万人の内の75%の方は医療機関で最期を迎えています。この病院の天井は年間100万人の方が人生最後に見ている景色です。私たちや皆様の大切な方が75%の確率で見るかもしれない景色です。人生100年時代、医療の発達は目覚ましいものがありますが、人には必ず最期があります。今の医療で治せない病気の方に何ができるかを考えていた時に、一人の余命わずかな患者さんに「旅行に行きたい」と言われました。その願いを叶えたいと思って他のドクターや旅行会社、航空会社、宿などを走り回りました。しかし、何かあったら危ない、辞めておいた方が良いと言われて時間だけが過ぎ、結局その患者さんは病室の天井を見上げながら、悔しいと言って亡くなりました。この体験から、他の患者さんにも尋ねてみると、温泉に入りたい、家族旅行に行きたい、お墓参りに行きたい、故郷に帰りたい、娘の結婚式に参加したいなど、病院や自宅で出来ない体験、つまり旅行がしたいと思っていることがわかりました。そこで、今の医療機関や在宅医療では出来ない、新たな医療の形として、病気で諦めていた旅行を叶える旅行医、トラベルドクターになろうと思いました。
ただ、多くの方は病気で旅行を諦めています。病気で不安があり、旅行に行くためには誰かの助けが必要だという医療介護の問題、独居や老々介護、子供が有給休暇を取りづらく旅行の同行者がいないという問題、さらに、どこに相談すれば良いのかなどの情報がないという問題があります。そして一番大きな問題は、病気が進行する中で時間だけが過ぎていくという時間の壁です。
先程の「何かあったら危ない」という漠然とした不安感が旅行の最大の壁だと考え、旅行に行けるように一つずつ解決して、医療と旅行の隙間を埋めて旅行を叶える立場の旅行医になろうと思いました。最初の数年間はボランティアとして土日に活動していたのですが、上司からそれは自己満足ではないかと言われました。私が叶えられる旅行者の数は週に1人、年間50人。日本で1日に亡くなる方は4,000人です。やはり、仕組みを作らないと世の中は変わらないと思い、大学病院を辞めて、経営をしっかり学び、2年前にトラベルドクター株式会社を立ち上げました。まだ始まったばかりですが、各地からお問い合わせをいただくようになり、おひとりおひとりの願いを叶えています。今は全ての旅行に私が同行していますが、全国から相談をいただくので、全国にトラベルドクターのチームをたくさん作っていきたいと考えています。
自宅から出られない寝たきりの方でも移動できるように、ストレッチャーが乗れるようなリフトがついた旅行専用の福祉車両を買い、私がプロドライバーの二種免許を取って実際に運転して沢山の方々の旅行を叶えています。
実際のご旅行の話をさせていただきます。
末期がんで余命2週間と主治医から宣告を受けた70代の男性は、生まれ育った熱海の海を見たい、そしてもう一度温泉に入りたいと願いを持っておられました。この方は鼻に酸素の管をつけて、眉毛が少し下がって、眉間にしわが寄り、どことなく寂しそうな、私が医療現場で出会ってきた多くの方々と同じような表情をされていました。ところが、熱海に行くために家を出た瞬間に表情が変わりました。酸素の管をつけているものの病気があるようには見えません。それまでは食欲もなかったのに、駅弁をほぼ完食に近いくらい召しあがりました。熱海に着いて車いすでビーチに行くと、帰ってきたという表情でじっと海を見ていました。気づくとシャツのボタンを外して海に入る気満々になっているほど、病気のことを忘れて童心に帰っていました。温泉に浸かったときも本当に気持ち良さそうにされていました。酸素の管を外してしまい、本当なら苦しいはずなのに、全然苦しそうではありません。これは旅行の不思議な力で、旅行中は痛みや辛さが和らぐようです。私は旅行処方という表現を使うのですが、痛み止めや抗がん剤は患者本人にしか効かず数時間しか効きませんが、旅行は家族や他の医療者にも効き、世代を超えて何十年とこの旅行が家族に受け継がれていく、それが旅行の持つ処方という形だと思っています。
旅行に行きたいという言葉の奥には、今を生きたいという願いが込められています。私は医療現場で患者さんからずっと、死にたい、死にたいと言われていましたが、初めて患者さんに「いきたい」と言われたのが、この「旅行に行きたい」という言葉でした。文字は違いますが、患者さんの生きる方法を医療の力で支えることができればと思っています。
今はまだ、病気になったら旅行はできないというのが社会の認識ですが、5年後10年後には旅行に行くのが当たり前になることを本気で目指して、一歩一歩取り組んでいます。
Q&A
Q: 先生と患者との最初のつながりはどうやってできるのですか。
A: 半分以上は在宅診療をしている主治医が、患者さんから旅行に行きたいという言葉を聞いてつなげていただいています。ご家族や患者ご本人から直接相談に来られることもあります。
Q: 旅行に行って元気になられると思いますが、その後の余命は伸びるのでしょうか。また地域医療を担われていたお父さんの医院は今どうなっているのでしょうか。
A: 奥様に会いたいと願われた方は危篤状態でしたが、願いを叶えた2日後に亡くなりました。やはり治らない病気の方が多いので、すぐに亡くなる方も多いのですが、余命1週間で娘さんの結婚式を叶えた方はその後数ヶ月間、ご飯も食べるようになり箱根旅行にも行かれるほど元気になりました。
父には医院を継ぎませんと宣言しましたが、親孝行したいという気持ちもあり、父が元気な内にこの仕組みを作って、父の病院を継承できるようにしたいと思っています。
Q: 費用はいくらぐらいかかるのでしょうか。
A: 多くのコストがかかるのが今の課題です。先ほどの熱海の旅行を叶えるとすると2泊3日で大体100万円くらいです。それでも赤字に近いくらいです。一部の富裕層だけのサービスにしたくないという思いがあり、規模が大きくなり拠点が増えれば今の費用の半分くらいは削減できると思っています。
Q: 素晴らしい活動をもっと広げていくためにどうすればよいとお考えでしょうか。
A: 一番のネックは人です。重度の病気を抱えた方の医療を旅行中も守るためには医師の存在は欠かせません。今は、私しか旅行に同行できる医師がいないのが一番の問題になっています。将来的にはオンラインで医師が見守る遠隔医療でサポートして旅行ができる仕組みを作りたいと思っています。
Q: 患者が旅行に行きたいと言っても医者は旅行はダメだということが多いようですが、是非患者の思いを叶えるようにしていただきたい。
A: 今旅行を叶える一番のネックは医師だと思います。医師が患者のことを思って旅行を辞めるように言ってしまい、そこで諦める方が多いです。医師を変えられるのは医師だと思うので、こういう旅行が叶えられると医師の背中を押してくれるような医療者を増やしていきたいと思っています。
卓話「コロナ禍で深刻化する日本の貧困~わたしたちにできることを考える~」
一般社団法人グラミン日本 理事長 百野公裕さま
SMBC日興証券株式会社 グローバル企画役員補佐
一般社団法人グラミン日本 理事 デービッド・シェーファーさま
2023年1月19日
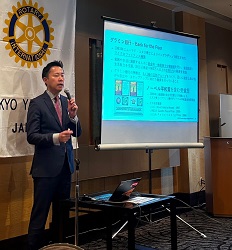
 グラミン日本の百野と申します。今日はお時間をいただき、このお題でお話させていただきます。
同じく、グラミン日本理事のデービッド・シェーファーと申します。本業はSMBC日興証券で働いており、2019年よりグラミン日本に参画してます。最後の方で企業とグラミンの連携についてご紹介させていただきます。
グラミン銀行は当時世界の最貧国であったバングラデシュでスタートしたマイクロファイナンス機関です。グラミン銀行はマイクロファイナンスで貧困層の女性の方々に融資して経済的自立を支援し貧困撲滅に寄与したことで、世界で初めて企業としてノーベル平和賞を受賞しました。現在、発展途上国だけでなく先進国を含め世界40カ国以上で貧困問題に取り組んでます。そして、マイクロファイナンスと共に、社会課題をビジネスの力で解決する、ソーシャルビジネスという考え方を提唱してます。社会起業家や社会課題解決という言葉がありますが、我々はビジネスとしてサステナブルな社会を実現するという考え方でソーシャルビジネスを進めています。
我々はマイクロファイナンスの金融機関ですが、残念ながら貧困問題はマイクロファイナンスだけでは解決できないので、様々な企業と連携しながらサービスを提供しています。例えば、ユニクロと組んでグラミン・ユニクロを設立したり、コロナのワクチンを世界中の方々に提供するために様々な団体と連携してます。
日本の貧困問題は「見えない貧困」と言われています。日本の相対的貧困を見ると2,000万人が年収122万円以下で生活しており、コロナ禍でその人数が更に増えていると言われてます。日本は先進国の中でも突出して地方の母子家庭や子供に貧困のしわ寄せが来ている状況です。グラミンでは女性の自立支援としてマイクロファイナンスで融資したり、デジタルスキルを習得し稼ぐ力を身に着けて頂くなどの取り組みをしています。コロナが始まった当初は、空港閉鎖の影響を受けた空港職員の方々が我々のところへ来られ、その後、飲食業、観光業、百貨店などの接客業の女性の方々が失職されて来られるようになりました。
国の施策も色々ありますがなかなか行き届いていません。日本のセーフティネットとしての最後の砦が生活保護ですが、日本で生活保護が必要な人に届いているかを示す捕捉率は18%で、82%の方々が必要な生活保護を受けずに困窮状態に置かれている状況です。財政的なインパクトを試算すると、生活保護を受ける一人に対してかかる財政コストは7,000万から1億1,000万円と言われています。そういった方々を100人サポートして、就労して納税するように変えると100億円の便益が生じるということになります。
グラミン日本としては、マイクロファイナンスとソーシャルビジネスの二つをベースに展開しています。ムハマド・ユヌス氏から強く言われたことが二つあります。一つは、政府やソーシャルセクターの力だけでは社会課題に対して限界があるので、企業の大きな力を社会課題に振り向けてほしいということです。我々は色々な企業との協働で社会課題に対する取り組みを行っています。二つ目は、若者にソーシャルビジネスの考え方を普及していってほしいということです。我々は今、複数の大学と組んで社会課題解決の授業を行っています。10代、20代の関心も非常に高く、ソーシャルビジネスの考え方が普及するように進めています。
今ご覧いただいたのは、生まれた環境で子どもたちのスタートラインが違うという子供の機会格差を示した海外の動画ですが、残念ながら日本でも同じような状況になっています。そこで、グラミン日本として行っていることをご紹介いたします。一つはSDGsの推進によって貧困をなくそうということです。具体的には3つあります。まず、マイクロファイナンス事業。金融サービスが届いていない人たちへの金融サービスです。次に、デジタル就労支援事業、これは生活困窮リスクのある地方のシングルマザーの方々がデジタルスキルを習得し、リモートで働けるようにする取り組みですが、複数の地方自治体と連携して進めています。そして、休眠預金事業、これは内閣府と連携しながら休眠預金を活用して、シングルマザーのデジタル就労支援を行おうというものです。
ロータリークラブの取り組みにTogethersというものがあると伺っていますが、グラミンでは「Fast alone, far together」と言うアフリカの諺をモットーにしています。それは、「早く行きたければ一人で行きなさい、遠くへ行きたければみんなと一緒に行きなさい」というものです。自治体や企業や金融機関など様々な方々と連携しながら進めております。最近では自動販売機にグラミンのラッピングをして、飲み物1本から社会貢献できる自動販売機の設置も進めています。
今、SMBCグループとの連携も行っておりますので、デービッドから最後にお話させていただきます。
プロボノ、聞きなれない言葉かと思いますが、元々はラテン語の公共善のためにという意味で、一般のボランティアと違うのは、自分のスキルや経験、本業での専門知識を使って社会貢献をすることです。様々な企業に支援をいただいておりますが、SMBC日興証券の事例を紹介いたします。
SMBC日興証券では、国内では珍しい業務時間の一部を使って社会貢献をするというプロボノワークを2020年からスタートしています。具体的には週1日を社会貢献に充てるというものです。当社では、経営戦略、人事戦略、サステナビリティ戦略の実現として、プロボノワークを位置付けています。様々なプロジェクトを通じてNPO団体の実行力を高めるという支援を行っています。参加している社員は、業務や社会人として培った経験やスキルをNPO団体の支援に活用し、その一方で社会課題への意識を高めたりリーダーシップを磨いたりしています。2020年3月に制度を導入、コロナによるロックダウンと重なり、最初は戸惑いましたが、オンラインで出来ることがわかり、今は完全にオンラインで全国から社員が参加しています。最初は業務時間の一部を使うことに不安を示す社員もいましたが、6ヶ月はあっという間に終わり、2期・3期と継続する社員もたくさん出ています。
グラミン日本には170名ぐらいのボランティアが参加していますが、プロボノという形で参加されている企業もたくさんあります。今日の皆さんとの出会いを是非、次に生かしたいと思っております。様々な業種業態で活躍されている経営者の皆様と一緒に、先ほどの貧困問題に取り組んでいくことができれば幸いでございます。ご清聴ありがとうございました。
グラミン日本の百野と申します。今日はお時間をいただき、このお題でお話させていただきます。
同じく、グラミン日本理事のデービッド・シェーファーと申します。本業はSMBC日興証券で働いており、2019年よりグラミン日本に参画してます。最後の方で企業とグラミンの連携についてご紹介させていただきます。
グラミン銀行は当時世界の最貧国であったバングラデシュでスタートしたマイクロファイナンス機関です。グラミン銀行はマイクロファイナンスで貧困層の女性の方々に融資して経済的自立を支援し貧困撲滅に寄与したことで、世界で初めて企業としてノーベル平和賞を受賞しました。現在、発展途上国だけでなく先進国を含め世界40カ国以上で貧困問題に取り組んでます。そして、マイクロファイナンスと共に、社会課題をビジネスの力で解決する、ソーシャルビジネスという考え方を提唱してます。社会起業家や社会課題解決という言葉がありますが、我々はビジネスとしてサステナブルな社会を実現するという考え方でソーシャルビジネスを進めています。
我々はマイクロファイナンスの金融機関ですが、残念ながら貧困問題はマイクロファイナンスだけでは解決できないので、様々な企業と連携しながらサービスを提供しています。例えば、ユニクロと組んでグラミン・ユニクロを設立したり、コロナのワクチンを世界中の方々に提供するために様々な団体と連携してます。
日本の貧困問題は「見えない貧困」と言われています。日本の相対的貧困を見ると2,000万人が年収122万円以下で生活しており、コロナ禍でその人数が更に増えていると言われてます。日本は先進国の中でも突出して地方の母子家庭や子供に貧困のしわ寄せが来ている状況です。グラミンでは女性の自立支援としてマイクロファイナンスで融資したり、デジタルスキルを習得し稼ぐ力を身に着けて頂くなどの取り組みをしています。コロナが始まった当初は、空港閉鎖の影響を受けた空港職員の方々が我々のところへ来られ、その後、飲食業、観光業、百貨店などの接客業の女性の方々が失職されて来られるようになりました。
国の施策も色々ありますがなかなか行き届いていません。日本のセーフティネットとしての最後の砦が生活保護ですが、日本で生活保護が必要な人に届いているかを示す捕捉率は18%で、82%の方々が必要な生活保護を受けずに困窮状態に置かれている状況です。財政的なインパクトを試算すると、生活保護を受ける一人に対してかかる財政コストは7,000万から1億1,000万円と言われています。そういった方々を100人サポートして、就労して納税するように変えると100億円の便益が生じるということになります。
グラミン日本としては、マイクロファイナンスとソーシャルビジネスの二つをベースに展開しています。ムハマド・ユヌス氏から強く言われたことが二つあります。一つは、政府やソーシャルセクターの力だけでは社会課題に対して限界があるので、企業の大きな力を社会課題に振り向けてほしいということです。我々は色々な企業との協働で社会課題に対する取り組みを行っています。二つ目は、若者にソーシャルビジネスの考え方を普及していってほしいということです。我々は今、複数の大学と組んで社会課題解決の授業を行っています。10代、20代の関心も非常に高く、ソーシャルビジネスの考え方が普及するように進めています。
今ご覧いただいたのは、生まれた環境で子どもたちのスタートラインが違うという子供の機会格差を示した海外の動画ですが、残念ながら日本でも同じような状況になっています。そこで、グラミン日本として行っていることをご紹介いたします。一つはSDGsの推進によって貧困をなくそうということです。具体的には3つあります。まず、マイクロファイナンス事業。金融サービスが届いていない人たちへの金融サービスです。次に、デジタル就労支援事業、これは生活困窮リスクのある地方のシングルマザーの方々がデジタルスキルを習得し、リモートで働けるようにする取り組みですが、複数の地方自治体と連携して進めています。そして、休眠預金事業、これは内閣府と連携しながら休眠預金を活用して、シングルマザーのデジタル就労支援を行おうというものです。
ロータリークラブの取り組みにTogethersというものがあると伺っていますが、グラミンでは「Fast alone, far together」と言うアフリカの諺をモットーにしています。それは、「早く行きたければ一人で行きなさい、遠くへ行きたければみんなと一緒に行きなさい」というものです。自治体や企業や金融機関など様々な方々と連携しながら進めております。最近では自動販売機にグラミンのラッピングをして、飲み物1本から社会貢献できる自動販売機の設置も進めています。
今、SMBCグループとの連携も行っておりますので、デービッドから最後にお話させていただきます。
プロボノ、聞きなれない言葉かと思いますが、元々はラテン語の公共善のためにという意味で、一般のボランティアと違うのは、自分のスキルや経験、本業での専門知識を使って社会貢献をすることです。様々な企業に支援をいただいておりますが、SMBC日興証券の事例を紹介いたします。
SMBC日興証券では、国内では珍しい業務時間の一部を使って社会貢献をするというプロボノワークを2020年からスタートしています。具体的には週1日を社会貢献に充てるというものです。当社では、経営戦略、人事戦略、サステナビリティ戦略の実現として、プロボノワークを位置付けています。様々なプロジェクトを通じてNPO団体の実行力を高めるという支援を行っています。参加している社員は、業務や社会人として培った経験やスキルをNPO団体の支援に活用し、その一方で社会課題への意識を高めたりリーダーシップを磨いたりしています。2020年3月に制度を導入、コロナによるロックダウンと重なり、最初は戸惑いましたが、オンラインで出来ることがわかり、今は完全にオンラインで全国から社員が参加しています。最初は業務時間の一部を使うことに不安を示す社員もいましたが、6ヶ月はあっという間に終わり、2期・3期と継続する社員もたくさん出ています。
グラミン日本には170名ぐらいのボランティアが参加していますが、プロボノという形で参加されている企業もたくさんあります。今日の皆さんとの出会いを是非、次に生かしたいと思っております。様々な業種業態で活躍されている経営者の皆様と一緒に、先ほどの貧困問題に取り組んでいくことができれば幸いでございます。ご清聴ありがとうございました。
卓話「勧進帳」
三味線家元 杵屋浅吉さま / 同行者 中西 如さま
2023年1月12日
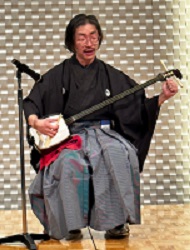
 【プロフィール】
四代目 杵屋浅吉さま 長唄三味線演奏家。江戸時代より続く杵屋佐吉派の当代家元七代目佐吉の長男。手ほどきは祖父・五世佐吉、父・七代目佐吉。長唄を杵屋佐登代、今藤尚之、三味線を故東音田島佳子、今藤長龍郎の各師に、ピアノを仲野真世、楽理を二橋潤一、トランペットを植木保彦、山本武雄の各師にそれぞれ師事。3歳での初舞台以来、代々伝わる伝統の上に多様なジャンルの経験を重ね合わせ、独自の奏法・音楽理論・指導法を展開。全国各地の演奏会、舞踊会、歌舞伎公演等に出演する一方、正しい江戸を現代に伝えるべく、古典にこだわりつつも即興から作詞作曲まで三味線一挺でこなし、弾き語りライブや他ジャンルとの共演、演劇作品への参加等幅広く活動中。
【プロフィール】
四代目 杵屋浅吉さま 長唄三味線演奏家。江戸時代より続く杵屋佐吉派の当代家元七代目佐吉の長男。手ほどきは祖父・五世佐吉、父・七代目佐吉。長唄を杵屋佐登代、今藤尚之、三味線を故東音田島佳子、今藤長龍郎の各師に、ピアノを仲野真世、楽理を二橋潤一、トランペットを植木保彦、山本武雄の各師にそれぞれ師事。3歳での初舞台以来、代々伝わる伝統の上に多様なジャンルの経験を重ね合わせ、独自の奏法・音楽理論・指導法を展開。全国各地の演奏会、舞踊会、歌舞伎公演等に出演する一方、正しい江戸を現代に伝えるべく、古典にこだわりつつも即興から作詞作曲まで三味線一挺でこなし、弾き語りライブや他ジャンルとの共演、演劇作品への参加等幅広く活動中。
卓話「ここ一番に勝つ秘訣」
プロゴルファー・医学修士 横田真一さま
2022年12月15日
 本日はお招きいただきましてありがとうございます。プロゴルファーの横田真一と申します。
僕がツアーで1勝目をあげたのは97年の25歳の時でしたが、2010年のキャノンオープンで13年振りに優勝しました。2006年にシード権を落としていたので、かなり力が落ちて選手寿命も終わっていたような時に、順天堂大学の小林先生に出会い、「自律神経をコントロールできたら、もう一回優勝できますよ」という一言から始まりました。この言葉を2010年に言われて、優勝争いのチャンスをものにした、その秘訣を皆さんにご紹介させていただきます。
小林先生は、『なぜ、「これ」は健康にいいのか?』をはじめとして自律神経コントロールに関する本を何冊も出されています。僕は、優勝した後に、自律神経をコントロールできるのはすごいと思い、順天堂大学大学院の医学研究科を受験して入り、4年間研究して医学修士を取りました。僕の修士論文は「プロゴルファーにおける自律神経活動とパフォーマンスの関係」というものです。ゴルフトーナメントの期間中にフィットネスカーに来てもらい、試合の朝、選手全員に2分半の自律神経の測定を行いました。皆さんご存知だと思いますが、自律神経には交感神経と副交感神経があります。交感神経は「闘争と逃走の神経」と言われています。例えば、ライオンに噛まれて、ライオンと闘うのか逃げるのかという時に交感神経が振り切った状態になります。そうすると身体中の血管が収縮して、顔面蒼白、頭は真っ白で、血流が非常に悪い状態になります。次に、副交感神経は上がると手足がポカポカしてきます。血流が上がったのかと思われるかもしれませんが、その逆で、指先の血管など末梢の血管が弛緩することで、心臓に集められた血液が流れ出てしまっている状態です。ホースでの水撒きをイメージすると、ホースが細すぎる時は交感神経優位で、太すぎる時が副交感神経優位な状態です。小林先生は、「健康もゴルフも、要は血流です。血が頭に回らなければ、パフォーマンスも出ないし健康にも悪いのです」とおっしゃいました。つまり、交感神経と副交感神経が調和した時に、血管のサイズが良い状態になるので、バランスが大切だということを教えてもらいました。
ランナーズハイのように、いわゆるゾーンに入った状態は、副交感神経も交感神経も高い状態です。副交感神経は自信と安心で上がります。副交感神経が高い自信満々の時は、ただリラックスしているという感じではありません。例えば、今日のような講演や、外科医が手術する時、大きなプレゼンテーションを行う時、どれだけ準備してきたかで自信満々になることができ、副交感神経の高さに直結します。そこに、行くぞという交感神経が上がった時が、いわゆるランナーズハイの状態で、最高のパフォーマンスが出るのです。
石川遼、松山英樹、横峯さくらといった超一流選手の共通点は、みんなどのような時でも副交感神経が高いということです。一流の選手は、日ごろからきちんと準備しているので自信満々ですから慌てません。ゆっくりと動きます。しかし、追いかけられている二流の選手は目が泳いだり、ソワソワと動いたりします。タイガーウッズがマスターズ優勝した日の朝の映像を見ると、ゆっくりとガムを噛みながらリラックスして歩いているのがわかります。今日頑張らなければならないという日の朝は、そのくらいのテンションでなければいけないのです。
僕は、優勝した2010年のキャノンオープンの日は、いかに交感神経を上げないかということを実行しました。自分にまったく期待せず、記者会見でも86打くらい打ちますと言って、笑いをとったら、気持ちがスーッと楽になりました。これだと思い、交感神経を上げないように、朝も高速道路を60キロでゆっくり走って戸塚カントリーまで行きました。家でリラックスして女房の手料理を食べたのも、良かった原因だと思います。
人は一日中怒っていることもできないし、一日中寝ていることもできません。興奮とリラックスは表裏一体です。例えば、伸びをするとぐーっと伸びて頑張るからリラックスでき、あくびも喉をはーっと緊張させてからリラックスしています。パフォーマンスを上げようと頑張り続ければ、交感神経が高い状態が続いて病気にもなりますし、続けられるわけでもありません。一日の中でのペース配分をどう持っていくかが大事です。何か目標があるならば、いかに自分の多忙なスケジュールや無駄をシンプルにそぎ落としていくかが大事です。着ていない服や使っていないものを捨てて、暇な時間を自分で作っていくことが、目標達成の一番の近道ではないかと思います。
頑張るためにはリラックスすることも大事です。眠いと思ったら10分でも良いので寝る。そうすると次の仕事がはかどります。そういう風に、自律神経をコントロールすれば、ここ一番というときに勝つ秘訣となるのではないかと思います。
私は今年シニアツアーにデビューして、シード権を獲得しています。これも小林先生のおかげだと思っています。皆さんにも僭越ながらおすそ分けして、少しでもお役に立てていただければとお話させていただきました。ご清聴いただき有難うございました。
Q&A
Q:私はゴルフ大好きなのですが、ドライバーイップスになってしまいました。スプーンやクリークは打てるのですが、ドライバーだけ打てません。どうすればよいでしょうか。
A:シニアツアーに出ると、往年のすごいプレイヤーばかりですが、皆さん、イップスを持っています。歳と共に、経験を重ねると共に、そういう症状は必ずやってきます。それをどうやって克服するかというと、全く違う動きを取り入れることだと思います。何か違う打ち方を編み出していただければ、よいのではないかと思います。
Q:今、女子プロのツアーの方が人気があり、男子プロのツアーは放送も少ないようですが、元会長として、今後男子プロをどのようにやっていけば良いとお考えですか。
A:僕も2005年、2006年と選手会長をやり、ツアーの理事もやっていたので、どうしたら良くなるかを死ぬほど考えました。日本のゴルフで一番欠けているのは、配信や放送、パブリシティーが一つにまとまっていない点です。アメリカのPGAツアーは一つにまとまっていて、ESPNなどが放映権を持って1年間放映しています。日本は戸張捷さんが作った仕組みで、スポンサーが仕切るため、テレビ局やBS、CS、インターネットと配信もばらけてしまっています。まとめてひとつで配信するというのが、やらなければならないテーマだと思っています。
でも、なぜ女子プロツアーの人気が男子に比べて高いかというと、満足度の問題だと思います。僕が女子ツアーの前夜祭に行った時に見た、財界やビジネス界の偉い方々の楽しそうな顔は、例え石川遼君がひざまずいてその方々にレッスンしても見られないと思います。それが答えでしょう。
本日はお招きいただきましてありがとうございます。プロゴルファーの横田真一と申します。
僕がツアーで1勝目をあげたのは97年の25歳の時でしたが、2010年のキャノンオープンで13年振りに優勝しました。2006年にシード権を落としていたので、かなり力が落ちて選手寿命も終わっていたような時に、順天堂大学の小林先生に出会い、「自律神経をコントロールできたら、もう一回優勝できますよ」という一言から始まりました。この言葉を2010年に言われて、優勝争いのチャンスをものにした、その秘訣を皆さんにご紹介させていただきます。
小林先生は、『なぜ、「これ」は健康にいいのか?』をはじめとして自律神経コントロールに関する本を何冊も出されています。僕は、優勝した後に、自律神経をコントロールできるのはすごいと思い、順天堂大学大学院の医学研究科を受験して入り、4年間研究して医学修士を取りました。僕の修士論文は「プロゴルファーにおける自律神経活動とパフォーマンスの関係」というものです。ゴルフトーナメントの期間中にフィットネスカーに来てもらい、試合の朝、選手全員に2分半の自律神経の測定を行いました。皆さんご存知だと思いますが、自律神経には交感神経と副交感神経があります。交感神経は「闘争と逃走の神経」と言われています。例えば、ライオンに噛まれて、ライオンと闘うのか逃げるのかという時に交感神経が振り切った状態になります。そうすると身体中の血管が収縮して、顔面蒼白、頭は真っ白で、血流が非常に悪い状態になります。次に、副交感神経は上がると手足がポカポカしてきます。血流が上がったのかと思われるかもしれませんが、その逆で、指先の血管など末梢の血管が弛緩することで、心臓に集められた血液が流れ出てしまっている状態です。ホースでの水撒きをイメージすると、ホースが細すぎる時は交感神経優位で、太すぎる時が副交感神経優位な状態です。小林先生は、「健康もゴルフも、要は血流です。血が頭に回らなければ、パフォーマンスも出ないし健康にも悪いのです」とおっしゃいました。つまり、交感神経と副交感神経が調和した時に、血管のサイズが良い状態になるので、バランスが大切だということを教えてもらいました。
ランナーズハイのように、いわゆるゾーンに入った状態は、副交感神経も交感神経も高い状態です。副交感神経は自信と安心で上がります。副交感神経が高い自信満々の時は、ただリラックスしているという感じではありません。例えば、今日のような講演や、外科医が手術する時、大きなプレゼンテーションを行う時、どれだけ準備してきたかで自信満々になることができ、副交感神経の高さに直結します。そこに、行くぞという交感神経が上がった時が、いわゆるランナーズハイの状態で、最高のパフォーマンスが出るのです。
石川遼、松山英樹、横峯さくらといった超一流選手の共通点は、みんなどのような時でも副交感神経が高いということです。一流の選手は、日ごろからきちんと準備しているので自信満々ですから慌てません。ゆっくりと動きます。しかし、追いかけられている二流の選手は目が泳いだり、ソワソワと動いたりします。タイガーウッズがマスターズ優勝した日の朝の映像を見ると、ゆっくりとガムを噛みながらリラックスして歩いているのがわかります。今日頑張らなければならないという日の朝は、そのくらいのテンションでなければいけないのです。
僕は、優勝した2010年のキャノンオープンの日は、いかに交感神経を上げないかということを実行しました。自分にまったく期待せず、記者会見でも86打くらい打ちますと言って、笑いをとったら、気持ちがスーッと楽になりました。これだと思い、交感神経を上げないように、朝も高速道路を60キロでゆっくり走って戸塚カントリーまで行きました。家でリラックスして女房の手料理を食べたのも、良かった原因だと思います。
人は一日中怒っていることもできないし、一日中寝ていることもできません。興奮とリラックスは表裏一体です。例えば、伸びをするとぐーっと伸びて頑張るからリラックスでき、あくびも喉をはーっと緊張させてからリラックスしています。パフォーマンスを上げようと頑張り続ければ、交感神経が高い状態が続いて病気にもなりますし、続けられるわけでもありません。一日の中でのペース配分をどう持っていくかが大事です。何か目標があるならば、いかに自分の多忙なスケジュールや無駄をシンプルにそぎ落としていくかが大事です。着ていない服や使っていないものを捨てて、暇な時間を自分で作っていくことが、目標達成の一番の近道ではないかと思います。
頑張るためにはリラックスすることも大事です。眠いと思ったら10分でも良いので寝る。そうすると次の仕事がはかどります。そういう風に、自律神経をコントロールすれば、ここ一番というときに勝つ秘訣となるのではないかと思います。
私は今年シニアツアーにデビューして、シード権を獲得しています。これも小林先生のおかげだと思っています。皆さんにも僭越ながらおすそ分けして、少しでもお役に立てていただければとお話させていただきました。ご清聴いただき有難うございました。
Q&A
Q:私はゴルフ大好きなのですが、ドライバーイップスになってしまいました。スプーンやクリークは打てるのですが、ドライバーだけ打てません。どうすればよいでしょうか。
A:シニアツアーに出ると、往年のすごいプレイヤーばかりですが、皆さん、イップスを持っています。歳と共に、経験を重ねると共に、そういう症状は必ずやってきます。それをどうやって克服するかというと、全く違う動きを取り入れることだと思います。何か違う打ち方を編み出していただければ、よいのではないかと思います。
Q:今、女子プロのツアーの方が人気があり、男子プロのツアーは放送も少ないようですが、元会長として、今後男子プロをどのようにやっていけば良いとお考えですか。
A:僕も2005年、2006年と選手会長をやり、ツアーの理事もやっていたので、どうしたら良くなるかを死ぬほど考えました。日本のゴルフで一番欠けているのは、配信や放送、パブリシティーが一つにまとまっていない点です。アメリカのPGAツアーは一つにまとまっていて、ESPNなどが放映権を持って1年間放映しています。日本は戸張捷さんが作った仕組みで、スポンサーが仕切るため、テレビ局やBS、CS、インターネットと配信もばらけてしまっています。まとめてひとつで配信するというのが、やらなければならないテーマだと思っています。
でも、なぜ女子プロツアーの人気が男子に比べて高いかというと、満足度の問題だと思います。僕が女子ツアーの前夜祭に行った時に見た、財界やビジネス界の偉い方々の楽しそうな顔は、例え石川遼君がひざまずいてその方々にレッスンしても見られないと思います。それが答えでしょう。
卓話「夢は果てしなく永遠に」
オリンピック体操競技 銀メダリスト 池谷幸雄さま
2022年11月24日

 皆さんこんにちは。池谷幸雄です。よろしくお願いいたします。
僕は、34年前、高校3年生18歳の時に、西川大輔君と二人で日本初の高校生の体操男子のオリンピック選手としてソウル五輪に出場し、大学4年生22歳の時にバルセロナ五輪に出場しました。その時に取ったメダルを今日お持ちしました。全部で4つのメダルですが、小さい方がソウル、大きい方がバルセロナです。皆様のお手元に回しますので、手に取ったり首にかけたりして重さを感じていただければと思います。
メダルの大きさがソウルとバルセロナでは全く違います。メダルはどんどん大きくなっています。昨年の東京オリンピックで、女子個人の床で初めて銅メダルを取った村上茉愛選手は、4歳から僕の体操クラブに入って18歳まで育てた教え子です。彼女が取ったメダルと僕のメダルを比べたら、ソウルのメダルの4倍の重さがあり、直径も今までのオリンピックの中で一番大きいそうです。
オリンピックのメダルにはたいてい横に刻印がしてあります。ソウルのメダルには男子団体の体操とわかるように、Gymnastic Men Team Compositionと刻印があります。ところがバルセロナのメダルはとても変わっていて、どこにも競技が書かれていません。そして、この銀メダルの中に埋め込んであるのは純銀です。金メダルの場合は純金が埋め込んであるんですね。大体のメダルはメッキで表面だけコーティングしてあるのですが、バルセロナのメダルは中が純粋な銀という珍しいものですので、是非ご覧になってください。
僕は4歳から体操を始めて本格にやるようになったのは小学校3年生からです。なぜ体操を始めたかというと、母が体操の良さを分かっていて僕を体操教室に入れたからです。母は体操教室で基礎を作った後は僕を野球選手にしたかったようです。僕自身は3歳で体操教室に入ったときは仮面ライダー1号になりたいと思っていました。仮面ライダーになりたいと思って始めた体操は、目立ちたがり屋の自分の性格にとても合っていました。バック転や宙返りが出来ること、個人競技なので僕個人が目立つ、人が出来ないことが出来ると、見ている人が驚いてくれる、喜んでくれるというのが嬉しかったのです。
体操では身体を柔らかくするための柔軟体操をしっかりやります。皆さんに身体が柔らかい人はいますかと聞くと、ほとんど手が挙がりません。何故かというと、身体は成長すると硬くなるのです。でも、ちゃんと柔軟体操、ストレッチをしていれば身体を柔らかいまま維持できます。そうすれば、今も柔らかくて手を挙げる人はいっぱいいるはずなのです。何故皆さんは柔軟体操をやらなかったのでしょうか。その理由は柔軟体操をすると痛いからです。痛いことはみんな避けてやらなくなるのです。僕はいつも予防接種と一緒だと言っています。注射は痛いけれど、身体に良いことが起こるから我慢しますよね。これと全く一緒です。柔軟体操で痛いのは効いている証拠です。そして、身体が柔らかいと血行が良くなり長生きできると科学的に証明されています。今日から自分の健康のために、お風呂上りの身体が温まった状態で、柔軟体操、ストレッチをやって下さい。身体が柔らかければ長生きにつながるし、どんなスポーツにもつながり上手くなります。身体が柔らかい方が怪我をしないから、たくさん練習ができて強くなるからです。
体操のもう一つ良い点は、身体のバランスが取れることです。バランスをとるために一番重要なのは体幹です。体幹とは胴体すべてのことです。この胴体、つまり胸もお腹も背中も肩甲骨まわりもしっかり鍛えることで、手足や身体がちゃんと動くのです。体幹の強さをお見せします。
皆さんこんにちは。池谷幸雄です。よろしくお願いいたします。
僕は、34年前、高校3年生18歳の時に、西川大輔君と二人で日本初の高校生の体操男子のオリンピック選手としてソウル五輪に出場し、大学4年生22歳の時にバルセロナ五輪に出場しました。その時に取ったメダルを今日お持ちしました。全部で4つのメダルですが、小さい方がソウル、大きい方がバルセロナです。皆様のお手元に回しますので、手に取ったり首にかけたりして重さを感じていただければと思います。
メダルの大きさがソウルとバルセロナでは全く違います。メダルはどんどん大きくなっています。昨年の東京オリンピックで、女子個人の床で初めて銅メダルを取った村上茉愛選手は、4歳から僕の体操クラブに入って18歳まで育てた教え子です。彼女が取ったメダルと僕のメダルを比べたら、ソウルのメダルの4倍の重さがあり、直径も今までのオリンピックの中で一番大きいそうです。
オリンピックのメダルにはたいてい横に刻印がしてあります。ソウルのメダルには男子団体の体操とわかるように、Gymnastic Men Team Compositionと刻印があります。ところがバルセロナのメダルはとても変わっていて、どこにも競技が書かれていません。そして、この銀メダルの中に埋め込んであるのは純銀です。金メダルの場合は純金が埋め込んであるんですね。大体のメダルはメッキで表面だけコーティングしてあるのですが、バルセロナのメダルは中が純粋な銀という珍しいものですので、是非ご覧になってください。
僕は4歳から体操を始めて本格にやるようになったのは小学校3年生からです。なぜ体操を始めたかというと、母が体操の良さを分かっていて僕を体操教室に入れたからです。母は体操教室で基礎を作った後は僕を野球選手にしたかったようです。僕自身は3歳で体操教室に入ったときは仮面ライダー1号になりたいと思っていました。仮面ライダーになりたいと思って始めた体操は、目立ちたがり屋の自分の性格にとても合っていました。バック転や宙返りが出来ること、個人競技なので僕個人が目立つ、人が出来ないことが出来ると、見ている人が驚いてくれる、喜んでくれるというのが嬉しかったのです。
体操では身体を柔らかくするための柔軟体操をしっかりやります。皆さんに身体が柔らかい人はいますかと聞くと、ほとんど手が挙がりません。何故かというと、身体は成長すると硬くなるのです。でも、ちゃんと柔軟体操、ストレッチをしていれば身体を柔らかいまま維持できます。そうすれば、今も柔らかくて手を挙げる人はいっぱいいるはずなのです。何故皆さんは柔軟体操をやらなかったのでしょうか。その理由は柔軟体操をすると痛いからです。痛いことはみんな避けてやらなくなるのです。僕はいつも予防接種と一緒だと言っています。注射は痛いけれど、身体に良いことが起こるから我慢しますよね。これと全く一緒です。柔軟体操で痛いのは効いている証拠です。そして、身体が柔らかいと血行が良くなり長生きできると科学的に証明されています。今日から自分の健康のために、お風呂上りの身体が温まった状態で、柔軟体操、ストレッチをやって下さい。身体が柔らかければ長生きにつながるし、どんなスポーツにもつながり上手くなります。身体が柔らかい方が怪我をしないから、たくさん練習ができて強くなるからです。
体操のもう一つ良い点は、身体のバランスが取れることです。バランスをとるために一番重要なのは体幹です。体幹とは胴体すべてのことです。この胴体、つまり胸もお腹も背中も肩甲骨まわりもしっかり鍛えることで、手足や身体がちゃんと動くのです。体幹の強さをお見せします。
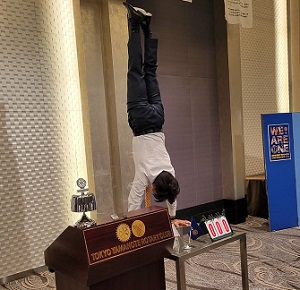
 皆さんは健康にとても注意していると思いますし、非常に興味があると思います。僕は明治安田生命の健康アンバサダーとして、健康に関するアドバイスをする仕事もさせていただいています。皆さん、健康の三大原則をご存知でしょうか。健康の三大原則とは、食べること、寝ること、身体を動かすことの三つです。では、この三つをやっていますか。食べることは、皆さんOKです。きちんと食べていることは見てわかります。食事は身体を作る上で大切です。特に和食は肉も魚も野菜も色んなものを食べられるのでバランスが取れています。このバランスを取れた食事をすることが健康のためにとても大切です。次に、寝ることですが、大人になるとぐっすり眠れる人は減ってきます。何故かというと体力が無いと眠れないからです。子どもは体力があるので、遊び回って疲れるとずっと寝ています。体力が無いと目が覚めてしまうのです。お年寄りは夜遅くに寝ても早く目が覚めてしまう。では、どうすればよいかというと、身体を動かすことです。身体を動かすことの基本は歩くことです。膝が痛くて歩けない方は、プールの中で歩くという方法があります。お勧めなのは縄跳びです。実は縄跳びは全身に力を入れないと飛べません。結構身体に効きます。一番お勧めするスポーツはゴルフです。大人が楽しめながら身体を動かせる競技はゴルフしかありません。子どもからお年寄りまでできるゴルフは実はたいした運動ではありません。しかし、ゴルフしながら歩くというのが大事なのです。ゴルフは生涯スポーツですので、是非ゴルフをお勧めします。
僕は、今52歳でゴルフのプロを目指しています。試合で活躍することは考えていませんが、ゴルフで事業をやりたいと思っています。ゴルフウェアやゴルフクラブを作ろうと思っています。ゴルフをやっている方は非常に多く、富裕層の方々もやっているので、ゴルフの事業をこれから展開しようと考えています。もちろん、体操もやっていきます。自分の夢として体操教室もやりますが、ゴルフの事業はまた別の夢としてやりたいと思っています。
最後に、今日の卓話の「夢果てしなく永遠に」は、僕が若い頃に出した本のタイトルです。夢を持つことがすごく大事だと思っています。僕がオリンピックに出られたのもメダルを取れたのも、夢、目標があったからです。夢や目標があると頑張れます。力が出てきます。そして今何をしたら良いかが見えてきて計画を立てられるということが大事だと思っています。僕は子供たちによく言うのですが、夢の近道、夢を叶える秘訣は、夢、目標を持ったときにみんなの前で発表することです。だから、今、皆さんにゴルフウェアのブランドを作ると言いました。言うことによって、誰かが協力してくれたり、導いてくれたり、サポートしたりする方々が出てくるので、子供たちにも思っていることをどんどん言ってくださいとアドバイスしています。
YouTubeに僕の体操クラブとゴルフの二つのチャンネルがありますので、よろしければ登録してご覧になってください。
ご清聴ありがとうございました。
皆さんは健康にとても注意していると思いますし、非常に興味があると思います。僕は明治安田生命の健康アンバサダーとして、健康に関するアドバイスをする仕事もさせていただいています。皆さん、健康の三大原則をご存知でしょうか。健康の三大原則とは、食べること、寝ること、身体を動かすことの三つです。では、この三つをやっていますか。食べることは、皆さんOKです。きちんと食べていることは見てわかります。食事は身体を作る上で大切です。特に和食は肉も魚も野菜も色んなものを食べられるのでバランスが取れています。このバランスを取れた食事をすることが健康のためにとても大切です。次に、寝ることですが、大人になるとぐっすり眠れる人は減ってきます。何故かというと体力が無いと眠れないからです。子どもは体力があるので、遊び回って疲れるとずっと寝ています。体力が無いと目が覚めてしまうのです。お年寄りは夜遅くに寝ても早く目が覚めてしまう。では、どうすればよいかというと、身体を動かすことです。身体を動かすことの基本は歩くことです。膝が痛くて歩けない方は、プールの中で歩くという方法があります。お勧めなのは縄跳びです。実は縄跳びは全身に力を入れないと飛べません。結構身体に効きます。一番お勧めするスポーツはゴルフです。大人が楽しめながら身体を動かせる競技はゴルフしかありません。子どもからお年寄りまでできるゴルフは実はたいした運動ではありません。しかし、ゴルフしながら歩くというのが大事なのです。ゴルフは生涯スポーツですので、是非ゴルフをお勧めします。
僕は、今52歳でゴルフのプロを目指しています。試合で活躍することは考えていませんが、ゴルフで事業をやりたいと思っています。ゴルフウェアやゴルフクラブを作ろうと思っています。ゴルフをやっている方は非常に多く、富裕層の方々もやっているので、ゴルフの事業をこれから展開しようと考えています。もちろん、体操もやっていきます。自分の夢として体操教室もやりますが、ゴルフの事業はまた別の夢としてやりたいと思っています。
最後に、今日の卓話の「夢果てしなく永遠に」は、僕が若い頃に出した本のタイトルです。夢を持つことがすごく大事だと思っています。僕がオリンピックに出られたのもメダルを取れたのも、夢、目標があったからです。夢や目標があると頑張れます。力が出てきます。そして今何をしたら良いかが見えてきて計画を立てられるということが大事だと思っています。僕は子供たちによく言うのですが、夢の近道、夢を叶える秘訣は、夢、目標を持ったときにみんなの前で発表することです。だから、今、皆さんにゴルフウェアのブランドを作ると言いました。言うことによって、誰かが協力してくれたり、導いてくれたり、サポートしたりする方々が出てくるので、子供たちにも思っていることをどんどん言ってくださいとアドバイスしています。
YouTubeに僕の体操クラブとゴルフの二つのチャンネルがありますので、よろしければ登録してご覧になってください。
ご清聴ありがとうございました。
卓話「機械化とこころ」
切り絵アーティスト 柴田あゆみさま
2022年10月13日

 ただいまご紹介に預かりました柴田あゆみです。切り絵の作家をしております。
切り絵と聞くと、皆さんは落語家の黒い紙を切る薄い二次元の切り絵を思い浮かべると思いますが、私が作っているのは立体の切り絵になります。自分の作品を説明するのに良い言葉がまだ見つからないので、まずは写真や作品をご覧いただいています。
普段は、手のひらに乗るくらいの小さなサイズの作品やティーポットの中に入るくらいの小さな世界を作っています。実はこの小さい中に何層にも詰まった切り絵の世界が広がっています。外からは全く見えないのですが、中の方に細かく切り絵を施してあります。
私はグラスの中の小さな切り絵の世界の中には、何億もの命が広がっているというイメージで制作しています。作品の中には、本のように何層にもレイヤーを重ねて作るものがあります。煩悩の数と同じ108ページを重ねた作品もあります。外からは見えない内側の各レイヤーにも細かく切り込みを入れて、各レイヤーの層が時間の重なりというイメージで作っています。本は前から読んで、最後後ろで閉じる。これは生命と同じだと思っています。巻き戻したり、後戻りすることはありません。一枚一枚が時間であり、それぞれの時間に物語や思い出があります
なぜ、外から全く見えない内側に切り絵を施すのか。それは私が子供の頃に両親からずっと言われてきた、お天道様は見ているよという言葉が心に強く残っているからです。誰も見ていないからこの程度でいいや、というのではなく、お天道様、それは神様であり自分の心が見ていると考えています。みんなそれぞれ神様から分け御霊のような美しいものを授かって生まれてきています。ですから、自分の中の神様を尊重して、心を込めて制作しています。
色付きの切り絵を作らないのかと、よく海外の方からご質問を受けるのですが、私はこだわって白い紙を使っています。日本の文化の中では、例えば神道や仏教では、白い紙に神様が宿ると考えるところがあります。お祓いの時にも白い紙が使われています。高野山ではしめ縄の代わりに白い紙を貼って場を清めています。障子や書道の半紙など身近な素材として白い紙が使われてきました。白い紙には自然界のマナ、エネルギーや精霊といったものが宿ると思っています。ですから、こだわって白い紙を使っています。白い紙で世界を切り出すことによって、マナやエネルギーが楽しみに遊びに来てくれる、そんな世界が作れたら良いと思っています。
私がなぜ切り絵をやっているかをお話いたします。
私は10代のころ音楽活動をしていました。18歳くらいのときに、夜遊びをして家に帰る月曜の早朝の電車で、乗客の皆さんが疲れ切って苦しそうなのを目にしました。とてもよく働く日本人の皆さんが月曜の朝一番に疲れている光景を見て、心が痛くなりました。現代は時間に追われ、お金に追われ、やることに追われ、メールに追われと、色々なものに追われています。あまりにも多くのことに追われすぎて、頭の中はもう次にやることがトントンと出てきて、まるで機械のようになってしまっています。
私たちの生活はとても豊かで便利になりました。今この世界があるのは私たちの祖父母や両親が必死の思いで築き上げてくれたからです。蛇口をひねればお湯が出て、屋根がある場所で安心して眠れて、飛行機や電車、車ですぐに移動できる。こんな時代は地球の長い歴史の中のほんの一瞬の奇跡のような時間だと思います。しかし、こうした機械化と引き換えに、地球の声、大地の声、私たちの魂の小さな声はどんどん聞きづらくなっています。社会が急速に発展して便利になっている一方で、人の心が置きざりにされていると感じます。便利な時代だからこそ、人の心が置いていかれないように、技術が発展するとともに人の心も発展して欲しいと思っています。今こそ、しっかりと考えて、心とは何か、日本人が世界と輪になって何ができるかということを考えるきっかけになればという思いから、私は切り絵にたどり着きました。
私は自分とは何か、日本の何を知っているのだろうと思い、ニューヨークに渡りました。最初は1,2年で、自分というものが分かるのではないかと思っていましたが、1,2年では何も分からないままでした。少しずつ自分を発見していき、生まれた場所や自分の家族、日本の文化の素晴らしさを一つずつ発見していきました。そしてアメリカに渡って8年経って、ようやく細いながらも一本の芯が立ちました。
その間、文化も言葉も分からず、時間の流れも速いニューヨークで、私はよく教会に行きました。扉を閉じれば周りの音は一切聴こえない静寂の世界、そこでよく瞑想をしていました。ある日教会で長い瞑想をして、目を開いた時に足元に広がるステンドグラスの美しい光を見ました。その瞬間、光の美しさに心が震え上がりました。小学校の図工の時間に黒い紙をカッターナイフで切って、カラーセロファンを貼って、簡単なステンドグラスを作ったのがとても楽しかったことを思い出し、すぐに紙とセロファンとカッターナイフを買って、家に帰って作り始めました。時間を忘れるほどただただ楽しく、夢中で作った切り絵の美しさに自分の心が歓び、和らぎ、私自身に戻れるという感覚を感じました。そんなきっかけで始めた切り絵は、気づけばもう12年になります。
さまざまなところで作品を展示させていただく機会があり、先日は丸の内KITTEで大きな作品を展示しました。そして、今年の12月1日から西武池袋で大きな巡回型の森の中に入ってご覧いただける展示を2週間開催いたします。また、12月半ばから来年6月いっぱいまで現代美術館で開催されるクリスチャン・ディオールの展示では、ガーデンという紙で作った壮大な庭を制作、プロデュースさせていただいています。機会があれば、是非皆様ご覧いただいて切り絵の世界に入っていただけたら幸いです。
本日はありがとうございました。
Q&A
Q: 卓話のタイトルに機械化とありましたが、作品にはどの程度機械を使われていますか。機械化の意味をご説明いただけますか。
A: 作品は全て手で作っています。タイトルの機械化の意味ですが、現代では何もかもが機械化されていますが、やはり大切なのは人間の心だと思います。機械に助けてもらうところと、人間にしかできないところ、ここを大切にしたいと思っています。
ただいまご紹介に預かりました柴田あゆみです。切り絵の作家をしております。
切り絵と聞くと、皆さんは落語家の黒い紙を切る薄い二次元の切り絵を思い浮かべると思いますが、私が作っているのは立体の切り絵になります。自分の作品を説明するのに良い言葉がまだ見つからないので、まずは写真や作品をご覧いただいています。
普段は、手のひらに乗るくらいの小さなサイズの作品やティーポットの中に入るくらいの小さな世界を作っています。実はこの小さい中に何層にも詰まった切り絵の世界が広がっています。外からは全く見えないのですが、中の方に細かく切り絵を施してあります。
私はグラスの中の小さな切り絵の世界の中には、何億もの命が広がっているというイメージで制作しています。作品の中には、本のように何層にもレイヤーを重ねて作るものがあります。煩悩の数と同じ108ページを重ねた作品もあります。外からは見えない内側の各レイヤーにも細かく切り込みを入れて、各レイヤーの層が時間の重なりというイメージで作っています。本は前から読んで、最後後ろで閉じる。これは生命と同じだと思っています。巻き戻したり、後戻りすることはありません。一枚一枚が時間であり、それぞれの時間に物語や思い出があります
なぜ、外から全く見えない内側に切り絵を施すのか。それは私が子供の頃に両親からずっと言われてきた、お天道様は見ているよという言葉が心に強く残っているからです。誰も見ていないからこの程度でいいや、というのではなく、お天道様、それは神様であり自分の心が見ていると考えています。みんなそれぞれ神様から分け御霊のような美しいものを授かって生まれてきています。ですから、自分の中の神様を尊重して、心を込めて制作しています。
色付きの切り絵を作らないのかと、よく海外の方からご質問を受けるのですが、私はこだわって白い紙を使っています。日本の文化の中では、例えば神道や仏教では、白い紙に神様が宿ると考えるところがあります。お祓いの時にも白い紙が使われています。高野山ではしめ縄の代わりに白い紙を貼って場を清めています。障子や書道の半紙など身近な素材として白い紙が使われてきました。白い紙には自然界のマナ、エネルギーや精霊といったものが宿ると思っています。ですから、こだわって白い紙を使っています。白い紙で世界を切り出すことによって、マナやエネルギーが楽しみに遊びに来てくれる、そんな世界が作れたら良いと思っています。
私がなぜ切り絵をやっているかをお話いたします。
私は10代のころ音楽活動をしていました。18歳くらいのときに、夜遊びをして家に帰る月曜の早朝の電車で、乗客の皆さんが疲れ切って苦しそうなのを目にしました。とてもよく働く日本人の皆さんが月曜の朝一番に疲れている光景を見て、心が痛くなりました。現代は時間に追われ、お金に追われ、やることに追われ、メールに追われと、色々なものに追われています。あまりにも多くのことに追われすぎて、頭の中はもう次にやることがトントンと出てきて、まるで機械のようになってしまっています。
私たちの生活はとても豊かで便利になりました。今この世界があるのは私たちの祖父母や両親が必死の思いで築き上げてくれたからです。蛇口をひねればお湯が出て、屋根がある場所で安心して眠れて、飛行機や電車、車ですぐに移動できる。こんな時代は地球の長い歴史の中のほんの一瞬の奇跡のような時間だと思います。しかし、こうした機械化と引き換えに、地球の声、大地の声、私たちの魂の小さな声はどんどん聞きづらくなっています。社会が急速に発展して便利になっている一方で、人の心が置きざりにされていると感じます。便利な時代だからこそ、人の心が置いていかれないように、技術が発展するとともに人の心も発展して欲しいと思っています。今こそ、しっかりと考えて、心とは何か、日本人が世界と輪になって何ができるかということを考えるきっかけになればという思いから、私は切り絵にたどり着きました。
私は自分とは何か、日本の何を知っているのだろうと思い、ニューヨークに渡りました。最初は1,2年で、自分というものが分かるのではないかと思っていましたが、1,2年では何も分からないままでした。少しずつ自分を発見していき、生まれた場所や自分の家族、日本の文化の素晴らしさを一つずつ発見していきました。そしてアメリカに渡って8年経って、ようやく細いながらも一本の芯が立ちました。
その間、文化も言葉も分からず、時間の流れも速いニューヨークで、私はよく教会に行きました。扉を閉じれば周りの音は一切聴こえない静寂の世界、そこでよく瞑想をしていました。ある日教会で長い瞑想をして、目を開いた時に足元に広がるステンドグラスの美しい光を見ました。その瞬間、光の美しさに心が震え上がりました。小学校の図工の時間に黒い紙をカッターナイフで切って、カラーセロファンを貼って、簡単なステンドグラスを作ったのがとても楽しかったことを思い出し、すぐに紙とセロファンとカッターナイフを買って、家に帰って作り始めました。時間を忘れるほどただただ楽しく、夢中で作った切り絵の美しさに自分の心が歓び、和らぎ、私自身に戻れるという感覚を感じました。そんなきっかけで始めた切り絵は、気づけばもう12年になります。
さまざまなところで作品を展示させていただく機会があり、先日は丸の内KITTEで大きな作品を展示しました。そして、今年の12月1日から西武池袋で大きな巡回型の森の中に入ってご覧いただける展示を2週間開催いたします。また、12月半ばから来年6月いっぱいまで現代美術館で開催されるクリスチャン・ディオールの展示では、ガーデンという紙で作った壮大な庭を制作、プロデュースさせていただいています。機会があれば、是非皆様ご覧いただいて切り絵の世界に入っていただけたら幸いです。
本日はありがとうございました。
Q&A
Q: 卓話のタイトルに機械化とありましたが、作品にはどの程度機械を使われていますか。機械化の意味をご説明いただけますか。
A: 作品は全て手で作っています。タイトルの機械化の意味ですが、現代では何もかもが機械化されていますが、やはり大切なのは人間の心だと思います。機械に助けてもらうところと、人間にしかできないところ、ここを大切にしたいと思っています。
卓話「GlobalのITとインド~60万人のIT企業で働く~」
日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社
代表取締役社長垣原弘道さま
2022年10月6日

 今日はお招きいただき有難うございます。
私の信条は日本が元気になるために働くことで、現在はタタ財閥の中のIT企業、タタ・コンサルタンシー・サービシズ、略してTCSで仕事をしております。
今日皆さんにお伝えしたいのはインドのタタ・グループ、TCSがどんな会社か、そして、なぜ私が、日本が元気になるために、競争力を上げるためにはインドとのコラボレーションが大切だと思っているか、なぜそこに意味があるかをお話ししたいと思います。
タタ・グループ、タタ財閥は150年の歴史がある財閥です。タタ家はペルシャからインドへ宗教的に逃れてきたので、迎え入れてくれたインドのために働くことを当初から約束しています。持株会社であるタタ・サンズの下に100社、タタ・モータース、タタ・スティール、買収したジャガーランドローバーなど約30社の上場会社があります。その中で50年前にゼロからスタートしたITの会社が現在のタタ・コンサルタンシー・サービシズです。タタグループ企業の持株会社のタタ・サンズの3分の2の株主はNPOのタタ・トラストであり、このタタ・トラストのオーナーがタタ家です。NPOで、医療・教育・環境・エンパワメントに年間200億円規模の寄付をしています。私自身もTCSに入社した時にサインをしたタタグループの行動規範の冒頭に、働くその地の人、社会のために働けと書かれていました。インドのためではありません。このような精神をグループで持ち、ビジネスで得た利益を持株会社を通じて社会に還元していることを誇りに仕事をしています。人々のタタ・グループに対する尊敬の念の理由の一つであり、ビジネスモデルそのものがSDGsと言われています。
TCSは時価総額約20兆円、ITでは世界のトップ企業の一社。従業員は60万人を超え、毎年更に増えています。日本TCSは従業員約3,000人、このほかにインド側で数千名が日本企業のお手伝いをしているので、合計9,000人以上で日本のお客様に向けてお仕事をさせていただいています。
インドには江戸から近未来までがあるとよく申し上げるのですが、様々な社会的な課題を抱えた江戸のような部分と日本のレベルをも超えた近未来までを持っている不思議な国です。インドは州の独自性が強く、民族も言葉も多様、私はEUと同じように、インドはインド・ユニオン、IUのような州、民族の連合体が一つの大国として動いていると思っています。
インドの人口は近いうちに中国を抜くと言われています。総人口の年齢中央値でみるとインドは25歳、アメリカと中国はその10歳上、日本は更にその10歳上という人口構成で人口構成ピラミッドを見るとため息が出るほど、これから世界でも最大の労働人口を輩出する国です。
また、インドが元気な理由はユニコーン企業の数にあります。世界で、アメリカ、中国に続いてインドからユニコーン企業が数多く生まれており、インドではテクノロジーをベースにした産業が大きく強くなっています。インドに生まれてインドの大学を出た人がグーグルやマイクロソフトのトップに登りつめ、NASAでもインド出身者が3分の1強を占めると言われています。
IT分野での日本の課題は、圧倒的な人材不足です。少子高齢化だけでなく理系、IT人材が圧倒的に不足しており、経産省の推計では近い将来45万人不足するとも言われています。今後日本でもITの高度化やデジタル・トランスフォーメーション、サイバーセキュリティなどが必須の状況下、日本の人材不足の問題に、私はインドパワーが貢献できるのではないかと思っています。
インドが輩出しているIT系の人材は、世界で奪い合いが起きており、多くの人材がアメリカに吸収されています。日本がその競争にもっと参加してこの人材を使いこなすことができるようになれば、日本企業がより元気になっていく可能性が拡大すると思っています。言葉や文化などの壁を乗り越えて、多様な人材や高度な能力を活用していくことがこれからの日本にとって必要だと思っています。
日本の企業の強みは、ものづくりや世界一の実行力といった自前主義で確立した良い部分がある一方で、多様な人材とのコミュニケーション、独自の文化、人材不足といった点で問題を抱えています。例えば製造業であれば、日本の強いハードの「ものづくり」とグローバルで鍛え上げられたソフトの「ことづくり」が上手に組み合わされることで日本企業に更なる成長の余地があるのではないかと思っています。TCSは日産自動車様向けに、自動運転、電気自動車などの開発を支援させていただいております。自動車のソフトウエア化の急伸の分野で私たちにお手伝いできる余地が多くあるということで、15年以上のお付き合いになります。日産様から見ると今や、アウトソースではなく、変動費のインソースのような位置づけだと私は思います。
日産自動車様とTCS の関係については、後述の日経ビジネスなどで取り上げていただいていますのでお時間あればご覧になってください。
TCSのビジネスモデルは、豊富な理系人材をトレーニングと経験を通じサービス化して外貨を稼ぐところから始まりました。TCSは機械工学、材料工学などITに限らず広く理系の人材を採用します。そしてグローバル大手企業から社内に足りないスキルをTCSで組み合わせてやって欲しいと依頼されます。例えば、求められた要件に沿ってメディカルデバイスの設計から試作までTCSで行ない、完成したら量産段階から依頼された企業に返すということも行っています。つまり、欧米の会社でも不足している理系の人材、スキルを揃えることで、欧米の会社が実現したいことをスピードを持って実行する黒子の役割を果たしているのです。
ただ、TCSはフロントに出てプロダクトを売る事業主にはなりません。企業の理系人材、その能力が不足するところをプロジェクトで補って実現するという、なかなか面白いポジションで世界中のニーズを満たしている存在です。
まだ日本でのブランドの浸透は十分でなく、皆さまにはTCSの名前は馴染みがないかもしれませんが、私の中では誇りに思える理念の上に立ったグループで働いていること、そして、付き合ってみると実は昭和の香りがするくらい生真面目で、日本が好きで、日本のことを本当によく勉強しているインドの人たちと一緒に、どうすれば日本をもっと元気にすることができるか考えて働いています。
本日は、有難うございました。
Q&A
Q:インドのIT関連の人材が日本を通り越してアメリカに行ってしまう状況を残念に思っています。日本にインドの人材が来るにはどうしたら良いかとお考えでしょうか。
A:やはり言語の問題から、インドの優秀な人材はアメリカなど英語圏に向かいがちですがインド人の中には、日本の文化が好きだという人も多くいます。現在日本に来ている700人くらいのTCSのインド人の多くは家族を連れてきており、子供も日本で教育を受け、所属を日本法人に変えている人も増えています。日本は安全で、住み心地の良い国、仕事があればより多くのインド人には来てもらえると思っています。
文化を越えた相手に対するリスペクトが大切なことは言うまでもありません。日本TCSには30カ国籍の社員がいますが、日本人とインド人だけではない豊かなダイバーシティの中で働く苦労と楽しさを経験することはキャリアのために良いよ、といって社員を励まし互いに学んでいます。
参考:
日刊工業新聞 2019年10月11日朝刊4面
『グローバルの眼』印タタ・グループのSDGs
日経ビジネス 2022年3月10日クルマ大転換
巨大化する車載ソフト開発に人材の壁日産はインドの巨人と組む
IT Media 2019年7月4日車載ソフトウエア
日産がクルマとソフトの両面を知る技術者育成を強化、研修施設を公開
※垣原さまより
「卓話の謝礼金はクラブの奉仕活動に役立ててください」
と謝礼の受け取りを辞退なされました。
垣原さまありがとうございます。当クラブの社会奉仕活動に活用させていただきます。
今日はお招きいただき有難うございます。
私の信条は日本が元気になるために働くことで、現在はタタ財閥の中のIT企業、タタ・コンサルタンシー・サービシズ、略してTCSで仕事をしております。
今日皆さんにお伝えしたいのはインドのタタ・グループ、TCSがどんな会社か、そして、なぜ私が、日本が元気になるために、競争力を上げるためにはインドとのコラボレーションが大切だと思っているか、なぜそこに意味があるかをお話ししたいと思います。
タタ・グループ、タタ財閥は150年の歴史がある財閥です。タタ家はペルシャからインドへ宗教的に逃れてきたので、迎え入れてくれたインドのために働くことを当初から約束しています。持株会社であるタタ・サンズの下に100社、タタ・モータース、タタ・スティール、買収したジャガーランドローバーなど約30社の上場会社があります。その中で50年前にゼロからスタートしたITの会社が現在のタタ・コンサルタンシー・サービシズです。タタグループ企業の持株会社のタタ・サンズの3分の2の株主はNPOのタタ・トラストであり、このタタ・トラストのオーナーがタタ家です。NPOで、医療・教育・環境・エンパワメントに年間200億円規模の寄付をしています。私自身もTCSに入社した時にサインをしたタタグループの行動規範の冒頭に、働くその地の人、社会のために働けと書かれていました。インドのためではありません。このような精神をグループで持ち、ビジネスで得た利益を持株会社を通じて社会に還元していることを誇りに仕事をしています。人々のタタ・グループに対する尊敬の念の理由の一つであり、ビジネスモデルそのものがSDGsと言われています。
TCSは時価総額約20兆円、ITでは世界のトップ企業の一社。従業員は60万人を超え、毎年更に増えています。日本TCSは従業員約3,000人、このほかにインド側で数千名が日本企業のお手伝いをしているので、合計9,000人以上で日本のお客様に向けてお仕事をさせていただいています。
インドには江戸から近未来までがあるとよく申し上げるのですが、様々な社会的な課題を抱えた江戸のような部分と日本のレベルをも超えた近未来までを持っている不思議な国です。インドは州の独自性が強く、民族も言葉も多様、私はEUと同じように、インドはインド・ユニオン、IUのような州、民族の連合体が一つの大国として動いていると思っています。
インドの人口は近いうちに中国を抜くと言われています。総人口の年齢中央値でみるとインドは25歳、アメリカと中国はその10歳上、日本は更にその10歳上という人口構成で人口構成ピラミッドを見るとため息が出るほど、これから世界でも最大の労働人口を輩出する国です。
また、インドが元気な理由はユニコーン企業の数にあります。世界で、アメリカ、中国に続いてインドからユニコーン企業が数多く生まれており、インドではテクノロジーをベースにした産業が大きく強くなっています。インドに生まれてインドの大学を出た人がグーグルやマイクロソフトのトップに登りつめ、NASAでもインド出身者が3分の1強を占めると言われています。
IT分野での日本の課題は、圧倒的な人材不足です。少子高齢化だけでなく理系、IT人材が圧倒的に不足しており、経産省の推計では近い将来45万人不足するとも言われています。今後日本でもITの高度化やデジタル・トランスフォーメーション、サイバーセキュリティなどが必須の状況下、日本の人材不足の問題に、私はインドパワーが貢献できるのではないかと思っています。
インドが輩出しているIT系の人材は、世界で奪い合いが起きており、多くの人材がアメリカに吸収されています。日本がその競争にもっと参加してこの人材を使いこなすことができるようになれば、日本企業がより元気になっていく可能性が拡大すると思っています。言葉や文化などの壁を乗り越えて、多様な人材や高度な能力を活用していくことがこれからの日本にとって必要だと思っています。
日本の企業の強みは、ものづくりや世界一の実行力といった自前主義で確立した良い部分がある一方で、多様な人材とのコミュニケーション、独自の文化、人材不足といった点で問題を抱えています。例えば製造業であれば、日本の強いハードの「ものづくり」とグローバルで鍛え上げられたソフトの「ことづくり」が上手に組み合わされることで日本企業に更なる成長の余地があるのではないかと思っています。TCSは日産自動車様向けに、自動運転、電気自動車などの開発を支援させていただいております。自動車のソフトウエア化の急伸の分野で私たちにお手伝いできる余地が多くあるということで、15年以上のお付き合いになります。日産様から見ると今や、アウトソースではなく、変動費のインソースのような位置づけだと私は思います。
日産自動車様とTCS の関係については、後述の日経ビジネスなどで取り上げていただいていますのでお時間あればご覧になってください。
TCSのビジネスモデルは、豊富な理系人材をトレーニングと経験を通じサービス化して外貨を稼ぐところから始まりました。TCSは機械工学、材料工学などITに限らず広く理系の人材を採用します。そしてグローバル大手企業から社内に足りないスキルをTCSで組み合わせてやって欲しいと依頼されます。例えば、求められた要件に沿ってメディカルデバイスの設計から試作までTCSで行ない、完成したら量産段階から依頼された企業に返すということも行っています。つまり、欧米の会社でも不足している理系の人材、スキルを揃えることで、欧米の会社が実現したいことをスピードを持って実行する黒子の役割を果たしているのです。
ただ、TCSはフロントに出てプロダクトを売る事業主にはなりません。企業の理系人材、その能力が不足するところをプロジェクトで補って実現するという、なかなか面白いポジションで世界中のニーズを満たしている存在です。
まだ日本でのブランドの浸透は十分でなく、皆さまにはTCSの名前は馴染みがないかもしれませんが、私の中では誇りに思える理念の上に立ったグループで働いていること、そして、付き合ってみると実は昭和の香りがするくらい生真面目で、日本が好きで、日本のことを本当によく勉強しているインドの人たちと一緒に、どうすれば日本をもっと元気にすることができるか考えて働いています。
本日は、有難うございました。
Q&A
Q:インドのIT関連の人材が日本を通り越してアメリカに行ってしまう状況を残念に思っています。日本にインドの人材が来るにはどうしたら良いかとお考えでしょうか。
A:やはり言語の問題から、インドの優秀な人材はアメリカなど英語圏に向かいがちですがインド人の中には、日本の文化が好きだという人も多くいます。現在日本に来ている700人くらいのTCSのインド人の多くは家族を連れてきており、子供も日本で教育を受け、所属を日本法人に変えている人も増えています。日本は安全で、住み心地の良い国、仕事があればより多くのインド人には来てもらえると思っています。
文化を越えた相手に対するリスペクトが大切なことは言うまでもありません。日本TCSには30カ国籍の社員がいますが、日本人とインド人だけではない豊かなダイバーシティの中で働く苦労と楽しさを経験することはキャリアのために良いよ、といって社員を励まし互いに学んでいます。
参考:
日刊工業新聞 2019年10月11日朝刊4面
『グローバルの眼』印タタ・グループのSDGs
日経ビジネス 2022年3月10日クルマ大転換
巨大化する車載ソフト開発に人材の壁日産はインドの巨人と組む
IT Media 2019年7月4日車載ソフトウエア
日産がクルマとソフトの両面を知る技術者育成を強化、研修施設を公開
※垣原さまより
「卓話の謝礼金はクラブの奉仕活動に役立ててください」
と謝礼の受け取りを辞退なされました。
垣原さまありがとうございます。当クラブの社会奉仕活動に活用させていただきます。
卓話 「博打と詐欺」
元(米国)ボーズ・コーポレーション副社長・(日本)ボーズ株式会社代表取締役
現 株式会社カタログハウス相談役 佐倉住嘉さま
2022年9月15日

 皆様、今ご紹介に預かりました佐倉と申します。
タイトルは物々しいのですが、決して裏の世界の話ではありません。まともなビジネスの話をさせていただきます。
タイトルにある博打ですが、古くは丁半博打、最近は競馬や競輪、競艇でしょうか。丁半博打の勝率5割に比べると、競馬、競輪、競艇は勝率が悪いです。この勝率を上げる方法というと、過去のデータと周囲の状況その他を的確に分析し、推測をするわけですが、それだけでは当たりません。博打には運が関わっています。その運をどうやって引っ張ってくるかは、なかなか難しい話です。
私は、商売は博打だと思っています。皆様も会社を経営されていらっしゃるので、あまり違和感を感じられないと思います。しかし、商売が博打だといっても、それほどリスクの大きいものではないとおっしゃる方もいらっしゃるでしょう。
たとえば、町の豆腐屋は豆を仕入れる時にお金を使います。そのお金は賭け金ということになります。一晩かけて豆腐を作っても、翌日必ず売れるという保証はありません。それでもお金を賭けて豆腐を作るわけです。そして翌日店を開けば、そこそこ売れます。なぜかというと、豆腐屋は過去何十年にわたる経験則から、翌日のお客の数の正確な予測を立てているからです。情報量が多いのでその精度が高いのです。
しかし、加山雄三さんがおっしゃったように、人生には坂が三つあります。上り坂と下り坂と、「まさか」という坂です。ですから油断はできません。コロナなんてものが出てくるとはだれも予測できませんから。これこそ、運のなせる業です。このコロナ禍で飲食店は次から次とつぶれました。その傍らで儲かっているところもあります。自分のところの話なのですが、通信販売業はうまくいっています。自転車屋も作れば作っただけ売れるという、ほとんど神風が吹いているような一生に一度の大チャンスになっているそうです。このように、商売に於いても博打同様に運は表裏一体の関係にあるのだと思います。
商売が賭け事だとまともに感じるのは、起業するときです。まず、資本金を銀行から借りたり、貯金を使ったりして商売を始めるわけですが、自分の分野の業界で始めるなら、データを豊富に持っているので、成功する確率、すなわち賭けに勝つ確率は比較的高いと思います。しかし、多くの場合、隣の芝生が青く見えて、自分の持っている貴重な情報を利用できない分野で商売を始めてしまう。そうすると賭けに負ける確率が高くなります。起業して3年目に利益を出せる会社はどのくらいあると思いますか。60年前のアメリカでは、成功率は3%でした。今は、SNSなどのコミュニケーションの手段もあり、自分で広報宣伝もできるので、起業環境は良くなっていますが、それでも恐らく10%位だと思います。以前、ソニーの盛田会長に新製品のヒット率を尋ねたら、13%とのことでした。ですから、会社をスタートして成功するのは10%というのはまともな数字だと思います。
さて、これから私のボーズでの仕事の話になります。創業者のボーズがMITの教授時代に、音楽をコンサートホールで聴く時の音と、野原で聴く時の音が全く違うのは何故かという研究を始め、その音色の違いの原因を解明しました。簡単にいうと、反響です。しかし、反響があれば心地よい音に聞こえるかというと違います。ステージでの音が最初に耳に届くのは、楽器の位置を感知するための信号である直接音です。そして感動させるエネルギーとなるのは、反響して自分の頭の周り360度から同じ音が適当な時差を持って届くことと、そしてその音のエネルギーが元のエネルギーとあまり差がないこと、この条件が整わないとコンサートホールの音にならないのです。
ボーズは音響効果を家庭で再現するスピーカーを作り、アメリカとヨーロッパで大当たりしました。そして、日本で1975~6年頃に売り出して大失敗をしました。なぜ失敗したかというと、このスピーカーは音が後ろから出て、後や横の壁に反響して良い音が届くというものでしたが、当時の日本の住宅では、ふすまや障子に吸収されて良い音にならなかったのです。そこで、私はそのスピーカーに見切りをつけて、いくつかあったモデルの中から大部分の音が前から出るスピーカーであったモデル301という製品を選んでこれに私の持てるマーケティング戦略を集中することにしました。このスピーカーは電子レンジくらいの大きさで、表面には木目を印刷したビニールが貼ってあり、一目瞭然で安物でした。1980年代当時は、オーディオの大ブームで、日本の大手のメーカーはどこもオーディオを作っており、日本は世界のオーディオの供給元になっていました。ただこのモデルは、音質は冷蔵庫ぐらいの大きさの日本の競合メーカーのスピーカーに比肩するものの、軽くて小さい。当時の常識では、良い音が出るスピーカーは大きくて重くなければいけない、且つ、部屋に置くのだから家具調でなければいけないと考えられていました。そして国産だから値段が安かった。この電子レンジの大きさのボーズのスピーカーはアメリカで300ドルでした。当時の為替レートは1ドル360円でしたから、日本で売ると10万円になってしまい、高くて勝負にならない、絶対に売れない商品で、勝負になりませんでした。一生懸命回っても無駄だと思っていました。
そこで運の話になるのですが、運には天災のように自分ではどうしようもないものと、自分の力で引っ張れるものの2種類があると思っています。運は大体情報という形でやって来るので、自分の運の探知機の感度を上げて、自分が求める解を見つけるように常に情報収集に努めることが重要になります。
ボーズのスピーカーはサイズが小さくても冷蔵庫サイズの大きなスピーカーに匹敵する良い音が出るので、何とか売る方法はないかと秋葉原を回っていた時、あるオーディオ屋の店長が私に、天井から釣れるスピーカーはないかというお客がいたと言ったのです。この一言が、私のバリバリに感度を上げた探知機にピーンと引っかかりました。実はその数十年前に、私は赤坂でレストランを経営していました。家賃が高いので、良い音が出る大きなスピーカーは置けません。テーブルの数が減って売り上げが下がってしまうからです。その経験が潜在する記憶に残っていたのでしょう。ひらめいたのです。モデル301なら軽くて小さい、音質申し分なし。飲食店向けに壁や天井に取り付けられる。そこで、天井からスピーカーを釣る金具を作ろうと考え、以前、私が製品を輸出したことがある丸茂電機という照明器具屋に照明器具を吊るす金具をスピーカー用に改造して、吊り下げ金具を作らせました。丸茂電機のことも私は情報として持っていたのです。
これで、月に20から30セットしか売れなかったスピーカーが100そして200セットと売れるようになりました。さらに、オーディオの編集もしている雑誌の編集長から、このスピーカーを真っ黒にして、正面に大きなBOSEのロゴをつけたら良いのではないかというアイデアをもらいました。ビニールの木目の安っぽさが無くなり、黒い業務用とすれば多少仕上がりが悪くとも目立たないと思い、早速作らせたところ、発表した翌月から月に1000という単位で売れるようになり、ボーズの日本のオぺレーションは2年目で大黒字になりました。
運を引っぱる力というのは、自分の潜在能力の中の解を求めるエネルギー、つまり自分の中の探知機の感度を上げるということと、業界をくまなく歩くこと、そして情報を探知して、そこからヒントを得ることです。私はこのようにしてボーズを多少なりとも日本で認知していただけるブランドにした次第です。
時間切れのためテーマ詐欺までお話できなかったのは遺憾であります。
どうもご清聴ありがとうございました。
皆様、今ご紹介に預かりました佐倉と申します。
タイトルは物々しいのですが、決して裏の世界の話ではありません。まともなビジネスの話をさせていただきます。
タイトルにある博打ですが、古くは丁半博打、最近は競馬や競輪、競艇でしょうか。丁半博打の勝率5割に比べると、競馬、競輪、競艇は勝率が悪いです。この勝率を上げる方法というと、過去のデータと周囲の状況その他を的確に分析し、推測をするわけですが、それだけでは当たりません。博打には運が関わっています。その運をどうやって引っ張ってくるかは、なかなか難しい話です。
私は、商売は博打だと思っています。皆様も会社を経営されていらっしゃるので、あまり違和感を感じられないと思います。しかし、商売が博打だといっても、それほどリスクの大きいものではないとおっしゃる方もいらっしゃるでしょう。
たとえば、町の豆腐屋は豆を仕入れる時にお金を使います。そのお金は賭け金ということになります。一晩かけて豆腐を作っても、翌日必ず売れるという保証はありません。それでもお金を賭けて豆腐を作るわけです。そして翌日店を開けば、そこそこ売れます。なぜかというと、豆腐屋は過去何十年にわたる経験則から、翌日のお客の数の正確な予測を立てているからです。情報量が多いのでその精度が高いのです。
しかし、加山雄三さんがおっしゃったように、人生には坂が三つあります。上り坂と下り坂と、「まさか」という坂です。ですから油断はできません。コロナなんてものが出てくるとはだれも予測できませんから。これこそ、運のなせる業です。このコロナ禍で飲食店は次から次とつぶれました。その傍らで儲かっているところもあります。自分のところの話なのですが、通信販売業はうまくいっています。自転車屋も作れば作っただけ売れるという、ほとんど神風が吹いているような一生に一度の大チャンスになっているそうです。このように、商売に於いても博打同様に運は表裏一体の関係にあるのだと思います。
商売が賭け事だとまともに感じるのは、起業するときです。まず、資本金を銀行から借りたり、貯金を使ったりして商売を始めるわけですが、自分の分野の業界で始めるなら、データを豊富に持っているので、成功する確率、すなわち賭けに勝つ確率は比較的高いと思います。しかし、多くの場合、隣の芝生が青く見えて、自分の持っている貴重な情報を利用できない分野で商売を始めてしまう。そうすると賭けに負ける確率が高くなります。起業して3年目に利益を出せる会社はどのくらいあると思いますか。60年前のアメリカでは、成功率は3%でした。今は、SNSなどのコミュニケーションの手段もあり、自分で広報宣伝もできるので、起業環境は良くなっていますが、それでも恐らく10%位だと思います。以前、ソニーの盛田会長に新製品のヒット率を尋ねたら、13%とのことでした。ですから、会社をスタートして成功するのは10%というのはまともな数字だと思います。
さて、これから私のボーズでの仕事の話になります。創業者のボーズがMITの教授時代に、音楽をコンサートホールで聴く時の音と、野原で聴く時の音が全く違うのは何故かという研究を始め、その音色の違いの原因を解明しました。簡単にいうと、反響です。しかし、反響があれば心地よい音に聞こえるかというと違います。ステージでの音が最初に耳に届くのは、楽器の位置を感知するための信号である直接音です。そして感動させるエネルギーとなるのは、反響して自分の頭の周り360度から同じ音が適当な時差を持って届くことと、そしてその音のエネルギーが元のエネルギーとあまり差がないこと、この条件が整わないとコンサートホールの音にならないのです。
ボーズは音響効果を家庭で再現するスピーカーを作り、アメリカとヨーロッパで大当たりしました。そして、日本で1975~6年頃に売り出して大失敗をしました。なぜ失敗したかというと、このスピーカーは音が後ろから出て、後や横の壁に反響して良い音が届くというものでしたが、当時の日本の住宅では、ふすまや障子に吸収されて良い音にならなかったのです。そこで、私はそのスピーカーに見切りをつけて、いくつかあったモデルの中から大部分の音が前から出るスピーカーであったモデル301という製品を選んでこれに私の持てるマーケティング戦略を集中することにしました。このスピーカーは電子レンジくらいの大きさで、表面には木目を印刷したビニールが貼ってあり、一目瞭然で安物でした。1980年代当時は、オーディオの大ブームで、日本の大手のメーカーはどこもオーディオを作っており、日本は世界のオーディオの供給元になっていました。ただこのモデルは、音質は冷蔵庫ぐらいの大きさの日本の競合メーカーのスピーカーに比肩するものの、軽くて小さい。当時の常識では、良い音が出るスピーカーは大きくて重くなければいけない、且つ、部屋に置くのだから家具調でなければいけないと考えられていました。そして国産だから値段が安かった。この電子レンジの大きさのボーズのスピーカーはアメリカで300ドルでした。当時の為替レートは1ドル360円でしたから、日本で売ると10万円になってしまい、高くて勝負にならない、絶対に売れない商品で、勝負になりませんでした。一生懸命回っても無駄だと思っていました。
そこで運の話になるのですが、運には天災のように自分ではどうしようもないものと、自分の力で引っ張れるものの2種類があると思っています。運は大体情報という形でやって来るので、自分の運の探知機の感度を上げて、自分が求める解を見つけるように常に情報収集に努めることが重要になります。
ボーズのスピーカーはサイズが小さくても冷蔵庫サイズの大きなスピーカーに匹敵する良い音が出るので、何とか売る方法はないかと秋葉原を回っていた時、あるオーディオ屋の店長が私に、天井から釣れるスピーカーはないかというお客がいたと言ったのです。この一言が、私のバリバリに感度を上げた探知機にピーンと引っかかりました。実はその数十年前に、私は赤坂でレストランを経営していました。家賃が高いので、良い音が出る大きなスピーカーは置けません。テーブルの数が減って売り上げが下がってしまうからです。その経験が潜在する記憶に残っていたのでしょう。ひらめいたのです。モデル301なら軽くて小さい、音質申し分なし。飲食店向けに壁や天井に取り付けられる。そこで、天井からスピーカーを釣る金具を作ろうと考え、以前、私が製品を輸出したことがある丸茂電機という照明器具屋に照明器具を吊るす金具をスピーカー用に改造して、吊り下げ金具を作らせました。丸茂電機のことも私は情報として持っていたのです。
これで、月に20から30セットしか売れなかったスピーカーが100そして200セットと売れるようになりました。さらに、オーディオの編集もしている雑誌の編集長から、このスピーカーを真っ黒にして、正面に大きなBOSEのロゴをつけたら良いのではないかというアイデアをもらいました。ビニールの木目の安っぽさが無くなり、黒い業務用とすれば多少仕上がりが悪くとも目立たないと思い、早速作らせたところ、発表した翌月から月に1000という単位で売れるようになり、ボーズの日本のオぺレーションは2年目で大黒字になりました。
運を引っぱる力というのは、自分の潜在能力の中の解を求めるエネルギー、つまり自分の中の探知機の感度を上げるということと、業界をくまなく歩くこと、そして情報を探知して、そこからヒントを得ることです。私はこのようにしてボーズを多少なりとも日本で認知していただけるブランドにした次第です。
時間切れのためテーマ詐欺までお話できなかったのは遺憾であります。
どうもご清聴ありがとうございました。
卓話 「『見た目も、心も』輝くための、美容情報(ヘアメイクの現場から)」
ヘアメイクアップアーティスト 近藤澄代さま
2022年9月8日

 皆さま初めまして近藤澄代と申します。本日はよろしくお願いいたします。
私は、ヘアメイクアーティストとして、タレントさん、芸能人、ミュージシャン、アスリートといった方々のヘアメイクをさせていただいております。そのかたわら、渋谷で経営する美容室で、お客様の髪の毛のカットなどもしております。中には30年も通って下さるお客様もいらっしゃいます。そのような方々とのお付き合いの中で顔や髪型だけでなく、内側から美しさが出るようなアドバイスができればと思い、心理カウンセラーや薬膳インストラクターの免許を取得したりしました。メイクやヘアでは、その人の一番良いところが引き出せるような仕事をいつも心がけています。
私が、ヘアメイクの世界で素晴らしいと思っているのは、各界のそれぞれ一流と言われる方たちにお会いして、間近で彼らの考えや思いを見聞きできることです。来てくれるお客様にどれだけ良いものを見せるかということを日々考えている姿を目の当たりにし、私も、お客様に対する思いに対してとても影響を受けております。仕事に対する非常に強いプロ意識や、撮影などの中でもこまめなスタッフに対する敬意など、一流の方々の素晴らしさに触れることができます。
パンフレットをご用意しましたが、私はシャンプー剤も販売しております。昔、私のアシスタントの美容師が、シャンプー剤でひどい手荒れになり、その手荒れが影響してカラー剤のアレルギーになり、顔や全身がひどく腫れ上がり、それが原因で美容師が出来なくなってしまいました。そのような人をもう出したくないという思いから、色々なメーカーとのシャンプー開発に参加させていただき、自身の会社で4年前にオーガニックのシャンプーシリーズを出しました。よろしかったらご覧になってください。
ヘアメイクの仕事とは、具体的にどのような仕事か?ということですが、若い頃は、ヘアメイクであのタレントのように見せたいとか、アイドルのこの人のように見せたいと思う時があります。それは、ヘアメイクによって「自分がどのようにしたいか?」という考えが多いと思います。しかし年齢を重ねるごとに、自分の社会的な立場を考えて、ヘアメイクで他の人に対して「自分をどのように見せたいか?」という風に変わってきます。
最近はマスクをしていることで、口角が下がってきている人が多いです。口角が下がると印象が暗くなり、怒っているように見えてしまいます。時々マスクの上からでも口角の横を触って口角を意識するようにする癖をつけるとよいと思います。
同じ年齢の人でも老けて見える人と若く見える人の差がどこにあるかを見てみると、年齢によって誰しもが瞼や口角が下がります。そして額が広く出ていると顔全体が出ることで、加齢によってお顔が下がってしまっているので縦のラインが強調されて、印象が老けて見えます。そこで、女性の場合は前髪を少し下ろして額を少し隠したり、トップの髪の毛のボリュームを出して、サイドにもボリュームを出してひし形のシルエットを作ると若く見えます。また、年を取ると目と眉毛の間が広がるので、眉毛の位置を少し下に下げてまっすぐに書き、唇は上唇を少しだけ上に書いて鼻と口の間が少し縮んでいるようにするのも若く見せるメイクです。
男性のヘアスタイルですが、若く爽やかに見せるポイントはトップのボリュームと額の見えている面積を少なくすること、そしてサイドをあまり膨らませないことです。これは、それぞれの人の顔の形と髪の毛の長さによって違いますが、トップに少し高さを出し、額の見える面積を減らすのが、若く見せるポイントになります。
最近は企業の社長さんのヘアメイクを担当することが多いです。社員の方々に、自分にはパワーがある、元気だということを示したい時や、社長のプロフィール写真の撮影にもヘアメイクが入ることが多いです。
印象の問題ですが、私が調べたところ、上司の髪型が整っていないと、清潔感がないとかだらしなく見えるという意見がありました。身だしなみの整っていない上司に対しては、何となく不安で尊敬できないというマイナスイメージがあるようです。逆に、身だしなみが整っている上司は、できる上司に見えるという答えが93%もあり、見せ方というのも大事になっていていると思います。
総括するとヘアメイクの仕事とは、その人に自信を持っていただくことだと思っております。最近は企業の社長さんたちへのヘアメイクに入らせていただき、各界の素晴らしい一流の方に出会い、お話を伺う中でその方々の気遣いや人に対する思い、優しさに触れて日々勉強させていただいております。そんなヘアメイクは素晴らしい仕事だと思っておりますので、これからも頑張ってやっていきたいと思っております。
ありがとうございました。
質疑応答
Q: あごのたるみも年齢によると思いますが、どのような対策をとればよいでしょうか。
A: あごのたるみはリンパの滞りからできます。最近は女性だけでなく男性も化粧水でフェイスケアされている方が多いと思います。そのときに、優しく手で頬骨からこめかみに向かってリンパを流し、最後に顎の下から耳の下へ持っていき、鎖骨に向かって流す。これを毎日やると本当に変わりますので是非お試しください。
Q: 男性も額を出すと老けて見えるというお話でしたが、髪の毛を前にかけずに若く見える髪型はありますか。
A: お仕事の関係で前髪を下ろせない方は多いと思います。前髪を後ろの方に上げたり横に流す時は、横を膨らませすぎないのが額を出すときのバランスのポイントです。後ろに上げる時は、トップに少しボリュームを出すスタイリングにすると、老けて見えなくなります。
皆さま初めまして近藤澄代と申します。本日はよろしくお願いいたします。
私は、ヘアメイクアーティストとして、タレントさん、芸能人、ミュージシャン、アスリートといった方々のヘアメイクをさせていただいております。そのかたわら、渋谷で経営する美容室で、お客様の髪の毛のカットなどもしております。中には30年も通って下さるお客様もいらっしゃいます。そのような方々とのお付き合いの中で顔や髪型だけでなく、内側から美しさが出るようなアドバイスができればと思い、心理カウンセラーや薬膳インストラクターの免許を取得したりしました。メイクやヘアでは、その人の一番良いところが引き出せるような仕事をいつも心がけています。
私が、ヘアメイクの世界で素晴らしいと思っているのは、各界のそれぞれ一流と言われる方たちにお会いして、間近で彼らの考えや思いを見聞きできることです。来てくれるお客様にどれだけ良いものを見せるかということを日々考えている姿を目の当たりにし、私も、お客様に対する思いに対してとても影響を受けております。仕事に対する非常に強いプロ意識や、撮影などの中でもこまめなスタッフに対する敬意など、一流の方々の素晴らしさに触れることができます。
パンフレットをご用意しましたが、私はシャンプー剤も販売しております。昔、私のアシスタントの美容師が、シャンプー剤でひどい手荒れになり、その手荒れが影響してカラー剤のアレルギーになり、顔や全身がひどく腫れ上がり、それが原因で美容師が出来なくなってしまいました。そのような人をもう出したくないという思いから、色々なメーカーとのシャンプー開発に参加させていただき、自身の会社で4年前にオーガニックのシャンプーシリーズを出しました。よろしかったらご覧になってください。
ヘアメイクの仕事とは、具体的にどのような仕事か?ということですが、若い頃は、ヘアメイクであのタレントのように見せたいとか、アイドルのこの人のように見せたいと思う時があります。それは、ヘアメイクによって「自分がどのようにしたいか?」という考えが多いと思います。しかし年齢を重ねるごとに、自分の社会的な立場を考えて、ヘアメイクで他の人に対して「自分をどのように見せたいか?」という風に変わってきます。
最近はマスクをしていることで、口角が下がってきている人が多いです。口角が下がると印象が暗くなり、怒っているように見えてしまいます。時々マスクの上からでも口角の横を触って口角を意識するようにする癖をつけるとよいと思います。
同じ年齢の人でも老けて見える人と若く見える人の差がどこにあるかを見てみると、年齢によって誰しもが瞼や口角が下がります。そして額が広く出ていると顔全体が出ることで、加齢によってお顔が下がってしまっているので縦のラインが強調されて、印象が老けて見えます。そこで、女性の場合は前髪を少し下ろして額を少し隠したり、トップの髪の毛のボリュームを出して、サイドにもボリュームを出してひし形のシルエットを作ると若く見えます。また、年を取ると目と眉毛の間が広がるので、眉毛の位置を少し下に下げてまっすぐに書き、唇は上唇を少しだけ上に書いて鼻と口の間が少し縮んでいるようにするのも若く見せるメイクです。
男性のヘアスタイルですが、若く爽やかに見せるポイントはトップのボリュームと額の見えている面積を少なくすること、そしてサイドをあまり膨らませないことです。これは、それぞれの人の顔の形と髪の毛の長さによって違いますが、トップに少し高さを出し、額の見える面積を減らすのが、若く見せるポイントになります。
最近は企業の社長さんのヘアメイクを担当することが多いです。社員の方々に、自分にはパワーがある、元気だということを示したい時や、社長のプロフィール写真の撮影にもヘアメイクが入ることが多いです。
印象の問題ですが、私が調べたところ、上司の髪型が整っていないと、清潔感がないとかだらしなく見えるという意見がありました。身だしなみの整っていない上司に対しては、何となく不安で尊敬できないというマイナスイメージがあるようです。逆に、身だしなみが整っている上司は、できる上司に見えるという答えが93%もあり、見せ方というのも大事になっていていると思います。
総括するとヘアメイクの仕事とは、その人に自信を持っていただくことだと思っております。最近は企業の社長さんたちへのヘアメイクに入らせていただき、各界の素晴らしい一流の方に出会い、お話を伺う中でその方々の気遣いや人に対する思い、優しさに触れて日々勉強させていただいております。そんなヘアメイクは素晴らしい仕事だと思っておりますので、これからも頑張ってやっていきたいと思っております。
ありがとうございました。
質疑応答
Q: あごのたるみも年齢によると思いますが、どのような対策をとればよいでしょうか。
A: あごのたるみはリンパの滞りからできます。最近は女性だけでなく男性も化粧水でフェイスケアされている方が多いと思います。そのときに、優しく手で頬骨からこめかみに向かってリンパを流し、最後に顎の下から耳の下へ持っていき、鎖骨に向かって流す。これを毎日やると本当に変わりますので是非お試しください。
Q: 男性も額を出すと老けて見えるというお話でしたが、髪の毛を前にかけずに若く見える髪型はありますか。
A: お仕事の関係で前髪を下ろせない方は多いと思います。前髪を後ろの方に上げたり横に流す時は、横を膨らませすぎないのが額を出すときのバランスのポイントです。後ろに上げる時は、トップに少しボリュームを出すスタイリングにすると、老けて見えなくなります。
卓話 「お燗番と言う仕事」
株式会社ガッツ代表取締役
会員制燗酒研究所 Guts lab所長 水原将さま
2022年8月25日

 ご紹介いただきました水原将です。よろしくお願いします。
私は今、池尻大橋で5席の会員制のお店を経営しております。元々はウィスキーの専門店を経営しており、ミュージシャンと飲食店の二足の草鞋で全国の小さなジャズクラブをツアーで回っておりました。日本各地の美味しいものを食べていたので、自分のウィスキー専門店で提供するのも良いかと思ったのですが、予算の問題があり、その夢は潰えてしまいました。その時に、自分は皆さんに何を提供するのが正しいのかと原点に立ち返ることができました。
その頃、多くの日本酒の専門店に行き、店の方に話を聞いたのですが、難しい話ばかりされて興味が全く湧かないという体験をしました。もっと面白おかしく、日本酒を深く理解しながら、舌と心に刺さる味を提供できないかと考えたのが、日本酒にのめり込んだきっかけでした。当時は、燗なんて安酒でするものだと思っていたので、勉強と称して、毎日冷たい酒を一日8合くらい飲んでいました。しかし、翌日には二日酔いでひどい頭痛になり、続けることができなくなりました。果たしてこの飲み方が正しいのだろうかと思い、また自分で歴史から調べるようになりました。酒蔵見学で訪れたお燗が好きな蔵元さんから、酒は温めて飲むのがデフォルトなのだという話を聞いて、ますます燗酒の世界にのめり込んでいきました。
お燗をすると何が違うかというと、翌日がとても楽なのです。ひょっとしたら1升超えても大丈夫かもしれないと思うようになりました。そして、自分が日本酒のスペシャリストとしてやる仕事は何かということも考えました。私が扱う日本酒はどれだけ飲んでも翌日に残らず健康的に飲めること、それをきちんと説明できるのが、お燗番というプロの仕事だと思うようになりました。
お燗番は、ただ酒を温めているだけではありません。酒を一つの食材だと捉えています。特に純米酒は水と米と米麹だけで作った素材そのものです。温め方にはきちんとしたプロセスがあり、それを間違えると焦げた焼き魚や焼きすぎた肉のような感じの酒になってしまうのです。お燗嫌いの人はこのような体験をされたのではないかと思っています。
実はこの三日間、寿司一貫に対して燗酒一杯をペアリングする催しを行いました。とても面倒でしたが、コハダ、マグロ、貝類では味わいが全く違うのですから、さまざまな寿司を一つの酒でまとめることはできません。中には、何故冷たい酒を出さないのかというお客さんもいました。それに対しては「お寿司を食べる時に冷たい水で合わせますか」と言いました。冷たいお茶や水は寿司と一緒に口に入れると生臭みが目立つのです。私が気持ちを込めて炊き上げた燗酒を飲んでいただいて、なるほどと納得していただきました。
私が日本酒をやり始めてから話すようになった言葉ですが、ウィスキーは最強です、ワインは最高です、でも純米酒のお燗は無敵なのです。なぜ、こういうことを言うかというと、無敵の概念は、武道でいえば誰も手を出さなくなり、みんなが仲間になることだと思うからです。
例えば、ウィスキーと合わせる食材として思い浮かぶチョコレート、ナッツ、アイスクリームは、お燗した日本酒に合わせると口の中でとろけてとても美味しいです。逆に日本酒に合う食材の刺身をウィスキーに合わせたらどうでしょう。嫌ですよね。次にワインと合う食材のチーズは、日本酒のお燗では口内調味で溶かすことができ美味しく味わえます。ステーキもお燗の熱で肉の脂を溶かすことができるので美味しく食べられます。逆に、日本の発酵食品のイカの塩辛や数の子をワインと合わせたらどうでしょう。口の中で合わせるととんでもない味になります。日本酒は全てを口内調味してきれいに調和するので苦手食材がありません。だから無敵なのです。
ただ、お燗番にとって一番の鬼門が魚です。蒸留したアルコールが含まれる本醸造酒であれば、アルコールの力で生臭みを少し抑えてくれますが、純米酒と魚をペアリングすると生臭みを誘発する場合があります。先ほどお話した三日間の催し、寿司一貫に燗酒一杯のペアリングは本当に難しかったのですが、選びに選んで熱を加えた燗酒で生臭みを抑えました。
日本酒が一番合うのは刺身や魚だと思っている方が多いかもしれませんが、肉や天ぷら、また日本酒と合うのかと思われそうな中華料理やタイカレー、インドカレーも純米酒と非常に合います。なぜなら、日本人はこうした料理をご飯で合わせるようにイノベーションをかけてきたからです。
私はミュージシャンなので、ペアリングという概念を考えた時、ライブの曲順と一緒だと思いました。食事をバンドだと捉えています。そしてボーカリストを酒と見立ててペアリングしています。兵庫の奥播磨という酒は、香りがあってざらざらしている質感です。私はジョー・コッカーみたいな酒だと例えています。皆さんよくご存じの獺祭は寝かせることが難しく、エイジングが進まない酒ですので、私は大地真央と呼んでいます。埼玉の神亀はエルビス・プレスリーのようなスターの味で苦手食材はほとんどありません。
私は、嘉永元年に創業した福島県郡山にある仁井田本家という全量純米の蔵元公認のお燗番をやらせていただいています。郡山のジャズクラブにツアーで訪れた時に見学させていただく良い酒蔵として紹介されたのが仁井田本家でした。蔵見学の時にお燗した酒をふるまっていただいたのですが、これが美味しくなかったのです。そこで、私が替わって燗付けして蔵元に飲んでいただいたところ、「うちの酒、こんなに美味しいのか」と言われました。蔵元は酒を造っている人で、酒のことを何でも知っていると思いがちですが、役割が違うのです。養豚農家がとんかつを揚げるのがうまいか、松阪牛を育てている農家が最高のビフテキを焼けるか、答えはノーです。彼らは造るプロで、私は提供するプロです。その時に仁井田本家から、うちのお燗番になってと言われた次第です。
今この段階でも、冷たい酒も美味しいと思っている方もいらっしゃるでしょう。ここで、はっきり申し上げます。冷たい酒を飲んでいる内は、まだまだ酒のことを理解されていません。機会がありましたら、たった5席しかない店ですけれども、よろしかったら皆さん、お越しいただけたらと思います。
こういう機会を与えて下さり、感謝申し上げます。有難うございました。
ご紹介いただきました水原将です。よろしくお願いします。
私は今、池尻大橋で5席の会員制のお店を経営しております。元々はウィスキーの専門店を経営しており、ミュージシャンと飲食店の二足の草鞋で全国の小さなジャズクラブをツアーで回っておりました。日本各地の美味しいものを食べていたので、自分のウィスキー専門店で提供するのも良いかと思ったのですが、予算の問題があり、その夢は潰えてしまいました。その時に、自分は皆さんに何を提供するのが正しいのかと原点に立ち返ることができました。
その頃、多くの日本酒の専門店に行き、店の方に話を聞いたのですが、難しい話ばかりされて興味が全く湧かないという体験をしました。もっと面白おかしく、日本酒を深く理解しながら、舌と心に刺さる味を提供できないかと考えたのが、日本酒にのめり込んだきっかけでした。当時は、燗なんて安酒でするものだと思っていたので、勉強と称して、毎日冷たい酒を一日8合くらい飲んでいました。しかし、翌日には二日酔いでひどい頭痛になり、続けることができなくなりました。果たしてこの飲み方が正しいのだろうかと思い、また自分で歴史から調べるようになりました。酒蔵見学で訪れたお燗が好きな蔵元さんから、酒は温めて飲むのがデフォルトなのだという話を聞いて、ますます燗酒の世界にのめり込んでいきました。
お燗をすると何が違うかというと、翌日がとても楽なのです。ひょっとしたら1升超えても大丈夫かもしれないと思うようになりました。そして、自分が日本酒のスペシャリストとしてやる仕事は何かということも考えました。私が扱う日本酒はどれだけ飲んでも翌日に残らず健康的に飲めること、それをきちんと説明できるのが、お燗番というプロの仕事だと思うようになりました。
お燗番は、ただ酒を温めているだけではありません。酒を一つの食材だと捉えています。特に純米酒は水と米と米麹だけで作った素材そのものです。温め方にはきちんとしたプロセスがあり、それを間違えると焦げた焼き魚や焼きすぎた肉のような感じの酒になってしまうのです。お燗嫌いの人はこのような体験をされたのではないかと思っています。
実はこの三日間、寿司一貫に対して燗酒一杯をペアリングする催しを行いました。とても面倒でしたが、コハダ、マグロ、貝類では味わいが全く違うのですから、さまざまな寿司を一つの酒でまとめることはできません。中には、何故冷たい酒を出さないのかというお客さんもいました。それに対しては「お寿司を食べる時に冷たい水で合わせますか」と言いました。冷たいお茶や水は寿司と一緒に口に入れると生臭みが目立つのです。私が気持ちを込めて炊き上げた燗酒を飲んでいただいて、なるほどと納得していただきました。
私が日本酒をやり始めてから話すようになった言葉ですが、ウィスキーは最強です、ワインは最高です、でも純米酒のお燗は無敵なのです。なぜ、こういうことを言うかというと、無敵の概念は、武道でいえば誰も手を出さなくなり、みんなが仲間になることだと思うからです。
例えば、ウィスキーと合わせる食材として思い浮かぶチョコレート、ナッツ、アイスクリームは、お燗した日本酒に合わせると口の中でとろけてとても美味しいです。逆に日本酒に合う食材の刺身をウィスキーに合わせたらどうでしょう。嫌ですよね。次にワインと合う食材のチーズは、日本酒のお燗では口内調味で溶かすことができ美味しく味わえます。ステーキもお燗の熱で肉の脂を溶かすことができるので美味しく食べられます。逆に、日本の発酵食品のイカの塩辛や数の子をワインと合わせたらどうでしょう。口の中で合わせるととんでもない味になります。日本酒は全てを口内調味してきれいに調和するので苦手食材がありません。だから無敵なのです。
ただ、お燗番にとって一番の鬼門が魚です。蒸留したアルコールが含まれる本醸造酒であれば、アルコールの力で生臭みを少し抑えてくれますが、純米酒と魚をペアリングすると生臭みを誘発する場合があります。先ほどお話した三日間の催し、寿司一貫に燗酒一杯のペアリングは本当に難しかったのですが、選びに選んで熱を加えた燗酒で生臭みを抑えました。
日本酒が一番合うのは刺身や魚だと思っている方が多いかもしれませんが、肉や天ぷら、また日本酒と合うのかと思われそうな中華料理やタイカレー、インドカレーも純米酒と非常に合います。なぜなら、日本人はこうした料理をご飯で合わせるようにイノベーションをかけてきたからです。
私はミュージシャンなので、ペアリングという概念を考えた時、ライブの曲順と一緒だと思いました。食事をバンドだと捉えています。そしてボーカリストを酒と見立ててペアリングしています。兵庫の奥播磨という酒は、香りがあってざらざらしている質感です。私はジョー・コッカーみたいな酒だと例えています。皆さんよくご存じの獺祭は寝かせることが難しく、エイジングが進まない酒ですので、私は大地真央と呼んでいます。埼玉の神亀はエルビス・プレスリーのようなスターの味で苦手食材はほとんどありません。
私は、嘉永元年に創業した福島県郡山にある仁井田本家という全量純米の蔵元公認のお燗番をやらせていただいています。郡山のジャズクラブにツアーで訪れた時に見学させていただく良い酒蔵として紹介されたのが仁井田本家でした。蔵見学の時にお燗した酒をふるまっていただいたのですが、これが美味しくなかったのです。そこで、私が替わって燗付けして蔵元に飲んでいただいたところ、「うちの酒、こんなに美味しいのか」と言われました。蔵元は酒を造っている人で、酒のことを何でも知っていると思いがちですが、役割が違うのです。養豚農家がとんかつを揚げるのがうまいか、松阪牛を育てている農家が最高のビフテキを焼けるか、答えはノーです。彼らは造るプロで、私は提供するプロです。その時に仁井田本家から、うちのお燗番になってと言われた次第です。
今この段階でも、冷たい酒も美味しいと思っている方もいらっしゃるでしょう。ここで、はっきり申し上げます。冷たい酒を飲んでいる内は、まだまだ酒のことを理解されていません。機会がありましたら、たった5席しかない店ですけれども、よろしかったら皆さん、お越しいただけたらと思います。
こういう機会を与えて下さり、感謝申し上げます。有難うございました。
卓話 「2019~2020年留学 帰国報告会」
青少年交換留学生 堀野れおなさま
2022年8月18日

 皆様、こんにちは。
国際ロータリー第2750地区、東京山の手ロータリークラブに推薦をいただき、2019-20年度に青少年交換プログラムの派遣生としてアメリカ合衆国に派遣していただきました順天堂大学2年の堀野れおなです。新型コロナの影響で早期帰国となりましたが、私の約8カ月の派遣生活の成果を皆様にご紹介できればと思います。
この青少年交換プログラムでは東京山の手ロータリークラブの皆様のご推薦をいただき、筆記試験、面接、自己アピールなどの厳しい試験を受け、二度目の試験で晴れて合格することができました。合格後は派遣候補生として1年間プレゼンテーションやスピーチの研修を受けて親善大使として活躍できるように成長させていただきました。このプログラムでは派遣国を自分で選ぶことはできません。研修の成果からアメリカ合衆国でやっていけると判断されて、派遣していただきました。
派遣生としてのボランティア活動とロータリーでの活動についてお話します。
一番記憶に残っているボランティア活動は、動物園のハロウィーンイベントで、二日間お菓子を配るコーナーで活動したことです。動物園ではボランティアの募集はなかったのですが、東京から来たロータリーの派遣生としてピッツバーグとの親善を図るためにボランティアをさせてほしいと動物園にメールを送ったところ、動物園から許可をもらいました。この時、自分から行動すれば夢を叶えられると思うことができました。
ロータリーのイベントでは、派遣生として日本の伝統料理のお寿司を100人分ほど作ってふるまったこともあります。私が作ったお寿司は他の伝統料理よりも早く、一番最初に無くなり、本当にうれしく思いました。パンケーキフェスティバルというチャリティーイベントでは一日中パンケーキやソーセージ、リンゴのジャムなどを作って提供し、来場者から少しだけお金をいただいて、そのお金をボランティアに活用することもしていました。
ロータリー主催の国際会議に参加した時には、ロータリー派遣生としての自分の発言がロータリーとしての発言とみなされることの重みを感じ、自分の発言に責任を持つことに恐さを感じたのを覚えています。
高校で寿司パーティーを主催したときは、みんなに日本の良さを知ってもらい、是非日本に来てほしいと言うことを意識しました。書道教室を開催した時には、墨汁で書くとみんなが喜んでくれるので、日本人としての希少価値を感じてうれしく思いました。
教会の日曜学校でアシスタントとして3歳児のクラスを担当した時は、分かりやすい英語を使わなければと頭を使い、そのおかげで英語力が格段に上がりました。
サンクスギビングデーに、食事を作って訪問した家で手渡しするというイベントを、ロータリークラブと地元警察が協力して行いました。貧困地域に行くのは危険なので、警官と一緒に食事を配っていきました。この経験で私は世界の不平等を実感しました。世界中の人々に平和をもたらすという私の思いは叶えられないと実感し、世界で一人でも多くの人に平和をもたらしたいという考えに変わりました。
ロータリーのトリップでは、同じ地区の派遣生とハイキングをしたり、国際会議を行ったりという研修を受けながら、さまざまなところに行きました。ナイアガラの滝では研修を全部忘れて楽しみました。ニューヨークトリップは二地区合同の大人数のトリップで、自由の女神、セントラルパーク、ブルックリンブリッジ、タイムズスクエアにも行きました。本当は最後の1か月間でディズニーワールドに行く予定でしたが、新型コロナの影響で実現しなかったのが本当に残念です。
私のホストファミリーは、私が空港に到着したとき、プラカードを持って待っていてくれました。ホストマザーは私を見つけると「れおなー!」と呼んでハグしてくれました。ひとりで15時間のフライトで寂しい思いをしていた私はうれし涙を必死でこらえました。
到着した日には家の玄関に国旗を飾ってくれていて、私を歓迎してくれているのだなとうれしい気持ちになりました。ホストファミリーの弟たちにはプレゼントした甚平で、日本の文化に初めて触れてもらいました。派遣生活から1ヶ月の記念日にはこの弟たちがケーキを作ってくれて本当にうれしく思いました。
しかし、ホストファミリーとの間に問題も少しありました。
ホストファーザーは、トランプ支持者で、私はちょっと怖いように感じました。アジアに対する考えや知識が乏しく、私に、中国の音楽を聴くのかとか韓国語を話すのかと尋ねてくるので、最初は困惑しました。でも派遣生活の最後の頃には、逆に私の方からホストファーザーに、スペイン語の曲を聞くのかと尋ねて、聞かないと言われると、私も一緒だよと対応できるようになりました。
ホストマザーはとても感情的で、料理をまったく作らない人でした。ピザか中華料理のデリバリーか、少し焼いた鶏むね肉というような食事でした。そこで、私は自分で料理したり、サラダを学校でのランチに持って行ったりしました。するとホストマザーに、自分が作るご飯が嫌いなのねとネガティブなことを言われたりしました。また、家族でディズニーワールドに行く計画では、私は別行動するように言われました。それがとても悲しかったので、勉強を理由に行くのをやめると伝えたところ、私を置き去りにしたと思われたくなかったのか、ロータリアンに私を批判する嘘の話をされたりしました。私一人ではどうにもならないと思い、日本のロータリアンの方に電話で相談したところ、自分でホストマザーと話して、どんな事があっても話し続けて解決するようにと、アドバイスをいただきました。ディズニーワールドから帰ってきたホストマザーに、私が傷ついたこと、でも大好きだから良い関係を保ちたいと率直に話しました。こうして分かり合い、今では良い関係を保っています。早期帰国が決まったときには、みんなが私との別れを惜しんでくれました。
日常生活でもいろいろな経験をしました。学校でのカウボーイデーという仮装、ロータリアンのお宅でのメキシカンタコスパーティ。成績優秀者のディーズリストにも選ばれました。ハロウィーンでお菓子を配ったり、スケートに連れて行ってもらったり、バレンタインデーにチョコや風船、ぬいぐるみをもらって喜んだり、いずれも楽しい思い出です。
今、私は大学生として活動しています。大学に入学した1年次に、この派遣生活が認められて特待生として奨学金をいただきました。また、大学1年の時の成績が学年でトップでしたので、今年も奨学金をいただいています。今の成績を残すことができたのも、皆さまからのご支援とサポートがあったおかげでございます。まだまだお話したいことはありますが、以上で私の帰国報告とさせていただきます。
ご清聴ありがとうございました。
皆様、こんにちは。
国際ロータリー第2750地区、東京山の手ロータリークラブに推薦をいただき、2019-20年度に青少年交換プログラムの派遣生としてアメリカ合衆国に派遣していただきました順天堂大学2年の堀野れおなです。新型コロナの影響で早期帰国となりましたが、私の約8カ月の派遣生活の成果を皆様にご紹介できればと思います。
この青少年交換プログラムでは東京山の手ロータリークラブの皆様のご推薦をいただき、筆記試験、面接、自己アピールなどの厳しい試験を受け、二度目の試験で晴れて合格することができました。合格後は派遣候補生として1年間プレゼンテーションやスピーチの研修を受けて親善大使として活躍できるように成長させていただきました。このプログラムでは派遣国を自分で選ぶことはできません。研修の成果からアメリカ合衆国でやっていけると判断されて、派遣していただきました。
派遣生としてのボランティア活動とロータリーでの活動についてお話します。
一番記憶に残っているボランティア活動は、動物園のハロウィーンイベントで、二日間お菓子を配るコーナーで活動したことです。動物園ではボランティアの募集はなかったのですが、東京から来たロータリーの派遣生としてピッツバーグとの親善を図るためにボランティアをさせてほしいと動物園にメールを送ったところ、動物園から許可をもらいました。この時、自分から行動すれば夢を叶えられると思うことができました。
ロータリーのイベントでは、派遣生として日本の伝統料理のお寿司を100人分ほど作ってふるまったこともあります。私が作ったお寿司は他の伝統料理よりも早く、一番最初に無くなり、本当にうれしく思いました。パンケーキフェスティバルというチャリティーイベントでは一日中パンケーキやソーセージ、リンゴのジャムなどを作って提供し、来場者から少しだけお金をいただいて、そのお金をボランティアに活用することもしていました。
ロータリー主催の国際会議に参加した時には、ロータリー派遣生としての自分の発言がロータリーとしての発言とみなされることの重みを感じ、自分の発言に責任を持つことに恐さを感じたのを覚えています。
高校で寿司パーティーを主催したときは、みんなに日本の良さを知ってもらい、是非日本に来てほしいと言うことを意識しました。書道教室を開催した時には、墨汁で書くとみんなが喜んでくれるので、日本人としての希少価値を感じてうれしく思いました。
教会の日曜学校でアシスタントとして3歳児のクラスを担当した時は、分かりやすい英語を使わなければと頭を使い、そのおかげで英語力が格段に上がりました。
サンクスギビングデーに、食事を作って訪問した家で手渡しするというイベントを、ロータリークラブと地元警察が協力して行いました。貧困地域に行くのは危険なので、警官と一緒に食事を配っていきました。この経験で私は世界の不平等を実感しました。世界中の人々に平和をもたらすという私の思いは叶えられないと実感し、世界で一人でも多くの人に平和をもたらしたいという考えに変わりました。
ロータリーのトリップでは、同じ地区の派遣生とハイキングをしたり、国際会議を行ったりという研修を受けながら、さまざまなところに行きました。ナイアガラの滝では研修を全部忘れて楽しみました。ニューヨークトリップは二地区合同の大人数のトリップで、自由の女神、セントラルパーク、ブルックリンブリッジ、タイムズスクエアにも行きました。本当は最後の1か月間でディズニーワールドに行く予定でしたが、新型コロナの影響で実現しなかったのが本当に残念です。
私のホストファミリーは、私が空港に到着したとき、プラカードを持って待っていてくれました。ホストマザーは私を見つけると「れおなー!」と呼んでハグしてくれました。ひとりで15時間のフライトで寂しい思いをしていた私はうれし涙を必死でこらえました。
到着した日には家の玄関に国旗を飾ってくれていて、私を歓迎してくれているのだなとうれしい気持ちになりました。ホストファミリーの弟たちにはプレゼントした甚平で、日本の文化に初めて触れてもらいました。派遣生活から1ヶ月の記念日にはこの弟たちがケーキを作ってくれて本当にうれしく思いました。
しかし、ホストファミリーとの間に問題も少しありました。
ホストファーザーは、トランプ支持者で、私はちょっと怖いように感じました。アジアに対する考えや知識が乏しく、私に、中国の音楽を聴くのかとか韓国語を話すのかと尋ねてくるので、最初は困惑しました。でも派遣生活の最後の頃には、逆に私の方からホストファーザーに、スペイン語の曲を聞くのかと尋ねて、聞かないと言われると、私も一緒だよと対応できるようになりました。
ホストマザーはとても感情的で、料理をまったく作らない人でした。ピザか中華料理のデリバリーか、少し焼いた鶏むね肉というような食事でした。そこで、私は自分で料理したり、サラダを学校でのランチに持って行ったりしました。するとホストマザーに、自分が作るご飯が嫌いなのねとネガティブなことを言われたりしました。また、家族でディズニーワールドに行く計画では、私は別行動するように言われました。それがとても悲しかったので、勉強を理由に行くのをやめると伝えたところ、私を置き去りにしたと思われたくなかったのか、ロータリアンに私を批判する嘘の話をされたりしました。私一人ではどうにもならないと思い、日本のロータリアンの方に電話で相談したところ、自分でホストマザーと話して、どんな事があっても話し続けて解決するようにと、アドバイスをいただきました。ディズニーワールドから帰ってきたホストマザーに、私が傷ついたこと、でも大好きだから良い関係を保ちたいと率直に話しました。こうして分かり合い、今では良い関係を保っています。早期帰国が決まったときには、みんなが私との別れを惜しんでくれました。
日常生活でもいろいろな経験をしました。学校でのカウボーイデーという仮装、ロータリアンのお宅でのメキシカンタコスパーティ。成績優秀者のディーズリストにも選ばれました。ハロウィーンでお菓子を配ったり、スケートに連れて行ってもらったり、バレンタインデーにチョコや風船、ぬいぐるみをもらって喜んだり、いずれも楽しい思い出です。
今、私は大学生として活動しています。大学に入学した1年次に、この派遣生活が認められて特待生として奨学金をいただきました。また、大学1年の時の成績が学年でトップでしたので、今年も奨学金をいただいています。今の成績を残すことができたのも、皆さまからのご支援とサポートがあったおかげでございます。まだまだお話したいことはありますが、以上で私の帰国報告とさせていただきます。
ご清聴ありがとうございました。
卓話 「心をつかむコミュニケーション」
元フジテレビアナウンサー 河野景子さま
2022年7月28日

 皆様こんにちは。河野景子でございます。
今日は、「心をつかむコミュニケーション」というテーマでお話をさせていただきます。
私はロータリークラブとは縁が深く、父が宮崎ロータリークラブの会員でした。私が中学3年の時、アメリカからのロータリー交換留学生が我が家にホームステイしました。高校生だった留学生のテリーは、日本語も全くわからない上に規則だらけの日本の高校に馴染めず、ホームシックにかかってしまいました。ところが、高校では日本の学生が優しくテリーに接し、コミュニケーションが交わされて行きました。次第に彼女は日本の生活習慣を受け入れられるようになり、日本文化を学び、あっという間に日本語を話せるようになり、日本が大好きになったのです。たった1年で大きく成長した彼女の姿を目の当たりにした私は、同じ経験をしたいと強く思い、ロータリークラブの交換留学生として1年間アメリカニューヨーク州に留学しました。アメリカでは、それまで習ってきた受験英語が現地での英会話に応用できず意思疎通にかなり苦労しましたが、一つ一つ学び異文化交流の経験を積み、貴重な1年間を過ごすことができました。大学進学時は、アナウンサーになる夢を抱いていたのですが、私の話す宮崎のイントネーションが標準語とかなり違っていることに気づき、一時はアナウンサーへの夢は封印しようと思いました。しかし、両親に背中を押され、チャレンジしたフジテレビに運良く入社することができました。当時、私は海外の情報を伝えることでフランス駐在を希望していました。会社からは、アナウンサーのフランス駐在は前例がないと言われていたのですが、毎年、社員全員が提出するレポートに、構わずその希望を書き続けました。すると、1990年の湾岸戦争勃発を機に、東京・ニューヨーク・パリを結ぶ3元生中継のニュース番組が始まり、フジテレビパリ支局にアナウンサー第1号として派遣されることになったのです。こうした経験から、夢は口に出すことで一歩近づき、チャンスが巡ってくる、さらに運が良ければつかむことができると強く思うようになりました。
これまで、フジテレビアナウンサーとして、結婚して勝負師の妻として、相撲部屋の女将として経験を積み、多種多様な場面で活躍する様々な人たちとコミュニケーションを深めてきました。その経験から今日は皆さまにお話いたします。
コミュニケーションは、「伝える」「聞く」「共有する」この三つが整ってからこそ、うまく成立したと言えます。コミュニケーション能力が高い人とはどのような人でしょうか。もちろん話が上手な人ですが、正確に伝わるように言葉を選び表現できる人、聞く力が備わっていて言葉の裏で何を伝えようとしているかを汲み取ろうとする人、またそれらを共有できる人がコミュニケーション能力の高い人だと思います。コミュニケーションには言葉で伝える「言語化コミュニケーション」の他に、言葉に頼らず、表情や身振り手振りなどの仕草や声のトーン、間の取り方などを手段とした「非言語化コミュニケーション」があります。アメリカの心理学者アルバート・メラビアンの「メラビアンの法則」という面白い研究発表があります。初めて会う人の第一印象がどこで決まるかというものです。この研究発表によると、視覚から入る情報が55%、例えば、服装や姿勢やジェスチャー、顔の表情など視覚から入る情報です。そして声の調子や話すペース、声色などの聴覚情報が38%。言語情報はたったの7%です。第一印象は視覚・聴覚情報で93%、9割が決まるということなのです。本日私は、手振りジェスチャーも使い、声もしっかりと届くように意識してお話し致します。
さて、私たちがマスクで顔の3分の2を覆う生活を強いられて2年半が経ちました。必要がなければ人に会わず、会ったとしても大きな声で話すことができない生活を送ってきました。日本語は便利なもので、口をあまり開けなくても話せる言語です。ですからマスク生活で、顔の筋肉を十分に使わずに過ごしてきました。その影響で顔の表現力がすっかり乏しくなったと感じていませんか?正確な口の開け方を忘れ、滑舌よく話せない、声が出にくい、顔の表情がついこわばり言いたいことが上手く伝わらないという声を最近多く聞きます。大変なことに第一印象を93%も左右する大事な情報(視覚・聴覚情報)が発揮できなくなっているということです。
ご存知ですか?リラックスして口を閉じている時の舌の位置は、上顎の前歯の歯茎のあたりについているのが正しい位置ということを。舌の先端が口の真ん中にあるという方や下顎の中にあるという方は、舌の先端を上の歯につけようとすると大変だなと感じると思います。そういう方は舌の筋肉を鍛えるために、上下の歯の外側に沿って舌をぐるりと大きく左右に3回ずつ回す体操をしてみましょう。ついでに、ほうれい線と頬も内側から舌で押しましょう。この体操をすると舌の筋肉を鍛えることもできますし、同時に口の中に唾液が出てきます。唾液は口の中を清潔で健康に保つ効果があります。また、唾液がたくさん出ることで舌が滑らかに動きます。舌が滑らかに動くということは 聞き取りやすい話し方ができ、声に表現力をつけるためにも大事なことです。
マスクで隠していた顔の表情筋は、日本語の母音「あいうえお」を正しい口の開け方で発音することで鍛えられます。「あ」は指が縦に3本入るくらい口を開き、上の歯が見える状態で大きく開けます。「え」は指2本が入るくらい唇を左右に開き、口角を横に上げます。そうすると大頬骨筋、小頬骨筋というほうれい線をぐっと上げる筋肉が動きます。「い」はニコッと笑った時の口元です。指1本入るくらい唇を左右に開きます。口角をキュッとしっかりあげましょう。前歯が8本見えるくらい開けるのが理想的な笑顔の口元です。私がフランス駐在時代にインタビューさせていただいたオードリー・ヘップバーンさんは終始この「い」の口元でした。「あ」「え」「い」で左右に引き上げる筋肉を鍛えたら、口をすぼめる「お」と「う」の動きをして口輪筋も刺激します。母音で顔の筋肉を鍛えて表情豊かに表現できるように。発音を明瞭にするにはいろんな訓練方法がありますが、まずは舌の体操と口の開け方を意識することから始めてください。第一印象の93%を占める視覚情報と聴覚情報を発揮するために大きく役立ちます。
伝え方にも様々な方法がありますが、相手がイメージできるような実際のエピソード、例え話や数字を使って話を組み立てると効果的です。例えば、相撲の話をするとして、『本場所で十両以上の力士は土俵に塩を撒きます。本場所中はものすごく大量の塩を使います。』と話をしたとします。あら、皆さまの目の色が随分変わりましたね。具体的な数字を補足しましょう。本場所中、1日にどれだけの塩が必要かというと、なんと45キロです。1場所15日間ありますから、1場所で675キロ必要で、巡業も含めると日本相撲協会が年間に使う塩は約6トンだそうです。『大量の塩が必要だ』と伝えるだけよりも実際に数字を伝えるとより印象深くなりますよね。数字を用いるとイメージしやすく説得力を増す効果があります。コミュニケーションでは、このようにイメージしやすく分かりやすく伝えることもお互いの感情や情報を共有するためのテクニックとして大事です。
締めに、日本語の「結ぶ」という言葉の語源の話をさせてください。日本には様々な結ぶ文化があります。着物の紐や帯、髪結い、お弁当のおむすび、仲間同士の絆や男女間の契り、神社ではおみくじも結びます。漢字で「結」は糸へんに吉と書きますが、糸はずっとつながっていくという意味があります。つまり良いことがずっとつながっていくということが「結ぶ」という漢字の語源になります。次に、「結ぶ=むす・ぶ」ひらがなで語源を調べてみますと、「むす」=「生す」「産す」「蒸す」とも書きます。生命が宿る、生きるという意味です。「むす・こ」「むす・め」も同じ語源から派生した言葉です。「ぶ」は日本神話のタカムスヒノカミ、カミムスヒノカミの「ヒ」からきているそうで、「ヒ」が活用して「ぶ」になっているそうです。意味は、生命を生み出す神秘的な力・神聖な霊力。そう読み解くと「結ぶ」という言葉は、「神秘的な何かが生まれ、永続的につながっていく」という深い意味があると理解できます。
「結ぶ」を英語にするとなんでしょう。「connect」が適していると思います。「connect」と同じ語源の言葉にcommunicationがあります。コミュニケーションは人の心と心を繋げ、コネクトしていきます。どちらも語源は一緒で、共有し、結ばれ、つながっていくということ。心をつかむ良いコミュニケーションを重ねていくと、何か神秘的な力が生まれると感じませんか?
本日の私の話は、皆様の心をつかむことができましたでしょうか。
ありがとうございました。
皆様こんにちは。河野景子でございます。
今日は、「心をつかむコミュニケーション」というテーマでお話をさせていただきます。
私はロータリークラブとは縁が深く、父が宮崎ロータリークラブの会員でした。私が中学3年の時、アメリカからのロータリー交換留学生が我が家にホームステイしました。高校生だった留学生のテリーは、日本語も全くわからない上に規則だらけの日本の高校に馴染めず、ホームシックにかかってしまいました。ところが、高校では日本の学生が優しくテリーに接し、コミュニケーションが交わされて行きました。次第に彼女は日本の生活習慣を受け入れられるようになり、日本文化を学び、あっという間に日本語を話せるようになり、日本が大好きになったのです。たった1年で大きく成長した彼女の姿を目の当たりにした私は、同じ経験をしたいと強く思い、ロータリークラブの交換留学生として1年間アメリカニューヨーク州に留学しました。アメリカでは、それまで習ってきた受験英語が現地での英会話に応用できず意思疎通にかなり苦労しましたが、一つ一つ学び異文化交流の経験を積み、貴重な1年間を過ごすことができました。大学進学時は、アナウンサーになる夢を抱いていたのですが、私の話す宮崎のイントネーションが標準語とかなり違っていることに気づき、一時はアナウンサーへの夢は封印しようと思いました。しかし、両親に背中を押され、チャレンジしたフジテレビに運良く入社することができました。当時、私は海外の情報を伝えることでフランス駐在を希望していました。会社からは、アナウンサーのフランス駐在は前例がないと言われていたのですが、毎年、社員全員が提出するレポートに、構わずその希望を書き続けました。すると、1990年の湾岸戦争勃発を機に、東京・ニューヨーク・パリを結ぶ3元生中継のニュース番組が始まり、フジテレビパリ支局にアナウンサー第1号として派遣されることになったのです。こうした経験から、夢は口に出すことで一歩近づき、チャンスが巡ってくる、さらに運が良ければつかむことができると強く思うようになりました。
これまで、フジテレビアナウンサーとして、結婚して勝負師の妻として、相撲部屋の女将として経験を積み、多種多様な場面で活躍する様々な人たちとコミュニケーションを深めてきました。その経験から今日は皆さまにお話いたします。
コミュニケーションは、「伝える」「聞く」「共有する」この三つが整ってからこそ、うまく成立したと言えます。コミュニケーション能力が高い人とはどのような人でしょうか。もちろん話が上手な人ですが、正確に伝わるように言葉を選び表現できる人、聞く力が備わっていて言葉の裏で何を伝えようとしているかを汲み取ろうとする人、またそれらを共有できる人がコミュニケーション能力の高い人だと思います。コミュニケーションには言葉で伝える「言語化コミュニケーション」の他に、言葉に頼らず、表情や身振り手振りなどの仕草や声のトーン、間の取り方などを手段とした「非言語化コミュニケーション」があります。アメリカの心理学者アルバート・メラビアンの「メラビアンの法則」という面白い研究発表があります。初めて会う人の第一印象がどこで決まるかというものです。この研究発表によると、視覚から入る情報が55%、例えば、服装や姿勢やジェスチャー、顔の表情など視覚から入る情報です。そして声の調子や話すペース、声色などの聴覚情報が38%。言語情報はたったの7%です。第一印象は視覚・聴覚情報で93%、9割が決まるということなのです。本日私は、手振りジェスチャーも使い、声もしっかりと届くように意識してお話し致します。
さて、私たちがマスクで顔の3分の2を覆う生活を強いられて2年半が経ちました。必要がなければ人に会わず、会ったとしても大きな声で話すことができない生活を送ってきました。日本語は便利なもので、口をあまり開けなくても話せる言語です。ですからマスク生活で、顔の筋肉を十分に使わずに過ごしてきました。その影響で顔の表現力がすっかり乏しくなったと感じていませんか?正確な口の開け方を忘れ、滑舌よく話せない、声が出にくい、顔の表情がついこわばり言いたいことが上手く伝わらないという声を最近多く聞きます。大変なことに第一印象を93%も左右する大事な情報(視覚・聴覚情報)が発揮できなくなっているということです。
ご存知ですか?リラックスして口を閉じている時の舌の位置は、上顎の前歯の歯茎のあたりについているのが正しい位置ということを。舌の先端が口の真ん中にあるという方や下顎の中にあるという方は、舌の先端を上の歯につけようとすると大変だなと感じると思います。そういう方は舌の筋肉を鍛えるために、上下の歯の外側に沿って舌をぐるりと大きく左右に3回ずつ回す体操をしてみましょう。ついでに、ほうれい線と頬も内側から舌で押しましょう。この体操をすると舌の筋肉を鍛えることもできますし、同時に口の中に唾液が出てきます。唾液は口の中を清潔で健康に保つ効果があります。また、唾液がたくさん出ることで舌が滑らかに動きます。舌が滑らかに動くということは 聞き取りやすい話し方ができ、声に表現力をつけるためにも大事なことです。
マスクで隠していた顔の表情筋は、日本語の母音「あいうえお」を正しい口の開け方で発音することで鍛えられます。「あ」は指が縦に3本入るくらい口を開き、上の歯が見える状態で大きく開けます。「え」は指2本が入るくらい唇を左右に開き、口角を横に上げます。そうすると大頬骨筋、小頬骨筋というほうれい線をぐっと上げる筋肉が動きます。「い」はニコッと笑った時の口元です。指1本入るくらい唇を左右に開きます。口角をキュッとしっかりあげましょう。前歯が8本見えるくらい開けるのが理想的な笑顔の口元です。私がフランス駐在時代にインタビューさせていただいたオードリー・ヘップバーンさんは終始この「い」の口元でした。「あ」「え」「い」で左右に引き上げる筋肉を鍛えたら、口をすぼめる「お」と「う」の動きをして口輪筋も刺激します。母音で顔の筋肉を鍛えて表情豊かに表現できるように。発音を明瞭にするにはいろんな訓練方法がありますが、まずは舌の体操と口の開け方を意識することから始めてください。第一印象の93%を占める視覚情報と聴覚情報を発揮するために大きく役立ちます。
伝え方にも様々な方法がありますが、相手がイメージできるような実際のエピソード、例え話や数字を使って話を組み立てると効果的です。例えば、相撲の話をするとして、『本場所で十両以上の力士は土俵に塩を撒きます。本場所中はものすごく大量の塩を使います。』と話をしたとします。あら、皆さまの目の色が随分変わりましたね。具体的な数字を補足しましょう。本場所中、1日にどれだけの塩が必要かというと、なんと45キロです。1場所15日間ありますから、1場所で675キロ必要で、巡業も含めると日本相撲協会が年間に使う塩は約6トンだそうです。『大量の塩が必要だ』と伝えるだけよりも実際に数字を伝えるとより印象深くなりますよね。数字を用いるとイメージしやすく説得力を増す効果があります。コミュニケーションでは、このようにイメージしやすく分かりやすく伝えることもお互いの感情や情報を共有するためのテクニックとして大事です。
締めに、日本語の「結ぶ」という言葉の語源の話をさせてください。日本には様々な結ぶ文化があります。着物の紐や帯、髪結い、お弁当のおむすび、仲間同士の絆や男女間の契り、神社ではおみくじも結びます。漢字で「結」は糸へんに吉と書きますが、糸はずっとつながっていくという意味があります。つまり良いことがずっとつながっていくということが「結ぶ」という漢字の語源になります。次に、「結ぶ=むす・ぶ」ひらがなで語源を調べてみますと、「むす」=「生す」「産す」「蒸す」とも書きます。生命が宿る、生きるという意味です。「むす・こ」「むす・め」も同じ語源から派生した言葉です。「ぶ」は日本神話のタカムスヒノカミ、カミムスヒノカミの「ヒ」からきているそうで、「ヒ」が活用して「ぶ」になっているそうです。意味は、生命を生み出す神秘的な力・神聖な霊力。そう読み解くと「結ぶ」という言葉は、「神秘的な何かが生まれ、永続的につながっていく」という深い意味があると理解できます。
「結ぶ」を英語にするとなんでしょう。「connect」が適していると思います。「connect」と同じ語源の言葉にcommunicationがあります。コミュニケーションは人の心と心を繋げ、コネクトしていきます。どちらも語源は一緒で、共有し、結ばれ、つながっていくということ。心をつかむ良いコミュニケーションを重ねていくと、何か神秘的な力が生まれると感じませんか?
本日の私の話は、皆様の心をつかむことができましたでしょうか。
ありがとうございました。
卓話 「アジアの高齢化とビジネスチャンス」
持続可能な開発のためのグローバルパートナーズ代表
元 公益財団法人アジア人口・開発協会(APDA)事務局長・業務執行理事(常務理事)楠本修さま
2022年7月14日

 ご紹介ありがとうございます。
私は32年間公益財団法人アジア人口・開発協会(APDA)で、人口と開発に関する国会議員活動を支援してきました。アフリカ・アラブの議連に関しては、当時、人口と開発に関するアジア議員フォーラム(AFPPD)議長であった桜井新議員の補佐を務めていたことから、その立ち上げからかかわり、今なお密接な関係が続いています。退任に際しては色々な形で高く評価していただきました。
日本は持続可能な開発分野にその当初から深くかかわってきました。SDGsの基になっている“持続可能な開発”という概念は、国際人口問題議員懇談会(JPFP)の会長を務めていた福田赳夫元総理が国連の日本政府代表部を通じて1984年にその設立を働きかけた国連のブルントラント委員会で確立した概念です。このことはほとんど知られていません。日本は自分たちの成果を宣伝することが下手ですね。
私も1994年の国際人口開発会議(ICPD)に先駆けて開催された国際人口開発議員会議(ICPPD)の宣言文の起草を担当するなど、かなり早い時期からその形成に関わりました。SDGsの概念形成にそれなりに貢献できたことを大変誇りに思っています。
実はSDGsはいろいろと矛盾する概念を寄せ集めています。議員活動の事務局として、この問題を解消するために呻吟してきたのですが、SDGsがそれをまとめる際にそのことを見事に棚上げにしたことに驚きました。
例えば「人権」を誰でも大事だといいますが、世界中どこにも定義がありません。そして戦争でも起これば簡単に踏みにじられます。アメリカ最高裁判決が世界的な話題になっていますが「中絶権」の問題もその一部です。私自身、中絶を人権とするという考え方には疑問を抱き、1994年以来長年この問題を考え続けました。2019年に「人権」の定義づけを行う過程で自分なりに答えが出ました。そして喜んでいたのですが、お釈迦さまが2500年も前にすでに考えられていたことを再発見しました。さすがお釈迦様ですね。
このような形で国会議員の人口と開発に関する活動の理論的基盤を提供することが私の主な仕事でした。
先日亡くなられた安倍晋三先生とも1995年の世界社会開発サミットに合わせて開催された議員会議に1週間ほど同行し、安倍先生のお人柄に触れることができました。今回の事件で惜しくも亡くなられましたが、世界的に見たときその殺害理由が理解できないであろうと考え、日本に対する誤解を避けたいと思い国連関係の通信社を通じて、弔意を世界中に配信させていただきました。
今日のテーマは“アジアの高齢化とビジネスチャンス”です。高齢化は現代の典型的な人口問題です。人口をどう理解したらよいかはなかなか難問ですが、端的に言えば、人口が急速に増えるのも減るのも困ります。安定、すなわち増加も減少もない状態が一番よいのです。持続可能な開発を実現するためには人口の安定が不可欠ですが、それは人口転換という過程を通じて実現されます。高齢化はその結果としてどうしても生じてしまう現象です。これらの課題に対応するために、人口問題の全体像を理解する必要が出てきます。これまでの議論をまとめたものをこの秋に「時潮社」から出版します。宣伝になりますが、機会がありましたら是非お読みください。
人口問題は数字で表されますが、その一つの数字は一人の人間のかけがえない人生を表していることを最初にご理解いただきたいと思います。つまり人口は社会そのものだといえます。世界では毎年1億2000万人くらいの子供が生まれていますが、そのうち3000万人くらいは望まれない妊娠の結果として生まれています。10年で3億人の人が望まれない形で生まれているわけで、子供に対する投資はされず、虐待や人身売買や援助交際や売春につながる可能性があります。これは世界だけでなく、日本でも問題かと思います。人口問題はひとりひとりの人生にかかわることだと想像すること、数字の後ろにある現実に思いをはせること、RIジョーンズ会長のおっしゃる通りイマジンすることが大切だと思います。
7月13日の日本経済新聞一面に“世界人口の増加率が1%を切った、世界経済の転換期”という記事が掲載されました。私はショックを受けました。経済成長1%といえば低成長のように感じますが、人口の場合、1%の増加率とは約70年で人口が倍増するということです。一人一人の豊かな生活を維持しながら、どうやってこの地球上で暮らしていけるのかという疑問が生まれてきます。私の師匠である黒田俊夫は人口増加率を1%以下に抑えることができれば、人類は持続可能な開発を達成できる可能性があると話していました。
日本では少子化の問題を捉えて、かつてのようなピラミッド型の人口構造を作らないと日本が成り立たないという議論がありますが、これは明らかに間違いです。かつては人口転換の中で生じる特殊な状況のなかで若者を安く使え、過剰な負担をかけることができた時代だったのです。経済発展に伴って人口は変化しますが、逆に経済のために人口を変化させることに成功した試しはありません。これは人類史の鉄則とも言えます。
子どもが欲しいカップルが子どもを持てるようすることは重要です。しかし、それがこれまでうまくいった経済システムを守るために必要だという議論は本末転倒です。人口と経済の関係から言えば、現在の人口を与件としてどのような社会をつくるかを考えていくしかありません。
人口問題には実は出生と死亡の2つの要素しかありません。そして持続可能な開発を達成するためには、この地球環境を壊さないことが不可欠です。その意味で人口の安定化への努力がその前提となり、そのうえで人口構造を踏まえた上で人口の変動に合わせたビジネスモデルを作るしかありません。日本は、その意味から考えると、世界の先行事例です。その優位性をいかしたモデルと作るかを考えていくことができれば、日本に勝機があると思います。
人口の高齢化は、多産多死から少産少死への移行、すなわち人口転換に伴って起こります。日本では、高齢化率が7%から14%に増加するのにかかった期間はわずか24年間です。ちなみに、フランスでは126年かかっています。アジアでは高齢化のスピードが速く、あと10年か15年で日本と同じ、あるいはそれ以上に深刻な高齢化の問題を抱えることになりそうです。人口転換の速さが速ければ、高齢化への移行も速く進みます。これからビジネスを考える場合でも、人口が増えていけばなんとかなるという幻想は捨てなければなりません。
高齢化のビジネスチャンスについては、日本の経験を活用することが必要です。しかしそこでは先行者利益をいかにとるかが課題となりますが、ことはそう簡単ではありません。先行者利益が取れる業界はオリジナリティのあるビジネスを開発してそれを知的所有権などで囲い込むことが出来る業界だけです。そのほかのビジネスでは、先行者の知識をほとんどただ乗りで使える後発者が利益をとってしまうのです。では、この中で日本はどうやって利益を得ていくか。これが本日の主題となります。
現実的に考えると次から次へと、他が追いつかないほど質が高く、安いものを生産するしかありません。ただ、このことは、あまりネガティブに考える必要もないと思います。日本政府はグローバリズムという視点から、医療産業などで利益を得ようと考えています。しかし、囲い込んで、特許で儲かるかというとなかなか難しいようです。先行者利益と後発者利益の関係は、ビジネスを考える場合に重要なポイントですので、覚えておいていただければと思います。
もう一点、学問と政治、政策、経営に関する話になります。学問的に考えて矛盾があっても成功するということはまずありません。人口も同じで、人口の変化を踏まえないビジネスは成功しないでしょう。つまり人口や学問の成果を無視して成功することはないということです。しかしながら、どうしたら上手くいくかは、センスや勘次第になります。松下幸之助が、経営学は教えられるけど、経営は教えられないと嘆いていたという話がありますが、それと同じです。
人口というものを理解しても成功するかはわかりませんが、ただそれを踏まえておかないと長期的にはマーケットを見失い、確実に失敗します。従って、人口を考慮に入れておくということは、それを知らないのに比べれば長期の企業戦略などを考える場合に段違いに有利な状況を生み出しうると思っています。
高齢化ビジネスについて一つだけ例をあげて、お話を終わりにしたいと思います。
高齢の義母を東京に呼び寄せた際に、介護のために住宅を改造する必要がありました。その際、普通の扉だと重くて開けられませんでしたが、それを吊り金具にするだけで扉の開け閉めが軽くできるようになりました。
その経験から言えば、マンションを建てる時に最初から逆梁工法を基本にして建築し、住居に最初から吊り金具をパッケージングしておくというアイデアはいかがでしょうか。そうすれば費用もあまりかからず介護が簡単にできるようになると思います。
具体的には、吊り金具で各部屋から廊下をつなぎ、ベッドをエレベーターまで運べるようにすれば一人でも軽く運べます。そうすれば大規模マンションで高齢化が進んでいったときに、それを改装して高齢者用マンションとすることが容易になります。そのような基本的な設計や設備があれば、介護が必要になった時は介護ベッドが簡単に運び込めます。
そのような無理のない使い方ができるような工夫をしておくという考え方です。そうすれば各国で高齢化対策を行う際に、規模の経済が活用できます。日本における今後の市場としても同じことが言えますが、アジアで高齢化ビジネスを展開する際には、いかに少ない負担で、メリットを増やすことができるか、ということを考え、それらをパッケージにして売り込むことが必要なのではないかと思います。
今日は、時間的な制約もあり具体的な話にはなかなかつながりませんでしたが、基本的な考え方はお伝え出来たのではないかと思います。
ご静聴ありがとうございました。
質疑応答
Q:先生のお考えでは、現在の日本の経済や日本の在り方から、日本の人口は何人が正しいと思っていますか。
A:レスター・ブラウンは、世界の人口が何人くらいが良いかは、あなたの希望する生活水準次第だと答えています。日本の人口に関しても同じだと思いますが、現実的に考えて江戸時代の人口である3000万人程度までであれば扶養できます。まったく環境破壊をしないで人間という種が地球という生態系の中で存在できる人口規模は1000万人が限界だと言われています。つまりとっくに超えてしまっているのです。その中で今の豊かな生活を維持できる社会を作っていけるか。どうやって他人の命を尊重できるか、この点がまさにロータリーの目標である“久遠の平和”を作るために重要だと思っています。
少子化との関係でいうと、AIの活用が進むと、労働力は無意味化するかもしれません。一番労働生産性の高い場所は人がほとんどいないAMAZONの倉庫です。それでは雇用につながらず、人間が食べていくことができないので、何のための生産性かわからなくなりつつあります。その意味では生産性という概念そのものを見直す必要が出てきていると思います。
しかし、間違いなく言えることは、未来を創るのは若者だということです。その意味では若者を鍛え上げる必要があります。目標設定ができるのは人間だけなのです。大学ではAIに使われる人生は、AIより安い仕事しかないということで面白くないよ、AIを使う人生を送れるように努力してほしいと日ごろから檄を飛ばしています。
ありがとうございました。
ご紹介ありがとうございます。
私は32年間公益財団法人アジア人口・開発協会(APDA)で、人口と開発に関する国会議員活動を支援してきました。アフリカ・アラブの議連に関しては、当時、人口と開発に関するアジア議員フォーラム(AFPPD)議長であった桜井新議員の補佐を務めていたことから、その立ち上げからかかわり、今なお密接な関係が続いています。退任に際しては色々な形で高く評価していただきました。
日本は持続可能な開発分野にその当初から深くかかわってきました。SDGsの基になっている“持続可能な開発”という概念は、国際人口問題議員懇談会(JPFP)の会長を務めていた福田赳夫元総理が国連の日本政府代表部を通じて1984年にその設立を働きかけた国連のブルントラント委員会で確立した概念です。このことはほとんど知られていません。日本は自分たちの成果を宣伝することが下手ですね。
私も1994年の国際人口開発会議(ICPD)に先駆けて開催された国際人口開発議員会議(ICPPD)の宣言文の起草を担当するなど、かなり早い時期からその形成に関わりました。SDGsの概念形成にそれなりに貢献できたことを大変誇りに思っています。
実はSDGsはいろいろと矛盾する概念を寄せ集めています。議員活動の事務局として、この問題を解消するために呻吟してきたのですが、SDGsがそれをまとめる際にそのことを見事に棚上げにしたことに驚きました。
例えば「人権」を誰でも大事だといいますが、世界中どこにも定義がありません。そして戦争でも起これば簡単に踏みにじられます。アメリカ最高裁判決が世界的な話題になっていますが「中絶権」の問題もその一部です。私自身、中絶を人権とするという考え方には疑問を抱き、1994年以来長年この問題を考え続けました。2019年に「人権」の定義づけを行う過程で自分なりに答えが出ました。そして喜んでいたのですが、お釈迦さまが2500年も前にすでに考えられていたことを再発見しました。さすがお釈迦様ですね。
このような形で国会議員の人口と開発に関する活動の理論的基盤を提供することが私の主な仕事でした。
先日亡くなられた安倍晋三先生とも1995年の世界社会開発サミットに合わせて開催された議員会議に1週間ほど同行し、安倍先生のお人柄に触れることができました。今回の事件で惜しくも亡くなられましたが、世界的に見たときその殺害理由が理解できないであろうと考え、日本に対する誤解を避けたいと思い国連関係の通信社を通じて、弔意を世界中に配信させていただきました。
今日のテーマは“アジアの高齢化とビジネスチャンス”です。高齢化は現代の典型的な人口問題です。人口をどう理解したらよいかはなかなか難問ですが、端的に言えば、人口が急速に増えるのも減るのも困ります。安定、すなわち増加も減少もない状態が一番よいのです。持続可能な開発を実現するためには人口の安定が不可欠ですが、それは人口転換という過程を通じて実現されます。高齢化はその結果としてどうしても生じてしまう現象です。これらの課題に対応するために、人口問題の全体像を理解する必要が出てきます。これまでの議論をまとめたものをこの秋に「時潮社」から出版します。宣伝になりますが、機会がありましたら是非お読みください。
人口問題は数字で表されますが、その一つの数字は一人の人間のかけがえない人生を表していることを最初にご理解いただきたいと思います。つまり人口は社会そのものだといえます。世界では毎年1億2000万人くらいの子供が生まれていますが、そのうち3000万人くらいは望まれない妊娠の結果として生まれています。10年で3億人の人が望まれない形で生まれているわけで、子供に対する投資はされず、虐待や人身売買や援助交際や売春につながる可能性があります。これは世界だけでなく、日本でも問題かと思います。人口問題はひとりひとりの人生にかかわることだと想像すること、数字の後ろにある現実に思いをはせること、RIジョーンズ会長のおっしゃる通りイマジンすることが大切だと思います。
7月13日の日本経済新聞一面に“世界人口の増加率が1%を切った、世界経済の転換期”という記事が掲載されました。私はショックを受けました。経済成長1%といえば低成長のように感じますが、人口の場合、1%の増加率とは約70年で人口が倍増するということです。一人一人の豊かな生活を維持しながら、どうやってこの地球上で暮らしていけるのかという疑問が生まれてきます。私の師匠である黒田俊夫は人口増加率を1%以下に抑えることができれば、人類は持続可能な開発を達成できる可能性があると話していました。
日本では少子化の問題を捉えて、かつてのようなピラミッド型の人口構造を作らないと日本が成り立たないという議論がありますが、これは明らかに間違いです。かつては人口転換の中で生じる特殊な状況のなかで若者を安く使え、過剰な負担をかけることができた時代だったのです。経済発展に伴って人口は変化しますが、逆に経済のために人口を変化させることに成功した試しはありません。これは人類史の鉄則とも言えます。
子どもが欲しいカップルが子どもを持てるようすることは重要です。しかし、それがこれまでうまくいった経済システムを守るために必要だという議論は本末転倒です。人口と経済の関係から言えば、現在の人口を与件としてどのような社会をつくるかを考えていくしかありません。
人口問題には実は出生と死亡の2つの要素しかありません。そして持続可能な開発を達成するためには、この地球環境を壊さないことが不可欠です。その意味で人口の安定化への努力がその前提となり、そのうえで人口構造を踏まえた上で人口の変動に合わせたビジネスモデルを作るしかありません。日本は、その意味から考えると、世界の先行事例です。その優位性をいかしたモデルと作るかを考えていくことができれば、日本に勝機があると思います。
人口の高齢化は、多産多死から少産少死への移行、すなわち人口転換に伴って起こります。日本では、高齢化率が7%から14%に増加するのにかかった期間はわずか24年間です。ちなみに、フランスでは126年かかっています。アジアでは高齢化のスピードが速く、あと10年か15年で日本と同じ、あるいはそれ以上に深刻な高齢化の問題を抱えることになりそうです。人口転換の速さが速ければ、高齢化への移行も速く進みます。これからビジネスを考える場合でも、人口が増えていけばなんとかなるという幻想は捨てなければなりません。
高齢化のビジネスチャンスについては、日本の経験を活用することが必要です。しかしそこでは先行者利益をいかにとるかが課題となりますが、ことはそう簡単ではありません。先行者利益が取れる業界はオリジナリティのあるビジネスを開発してそれを知的所有権などで囲い込むことが出来る業界だけです。そのほかのビジネスでは、先行者の知識をほとんどただ乗りで使える後発者が利益をとってしまうのです。では、この中で日本はどうやって利益を得ていくか。これが本日の主題となります。
現実的に考えると次から次へと、他が追いつかないほど質が高く、安いものを生産するしかありません。ただ、このことは、あまりネガティブに考える必要もないと思います。日本政府はグローバリズムという視点から、医療産業などで利益を得ようと考えています。しかし、囲い込んで、特許で儲かるかというとなかなか難しいようです。先行者利益と後発者利益の関係は、ビジネスを考える場合に重要なポイントですので、覚えておいていただければと思います。
もう一点、学問と政治、政策、経営に関する話になります。学問的に考えて矛盾があっても成功するということはまずありません。人口も同じで、人口の変化を踏まえないビジネスは成功しないでしょう。つまり人口や学問の成果を無視して成功することはないということです。しかしながら、どうしたら上手くいくかは、センスや勘次第になります。松下幸之助が、経営学は教えられるけど、経営は教えられないと嘆いていたという話がありますが、それと同じです。
人口というものを理解しても成功するかはわかりませんが、ただそれを踏まえておかないと長期的にはマーケットを見失い、確実に失敗します。従って、人口を考慮に入れておくということは、それを知らないのに比べれば長期の企業戦略などを考える場合に段違いに有利な状況を生み出しうると思っています。
高齢化ビジネスについて一つだけ例をあげて、お話を終わりにしたいと思います。
高齢の義母を東京に呼び寄せた際に、介護のために住宅を改造する必要がありました。その際、普通の扉だと重くて開けられませんでしたが、それを吊り金具にするだけで扉の開け閉めが軽くできるようになりました。
その経験から言えば、マンションを建てる時に最初から逆梁工法を基本にして建築し、住居に最初から吊り金具をパッケージングしておくというアイデアはいかがでしょうか。そうすれば費用もあまりかからず介護が簡単にできるようになると思います。
具体的には、吊り金具で各部屋から廊下をつなぎ、ベッドをエレベーターまで運べるようにすれば一人でも軽く運べます。そうすれば大規模マンションで高齢化が進んでいったときに、それを改装して高齢者用マンションとすることが容易になります。そのような基本的な設計や設備があれば、介護が必要になった時は介護ベッドが簡単に運び込めます。
そのような無理のない使い方ができるような工夫をしておくという考え方です。そうすれば各国で高齢化対策を行う際に、規模の経済が活用できます。日本における今後の市場としても同じことが言えますが、アジアで高齢化ビジネスを展開する際には、いかに少ない負担で、メリットを増やすことができるか、ということを考え、それらをパッケージにして売り込むことが必要なのではないかと思います。
今日は、時間的な制約もあり具体的な話にはなかなかつながりませんでしたが、基本的な考え方はお伝え出来たのではないかと思います。
ご静聴ありがとうございました。
質疑応答
Q:先生のお考えでは、現在の日本の経済や日本の在り方から、日本の人口は何人が正しいと思っていますか。
A:レスター・ブラウンは、世界の人口が何人くらいが良いかは、あなたの希望する生活水準次第だと答えています。日本の人口に関しても同じだと思いますが、現実的に考えて江戸時代の人口である3000万人程度までであれば扶養できます。まったく環境破壊をしないで人間という種が地球という生態系の中で存在できる人口規模は1000万人が限界だと言われています。つまりとっくに超えてしまっているのです。その中で今の豊かな生活を維持できる社会を作っていけるか。どうやって他人の命を尊重できるか、この点がまさにロータリーの目標である“久遠の平和”を作るために重要だと思っています。
少子化との関係でいうと、AIの活用が進むと、労働力は無意味化するかもしれません。一番労働生産性の高い場所は人がほとんどいないAMAZONの倉庫です。それでは雇用につながらず、人間が食べていくことができないので、何のための生産性かわからなくなりつつあります。その意味では生産性という概念そのものを見直す必要が出てきていると思います。
しかし、間違いなく言えることは、未来を創るのは若者だということです。その意味では若者を鍛え上げる必要があります。目標設定ができるのは人間だけなのです。大学ではAIに使われる人生は、AIより安い仕事しかないということで面白くないよ、AIを使う人生を送れるように努力してほしいと日ごろから檄を飛ばしています。
ありがとうございました。
卓話 「玉川上水の世界遺産化について」
駒澤大学名誉教授 近藤禎夫さま
2022年6月23日
 本日はお招きいただき有難うございます。
今日の話は、川柳でいうなら「噺家は見てきたような嘘を言い」というように、話は半分嘘だと思って聞いていただきたいと思います。
今日の東京は1200~1300万人の膨大な人口を抱える都市ですが、京都を差し置いて東京が首都になったのは、400年前に徳川家康が江戸に来て、人が生きるために必要な水の供給がうまくいったためです。 現在、東京都の保有水源量は1日680万立方メートル、消費水量が平均460~470万立方メートルと、多少余裕があります。現在の東京都の水道は利根川と荒川から約8割、残りの17,18%が多摩川水系からですが、多摩川の水は利根川と荒川が厳しい時に補強するという役割を持っています。
なぜ玉川上水が世界遺産としてふさわしいかという問題の歴史と意義についてお話いたします。それは、18世紀以前は玉川上水の給水技術が世界で最も優れていたという点です。
まず、江戸初期の街づくりについてお話していきます。資料でお渡しした約400年前の江戸の姿の図面をご覧いただくとお分かりのように、江戸城のすぐ下まで海で、浅草のあたりもほとんど湿地帯で人が住めないような場所でした。家康が来る前は、江戸重継の館があり、一帯が江戸の郷というわけで、江戸という名前はこの地名、人名から来ています。
家康がこんな不便な江戸に来たのは、豊臣秀吉が実力者の家康を目障りに感じ、遠くの辺鄙なところへ追いやったからではないかと思います。幕府の候補に鎌倉・小田原も上りましたが、江戸は関東平野にあり、発展の余地があると考えて街づくりをしたのが家康です。家康は江戸城の下に道三堀を作り、その掘った土で丸の内や八重洲の埋め立てを行いました。また慶長8年(1603)頃には江戸城の北部の神田山(今の駿河台)を掘り崩して、日本橋、京橋、新橋のあたりの城下町の整備を進めていきました。
なお幕末の絵図でわかるように、現在の浅草仲見世のあたりは、全部お寺でした。このお寺の境内の横で、掃除をするという約束で茶店を出せるようにしたのが仲見世の始まりです。徳川幕府は、今の人形町2丁目、3丁目にあった吉原の遊郭を、街づくりの邪魔であり風紀上良くないということで、浅草の観音様の裏に新吉原として移転させました。その後、観音様の裏手に芝居小屋ができ、芝居小屋ができると茶店、料亭ができて芸者がいるようになるという形で、浅草寺の近辺は発展してきました。
18世紀の頃には江戸は人口100万人の大都市でした。当時のロンドンが87万人、パリが55万人ですから、江戸が巨大な都市であったことが分かると思います。ただ、土地の7割以上は武家屋敷、1割がお寺が占めており、残りのわずかな1割弱のところに町人がひしめいて暮らしていました。
江戸初期の上水道開削についてお話いたします。人の生活のために必要な水ですが、飲み水と灌漑用の用水と生活用水として使われる上水の二種類の水がありました。江戸で初めて引かれた上水が、日本の都市水道の始まりといわれています。徳川家康が、湿地帯の江戸では井戸を掘っても海水の塩分で飲めないため、家来の大久保藤五郎忠行という家来に水源を探すように命じました。大久保は三河一向一揆のときに鉄砲の弾に当たって侍として働けなくなり、幕府御用の菓子づくりになりました。水の吟味に一家言あった大久保が見つけたのが井の頭池の湧水です。井の頭の池から下ってきたのが小石川上水や神田上水になりました。しかし、江戸の人口が増えるとこれらの上水も濁ってきたために、他の上水道が必要になりました。そこで開削が行われたのが玉川上水です。
玉川上水の開削にあたっては、承応元年(1652)に工事の総奉行として老中・松平信綱(川越藩主)、取締奉行に伊那忠治が任命され、実際の工事は庄右衛門と清右衛門の二人の兄弟が請け負いました。
多摩川の取水堰の羽村から江戸まで上水を引く工事は難航し、第一案、第二案が失敗し、庄右衛門兄弟による第三案の工法が実施されました。この工法では、水質の汚染を恐れて川べりを高く築いたために工事費がかさみ、途中で幕府からの資金が底をつきました。庄右衛門兄弟は自分たちの屋敷や私財を投げ打って、羽村から四谷大木戸間の工事を完成させました。この功績により、幕府から玉川という姓を賜り200石取りになりました。世襲制で水の管理を行っていましたが、1700年代に職務怠慢、不正の疑いで職を解かれました。これは濡れ衣で、幕府が財政として水利の利権を得るために理屈をつけてクビにしたようです。
この上水は、羽村から四谷大木戸まで約43キロの距離を落差92メートルという自然の高低差を利用して江戸まで水を引いたものです。上水の管理は厳しく行われ、洗い物、魚釣り、水浴び、ごみ捨てはご法度でした。水路の両側に約5メートルの保護地帯を設けて樹木を植え、立ち入りも厳しく管理しました。上水沿いに山桜を植えて花見客に歩いてもらって土を踏み固めさせたのが、上水沿いの今の小金井の桜の名残だと言われています。
給水管の木の樋などはどうしても腐ってしまったり汚物が混入する可能性があるので、腐蝕の改修費は武家と町人にそれぞれ石高や小間割りに応じて負担させました。
玉川上水は給水管が江戸市中に及び世界遺産にふさわしい優れた先見性と江戸のエコ社会についてお話いたします。江戸の場合は自然流下式でした。一方、フランス・パリの場合は19世紀にナポレオン3世が大改革を行うまで、蒸気機関が無かったために自然流水で汚れた水を使っていました。公衆トイレもなかったために、絵に残っているようにチュイルリー宮殿の茂みのあたりで紳士が排泄しているような汚い街でした。蒸気機関を使って上流で水を汲み上げて配水するようになって、ようやく飲用の水が使えるようになったと言われています。
江戸では、チリ紙交換のように、捨てた紙を集めてトイレ用の紙に再生していました。長屋や武家屋敷から出る排泄物はすべて汲み取って農地に肥料として撒いていました。すべて有機物として利用したために無駄がありません。また濠を作るために堀った土は深川や木場の埋め立てに使うなど、すべて清潔と廃棄物処理が徹底したエコ社会でした。日本人は古代から穢れ、汚れに対して非常に潔癖です。そのため、訪れる外国人が驚くほど日本人は長い間きれい好きで通ってきたのです。
このような歴史をもつ玉川上水を世界遺産にする活動には、世田谷南クラブの建築家天野彰さんが非常に熱心で2015年から活動しております。本当は東京オリンピックのときまでにアピールしたかったのですが、残念ながらコロナの影響などで活動が少し鈍っています。世の中が落ち着いたら更に玉川上水の世界遺産化を目指して活動を復活しようと思います。
尚、玉川上水は平成14年に東京地裁の調停によって、国が譲歩し、現在所有権は東京都に移管されています。
お時間も無くなってきたのでここまでにいたします。ありがとうございました。
本日はお招きいただき有難うございます。
今日の話は、川柳でいうなら「噺家は見てきたような嘘を言い」というように、話は半分嘘だと思って聞いていただきたいと思います。
今日の東京は1200~1300万人の膨大な人口を抱える都市ですが、京都を差し置いて東京が首都になったのは、400年前に徳川家康が江戸に来て、人が生きるために必要な水の供給がうまくいったためです。 現在、東京都の保有水源量は1日680万立方メートル、消費水量が平均460~470万立方メートルと、多少余裕があります。現在の東京都の水道は利根川と荒川から約8割、残りの17,18%が多摩川水系からですが、多摩川の水は利根川と荒川が厳しい時に補強するという役割を持っています。
なぜ玉川上水が世界遺産としてふさわしいかという問題の歴史と意義についてお話いたします。それは、18世紀以前は玉川上水の給水技術が世界で最も優れていたという点です。
まず、江戸初期の街づくりについてお話していきます。資料でお渡しした約400年前の江戸の姿の図面をご覧いただくとお分かりのように、江戸城のすぐ下まで海で、浅草のあたりもほとんど湿地帯で人が住めないような場所でした。家康が来る前は、江戸重継の館があり、一帯が江戸の郷というわけで、江戸という名前はこの地名、人名から来ています。
家康がこんな不便な江戸に来たのは、豊臣秀吉が実力者の家康を目障りに感じ、遠くの辺鄙なところへ追いやったからではないかと思います。幕府の候補に鎌倉・小田原も上りましたが、江戸は関東平野にあり、発展の余地があると考えて街づくりをしたのが家康です。家康は江戸城の下に道三堀を作り、その掘った土で丸の内や八重洲の埋め立てを行いました。また慶長8年(1603)頃には江戸城の北部の神田山(今の駿河台)を掘り崩して、日本橋、京橋、新橋のあたりの城下町の整備を進めていきました。
なお幕末の絵図でわかるように、現在の浅草仲見世のあたりは、全部お寺でした。このお寺の境内の横で、掃除をするという約束で茶店を出せるようにしたのが仲見世の始まりです。徳川幕府は、今の人形町2丁目、3丁目にあった吉原の遊郭を、街づくりの邪魔であり風紀上良くないということで、浅草の観音様の裏に新吉原として移転させました。その後、観音様の裏手に芝居小屋ができ、芝居小屋ができると茶店、料亭ができて芸者がいるようになるという形で、浅草寺の近辺は発展してきました。
18世紀の頃には江戸は人口100万人の大都市でした。当時のロンドンが87万人、パリが55万人ですから、江戸が巨大な都市であったことが分かると思います。ただ、土地の7割以上は武家屋敷、1割がお寺が占めており、残りのわずかな1割弱のところに町人がひしめいて暮らしていました。
江戸初期の上水道開削についてお話いたします。人の生活のために必要な水ですが、飲み水と灌漑用の用水と生活用水として使われる上水の二種類の水がありました。江戸で初めて引かれた上水が、日本の都市水道の始まりといわれています。徳川家康が、湿地帯の江戸では井戸を掘っても海水の塩分で飲めないため、家来の大久保藤五郎忠行という家来に水源を探すように命じました。大久保は三河一向一揆のときに鉄砲の弾に当たって侍として働けなくなり、幕府御用の菓子づくりになりました。水の吟味に一家言あった大久保が見つけたのが井の頭池の湧水です。井の頭の池から下ってきたのが小石川上水や神田上水になりました。しかし、江戸の人口が増えるとこれらの上水も濁ってきたために、他の上水道が必要になりました。そこで開削が行われたのが玉川上水です。
玉川上水の開削にあたっては、承応元年(1652)に工事の総奉行として老中・松平信綱(川越藩主)、取締奉行に伊那忠治が任命され、実際の工事は庄右衛門と清右衛門の二人の兄弟が請け負いました。
多摩川の取水堰の羽村から江戸まで上水を引く工事は難航し、第一案、第二案が失敗し、庄右衛門兄弟による第三案の工法が実施されました。この工法では、水質の汚染を恐れて川べりを高く築いたために工事費がかさみ、途中で幕府からの資金が底をつきました。庄右衛門兄弟は自分たちの屋敷や私財を投げ打って、羽村から四谷大木戸間の工事を完成させました。この功績により、幕府から玉川という姓を賜り200石取りになりました。世襲制で水の管理を行っていましたが、1700年代に職務怠慢、不正の疑いで職を解かれました。これは濡れ衣で、幕府が財政として水利の利権を得るために理屈をつけてクビにしたようです。
この上水は、羽村から四谷大木戸まで約43キロの距離を落差92メートルという自然の高低差を利用して江戸まで水を引いたものです。上水の管理は厳しく行われ、洗い物、魚釣り、水浴び、ごみ捨てはご法度でした。水路の両側に約5メートルの保護地帯を設けて樹木を植え、立ち入りも厳しく管理しました。上水沿いに山桜を植えて花見客に歩いてもらって土を踏み固めさせたのが、上水沿いの今の小金井の桜の名残だと言われています。
給水管の木の樋などはどうしても腐ってしまったり汚物が混入する可能性があるので、腐蝕の改修費は武家と町人にそれぞれ石高や小間割りに応じて負担させました。
玉川上水は給水管が江戸市中に及び世界遺産にふさわしい優れた先見性と江戸のエコ社会についてお話いたします。江戸の場合は自然流下式でした。一方、フランス・パリの場合は19世紀にナポレオン3世が大改革を行うまで、蒸気機関が無かったために自然流水で汚れた水を使っていました。公衆トイレもなかったために、絵に残っているようにチュイルリー宮殿の茂みのあたりで紳士が排泄しているような汚い街でした。蒸気機関を使って上流で水を汲み上げて配水するようになって、ようやく飲用の水が使えるようになったと言われています。
江戸では、チリ紙交換のように、捨てた紙を集めてトイレ用の紙に再生していました。長屋や武家屋敷から出る排泄物はすべて汲み取って農地に肥料として撒いていました。すべて有機物として利用したために無駄がありません。また濠を作るために堀った土は深川や木場の埋め立てに使うなど、すべて清潔と廃棄物処理が徹底したエコ社会でした。日本人は古代から穢れ、汚れに対して非常に潔癖です。そのため、訪れる外国人が驚くほど日本人は長い間きれい好きで通ってきたのです。
このような歴史をもつ玉川上水を世界遺産にする活動には、世田谷南クラブの建築家天野彰さんが非常に熱心で2015年から活動しております。本当は東京オリンピックのときまでにアピールしたかったのですが、残念ながらコロナの影響などで活動が少し鈍っています。世の中が落ち着いたら更に玉川上水の世界遺産化を目指して活動を復活しようと思います。
尚、玉川上水は平成14年に東京地裁の調停によって、国が譲歩し、現在所有権は東京都に移管されています。
お時間も無くなってきたのでここまでにいたします。ありがとうございました。
卓話 「最高の仕事 『日本舞踊家』 ~人から喜ばれる伝統芸能を目指して~」
日本舞踊家 有馬和歌子さま
2022年4月28日

 皆様こんにちは。 ご紹介に預かりました日本舞踊家の有馬和歌子と申します。
今、社会人2年目の私は、日本舞踊家という仕事にやりがいと誇りをもって、大好きな仕事として頑張っているところです。そして、私が活動する中で一番大切に考えていることが、副題につけた「人から喜ばれる」ことについてです。
まず、緊張をほぐしたいという思いで、中国の伝統楽器二胡で踊った「睡蓮」という演目をほんのワンフレーズだけ実演で踊らせていただきます。
(実演)
そもそも日本舞踊のルーツは祈りから来ていると思います。日本は農耕民族ですので、神様に「豊作になるように」、「天災や災害が起きないように」と祈ることから踊りが始まったのではないでしょうか。それが豪華な衣装や様々な趣向で踊りの幅が広がり、今に伝わっていると考えています。
私のプロフィールを少しご紹介いたします。私は1998年、平成10年に生まれました。この年は冬季長野オリンピックが開催され、郵便番号が7桁になった年だそうです。
父は坂東寛二郎という名の日本舞踊家で、私は父から日本舞踊を習いました。13歳で坂東流の名前をいただき、18歳で師範の資格をいただき、19歳の時に子供向けの日本舞踊教室の「子供舞踊塾」を父から引継ぎ、代表として取り組んでおります。
今まで、半蔵門の国立劇場や増上寺の野外と屋内にて踊らせていただいたり、奈良の東大寺の野外で5000人の観客の前で踊らせていただいたりしています。最近では、伊藤忠商事の「未来を試着しよう。」というCMに、日本の伝統的な衣服の着物姿で登場させていただきました。
https://www.youtube.com/watch?v=JSM0OtznLYE(外部リンク)
私は日本舞踊家として主に5つの仕事をさせていただいております。
表舞台に立つ仕事としては、映像やCMがあります。ベネッセの「こどもちゃれんじ」という子供向けの媒体にも出演させていただきました。二つ目は舞台やイベント、コンサートへの出演です。そして、三つ目は取材やインタビューを受けることも表舞台に立つ仕事です。また、四つ目にプロデュースという仕事では、映像やイベント、舞台の中味を相手のコンセプトや予算を勘案しながら作っています。最後の教育事業の仕事では、子供が大好きなので「子供舞踊塾」の事業を頑張っているところです。
社会人2年目の私が日本舞踊家という仕事の中で一番考えているのは、「伝統芸能イコール価値がある」という固定観念を見直すことです。日本舞踊はブランドで価値があるから良いものだというだけでは、なかなか日本舞踊の良さは伝わらないと考えました。お客様にとって日本舞踊のどこが喜んでいただけるのかをもっと研究し、伝統芸能として良質な部分を守りつつ、今一番喜んでもらえることは何かを考えてうまくバランスをとることが、伝統芸能の継承者としてやるべきことだと考えるようになりました。
私の2歳の初舞台の写真をご紹介します。この初舞台は泣いたり笑ったりの経験でした。私はこの初舞台のことも泣いた理由も鮮明に覚えています。日本舞踊は職人さんの種類と人数が多く、沢山の人に支えられて一つの舞台が出来上がっていきます。私の初舞台の時、普段は落ち着いた印象の職人さんたちが、ものすごい気迫で私に衣装を着せ、髪の毛を整えたのに圧倒されて泣いてしまいました。
次の映像は、私が2,3歳の時のお稽古の映像と、小学校2年生のときの「五条橋」という演目のお稽古の映像です。「五条橋」では父が弁慶、私が牛若丸を演じました。このように2歳からずっと父に日本舞踊を習い続けてきました。父が先生であるのが自然なことで、家にいれば優しいお父さん、稽古場では厳しい先生というのが当たり前になっています。
幼少のころから日本舞踊家になりたいという夢は変わらず、父に憧れて同じ職業に就きたいと思っていた私に、思わぬタイミングで仕事としての日本舞踊家を意識する転機が訪れました。それは、中学高校の部活動でした。私はコーラス部に所属していました。引退を控えた高校2年の文化祭で上演するミュージカルについて、コーラス部の部長として部員をまとめ、限りある予算と能力の中でできることを最大限発揮するにはどうしたら良いか、どう表現したらお客様に喜んでもらえるかと、仲間とお客様のことをとてもよく考えました。ふと、日本舞踊はどうだろうと考えたのがこの時期でした。日本舞踊を仕事として続けるなら、人のためにやっていくのが良いのではないかと考えたのです。
大学1年生の時の初めての仕事の映像をご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=0-ztFizPxxY(外部リンク)
舞台の構成、出演など色々なことを担当させてもらった連獅子の映像です。舞浜のアンフィシアターで開催されたIT企業レノボの年度初めのパーティで演じました。オープニングで役員の方々が飛び入り参加するという演出の要望がありましたので、初めて日本舞踊に挑戦する日本語の通じない外国人の方にもできることを考えて構成しました。白い親獅子が父で、赤い子獅子が私です。後ろで振っているカラフルな晒はレノボのカラー6色から5色を選んで小道具屋に頼んで五色晒にする工夫をしました。
目の前に顔が見える誰かを喜ばせたいという思いから始めたのが「子供舞踊塾」です。「子供舞踊塾」では、子供たちに日本舞踊の稽古と舞台に出ることを1年間の短い期間で全てを体験してもらうという企画を行っています。国立劇場の大稽古場でリハーサルを行い、化粧して衣装を着せてもらって舞台に上がるという流れです。それ以外にも子供たちに日本の良いものを吸収してもらいたいという思いから、虎屋の協力を得て和菓子をみんなで作ったり、日本舞踊の本格的な小道具に実際に触れてもらったり、日本の鰹節や昆布のおだしについて学びを深めたり、増上寺にお邪魔して境内の中を見学させてもらったりと、日本の良いものを体験するという企画を行っています。昨年度から三菱UFJフィナンシャル・グループにも応援していただけるようになりました。あくまでも日本舞踊の教室ですが、子供たちが成長できる大事な居場所という役割であってほしいという気持ちで頑張っています。日本舞踊を通して得られるものがあれば、日本舞踊の価値を上げるきっかけになると信じています。そして、子供たちが喜ぶのと同時に、日本舞踊に携わる多くの職人さんが次の世代を育てて、その職業だけで生活していける、誇りを持てるようにすることに貢献したいと思っています。
私は、可能性の眼鏡をかけることをいつも考えています。自分の活動や自分の視野の中に、日本舞踊の価値が眠っていると思います。可能性の眼鏡をかけて、まだ掘り起こしていない日本舞踊の価値を見つけたいと思っています。
最後に今チャレンジしていることをご紹介いたします。「ひとのときを、思う。JT」というキャッチフレーズでおなじみの日本たばこ産業が、法人向けの日本舞踊体験プログラムに参加されています。私は主に子供たちを対象としていますが、父は大人の方を対象とした教室を40年以上続けております。大人の方にも日本舞踊を通して日本を学んでもらいたいという気持ちから単発の体験プログラムを企画し、赤坂区民センターのホールや国立劇場の舞台に立つことを目指して稽古するというプログラムになっています。
今日、ほとんどの方と初めてお目にかかりましたが、もう少し話を聞いても良い、育ててあげても良いという方がいらっしゃいましたら、是非ご指導いただければと思います。「子供舞踊塾」、そして父が主催する大人向けの「寛和会」もご協賛、ご支援を募っております。ご賛同いただけましたら嬉しいです。本日はありがとうございました。
皆様こんにちは。 ご紹介に預かりました日本舞踊家の有馬和歌子と申します。
今、社会人2年目の私は、日本舞踊家という仕事にやりがいと誇りをもって、大好きな仕事として頑張っているところです。そして、私が活動する中で一番大切に考えていることが、副題につけた「人から喜ばれる」ことについてです。
まず、緊張をほぐしたいという思いで、中国の伝統楽器二胡で踊った「睡蓮」という演目をほんのワンフレーズだけ実演で踊らせていただきます。
(実演)
そもそも日本舞踊のルーツは祈りから来ていると思います。日本は農耕民族ですので、神様に「豊作になるように」、「天災や災害が起きないように」と祈ることから踊りが始まったのではないでしょうか。それが豪華な衣装や様々な趣向で踊りの幅が広がり、今に伝わっていると考えています。
私のプロフィールを少しご紹介いたします。私は1998年、平成10年に生まれました。この年は冬季長野オリンピックが開催され、郵便番号が7桁になった年だそうです。
父は坂東寛二郎という名の日本舞踊家で、私は父から日本舞踊を習いました。13歳で坂東流の名前をいただき、18歳で師範の資格をいただき、19歳の時に子供向けの日本舞踊教室の「子供舞踊塾」を父から引継ぎ、代表として取り組んでおります。
今まで、半蔵門の国立劇場や増上寺の野外と屋内にて踊らせていただいたり、奈良の東大寺の野外で5000人の観客の前で踊らせていただいたりしています。最近では、伊藤忠商事の「未来を試着しよう。」というCMに、日本の伝統的な衣服の着物姿で登場させていただきました。
https://www.youtube.com/watch?v=JSM0OtznLYE(外部リンク)
私は日本舞踊家として主に5つの仕事をさせていただいております。
表舞台に立つ仕事としては、映像やCMがあります。ベネッセの「こどもちゃれんじ」という子供向けの媒体にも出演させていただきました。二つ目は舞台やイベント、コンサートへの出演です。そして、三つ目は取材やインタビューを受けることも表舞台に立つ仕事です。また、四つ目にプロデュースという仕事では、映像やイベント、舞台の中味を相手のコンセプトや予算を勘案しながら作っています。最後の教育事業の仕事では、子供が大好きなので「子供舞踊塾」の事業を頑張っているところです。
社会人2年目の私が日本舞踊家という仕事の中で一番考えているのは、「伝統芸能イコール価値がある」という固定観念を見直すことです。日本舞踊はブランドで価値があるから良いものだというだけでは、なかなか日本舞踊の良さは伝わらないと考えました。お客様にとって日本舞踊のどこが喜んでいただけるのかをもっと研究し、伝統芸能として良質な部分を守りつつ、今一番喜んでもらえることは何かを考えてうまくバランスをとることが、伝統芸能の継承者としてやるべきことだと考えるようになりました。
私の2歳の初舞台の写真をご紹介します。この初舞台は泣いたり笑ったりの経験でした。私はこの初舞台のことも泣いた理由も鮮明に覚えています。日本舞踊は職人さんの種類と人数が多く、沢山の人に支えられて一つの舞台が出来上がっていきます。私の初舞台の時、普段は落ち着いた印象の職人さんたちが、ものすごい気迫で私に衣装を着せ、髪の毛を整えたのに圧倒されて泣いてしまいました。
次の映像は、私が2,3歳の時のお稽古の映像と、小学校2年生のときの「五条橋」という演目のお稽古の映像です。「五条橋」では父が弁慶、私が牛若丸を演じました。このように2歳からずっと父に日本舞踊を習い続けてきました。父が先生であるのが自然なことで、家にいれば優しいお父さん、稽古場では厳しい先生というのが当たり前になっています。
幼少のころから日本舞踊家になりたいという夢は変わらず、父に憧れて同じ職業に就きたいと思っていた私に、思わぬタイミングで仕事としての日本舞踊家を意識する転機が訪れました。それは、中学高校の部活動でした。私はコーラス部に所属していました。引退を控えた高校2年の文化祭で上演するミュージカルについて、コーラス部の部長として部員をまとめ、限りある予算と能力の中でできることを最大限発揮するにはどうしたら良いか、どう表現したらお客様に喜んでもらえるかと、仲間とお客様のことをとてもよく考えました。ふと、日本舞踊はどうだろうと考えたのがこの時期でした。日本舞踊を仕事として続けるなら、人のためにやっていくのが良いのではないかと考えたのです。
大学1年生の時の初めての仕事の映像をご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=0-ztFizPxxY(外部リンク)
舞台の構成、出演など色々なことを担当させてもらった連獅子の映像です。舞浜のアンフィシアターで開催されたIT企業レノボの年度初めのパーティで演じました。オープニングで役員の方々が飛び入り参加するという演出の要望がありましたので、初めて日本舞踊に挑戦する日本語の通じない外国人の方にもできることを考えて構成しました。白い親獅子が父で、赤い子獅子が私です。後ろで振っているカラフルな晒はレノボのカラー6色から5色を選んで小道具屋に頼んで五色晒にする工夫をしました。
目の前に顔が見える誰かを喜ばせたいという思いから始めたのが「子供舞踊塾」です。「子供舞踊塾」では、子供たちに日本舞踊の稽古と舞台に出ることを1年間の短い期間で全てを体験してもらうという企画を行っています。国立劇場の大稽古場でリハーサルを行い、化粧して衣装を着せてもらって舞台に上がるという流れです。それ以外にも子供たちに日本の良いものを吸収してもらいたいという思いから、虎屋の協力を得て和菓子をみんなで作ったり、日本舞踊の本格的な小道具に実際に触れてもらったり、日本の鰹節や昆布のおだしについて学びを深めたり、増上寺にお邪魔して境内の中を見学させてもらったりと、日本の良いものを体験するという企画を行っています。昨年度から三菱UFJフィナンシャル・グループにも応援していただけるようになりました。あくまでも日本舞踊の教室ですが、子供たちが成長できる大事な居場所という役割であってほしいという気持ちで頑張っています。日本舞踊を通して得られるものがあれば、日本舞踊の価値を上げるきっかけになると信じています。そして、子供たちが喜ぶのと同時に、日本舞踊に携わる多くの職人さんが次の世代を育てて、その職業だけで生活していける、誇りを持てるようにすることに貢献したいと思っています。
私は、可能性の眼鏡をかけることをいつも考えています。自分の活動や自分の視野の中に、日本舞踊の価値が眠っていると思います。可能性の眼鏡をかけて、まだ掘り起こしていない日本舞踊の価値を見つけたいと思っています。
最後に今チャレンジしていることをご紹介いたします。「ひとのときを、思う。JT」というキャッチフレーズでおなじみの日本たばこ産業が、法人向けの日本舞踊体験プログラムに参加されています。私は主に子供たちを対象としていますが、父は大人の方を対象とした教室を40年以上続けております。大人の方にも日本舞踊を通して日本を学んでもらいたいという気持ちから単発の体験プログラムを企画し、赤坂区民センターのホールや国立劇場の舞台に立つことを目指して稽古するというプログラムになっています。
今日、ほとんどの方と初めてお目にかかりましたが、もう少し話を聞いても良い、育ててあげても良いという方がいらっしゃいましたら、是非ご指導いただければと思います。「子供舞踊塾」、そして父が主催する大人向けの「寛和会」もご協賛、ご支援を募っております。ご賛同いただけましたら嬉しいです。本日はありがとうございました。
卓話 「目の錯覚でコロナ太りも無かったことに!」
ファッションスタイリスト 渡邉美奈さま
2022年3月10日

 おはようございます。スタイリストの渡邉美奈と申します。
私は実はロータリアンの家庭で育っております。ロータリーの楽しい思い出はクリスマスパーティで、毎回笑顔があふれる会だと思い楽しみにしていました。
笑顔が好きで、人を笑顔にするのも好きな子供でした。人の良い所をみつけるのが昔から得意でした。ネガティブをポジティブに変える力を持っていたのかもしれません。それが今生かされていると思います。
イケイケバブルの時代には、生意気で鼻持ちならないアフロのスタイリストだったこともありますが、周りの方々の気遣いとお力添えで今があると感謝しております。
私が人生を楽しみ笑えるのはこの仕事のおかげだと思っています。衣装デザインのスタイリング、テレビ、広告、映画、ミュージカル、海外イベント、商品企画など色々な分野の仕事をしてきました。具体的には、テレビの「王様のブランチ」や「とくダネ!」や、「サンリオ」のミュージカル、「ライザップ」の広告、元AKBの方の企画などもやっています。その他、JALの機内誌やスタイリストがセレクトするパソコン、「SONY」のスタイリスト的なカメラの使い方などにも出させていただきました。アフロの頃には沢尻エリカさんが出演していた「Harajukuロンチャーズ」という番組にスタイリストの先生として毎週出演させていただきました。
面白い仕事としては、テレビ番組の「亭主改造計画」でスタイリストをしていました。そのときに、人目にさらされていない一般の方々のスタイリングで、目の錯覚を使って体型を美しく見せるということに面白さを感じるようになりました。錯覚を学んで自分に取り入れればスタイルを変化させて見せることができるのです。
コロナでお家時間が増えて太った方も多いと思います。太るのは簡単ですが痩せるのは本当に大変です。そういう時に活用したいのがストライプで縦長に見せるスタイリングです。
ストライプを使って背を高く見せるには、ボトムスの切り替え位置、ウエストを少しだけ3センチ以内で上に上げます。そしてトップスを3センチ短くします。両方合わせると6センチ長さが下に伸びて見えます。上半身が小さく見えると全体バランスが八頭身に近づきます。切り替えをしたウエストから下を同系色でまとめて縦に長く見せると足長効果が生まれます。スタイルの錯覚としては、トップスを小さくして、肩幅はそのままで腕をおろすとウエストが少しへこんで見えます。そのウエストからAラインの開くスカートにすると、ウエストの幅とスカートの幅の対比でウエストが細く見えます。こういうことを少しずつ積み重ねて全体的にスタイルを良く見せることができます。
手首、足首、首の5か所を見せると細見え効果が生まれて全体に細いような錯覚が起こります。例えば、足首がしまって細く見えるブーツを履いていると全体が細いのだろうという錯覚が起こります。短いブーティも細い足首を見せることで細見え効果が生まれます。
私の仕事の中で目の錯覚を取り入れたなりきりスタイリングの例として対照的なお二人をご紹介します。
まず、水谷豊さん。周りの方々やスタッフにまで気を遣われる方で、穏やかで、知的で、博学で、こだわりのある素晴らしい方でした。そんな素晴らしい水谷さんですので、その素晴らしさを織り込んだなりきりスタイリングを考えました。男性のスーツの襟から中の三角形をゴールデントライアングルと呼び、一番目がいく場所です。水谷さんは小柄なので、このゴールデントライアングルを小さくまとめました。ネクタイは細目にし、ジャケットの襟幅もネクタイに合わせ、少し複雑にするためにベストをいれました。そして小物にはイギリス紳士のような上品な素材の眼鏡を選びました。水谷さんにはイギリスの紳士というイメージを伝えて、なり切っていただきました。
水谷さんとは対照的なのは、北島音楽事務所の小金沢昇司さんです。裏表がなく、嘘は言わない、おべっかを使わない、本当に筋を通す良い方でした。決して硬いわけではなく、朗らかで穏やかで、いつも笑わせてくださる面白い方でした。小金沢さんは身長が高く横幅もあり筋肉質でがっちりしており、お顔もちょっと大きめです。そこでお顔が小さく見えて全体のバランスが整うように、ゴールデントライアングルは襟幅を少し太めにし、ネクタイも太目にしました。小物としてネックレス、ブレスレット、指輪などをつけていただきました。素材感としては光沢感のあるどっしりとしたものにして、イタリアの伊達男、ゴッドファーザー的なイメージを伝えて、なり切っていただきました。このようにイメージを伝えてなり切ってもらうのが一番分かりやすくて速いです。
ファッションのアドバイス的な話になりますが、ヒートテックは生地が汗を吸って熱を出すので、肌を乾燥させる素材だということはご存知ですか。乾燥を避けたいのであれば、シルク。シルクがニットになったものを着るのが肌に一番良いです。着るコラーゲンと言われ、アミノ酸バランスがよくてお肌によい素材です。
また、革は濡らしてはいけないと言われますが、汚れを落としてきれいな水で洗い、乾く前にミンクオイルをつけてください。ミンクオイルがない場合は純粋なワセリンでも大丈夫です。そうすれば保湿効果で長持ちします。靴も同じですので、是非ともやってみてください。
あと一つだけお話させてください。
私は今、乳癌のブラジャーを作っています。私が乳癌になったのは50代で手術は命の選択の一つだと思い、悲しいことはありませんでした。ただ、同時期に20代の乳癌の女の子が手術室に入ったときに、ご両親が顔を手で覆った姿がとても辛く目に焼き付いてしまいました。私はその子のブラジャーを作ろうと思いました。今までのブラジャーは不細工でとても見せられるものではありません。私は見せても可愛いブラジャー、自信をもってつけられるブラジャーを作ろうと思っています。
今、主治医の先生とシリコンの変形を防ぎ、自分の胸の老化に真っ向から立ち向かう唯一無二のブラジャーを作ろうと頑張っています。まだサンプル工場探しの段階ですが、頭に浮かんだものは必ずできると信じているので、自分を追い込むためにも皆さまの前で公言させていただきました。
最後になりますが、私はファッションの面白いところ、楽しめるところが大好きです。皆さまも無理なく錯覚を取り入れて、なりきりファッションをたくさん楽しんでください。
おはようございます。スタイリストの渡邉美奈と申します。
私は実はロータリアンの家庭で育っております。ロータリーの楽しい思い出はクリスマスパーティで、毎回笑顔があふれる会だと思い楽しみにしていました。
笑顔が好きで、人を笑顔にするのも好きな子供でした。人の良い所をみつけるのが昔から得意でした。ネガティブをポジティブに変える力を持っていたのかもしれません。それが今生かされていると思います。
イケイケバブルの時代には、生意気で鼻持ちならないアフロのスタイリストだったこともありますが、周りの方々の気遣いとお力添えで今があると感謝しております。
私が人生を楽しみ笑えるのはこの仕事のおかげだと思っています。衣装デザインのスタイリング、テレビ、広告、映画、ミュージカル、海外イベント、商品企画など色々な分野の仕事をしてきました。具体的には、テレビの「王様のブランチ」や「とくダネ!」や、「サンリオ」のミュージカル、「ライザップ」の広告、元AKBの方の企画などもやっています。その他、JALの機内誌やスタイリストがセレクトするパソコン、「SONY」のスタイリスト的なカメラの使い方などにも出させていただきました。アフロの頃には沢尻エリカさんが出演していた「Harajukuロンチャーズ」という番組にスタイリストの先生として毎週出演させていただきました。
面白い仕事としては、テレビ番組の「亭主改造計画」でスタイリストをしていました。そのときに、人目にさらされていない一般の方々のスタイリングで、目の錯覚を使って体型を美しく見せるということに面白さを感じるようになりました。錯覚を学んで自分に取り入れればスタイルを変化させて見せることができるのです。
コロナでお家時間が増えて太った方も多いと思います。太るのは簡単ですが痩せるのは本当に大変です。そういう時に活用したいのがストライプで縦長に見せるスタイリングです。
ストライプを使って背を高く見せるには、ボトムスの切り替え位置、ウエストを少しだけ3センチ以内で上に上げます。そしてトップスを3センチ短くします。両方合わせると6センチ長さが下に伸びて見えます。上半身が小さく見えると全体バランスが八頭身に近づきます。切り替えをしたウエストから下を同系色でまとめて縦に長く見せると足長効果が生まれます。スタイルの錯覚としては、トップスを小さくして、肩幅はそのままで腕をおろすとウエストが少しへこんで見えます。そのウエストからAラインの開くスカートにすると、ウエストの幅とスカートの幅の対比でウエストが細く見えます。こういうことを少しずつ積み重ねて全体的にスタイルを良く見せることができます。
手首、足首、首の5か所を見せると細見え効果が生まれて全体に細いような錯覚が起こります。例えば、足首がしまって細く見えるブーツを履いていると全体が細いのだろうという錯覚が起こります。短いブーティも細い足首を見せることで細見え効果が生まれます。
私の仕事の中で目の錯覚を取り入れたなりきりスタイリングの例として対照的なお二人をご紹介します。
まず、水谷豊さん。周りの方々やスタッフにまで気を遣われる方で、穏やかで、知的で、博学で、こだわりのある素晴らしい方でした。そんな素晴らしい水谷さんですので、その素晴らしさを織り込んだなりきりスタイリングを考えました。男性のスーツの襟から中の三角形をゴールデントライアングルと呼び、一番目がいく場所です。水谷さんは小柄なので、このゴールデントライアングルを小さくまとめました。ネクタイは細目にし、ジャケットの襟幅もネクタイに合わせ、少し複雑にするためにベストをいれました。そして小物にはイギリス紳士のような上品な素材の眼鏡を選びました。水谷さんにはイギリスの紳士というイメージを伝えて、なり切っていただきました。
水谷さんとは対照的なのは、北島音楽事務所の小金沢昇司さんです。裏表がなく、嘘は言わない、おべっかを使わない、本当に筋を通す良い方でした。決して硬いわけではなく、朗らかで穏やかで、いつも笑わせてくださる面白い方でした。小金沢さんは身長が高く横幅もあり筋肉質でがっちりしており、お顔もちょっと大きめです。そこでお顔が小さく見えて全体のバランスが整うように、ゴールデントライアングルは襟幅を少し太めにし、ネクタイも太目にしました。小物としてネックレス、ブレスレット、指輪などをつけていただきました。素材感としては光沢感のあるどっしりとしたものにして、イタリアの伊達男、ゴッドファーザー的なイメージを伝えて、なり切っていただきました。このようにイメージを伝えてなり切ってもらうのが一番分かりやすくて速いです。
ファッションのアドバイス的な話になりますが、ヒートテックは生地が汗を吸って熱を出すので、肌を乾燥させる素材だということはご存知ですか。乾燥を避けたいのであれば、シルク。シルクがニットになったものを着るのが肌に一番良いです。着るコラーゲンと言われ、アミノ酸バランスがよくてお肌によい素材です。
また、革は濡らしてはいけないと言われますが、汚れを落としてきれいな水で洗い、乾く前にミンクオイルをつけてください。ミンクオイルがない場合は純粋なワセリンでも大丈夫です。そうすれば保湿効果で長持ちします。靴も同じですので、是非ともやってみてください。
あと一つだけお話させてください。
私は今、乳癌のブラジャーを作っています。私が乳癌になったのは50代で手術は命の選択の一つだと思い、悲しいことはありませんでした。ただ、同時期に20代の乳癌の女の子が手術室に入ったときに、ご両親が顔を手で覆った姿がとても辛く目に焼き付いてしまいました。私はその子のブラジャーを作ろうと思いました。今までのブラジャーは不細工でとても見せられるものではありません。私は見せても可愛いブラジャー、自信をもってつけられるブラジャーを作ろうと思っています。
今、主治医の先生とシリコンの変形を防ぎ、自分の胸の老化に真っ向から立ち向かう唯一無二のブラジャーを作ろうと頑張っています。まだサンプル工場探しの段階ですが、頭に浮かんだものは必ずできると信じているので、自分を追い込むためにも皆さまの前で公言させていただきました。
最後になりますが、私はファッションの面白いところ、楽しめるところが大好きです。皆さまも無理なく錯覚を取り入れて、なりきりファッションをたくさん楽しんでください。
卓話 「2022年の世界経済と市場展望~アフターコロナで世界はどうなるのか~」
株式会社武者リサーチ 代表 武者陵司さま
2022年1月20日

 皆様こんにちは。 本日はこのような席にお招きいただき有難うございます。
最初から宣伝して恐縮ですが、来月発売の本を書いております。『安い日本が日本を大復活させる』という本で、相当面白い本ですので、よろしければお買いいただくか、言っていただければ、プレゼントさせていただきます。
日本では、コロナ敗戦、グリーン敗戦、ハイテク敗戦、金融敗戦と、敗戦ばかりが言われておりますが、日本が一番悪かったのは8年前です。アベノミクスが始まった2011年、日経平均は7,000円でした。最近は3万円をつけて、日本の株価は上昇過程に入っています。リーマンショック以降の12年間で日本の株価は4.3倍になっており、年率13%の上昇です。この上昇率が10年続くと、日経平均は10万円になると思います。
1年前、2年前は、米中対決という覇権争いと、コロナの影響で将来どうなるか不安でした。しかし、米中対決は持久戦となり短期的に事態が深刻化する可能性は低くなり、コロナもそろそろ終盤に来ているので、先行きの見通しは明るいように思えます。皆様の関心は米国の金融引き締めの経済への影響、そして、日本の最悪期は終わったと私が申し上げる理由だと思います。 本日はこの2点、米国の金融政策転換が持つ意味と日本の復活についてお話いたします。
今、我々の世界は歴史的な技術革新により劇的に変化しています。技術革新がもたらす供給力余剰によって、需給の逼迫がなくなりました。このためデフレとなっています。技術の向上により生産性が上がり、人を減らしても生産できるようになり、人余りとなっています。また、コンピュータなどに見られるように10年前に比べて製品価格が大幅に下がり、金余りとなっています。デフレ、人余り、金余りはすべて技術革新の急速な進化によるものです。だからインフレにならないのです。
この状態を放っておくと、供給は過剰となり、金余りとなり、大不況に陥ります。このような局面で一番大事なことは、需要を増やすことです。技術革新によって生産性が上がり供給力が2倍になったら、我々の生活水準を2倍に押し上げることです。しかし、日本人には質素倹約が美徳だという観念が染みついています。これからは消費が美徳なのです。この消費が美徳と言う精神が極めて旺盛なのが米国です。先進国の中でも日本ほどコロナの影響が抑えられている国はないのですがOECDによると、2021年の日本の経済見通しは1.8%、米国は5.6%、ユーロ圏が5.2%と、日本の経済成長の悪さが際立っています。なぜかといえば、日本は質素倹約の精神で必要以上に経済活動が低迷しているからです。日本ではコロナに対する過剰な警戒で経済にマイナスの影響が及んでいますが、今年コロナが終わった後のリバウンドは大きいと思います。コロナによって溜まった欲求不満とお金が一気に爆発して、景気は良くなるでしょう。
歴史を振り返ると、200年前の米国では100人の内74人が農民、つまり、農民1人が1.34人分の食料を生産していました。200年後、農民2人で100人分の食料が生産でき、生産性は50に上がりました。この生産性の劇的な上昇が過去200年の経済における最も重要な変化です。74人が2人になり、農業を失業した72人はどのような職業に就いたでしょうか。それは人々をより幸せにする新しい産業です。衣料、住宅、より質の高い教育、エンターテイメント、また新しく生まれた産業です。そのおかげで我々の生活は、200年前の王侯貴族よりも豊かで便利になっています。
今また、同じことが起こっています。恐らくあと10年もしないうち仕事は全てロボットがやってくれるようになるでしょう。工場や職場に人が必要なくなる。しかし、その失業者は、新たに生まれるビジネスに吸収され、雇用され経済は発展していきます。
どのようなビジネスが増えるかと言えば、私は芸術、エンターテインメント、スポーツなどが発展すると思います。仕事に出かける必要がなくなると、筋肉を使わなくなり欲求不満になります。その結果、猛烈なスポーツブームが起こるのではないでしょうか。
このように、お金さえあれば、人は次から次へと欲求を満たす新しいビジネス、あるいは雇用を生み出しますが、問題は時間が足りないことです。米国は200年かけて72人の失業者を吸収しましたが、同じことを5年、10年ではできません。その幕間をつなぐのが政府の役割です。人余り、金余りであれば政府が人と金を使って新たな需要を作る。そのような政策が打ち出されれば経済は安泰です。しかし、財政赤字を減らせというような政策が打ち出されれば、ますます人と金が余り、デフレ化して経済は混乱に陥ります。我々は政策が極めて大事だということを念頭に置く必要があると思います。この考え方をはっきり認識しているのが米財務長官のジャネット・イエレンとFRB議長のジェローム・パウエルです。彼らは、一時的に金融引き締めに転じたとしても、需要創造を促進する政府の政策に水を差すことは決してしないので、安心して良いと思います。今、テーパリングとか金利引き上げといったことが起こっていますが、株価の急落とか景気の悪化などは起こりようもありません。ただ、金融政策が転換する局面では乱高下がありますから怪我をしないように警戒する必要があります。
2点目の日本の復活についてご説明します。
私はいよいよ日本の復活の時代が来たと思っています。先ほど、今のペースでいけば日経平均はあと10年で10万円と言いました。2012年頃から上昇軌道に入った日本の株価上昇はこれからも続いていくでしょう。日本には新しい主役が揃っています。2000年からの日本の株式時価総額トップ20の企業推移を見ていくと、現在のトップ20社の中には、新興企業が台頭していること、ニュープレイヤーが舞台の中心に立っていることがわかります。私は、そのうち12社を将来のリーディングカンパニーと位置付けています。具体的に名前を挙げれば、ソニー、キーエンス、リクルート、ソフトバンク、日本電産、ダイキン工業、任天堂、ファーストリテイリング、HOYA、東京エレクトロン、信越化学、村田製作所です。これらの企業は新たな情報化の時代を担い得るビジネスモデルを持ち、それぞれグローバルナンバーワンのプレイヤーです。説得力のあるキャッチフレーズを発信する、将来の日本経済を担う新たな主役が誕生しているのです。
さて、日本の株式市場の主役は揃いました。そしていよいよ株の買い手が登場します。それは日本の個人投資家です。
今、日本の株式、金融資産、家計の金融資産の全体を100とすると現金・預金が75%を占めて、株・投信は2割しかありません。米国では金融資産の内、現金・預金は18%で株・投信が7割を占めています。つまりアメリカ人にはこれ以上株を買う余力はありません。一方日本人は現金・預金がたっぷりあるので、株をたくさん買う余裕があります。全部で1000兆円というお金が、iDeCoやNISAといった個人の証券投資勘定と言う形でどっと株式市場に入ってきます。新しいお金がいよいよ動き始めているのです。
昨年、日本の株は米国に比べると調子が良くありませんでした。しかし日本の株式のパフォーマンスをみると、年間で5%上がっています。日銀が買わなくなり、外人も売りに回った中で、日本株が5%も上がったということは、相場の基礎的な体温がだいぶ上がってきているといえます。
このように、グローバルな技術のトレンドも良し。日本の新しいプレイヤーも揃ってきた。さらには株の買い手も揃っている。これからは明るいシナリオで対処していける。年の初めでもありますが、今年は大いに希望を持っていただきたいと思っています。
どうもご清聴ありがとうございました。
【本卓話掲載は例会の卓話を紹介することを目的としたものであり、投資を勧誘・推奨したものではありません。】
皆様こんにちは。 本日はこのような席にお招きいただき有難うございます。
最初から宣伝して恐縮ですが、来月発売の本を書いております。『安い日本が日本を大復活させる』という本で、相当面白い本ですので、よろしければお買いいただくか、言っていただければ、プレゼントさせていただきます。
日本では、コロナ敗戦、グリーン敗戦、ハイテク敗戦、金融敗戦と、敗戦ばかりが言われておりますが、日本が一番悪かったのは8年前です。アベノミクスが始まった2011年、日経平均は7,000円でした。最近は3万円をつけて、日本の株価は上昇過程に入っています。リーマンショック以降の12年間で日本の株価は4.3倍になっており、年率13%の上昇です。この上昇率が10年続くと、日経平均は10万円になると思います。
1年前、2年前は、米中対決という覇権争いと、コロナの影響で将来どうなるか不安でした。しかし、米中対決は持久戦となり短期的に事態が深刻化する可能性は低くなり、コロナもそろそろ終盤に来ているので、先行きの見通しは明るいように思えます。皆様の関心は米国の金融引き締めの経済への影響、そして、日本の最悪期は終わったと私が申し上げる理由だと思います。 本日はこの2点、米国の金融政策転換が持つ意味と日本の復活についてお話いたします。
今、我々の世界は歴史的な技術革新により劇的に変化しています。技術革新がもたらす供給力余剰によって、需給の逼迫がなくなりました。このためデフレとなっています。技術の向上により生産性が上がり、人を減らしても生産できるようになり、人余りとなっています。また、コンピュータなどに見られるように10年前に比べて製品価格が大幅に下がり、金余りとなっています。デフレ、人余り、金余りはすべて技術革新の急速な進化によるものです。だからインフレにならないのです。
この状態を放っておくと、供給は過剰となり、金余りとなり、大不況に陥ります。このような局面で一番大事なことは、需要を増やすことです。技術革新によって生産性が上がり供給力が2倍になったら、我々の生活水準を2倍に押し上げることです。しかし、日本人には質素倹約が美徳だという観念が染みついています。これからは消費が美徳なのです。この消費が美徳と言う精神が極めて旺盛なのが米国です。先進国の中でも日本ほどコロナの影響が抑えられている国はないのですがOECDによると、2021年の日本の経済見通しは1.8%、米国は5.6%、ユーロ圏が5.2%と、日本の経済成長の悪さが際立っています。なぜかといえば、日本は質素倹約の精神で必要以上に経済活動が低迷しているからです。日本ではコロナに対する過剰な警戒で経済にマイナスの影響が及んでいますが、今年コロナが終わった後のリバウンドは大きいと思います。コロナによって溜まった欲求不満とお金が一気に爆発して、景気は良くなるでしょう。
歴史を振り返ると、200年前の米国では100人の内74人が農民、つまり、農民1人が1.34人分の食料を生産していました。200年後、農民2人で100人分の食料が生産でき、生産性は50に上がりました。この生産性の劇的な上昇が過去200年の経済における最も重要な変化です。74人が2人になり、農業を失業した72人はどのような職業に就いたでしょうか。それは人々をより幸せにする新しい産業です。衣料、住宅、より質の高い教育、エンターテイメント、また新しく生まれた産業です。そのおかげで我々の生活は、200年前の王侯貴族よりも豊かで便利になっています。
今また、同じことが起こっています。恐らくあと10年もしないうち仕事は全てロボットがやってくれるようになるでしょう。工場や職場に人が必要なくなる。しかし、その失業者は、新たに生まれるビジネスに吸収され、雇用され経済は発展していきます。
どのようなビジネスが増えるかと言えば、私は芸術、エンターテインメント、スポーツなどが発展すると思います。仕事に出かける必要がなくなると、筋肉を使わなくなり欲求不満になります。その結果、猛烈なスポーツブームが起こるのではないでしょうか。
このように、お金さえあれば、人は次から次へと欲求を満たす新しいビジネス、あるいは雇用を生み出しますが、問題は時間が足りないことです。米国は200年かけて72人の失業者を吸収しましたが、同じことを5年、10年ではできません。その幕間をつなぐのが政府の役割です。人余り、金余りであれば政府が人と金を使って新たな需要を作る。そのような政策が打ち出されれば経済は安泰です。しかし、財政赤字を減らせというような政策が打ち出されれば、ますます人と金が余り、デフレ化して経済は混乱に陥ります。我々は政策が極めて大事だということを念頭に置く必要があると思います。この考え方をはっきり認識しているのが米財務長官のジャネット・イエレンとFRB議長のジェローム・パウエルです。彼らは、一時的に金融引き締めに転じたとしても、需要創造を促進する政府の政策に水を差すことは決してしないので、安心して良いと思います。今、テーパリングとか金利引き上げといったことが起こっていますが、株価の急落とか景気の悪化などは起こりようもありません。ただ、金融政策が転換する局面では乱高下がありますから怪我をしないように警戒する必要があります。
2点目の日本の復活についてご説明します。
私はいよいよ日本の復活の時代が来たと思っています。先ほど、今のペースでいけば日経平均はあと10年で10万円と言いました。2012年頃から上昇軌道に入った日本の株価上昇はこれからも続いていくでしょう。日本には新しい主役が揃っています。2000年からの日本の株式時価総額トップ20の企業推移を見ていくと、現在のトップ20社の中には、新興企業が台頭していること、ニュープレイヤーが舞台の中心に立っていることがわかります。私は、そのうち12社を将来のリーディングカンパニーと位置付けています。具体的に名前を挙げれば、ソニー、キーエンス、リクルート、ソフトバンク、日本電産、ダイキン工業、任天堂、ファーストリテイリング、HOYA、東京エレクトロン、信越化学、村田製作所です。これらの企業は新たな情報化の時代を担い得るビジネスモデルを持ち、それぞれグローバルナンバーワンのプレイヤーです。説得力のあるキャッチフレーズを発信する、将来の日本経済を担う新たな主役が誕生しているのです。
さて、日本の株式市場の主役は揃いました。そしていよいよ株の買い手が登場します。それは日本の個人投資家です。
今、日本の株式、金融資産、家計の金融資産の全体を100とすると現金・預金が75%を占めて、株・投信は2割しかありません。米国では金融資産の内、現金・預金は18%で株・投信が7割を占めています。つまりアメリカ人にはこれ以上株を買う余力はありません。一方日本人は現金・預金がたっぷりあるので、株をたくさん買う余裕があります。全部で1000兆円というお金が、iDeCoやNISAといった個人の証券投資勘定と言う形でどっと株式市場に入ってきます。新しいお金がいよいよ動き始めているのです。
昨年、日本の株は米国に比べると調子が良くありませんでした。しかし日本の株式のパフォーマンスをみると、年間で5%上がっています。日銀が買わなくなり、外人も売りに回った中で、日本株が5%も上がったということは、相場の基礎的な体温がだいぶ上がってきているといえます。
このように、グローバルな技術のトレンドも良し。日本の新しいプレイヤーも揃ってきた。さらには株の買い手も揃っている。これからは明るいシナリオで対処していける。年の初めでもありますが、今年は大いに希望を持っていただきたいと思っています。
どうもご清聴ありがとうございました。
【本卓話掲載は例会の卓話を紹介することを目的としたものであり、投資を勧誘・推奨したものではありません。】
卓話 「ビスポーク(オーダー靴)の魅力について」
靴職人 土屋聡氏
2021年12月16日

 皆さん初めまして、土屋と申します。よろしくお願いいたします。
私は東京の国分寺でビスポークというオーダー靴、手で一つずつ靴を作る仕事をしております。今回、オーダー靴がどういうものかを知っていただけたらと思いお話しさせていただきます。
私は、靴を作り始めて20年、年齢は46歳です。高校卒業後にプロのダンサーとして、ヒップホップと言われるストリートダンスをやっていました。ヒップホップダンスは黒人の音楽から始まったもので、黒人のダンサーとも仲良くショータイムに出演したりしていたのですが、その中で黒人に対する差別などがあることを知り、自分は何も知らない人間なのだと気づき、世界の文化に対する興味が広がりました。そこでバックパックで旅に出ることにしました。7か月余り、少ない荷物を背負って陸路で世界中を回る中で色々な経験をしました。ストリートで手で物を作って売る人々をみたりして、物づくりに興味を持つようになりました。
日本の二大巨頭の靴の町の一つ、東京浅草にある東京都の職業訓練校に入ったことで私の靴との関わりが始まりました。単純に手で靴を作ることが楽しかったので、この感じで就職できないかと考えましたが、当時は量産靴を買うのが主流の時代でした。靴を手で作る唯一の就職先が義肢装具の会社でした。障害者のための靴は一つずつ、お客様の足と症状に合わせて作っていきます。この義肢装具の会社で靴を作っていく中で二人の師匠と出会いました。
一人はオーダーパンプスの巨匠の斉藤師匠です。師匠は、昨年引退されましたが、それまで私は週1回お手伝いをしながら、足のことや健康のことをたくさん学びました。
もう一人が、津久井玲子師匠です。日本の伝説の靴職人で業界ではレジェンドと呼ばれる関信義さんの一番弟子です。関さんは亡くなられましたが、私は関さんの一番弟子の一番弟子なので孫弟子となります。その縁があって、きれいな革靴、長く持つ革靴を学ぶことができました。
こうしてずっと靴を作り続けています。そして今は、専門学校で特別専門技術を教えたり、自分の工房に皆様もご存知のような某大手靴メーカーのプロの方々が習いに来ています。量産靴は、専門が分かれており完全分業で作られています。分業ゆえにプロフェッショナルであり、良い点がたくさんあります。 一方、私のビスポークという一人が一つずつ全てを作っていく靴は、一つずつの工程で問題解決をすることができ、終始細部まで丁寧に作り上げられます。この一人が最後まで全部責任を持って作業できることが一番大きな魅力です。私は習いに来ている方々からもたくさん教えてもらって、日々精進しています。
古い時代にはヨーロッパで職人同士が技術を競い合う大会が開催されていましたが、近年は手作りの靴が主流でなかったために長年開催されていませんでした。それが最近、手作りの靴の魅力が見直され、2018年に世界大会が復活しました。この大会にはジョンロブやコルテ、カジアーノ&ガーリングなどの名店と言われる靴屋のビスポークを扱う職長クラスが参加しています。私も面白いと思って2019年の大会に出場しました。この世界的に技術を競う靴の大会で10位までが入賞のところ、私は7位になり世界のトップテンに入ることができました。
また、国分寺市のふるさと納税で私の靴を買うことができます。そこで会員の青栁様と出会い、今回の卓話に至るということになりました。
さて、ビスポークについてお話いたします。
ビスポークはオーダー靴ということになります。ビースポーク、ビースポークンとも言います。直訳すると職人の話を聞きながらオーダーするという意味のようです。スーツのオーダーでも使われる言葉です。私は、「話される」の直訳から、ビスポークを「仰せのままに」と捉えています。高い技術でお客様の要望を叶える。足に合わせて、格好良いデザインで、堅牢で一生持つような靴を作る責務がある仕事だと考えています。
ビスポーク靴の魅力の一つは堅牢であることです。皆さんが履いているような靴の形はイギリスのノーザンプトンで生まれたと言われています。産業革命でセメント靴など値段が安く気軽に買える靴が登場しました。しかし、昔からある作りで、いまだにそれを超える製法がない堅牢な靴であることがビスポーク靴の大きな魅力となっていることを知っていただきたいと思います。
もう一つの魅力は一人の職人が一つの靴を徹底的に作り上げる点です。先ほどお話したように、私は教職にもあるので、某大手メーカーの企画の方から相談を受けることもあります。量産靴で専門性を持っている人はその専門分野については長けています。しかし、他の分野で問題が起こったり、最後の完成図が見えないために問題解決ができないことがあります。ですから、お客さまの足を見て、歩き方や好み、普段の生活を聞いた上で一つの形を作り上げていくことが一つの魅力だと思います。
皆様に靴でのトラブルなど何かあれば伺えますか。
Q: 私はくるぶしが人よりも出ているので、既成靴だと脇の部分がくるぶしに当たって血が出たりするのが困ります。
A: 足には56本の骨があります。脚部の脛骨腓骨が拠点を取る距骨がありその下に踵骨つまり地面を踏むかかとの骨があります。脛骨腓骨が距骨とつながるそのでっぱりがくるぶしです。くるぶしの高さは人によって異なります。一方、既製品は一つの形で、統計的にこのサイズならくるぶしの位置はこのあたりと決めています。ですから自分の足よりも大きいサイズの靴を履くとくるぶしに当たるという可能性があります。ビスポーク靴の場合はくるぶしもきちんと測って当たらないようにデザインすることができます。
Q: 私は女性用の靴をオーダーで作ったのですが、出来上がった靴がリハビリで履くようなみっともない靴で、外で履けるような靴ではありません。結局今はスニーカーを履いていますが、スニーカーだとヒールの靴が履けなくなります。ヒールの靴は常に履いていないといけないのでしょうか。
A: オーダー靴の難しい点は、足に合わせると足に近い形になってしまうという点です。既製品はある一定の足の体積と作りやすさ、足へのなじみ方で成立するように作られているので、時には過度に格好よく作られています。
ヒールの靴は見た目に美しいと思います。ふくらはぎを緊張させるので鍛えられます。ただ地面を踏む場所の高低差があるので、痛かったり疲れたりします。ヨーロッパでは足のことを考えて、パンプスなどは現地で履き替える風習もあるようですが、日本ではそういうことがないので、女性の悩みとしては一番多いですね。
Q: オーダー靴を注文した場合、依頼してから商品が届くまでどれくらいの時間がかかりますか。
A: 私の実働時間を1日12~16時間労働として考えると14日から16日くらい、8時間労働として考えるとおひとり様約1ヶ月となります。 しかし、一人のお客様の靴だけを作るわけではありませんし、革のなじみとかマテリアルの伸びなどの時間がありますので、私がオーダーを受けるときは1足9か月いただきます。早いと半年くらいの場合もあります。
今日はどうもありがとうございました。
皆さん初めまして、土屋と申します。よろしくお願いいたします。
私は東京の国分寺でビスポークというオーダー靴、手で一つずつ靴を作る仕事をしております。今回、オーダー靴がどういうものかを知っていただけたらと思いお話しさせていただきます。
私は、靴を作り始めて20年、年齢は46歳です。高校卒業後にプロのダンサーとして、ヒップホップと言われるストリートダンスをやっていました。ヒップホップダンスは黒人の音楽から始まったもので、黒人のダンサーとも仲良くショータイムに出演したりしていたのですが、その中で黒人に対する差別などがあることを知り、自分は何も知らない人間なのだと気づき、世界の文化に対する興味が広がりました。そこでバックパックで旅に出ることにしました。7か月余り、少ない荷物を背負って陸路で世界中を回る中で色々な経験をしました。ストリートで手で物を作って売る人々をみたりして、物づくりに興味を持つようになりました。
日本の二大巨頭の靴の町の一つ、東京浅草にある東京都の職業訓練校に入ったことで私の靴との関わりが始まりました。単純に手で靴を作ることが楽しかったので、この感じで就職できないかと考えましたが、当時は量産靴を買うのが主流の時代でした。靴を手で作る唯一の就職先が義肢装具の会社でした。障害者のための靴は一つずつ、お客様の足と症状に合わせて作っていきます。この義肢装具の会社で靴を作っていく中で二人の師匠と出会いました。
一人はオーダーパンプスの巨匠の斉藤師匠です。師匠は、昨年引退されましたが、それまで私は週1回お手伝いをしながら、足のことや健康のことをたくさん学びました。
もう一人が、津久井玲子師匠です。日本の伝説の靴職人で業界ではレジェンドと呼ばれる関信義さんの一番弟子です。関さんは亡くなられましたが、私は関さんの一番弟子の一番弟子なので孫弟子となります。その縁があって、きれいな革靴、長く持つ革靴を学ぶことができました。
こうしてずっと靴を作り続けています。そして今は、専門学校で特別専門技術を教えたり、自分の工房に皆様もご存知のような某大手靴メーカーのプロの方々が習いに来ています。量産靴は、専門が分かれており完全分業で作られています。分業ゆえにプロフェッショナルであり、良い点がたくさんあります。 一方、私のビスポークという一人が一つずつ全てを作っていく靴は、一つずつの工程で問題解決をすることができ、終始細部まで丁寧に作り上げられます。この一人が最後まで全部責任を持って作業できることが一番大きな魅力です。私は習いに来ている方々からもたくさん教えてもらって、日々精進しています。
古い時代にはヨーロッパで職人同士が技術を競い合う大会が開催されていましたが、近年は手作りの靴が主流でなかったために長年開催されていませんでした。それが最近、手作りの靴の魅力が見直され、2018年に世界大会が復活しました。この大会にはジョンロブやコルテ、カジアーノ&ガーリングなどの名店と言われる靴屋のビスポークを扱う職長クラスが参加しています。私も面白いと思って2019年の大会に出場しました。この世界的に技術を競う靴の大会で10位までが入賞のところ、私は7位になり世界のトップテンに入ることができました。
また、国分寺市のふるさと納税で私の靴を買うことができます。そこで会員の青栁様と出会い、今回の卓話に至るということになりました。
さて、ビスポークについてお話いたします。
ビスポークはオーダー靴ということになります。ビースポーク、ビースポークンとも言います。直訳すると職人の話を聞きながらオーダーするという意味のようです。スーツのオーダーでも使われる言葉です。私は、「話される」の直訳から、ビスポークを「仰せのままに」と捉えています。高い技術でお客様の要望を叶える。足に合わせて、格好良いデザインで、堅牢で一生持つような靴を作る責務がある仕事だと考えています。
ビスポーク靴の魅力の一つは堅牢であることです。皆さんが履いているような靴の形はイギリスのノーザンプトンで生まれたと言われています。産業革命でセメント靴など値段が安く気軽に買える靴が登場しました。しかし、昔からある作りで、いまだにそれを超える製法がない堅牢な靴であることがビスポーク靴の大きな魅力となっていることを知っていただきたいと思います。
もう一つの魅力は一人の職人が一つの靴を徹底的に作り上げる点です。先ほどお話したように、私は教職にもあるので、某大手メーカーの企画の方から相談を受けることもあります。量産靴で専門性を持っている人はその専門分野については長けています。しかし、他の分野で問題が起こったり、最後の完成図が見えないために問題解決ができないことがあります。ですから、お客さまの足を見て、歩き方や好み、普段の生活を聞いた上で一つの形を作り上げていくことが一つの魅力だと思います。
皆様に靴でのトラブルなど何かあれば伺えますか。
Q: 私はくるぶしが人よりも出ているので、既成靴だと脇の部分がくるぶしに当たって血が出たりするのが困ります。
A: 足には56本の骨があります。脚部の脛骨腓骨が拠点を取る距骨がありその下に踵骨つまり地面を踏むかかとの骨があります。脛骨腓骨が距骨とつながるそのでっぱりがくるぶしです。くるぶしの高さは人によって異なります。一方、既製品は一つの形で、統計的にこのサイズならくるぶしの位置はこのあたりと決めています。ですから自分の足よりも大きいサイズの靴を履くとくるぶしに当たるという可能性があります。ビスポーク靴の場合はくるぶしもきちんと測って当たらないようにデザインすることができます。
Q: 私は女性用の靴をオーダーで作ったのですが、出来上がった靴がリハビリで履くようなみっともない靴で、外で履けるような靴ではありません。結局今はスニーカーを履いていますが、スニーカーだとヒールの靴が履けなくなります。ヒールの靴は常に履いていないといけないのでしょうか。
A: オーダー靴の難しい点は、足に合わせると足に近い形になってしまうという点です。既製品はある一定の足の体積と作りやすさ、足へのなじみ方で成立するように作られているので、時には過度に格好よく作られています。
ヒールの靴は見た目に美しいと思います。ふくらはぎを緊張させるので鍛えられます。ただ地面を踏む場所の高低差があるので、痛かったり疲れたりします。ヨーロッパでは足のことを考えて、パンプスなどは現地で履き替える風習もあるようですが、日本ではそういうことがないので、女性の悩みとしては一番多いですね。
Q: オーダー靴を注文した場合、依頼してから商品が届くまでどれくらいの時間がかかりますか。
A: 私の実働時間を1日12~16時間労働として考えると14日から16日くらい、8時間労働として考えるとおひとり様約1ヶ月となります。 しかし、一人のお客様の靴だけを作るわけではありませんし、革のなじみとかマテリアルの伸びなどの時間がありますので、私がオーダーを受けるときは1足9か月いただきます。早いと半年くらいの場合もあります。
今日はどうもありがとうございました。
卓話 「『後列のひと』を描き続けるわけ」
ノンフィクション作家 清武英利様
2020年1月30日

 ご紹介いただきました清武です。
私は今、三つ目の人生を生きております。元々は、読売新聞社会部の記者を長く務めました。その後、読売巨人軍の球団代表を務めましたが、その非を訴えて辞めて、今は、ノンフィクションを書いています。
現在、文芸春秋で連載している『後列のひと』は、当初1年の約束でしたが、面白いので続けるように依頼され、2年目になりました。週刊文春では『サラリーマン球団社長』を連載しております。基本的に私のテーマは、組織を支える人です。『後列のひと』とは、例えば、講堂に集まった時に後方にいるような人々のことです。私はそういう人が好きですし、自分もその一人でした。
私が、中部本社の社会部長を務めていた頃に『幸せの新聞』というものを作っていました。新聞を読んでいると悲しいことや怒ることが多いですね。新聞記者がそういうニュースを選んでいるからなのです。私は長い間トップランナーを追いかけ、特ダネを追いかけ、人を傷つけたりもしたので、中部本社社会部長になったとき、これからは1ページだけ幸せの記事で埋めたいと思いました。編集長の私も自分で書き、実際に一年半続けて、後輩に引き継ぎました。
人間には不幸なこともたくさんありますが、例えば倒産した場合、人は倒れたら起き上がるしかありません。そこを捉えると、もしかすると、幸せに向かう道を切り取れるかもしれないと思い、そのようなニュースを積極的に取り上げました。『後列のひと』は、その路線上にあると思っています。
私は球団代表を辞めた後に、『しんがり 山一證券最後の12人』というノンフィクションで、山一證券破綻の際に会社に踏みとどまって清算活動をしたり、破綻の真相について一生懸命追求した人々、今まで全く目立たなかったが、破綻した時点で光り輝くような、心の中に核のようなものを持っている人々を描きました。当時、私は読売新聞グループとの間で6、7件の関連の裁判を抱えて、1年間に証人尋問が何度もあり、大変緊張しておりました。そのようなときに、山一證券の人々は今何をしているのだろうと思って取材したところ、自分自身の苦しみや怒りは大したものではないと思えました。
この『しんがり』で講談社からノンフィクション賞をいただき、その後『プライベートバンカー』や『石つぶて』を書き、少し前に『トッカイ』を書きました。『しんがり』と『石つぶて』はWOWOWでドラマ化されており、『トッカイ』も多分ドラマ化されるでしょう。『トッカイ』とは、不良債権の特別回収部のことで、整理回収機構の中で日本の不良債権を回収するために歩いた人々の実話です。私はずっとノンフィクションを書いているので、そういう人々に心打たれるところがあります。
『後列のひと』では、心打たれるような人、胸の奥をつかまれるような人を探しています。本当はそういう人々がたくさんいると思います。本日も、この卓話の後、特攻兵士のための旅館を経営されていたご夫婦の話をお伺いすることになっています。そういう人々を探していく作業は、大変厄介で面倒ですが、お話を聞くと何時間でも聞くことができるようになりました。人の人格はそう簡単に分かるわけがないので、私は1回会っただけではまず書きません。3回、4回と会い、色んな取材をします。聞いたお話は可能ならばテープに録音して全文を書き起こします。新聞記者は基本的に人が言ったことを書くわけです。言わないことは書いてはいけないので。しかし、人は本音をなかなか言わないものです。言わんとするところをどう汲み取るかが大事なのです。
よく、人間は肉体が滅びただけでは死なない、その人を知る人が亡くなった時にその人生がこの世界から消えるといいます。でも、自分を知っていると思う人が、本当はどこまで知っているのでしょうか。人間はプリズムのような多面体ですから、自分だけが知っている自分、他人が知っている自分、他人も自分も知らない自分があるかもしれません。そういう多面的なものを何とかして残すべきだと思います。
この会場には、亡くなられたときに新聞の死亡欄に載られる方が何人もいらっしゃると思います。業界の用語で「亡者記事」と言います。私もあるいは載るかもしれませんが、私は自分を知らない若い記者に書かれたくないので、自分で亡者記事の予定稿を書いています。自分の亡者原稿を書くのに大事なことは何歳で死ぬかと考えることです。私は今69歳ですが父の人生を超えたいと思っているので、79歳、80歳くらいまで頑張りたいと思っています。例えば、79歳で死ぬとしたら、あと10年あります。その10年間に何をやるかを考えなければいけません。亡者原稿にはまだ実現していないことも書き入れるのです。私は最後に桜の盆栽家と言われたいので、亡者原稿には、晩年は桜の盆栽家としてこのような作品を残したというように書きます。そうすると、亡者記事が死亡記事ではなく希望記事のようになります。
また、死ぬまでに自分がやりたいことのリスト、「バケットリスト」を作るという方法もあります。これは、モーガン・フリーマンとジャック・ニコルソンが出演した映画、邦題の課『最高の人生の見つけ方』で非常に有名になりました。バケットリストには自分が本当にやりたいこと、欲しいものを書いて、実現したら消していくことが大事です。私は、「ノンフィクションの賞が欲しい」と書き、実現したのでそれを消しました。バケットリストには出来るだけ実現可能な、しかし最大限の努力を要するものを書き、人に見せずにひとつずつ実現していきます。そしていつか残された人が亡者原稿と合わせて知ることになるでしょう。
今、週刊文春で連載している『サラリーマン球団社長』では、阪神電鉄の傍流の部長が、ある日突然「阪神タイガースに出向せよ」と言われて、全くの素人が球団社長となって再建するという話を書いています。私は巨人から阪神を見ていて、本当に不思議な球団だと思いました。1リーグ6チームでやっているのだから6年に1回は優勝できるはずなのに、15年以上も優勝できないのは自然の理に反しています。球界七不思議のひとつです。それを変えようとして、サラリーマンの目からみた経営改善、改造に取り組む苦労と壁を描いています。球団社長としては安い給料でしたが、それでも頑張るという気持ちを支えていたのは、あきらめたらあかん、という後列人の意気地です。タイガースファンの方々、阪神タイガースを甘やかしてはいけません。
どうも野球の話になると熱を帯びてしまいますが、本日は、亡者原稿とバケットリストのことだけ覚えておいて下さい。どうもありがとうございました。
【卓話編集後記】
今回の卓話では、困難な問題に直面した時、それまで目立つこともなかった人が力を発揮して道を切り開いていく姿を描いたノンフィクション作品を発表している清武様のお話を伺いました。清武様の作品は読者に勇気と感動を与えていますが、その陰には、描かれている人たちの声に耳を傾けしっかりと聞くという取材への強いこだわりがあったことに感銘を受けました。
また、死ぬまでにやりたいことのリストを作るだけでなく、新聞の死亡記事「亡者原稿」を自分自身で書いておくというお話は、残りの人生をどう生きるかを考える大事なヒントになり、会員の方々もなるほどと思われたようです。
ご紹介いただきました清武です。
私は今、三つ目の人生を生きております。元々は、読売新聞社会部の記者を長く務めました。その後、読売巨人軍の球団代表を務めましたが、その非を訴えて辞めて、今は、ノンフィクションを書いています。
現在、文芸春秋で連載している『後列のひと』は、当初1年の約束でしたが、面白いので続けるように依頼され、2年目になりました。週刊文春では『サラリーマン球団社長』を連載しております。基本的に私のテーマは、組織を支える人です。『後列のひと』とは、例えば、講堂に集まった時に後方にいるような人々のことです。私はそういう人が好きですし、自分もその一人でした。
私が、中部本社の社会部長を務めていた頃に『幸せの新聞』というものを作っていました。新聞を読んでいると悲しいことや怒ることが多いですね。新聞記者がそういうニュースを選んでいるからなのです。私は長い間トップランナーを追いかけ、特ダネを追いかけ、人を傷つけたりもしたので、中部本社社会部長になったとき、これからは1ページだけ幸せの記事で埋めたいと思いました。編集長の私も自分で書き、実際に一年半続けて、後輩に引き継ぎました。
人間には不幸なこともたくさんありますが、例えば倒産した場合、人は倒れたら起き上がるしかありません。そこを捉えると、もしかすると、幸せに向かう道を切り取れるかもしれないと思い、そのようなニュースを積極的に取り上げました。『後列のひと』は、その路線上にあると思っています。
私は球団代表を辞めた後に、『しんがり 山一證券最後の12人』というノンフィクションで、山一證券破綻の際に会社に踏みとどまって清算活動をしたり、破綻の真相について一生懸命追求した人々、今まで全く目立たなかったが、破綻した時点で光り輝くような、心の中に核のようなものを持っている人々を描きました。当時、私は読売新聞グループとの間で6、7件の関連の裁判を抱えて、1年間に証人尋問が何度もあり、大変緊張しておりました。そのようなときに、山一證券の人々は今何をしているのだろうと思って取材したところ、自分自身の苦しみや怒りは大したものではないと思えました。
この『しんがり』で講談社からノンフィクション賞をいただき、その後『プライベートバンカー』や『石つぶて』を書き、少し前に『トッカイ』を書きました。『しんがり』と『石つぶて』はWOWOWでドラマ化されており、『トッカイ』も多分ドラマ化されるでしょう。『トッカイ』とは、不良債権の特別回収部のことで、整理回収機構の中で日本の不良債権を回収するために歩いた人々の実話です。私はずっとノンフィクションを書いているので、そういう人々に心打たれるところがあります。
『後列のひと』では、心打たれるような人、胸の奥をつかまれるような人を探しています。本当はそういう人々がたくさんいると思います。本日も、この卓話の後、特攻兵士のための旅館を経営されていたご夫婦の話をお伺いすることになっています。そういう人々を探していく作業は、大変厄介で面倒ですが、お話を聞くと何時間でも聞くことができるようになりました。人の人格はそう簡単に分かるわけがないので、私は1回会っただけではまず書きません。3回、4回と会い、色んな取材をします。聞いたお話は可能ならばテープに録音して全文を書き起こします。新聞記者は基本的に人が言ったことを書くわけです。言わないことは書いてはいけないので。しかし、人は本音をなかなか言わないものです。言わんとするところをどう汲み取るかが大事なのです。
よく、人間は肉体が滅びただけでは死なない、その人を知る人が亡くなった時にその人生がこの世界から消えるといいます。でも、自分を知っていると思う人が、本当はどこまで知っているのでしょうか。人間はプリズムのような多面体ですから、自分だけが知っている自分、他人が知っている自分、他人も自分も知らない自分があるかもしれません。そういう多面的なものを何とかして残すべきだと思います。
この会場には、亡くなられたときに新聞の死亡欄に載られる方が何人もいらっしゃると思います。業界の用語で「亡者記事」と言います。私もあるいは載るかもしれませんが、私は自分を知らない若い記者に書かれたくないので、自分で亡者記事の予定稿を書いています。自分の亡者原稿を書くのに大事なことは何歳で死ぬかと考えることです。私は今69歳ですが父の人生を超えたいと思っているので、79歳、80歳くらいまで頑張りたいと思っています。例えば、79歳で死ぬとしたら、あと10年あります。その10年間に何をやるかを考えなければいけません。亡者原稿にはまだ実現していないことも書き入れるのです。私は最後に桜の盆栽家と言われたいので、亡者原稿には、晩年は桜の盆栽家としてこのような作品を残したというように書きます。そうすると、亡者記事が死亡記事ではなく希望記事のようになります。
また、死ぬまでに自分がやりたいことのリスト、「バケットリスト」を作るという方法もあります。これは、モーガン・フリーマンとジャック・ニコルソンが出演した映画、邦題の課『最高の人生の見つけ方』で非常に有名になりました。バケットリストには自分が本当にやりたいこと、欲しいものを書いて、実現したら消していくことが大事です。私は、「ノンフィクションの賞が欲しい」と書き、実現したのでそれを消しました。バケットリストには出来るだけ実現可能な、しかし最大限の努力を要するものを書き、人に見せずにひとつずつ実現していきます。そしていつか残された人が亡者原稿と合わせて知ることになるでしょう。
今、週刊文春で連載している『サラリーマン球団社長』では、阪神電鉄の傍流の部長が、ある日突然「阪神タイガースに出向せよ」と言われて、全くの素人が球団社長となって再建するという話を書いています。私は巨人から阪神を見ていて、本当に不思議な球団だと思いました。1リーグ6チームでやっているのだから6年に1回は優勝できるはずなのに、15年以上も優勝できないのは自然の理に反しています。球界七不思議のひとつです。それを変えようとして、サラリーマンの目からみた経営改善、改造に取り組む苦労と壁を描いています。球団社長としては安い給料でしたが、それでも頑張るという気持ちを支えていたのは、あきらめたらあかん、という後列人の意気地です。タイガースファンの方々、阪神タイガースを甘やかしてはいけません。
どうも野球の話になると熱を帯びてしまいますが、本日は、亡者原稿とバケットリストのことだけ覚えておいて下さい。どうもありがとうございました。
【卓話編集後記】
今回の卓話では、困難な問題に直面した時、それまで目立つこともなかった人が力を発揮して道を切り開いていく姿を描いたノンフィクション作品を発表している清武様のお話を伺いました。清武様の作品は読者に勇気と感動を与えていますが、その陰には、描かれている人たちの声に耳を傾けしっかりと聞くという取材への強いこだわりがあったことに感銘を受けました。
また、死ぬまでにやりたいことのリストを作るだけでなく、新聞の死亡記事「亡者原稿」を自分自身で書いておくというお話は、残りの人生をどう生きるかを考える大事なヒントになり、会員の方々もなるほどと思われたようです。
卓話 「英語の語源を学べばわかる日本の古さ」
明治大学教授 織田哲司様
2020年1月23日

 本日はお招きいただきましてありがとうございます。
今日は「英語の語源を学べばわかる日本の古さ」というタイトルで、英語と日本がどう繋がるのか不思議に思われるかもしれませんが、話が進むにつれて繋がっていくのが見えてくれば良いと思っています。
この会はいつもキャピトル東急ホテルで開催されているということですが、実はこの場所はパワースポットです。パワースポットというのは神様から良い力をいただける場所です。隣に日枝神社、総理官邸などもありますが、昔から日本人はパワースポットであることを分かっていて、重要な建物を建てていました。何故なのかというのは、これから徐々に話が繋がっていくと思います。
私の専門は英語の歴史で、1500年の歴史がある英語の、どの時代の文献も読めます。 そしてこの英語の歴史から、なんの関係もないような日本のことも見えてくるというのが分かってきたということをお話してまいります。
今日は普段英語とは縁のない方にも親しみのある単語で、この場所にも関係のある単語を探してきました。
まず、「soul」という単語、「魂」という意味です。日本語の場合、漢字は偏と旁から成り立っているので、肉月があれば身体に関係する漢字だということが予想できますし、自分でも分けてバラバラにすることができます。英語の場合も、語源を知るために分けることができます。この「soul」という単語を語源で分けると、「sou」と「l」の間で分けることができます。「sou」は「海」、「l」は「~に属するもの」という意味です。何故、魂は海に属するものなのかというと、イギリス人の祖先であるドイツの人々あるいは北欧の人々、特に沿岸部の人々は皆、魂は海から来て海へ還ると考えていたようです。このことを知った時に私は、日本と同じではないかということに気づきました。
キャピトル東急ホテルのある赤坂から銀座のあたりの縄文時代の地図を見ると、外堀通りは、昔は海の底で、日枝神社のある場所は岬の突端になります。かつて岬の突端だった場所は、多くの場合、現在、神社か寺か墓地になっているという特徴があります。何故かというと、先祖の魂は海の底に眠っていると考えられて、海に一番近い岬の突端で先祖のためのお祭りを昔から行ってきたからです。岬は魂に会える聖なる場所であり、魂は海に還ると日本人も思っていたようです。 「soul」の語源を調べていくと、あの世に対して日本人の祖先と同じような感覚を持っていたことが分かるということで、ご紹介しました。
地名も語源をたどると面白い発見があります。 何故「赤坂」という地名がついたかというと、この辺りは昔海の底でしたから、地面は粘土質の土です。粘土で作る埴輪でもお分かりのように赤っぽい土です。つまりこの辺りは赤い土の坂道だったので「赤坂」と呼ばれるようになったようです。赤坂の「坂」という言葉は「底」や「境」と関係があります。この世とあの世(異界)の境、この世とあの世をつなぐのが坂である、坂道の下にはこちらとは違う世界がある、ひょっとしたら神様がおられると、昔の日本人は考えていたようです。
次の単語は「king」、王様です。この短い単語も語源で敢えて分けてみると、nの真ん中で分けることができます。「kin」と「ing」という成り立ちで、1000年位前までは「キング」ではなく「キニング」と呼んでいたようです。「kin」は一族や生まれを表し、「ing」は跡取りを表し、一族の跡取りというのが元々の意味でした。 一族の跡取りを一番大事にする家系は世界中どこでも王家です。この一族の跡取りから、リーダー、王様というように意味が変わってきたと考えられます。
ヨーロッパのさまざまな言語は、今から6000年、8000年前には一つのところの一つの言葉であったと考えられています。 その場所は、南ロシアのカスピ海と黒海の間にひろがるステップ地帯であったと言われています。このステップ地帯から、やがて西へ移動していった人々が今のヨーロッパの人々です。そして、東南の方へ移動していった人々がアフガニスタン、イランを経てインドの人々になりました。 よく考えてみると、南ロシアのステップ地帯はシルクロードの終点です。この地域から西に移動した人々はアルファベットの文字を使い、東に移動した人々は恐らく漢字を使っていたはずです。
先ほどのkinは一族や生まれを表す言葉でしたが、ガ行になるとgen(ゲン)となります。例えば、「generate」は「生み出す」という意味ですし、生み出された人々の集まり、「generation」は「世代」という意味になります。漢字でサンズイに「原」を書いた「源(ゲン)」という言葉も生まれを表しています。証明するのは難しいのですが、語源は同じだと考えられているようです。
ヨーロッパの王家の家系図では、先祖をたどると必ず神に繋がっています。父なる天の神と母なる大地の神が結ばれて生まれたのが王の先祖だと考えられています。考えてみると日本も同じです。天照大御神(アマテラスオオミカミ)から繋がっていると言われているのですから非常に似た考え方です。 ここで面白いのは、父なる天と母なる大地が結ばれて生まれた子供の末裔がこの世を治めるkingであるという考え方は、日本の王家(皇室)にも通じていることです。神武天皇の父親の家系は天の神です。最終的には天照大御神につながりますが、父親は天神です。一方、母親の家系は木花佐久夜姫(コノハナサクヤヒメ)につながる、大地系の神です。天と地が結ばれて、その結果生まれた王が日本を統べるという考え方です。 そして日本の天皇は、大嘗祭で天照大御神から霊性をチャージされて、治める力を得るという儀式を行っています。天と地の交わりから生まれた人がこの国を治める力を持つという考え方は西洋も日本も同じですが、大嘗祭のような天の力をチャージされるということが今でも続いている国、古代性が現代にも残っている国は日本だけです。
私の恩師の渡部昇一先生は、日本の歴史や政治評論などでも活躍されていましたが、元々は英語研究の専門家でした。私たちに「英語の古い言葉を勉強しているのは、それで良いけれど、いつかは日本に戻ってくるんだよ」とおっしゃっていました。こうしてみると、英単語の語源からイギリス人の先祖の世界観をうかがい知ると同時に、日本には古代性が残っているという、英語から日本の古さに繋がることができ、日本は歴史があって本当に良い国だということで、そのような話の一端をご紹介させていただきました。
ありがとうございました。
【卓話編集後記】
親しみやすい英単語を例に挙げて、言葉の成り立ちを解説していただき、語源を遡ると英語と日本語に共通点があることや、神話から読み解ける日本の皇室とヨーロッパの王家の共通点など、思いがけない発見がありました。
例会場のキャピトル東急ホテル周辺の縄文時代の地図を見ながら、地名の由来も説明していただきました。例会場周辺はパワースポットであるというお話に、参加した会員は新なパワーをもらったような心地になりました。
本日はお招きいただきましてありがとうございます。
今日は「英語の語源を学べばわかる日本の古さ」というタイトルで、英語と日本がどう繋がるのか不思議に思われるかもしれませんが、話が進むにつれて繋がっていくのが見えてくれば良いと思っています。
この会はいつもキャピトル東急ホテルで開催されているということですが、実はこの場所はパワースポットです。パワースポットというのは神様から良い力をいただける場所です。隣に日枝神社、総理官邸などもありますが、昔から日本人はパワースポットであることを分かっていて、重要な建物を建てていました。何故なのかというのは、これから徐々に話が繋がっていくと思います。
私の専門は英語の歴史で、1500年の歴史がある英語の、どの時代の文献も読めます。 そしてこの英語の歴史から、なんの関係もないような日本のことも見えてくるというのが分かってきたということをお話してまいります。
今日は普段英語とは縁のない方にも親しみのある単語で、この場所にも関係のある単語を探してきました。
まず、「soul」という単語、「魂」という意味です。日本語の場合、漢字は偏と旁から成り立っているので、肉月があれば身体に関係する漢字だということが予想できますし、自分でも分けてバラバラにすることができます。英語の場合も、語源を知るために分けることができます。この「soul」という単語を語源で分けると、「sou」と「l」の間で分けることができます。「sou」は「海」、「l」は「~に属するもの」という意味です。何故、魂は海に属するものなのかというと、イギリス人の祖先であるドイツの人々あるいは北欧の人々、特に沿岸部の人々は皆、魂は海から来て海へ還ると考えていたようです。このことを知った時に私は、日本と同じではないかということに気づきました。
キャピトル東急ホテルのある赤坂から銀座のあたりの縄文時代の地図を見ると、外堀通りは、昔は海の底で、日枝神社のある場所は岬の突端になります。かつて岬の突端だった場所は、多くの場合、現在、神社か寺か墓地になっているという特徴があります。何故かというと、先祖の魂は海の底に眠っていると考えられて、海に一番近い岬の突端で先祖のためのお祭りを昔から行ってきたからです。岬は魂に会える聖なる場所であり、魂は海に還ると日本人も思っていたようです。 「soul」の語源を調べていくと、あの世に対して日本人の祖先と同じような感覚を持っていたことが分かるということで、ご紹介しました。
地名も語源をたどると面白い発見があります。 何故「赤坂」という地名がついたかというと、この辺りは昔海の底でしたから、地面は粘土質の土です。粘土で作る埴輪でもお分かりのように赤っぽい土です。つまりこの辺りは赤い土の坂道だったので「赤坂」と呼ばれるようになったようです。赤坂の「坂」という言葉は「底」や「境」と関係があります。この世とあの世(異界)の境、この世とあの世をつなぐのが坂である、坂道の下にはこちらとは違う世界がある、ひょっとしたら神様がおられると、昔の日本人は考えていたようです。
次の単語は「king」、王様です。この短い単語も語源で敢えて分けてみると、nの真ん中で分けることができます。「kin」と「ing」という成り立ちで、1000年位前までは「キング」ではなく「キニング」と呼んでいたようです。「kin」は一族や生まれを表し、「ing」は跡取りを表し、一族の跡取りというのが元々の意味でした。 一族の跡取りを一番大事にする家系は世界中どこでも王家です。この一族の跡取りから、リーダー、王様というように意味が変わってきたと考えられます。
ヨーロッパのさまざまな言語は、今から6000年、8000年前には一つのところの一つの言葉であったと考えられています。 その場所は、南ロシアのカスピ海と黒海の間にひろがるステップ地帯であったと言われています。このステップ地帯から、やがて西へ移動していった人々が今のヨーロッパの人々です。そして、東南の方へ移動していった人々がアフガニスタン、イランを経てインドの人々になりました。 よく考えてみると、南ロシアのステップ地帯はシルクロードの終点です。この地域から西に移動した人々はアルファベットの文字を使い、東に移動した人々は恐らく漢字を使っていたはずです。
先ほどのkinは一族や生まれを表す言葉でしたが、ガ行になるとgen(ゲン)となります。例えば、「generate」は「生み出す」という意味ですし、生み出された人々の集まり、「generation」は「世代」という意味になります。漢字でサンズイに「原」を書いた「源(ゲン)」という言葉も生まれを表しています。証明するのは難しいのですが、語源は同じだと考えられているようです。
ヨーロッパの王家の家系図では、先祖をたどると必ず神に繋がっています。父なる天の神と母なる大地の神が結ばれて生まれたのが王の先祖だと考えられています。考えてみると日本も同じです。天照大御神(アマテラスオオミカミ)から繋がっていると言われているのですから非常に似た考え方です。 ここで面白いのは、父なる天と母なる大地が結ばれて生まれた子供の末裔がこの世を治めるkingであるという考え方は、日本の王家(皇室)にも通じていることです。神武天皇の父親の家系は天の神です。最終的には天照大御神につながりますが、父親は天神です。一方、母親の家系は木花佐久夜姫(コノハナサクヤヒメ)につながる、大地系の神です。天と地が結ばれて、その結果生まれた王が日本を統べるという考え方です。 そして日本の天皇は、大嘗祭で天照大御神から霊性をチャージされて、治める力を得るという儀式を行っています。天と地の交わりから生まれた人がこの国を治める力を持つという考え方は西洋も日本も同じですが、大嘗祭のような天の力をチャージされるということが今でも続いている国、古代性が現代にも残っている国は日本だけです。
私の恩師の渡部昇一先生は、日本の歴史や政治評論などでも活躍されていましたが、元々は英語研究の専門家でした。私たちに「英語の古い言葉を勉強しているのは、それで良いけれど、いつかは日本に戻ってくるんだよ」とおっしゃっていました。こうしてみると、英単語の語源からイギリス人の先祖の世界観をうかがい知ると同時に、日本には古代性が残っているという、英語から日本の古さに繋がることができ、日本は歴史があって本当に良い国だということで、そのような話の一端をご紹介させていただきました。
ありがとうございました。
【卓話編集後記】
親しみやすい英単語を例に挙げて、言葉の成り立ちを解説していただき、語源を遡ると英語と日本語に共通点があることや、神話から読み解ける日本の皇室とヨーロッパの王家の共通点など、思いがけない発見がありました。
例会場のキャピトル東急ホテル周辺の縄文時代の地図を見ながら、地名の由来も説明していただきました。例会場周辺はパワースポットであるというお話に、参加した会員は新なパワーをもらったような心地になりました。
卓話 「脳を元気に働かせるための考え方と記憶の技術」
ライフアセットコンサルティング株式会社 代表取締役 菱田雅生様
2019年12月12日

 皆さま、こんにちは。ご紹介いただきました菱田雅生です。
「脳を元気に働かせるための考え方と記憶の技術」というお話をします。
よりよく脳を働かせる考え方を説明し、たった5分で15個の単語を完璧に順番通りに記憶できるという記憶法を体験していただきます。
皆さん、自分は元々記憶力が悪い、頭が悪いとか、能力は遺伝で決まっている、年齢と共に記憶力は悪くなる、暗記や勉強は大変で辛いものだ、能力や記憶力の要領には限界がある、と思ったことはないでしょうか。これは全部間違っています。
人間の能力や記憶力には、とてつもない力があります。しかし、その使い方をよく知らないので上手に使いきれていません。年を取っても記憶力は衰えません。年を取ると興味があることと無いことの区別がはっきりして、興味のないことは覚えません。人の顔と名前が覚えられない理由はその人に興味が無いからなのです。能力は遺伝によってだけでは決定されませんし、能力や記憶力の容量に限界はありません。暗記や勉強はとても楽しいものなのです。
9年前に米国のタフツ大学のアヤナ・トーマス先生が行った実験があります。20代と60代の人たちに50個の単語を渡して覚えてもらいました。一つのグループには心理学のテストですと言って覚えてもらい、もう一つのグループには記憶力のテストですと言って覚えてもらいました。覚えてもらった後で、50個の単語が書いてある新しい紙を渡して、先ほど覚えた単語と同じ単語があれば丸をつけてもらいました。すると、心理学のテストだと伝えたグループは20代も60代もほぼ同じ正答率でした。一方、記憶力のテストだと伝えたグループは60代の正答率が低かったそうです。 これは、年と共に記憶力が悪くなるという思い込みによるものです。そう思い込むとそうなってしまうのです。
では、記憶の実験を始めます。これから私が言う15個の単語を覚えていただきます。覚えてもらったあとで、私がどうぞといったら書いていただきます。番号と言葉が合っていたら2点、言葉が出てきたら1点と採点します。15個ですので30点満点です。 記憶のやり方をまだお伝えしていないので、今の状態でチャレンジしてみてください。
1番 灯台、2番 金網、3番 王様、4番 ハート、5番 サイコロ、6番 ハチ、7番 標識、8番 ホッカイロ、9番 博多ラーメン、10番 しずかちゃん、11番 水戸黄門、12番 広場、13番 教会、14番 牛タン弁当、15番 佐渡島、以上です。
エビングハウス博士の忘却曲線をご存知ですか。人間は記憶したものの量を時間の経過に比例して忘れていくのではなく、一気に忘れてしまうようです。一日経つと7割は忘れるそうです。 私たちの脳にある短期記憶は2,3分で消えるようです。
では、先ほどの15個の単語を書いてみてください。(会員は回答記入)
30点満点の方は、さすがにいらっしゃらないようですね。 後でやり方をお教えします。
次に20個の単語の瞬間記憶、皆さんに出していただいた20個の単語を私が完璧に覚えてみせます。1番から20番まで順番に言うことが出来るし、20番から遡ることもできるし、何番と聞かれたらその単語を答えるし、単語を言われたら何番と答えます。
(菱田氏の記憶術デモンストレーション)
ここで私が覚えた20の単語は長期記憶の中に入れる方法で覚えたので、1,2週間は忘れません。これは私が記憶のセミナーの講師だから出来るというわけではありません。皆さんも2日間の本講座を受ければ全員できるようになります。やり方があるのです。
よりよく脳を働かせる考え方には6つのポイントがあります。
① 「できる」という自信と決意。プラスの言葉を使う
② 好奇心と集中
③ イメージと感受性
④ 目的とビジョン
⑤ 反復
⑥ きちんと理解する
プラスの言葉を使うのは重要です。「無理」「難しい」「苦手」というと思考が止まってしまいます。好奇心を持って物を見ると脳は年齢に関係なく元気になります。はっきりイメージすると脳に残る仕組みになっています。1週間前の昼ご飯は覚えていないのに、何年も前にレストランで食べた美味しかったご飯をなぜ覚えているかというと、感情が動いているからです。目的やビジョンがあると脳は元気に働きます。反復することで非常に大きな刺激を脳に与えます。そしてきちんと理解したことは忘れないという仕組みになっています。
さて、先ほどの15個の単語をストーリー法で記憶するという技法で皆さんの脳の中に入れます。記憶の技法は6種類ほどありますが、その中の一つの技法です。物語のように単語をくっつけますので、頭の中で思い浮かべてください。
灯台の先から金網が出ていて、王様がぐるぐる巻きにされていて、ハートのクッションが落ちてきて、中からサイコロが出てきて、ハチが飛んできてサイコロ1個摘み上げて飛んでいったら「止まれ」という標識にぶつかって、標識が倒れてホッカイロにぶつかって、ホッカイロから砂が飛び散って、博多ラーメンに入ってしまって、しずかちゃんがキャーっと言ったら、水戸黄門が近づいてきて「お嬢ちゃんわしと何か食べに行こう」と言われ、表に出たら広場があって、広場の先に教会があって、教会の前で神父が牛タン弁当を売っていて、牛タン弁当を買って歩いていったら佐渡島が見えました。
さあ、皆さん1番から15番まで順番に言ってみてください。
皆さんが今覚えた単語は、実は意味のある単語でした。人口の多い都道府県の1位から15位だったのです。 灯台は東京都、金網は神奈川県、王様は大阪府、ハートは愛の象徴で愛知県、サイコロは埼玉県、ハチは千葉県、標識は兵庫県、ホッカイロは北海道、博多ラーメンは福岡県、しずかちゃんは静岡県、水戸黄門は茨城県、広場は広島県、教会は京都府、牛タン弁当は宮城県、佐渡島は新潟県、と、人口の多い都道府県の1位から15位になります。このような覚え方をすると記憶の干渉が起きないという仕組みになっています。
以上で私の話を終わります。有難うございました。
【卓話編集後記】
20個の単語を即座に記憶し、順番を変えても見事に再生できる菱田様のデモンストレーションに、会場では会員の感嘆の声が響きました。
また、菱田様に教えていただきながら、会員も15個の単語を短時間で覚える記憶法の実験に楽しく参加しました。
記憶力の衰えは歳のせいだと物忘れする自分を慰めていましたが、歳のせいにしてはいけない、記憶力は年を取っても衰えないという言葉に励まされました。
これからも、自信や好奇心、プラス思考を備えて、脳を元気に働かせ、記憶技術にチャレンジしたいと意欲をかきたてられた卓話でした。
皆さま、こんにちは。ご紹介いただきました菱田雅生です。
「脳を元気に働かせるための考え方と記憶の技術」というお話をします。
よりよく脳を働かせる考え方を説明し、たった5分で15個の単語を完璧に順番通りに記憶できるという記憶法を体験していただきます。
皆さん、自分は元々記憶力が悪い、頭が悪いとか、能力は遺伝で決まっている、年齢と共に記憶力は悪くなる、暗記や勉強は大変で辛いものだ、能力や記憶力の要領には限界がある、と思ったことはないでしょうか。これは全部間違っています。
人間の能力や記憶力には、とてつもない力があります。しかし、その使い方をよく知らないので上手に使いきれていません。年を取っても記憶力は衰えません。年を取ると興味があることと無いことの区別がはっきりして、興味のないことは覚えません。人の顔と名前が覚えられない理由はその人に興味が無いからなのです。能力は遺伝によってだけでは決定されませんし、能力や記憶力の容量に限界はありません。暗記や勉強はとても楽しいものなのです。
9年前に米国のタフツ大学のアヤナ・トーマス先生が行った実験があります。20代と60代の人たちに50個の単語を渡して覚えてもらいました。一つのグループには心理学のテストですと言って覚えてもらい、もう一つのグループには記憶力のテストですと言って覚えてもらいました。覚えてもらった後で、50個の単語が書いてある新しい紙を渡して、先ほど覚えた単語と同じ単語があれば丸をつけてもらいました。すると、心理学のテストだと伝えたグループは20代も60代もほぼ同じ正答率でした。一方、記憶力のテストだと伝えたグループは60代の正答率が低かったそうです。 これは、年と共に記憶力が悪くなるという思い込みによるものです。そう思い込むとそうなってしまうのです。
では、記憶の実験を始めます。これから私が言う15個の単語を覚えていただきます。覚えてもらったあとで、私がどうぞといったら書いていただきます。番号と言葉が合っていたら2点、言葉が出てきたら1点と採点します。15個ですので30点満点です。 記憶のやり方をまだお伝えしていないので、今の状態でチャレンジしてみてください。
1番 灯台、2番 金網、3番 王様、4番 ハート、5番 サイコロ、6番 ハチ、7番 標識、8番 ホッカイロ、9番 博多ラーメン、10番 しずかちゃん、11番 水戸黄門、12番 広場、13番 教会、14番 牛タン弁当、15番 佐渡島、以上です。
エビングハウス博士の忘却曲線をご存知ですか。人間は記憶したものの量を時間の経過に比例して忘れていくのではなく、一気に忘れてしまうようです。一日経つと7割は忘れるそうです。 私たちの脳にある短期記憶は2,3分で消えるようです。
では、先ほどの15個の単語を書いてみてください。(会員は回答記入)
30点満点の方は、さすがにいらっしゃらないようですね。 後でやり方をお教えします。
次に20個の単語の瞬間記憶、皆さんに出していただいた20個の単語を私が完璧に覚えてみせます。1番から20番まで順番に言うことが出来るし、20番から遡ることもできるし、何番と聞かれたらその単語を答えるし、単語を言われたら何番と答えます。
(菱田氏の記憶術デモンストレーション)
ここで私が覚えた20の単語は長期記憶の中に入れる方法で覚えたので、1,2週間は忘れません。これは私が記憶のセミナーの講師だから出来るというわけではありません。皆さんも2日間の本講座を受ければ全員できるようになります。やり方があるのです。
よりよく脳を働かせる考え方には6つのポイントがあります。
① 「できる」という自信と決意。プラスの言葉を使う
② 好奇心と集中
③ イメージと感受性
④ 目的とビジョン
⑤ 反復
⑥ きちんと理解する
プラスの言葉を使うのは重要です。「無理」「難しい」「苦手」というと思考が止まってしまいます。好奇心を持って物を見ると脳は年齢に関係なく元気になります。はっきりイメージすると脳に残る仕組みになっています。1週間前の昼ご飯は覚えていないのに、何年も前にレストランで食べた美味しかったご飯をなぜ覚えているかというと、感情が動いているからです。目的やビジョンがあると脳は元気に働きます。反復することで非常に大きな刺激を脳に与えます。そしてきちんと理解したことは忘れないという仕組みになっています。
さて、先ほどの15個の単語をストーリー法で記憶するという技法で皆さんの脳の中に入れます。記憶の技法は6種類ほどありますが、その中の一つの技法です。物語のように単語をくっつけますので、頭の中で思い浮かべてください。
灯台の先から金網が出ていて、王様がぐるぐる巻きにされていて、ハートのクッションが落ちてきて、中からサイコロが出てきて、ハチが飛んできてサイコロ1個摘み上げて飛んでいったら「止まれ」という標識にぶつかって、標識が倒れてホッカイロにぶつかって、ホッカイロから砂が飛び散って、博多ラーメンに入ってしまって、しずかちゃんがキャーっと言ったら、水戸黄門が近づいてきて「お嬢ちゃんわしと何か食べに行こう」と言われ、表に出たら広場があって、広場の先に教会があって、教会の前で神父が牛タン弁当を売っていて、牛タン弁当を買って歩いていったら佐渡島が見えました。
さあ、皆さん1番から15番まで順番に言ってみてください。
皆さんが今覚えた単語は、実は意味のある単語でした。人口の多い都道府県の1位から15位だったのです。 灯台は東京都、金網は神奈川県、王様は大阪府、ハートは愛の象徴で愛知県、サイコロは埼玉県、ハチは千葉県、標識は兵庫県、ホッカイロは北海道、博多ラーメンは福岡県、しずかちゃんは静岡県、水戸黄門は茨城県、広場は広島県、教会は京都府、牛タン弁当は宮城県、佐渡島は新潟県、と、人口の多い都道府県の1位から15位になります。このような覚え方をすると記憶の干渉が起きないという仕組みになっています。
以上で私の話を終わります。有難うございました。
【卓話編集後記】
20個の単語を即座に記憶し、順番を変えても見事に再生できる菱田様のデモンストレーションに、会場では会員の感嘆の声が響きました。
また、菱田様に教えていただきながら、会員も15個の単語を短時間で覚える記憶法の実験に楽しく参加しました。
記憶力の衰えは歳のせいだと物忘れする自分を慰めていましたが、歳のせいにしてはいけない、記憶力は年を取っても衰えないという言葉に励まされました。
これからも、自信や好奇心、プラス思考を備えて、脳を元気に働かせ、記憶技術にチャレンジしたいと意欲をかきたてられた卓話でした。
卓話 「いま人気!船旅の魅力とは?」
株式会社JTB JTBクルーズ本店 マネジャー 横山憲一郎様
2019年11月28日

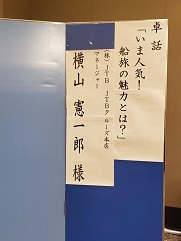 皆さまこんにちは。ご紹介いただきましたJTBの横山と申します。JTBクルーズ本店で、海外のクルーズのパッケージツアーやパンフレットの作成、全国のお客様にクルーズをご案内させていただく仕事をしております。
クルーズは一度乗船されると多くの方はリピーターになります。船旅は楽しい旅行であり、非常に楽な旅行です。乗船すると、最後までずっと同じ部屋で過ごせるからです。例えば、バスでヨーロッパ移動する場合、何百キロも長時間、座りっぱなしで疲れます。ところが船の場合は、夜寝ている間に移動ができるのです。
朝、港に入ると、船は日中ずっと停泊しています。観光や散策、買い物を楽しみ、夕方船に戻り夕食となります。船の中では、劇場でショーを楽しんだり、バーやラウンジでお酒を飲んだり、外国のクルーズ客船であればカジノで遊ぶこともできます。そして部屋に戻られた夜間に、船は次の目的地に向かって進み、翌朝目覚めると次の寄港地に到着しているので、身体への負担が少なく旅行ができるのです。
船旅のお客様の平均年齢は64.5歳です。60代、70代が多く、80代90代の方も乗られています。年配のお客さまが多いのは、バスや新幹線、飛行機での移動よりも、船なら楽に移動できるからでしょう。一度船に乗ると、身体の負担が少なく、船内には遊べる施設や色々なレストランがあり楽しいと実感され、次の旅行も船でというリピーターになっていただいています。
日本のクルーズ船、飛鳥IIの場合は、ほとんどのお客様が日本人です。日本語が通じるし、和食も出るし、大浴場もあるし、チップという制度もないので、日本と同じ感覚で過ごせます。一番長いものでは、約100日間で世界一周するクルーズがあります。船は飛行機ほど速くないので時差ボケを感じることがありません。飛行機で1時間の距離を船は1日かけて移動するので、時差ボケという身体への負担がなく世界各地を回ることができます。
外国のクルーズ船は、5万トンと小型の飛鳥IIに比べると大きい船が多く、10万トン、15万トン、世界最大で22万5000トンという船もあります。大きな船内にレストランが20カ所くらいあり、1500名が入れる劇場でミュージカルを楽しむことができます。
クルーズは長くて高いので自分には縁がないと思われている方が多いのですが、期間が短く代金が安いものもありますので、一度は船旅を体験していただきたいと思います。
(クルーズ紹介映像)
映像のナレーションに「何でもできる自由」と「何もしない自由」というフレーズがありました。船旅の良いところは、ご自身のペースに合わせて旅行できることです。船の中では基本的に自由です。何かをしなければいけないという場面はほとんどありません。港に着いても、船から降りるか降りないかは自由です。
船内では日中、ダンス教室や映画の上映などのイベントが用意されています。ご夫婦で乗船されても船の中では別行動という方もいらっしゃいます。つかず離れずで、食事の時だけ合流するという過ごし方もできます。
日本では年間32万人が船旅に参加されています。10年前の倍くらいの人数になっています。いずれは50万人、100万人になると言われています。人口が日本の約半分の英国では年間150万人がクルーズに参加しています。日本では、クルーズはまだ身近な旅行ではないかもしれませんが、いずれは多くの人が参加する身近なものになるのではないかと思います。
船旅というと、タキシードやドレスが必要、晩餐会が毎日というような堅苦しいイメージがあるかもしれませんが、今のクルーズは違います。日中は普通の恰好で構いません。クイーン・エリザベスであっても飛鳥IIであっても、Tシャツや短パンのような、リゾートホテルで過ごすような服装で全く構いません。夕食の時間にはドレスコードが設けられています。しかし、毎日タキシードやドレスを着る必要はなく、普段の服装での夕食が半分以上です。1週間程度のクルーズであれば2回ほどドレスアップする夕食がありますが、男性は普通のスーツにネクタイ、女性はスーツかワンピースで構いません。思ったよりも堅苦しくなく、楽しんでいただけるのが今のクルーズです。
外国のクルーズの場合は、お客様の98%程度が外国人ですので、船の中では英語になります。英語は苦手という日本のお客様のために、各旅行会社の添乗員が色々とお手伝いいたします。今では横浜や神戸から乗船できる外国のクルーズ船が増えており、その場合は日本のお客様が多くなり、あまり言葉の心配をせずに楽しんでいただけます。
船内では、朝のラジオ体操から始まり、マッサージやクイズ大会、チェスの大会、ダンス教室など沢山のイベントが催されています。クルーズの代金には、朝昼晩の食事や船内でのイベントがすべて含まれています。クルーズは高いと思われがちですが、色々なものが代金に含まれているのでお得です。
一度ご参加いただけると、新たな旅行の選択肢の幅が広がるので、近い将来のご旅行の中に船旅を加えていただければ大変ありがたいと思います。
私からのお話は以上となります。 誠に有難うございました。
質疑応答
Q: 一人で参加しても船旅を楽しめますか?
A: おひとり様、特に女性1名での参加は多いです。女性に比べると、男性1名の参加は少ないほうです。部屋はツインを使うので少し割高の代金になります。船内では「おひとり様大集合」という出逢いの場を設けるイベントもあります。
Q: 船内でのトラブルや困ったことについてお聞かせいただけますか?
A: 日本の船では高齢のお客様が多いため、自分の部屋がわからなくなって夜中に徘徊されたり、最後の夜に荷物を全部入れてスーツケースを出して、翌朝、着替えがないことに気づいて、パジャマのまま下船される方が時々いらっしゃいます。事前にきちんとご案内しなくてはと思います。
Q: 瀬戸内海のクルーズについて話を聞かせてください。
A: 風光明媚な瀬戸内海ですが、以前は夜しか通れませんでした。今は日中も通れるようになり、外の景色をご覧いただけます。ただ、狭いところに定置網などが張られているので、船が通れる時間は厳しく制限されています。瀬戸内海に限らず、船が通れる道や時間はかなり制限があります。船長や乗組員に話を聞くと色々教えてくれるので、それも船の楽しみの一つかと思います。
【卓話編集後記】
今回の卓話では、クルーズの旅の魅力を、映像を交えてご紹介いただきました。クルーズの過ごし方には「何でもできる自由」と「何もしない自由」があり、各人が自分らしい旅を楽しめること、特に、時差ボケに悩まされずに各地を回ることができるのは、とても魅力的だと思いました。幅広い人々のニーズに応えて、高齢者も独身者も楽しめるイベントが用意されており、家族や友人と一緒に参加しても、一人で参加しても十分に楽しめるというクルーズの旅に、出席された会員の方々も大いに関心を持たれたようでした。
皆さまこんにちは。ご紹介いただきましたJTBの横山と申します。JTBクルーズ本店で、海外のクルーズのパッケージツアーやパンフレットの作成、全国のお客様にクルーズをご案内させていただく仕事をしております。
クルーズは一度乗船されると多くの方はリピーターになります。船旅は楽しい旅行であり、非常に楽な旅行です。乗船すると、最後までずっと同じ部屋で過ごせるからです。例えば、バスでヨーロッパ移動する場合、何百キロも長時間、座りっぱなしで疲れます。ところが船の場合は、夜寝ている間に移動ができるのです。
朝、港に入ると、船は日中ずっと停泊しています。観光や散策、買い物を楽しみ、夕方船に戻り夕食となります。船の中では、劇場でショーを楽しんだり、バーやラウンジでお酒を飲んだり、外国のクルーズ客船であればカジノで遊ぶこともできます。そして部屋に戻られた夜間に、船は次の目的地に向かって進み、翌朝目覚めると次の寄港地に到着しているので、身体への負担が少なく旅行ができるのです。
船旅のお客様の平均年齢は64.5歳です。60代、70代が多く、80代90代の方も乗られています。年配のお客さまが多いのは、バスや新幹線、飛行機での移動よりも、船なら楽に移動できるからでしょう。一度船に乗ると、身体の負担が少なく、船内には遊べる施設や色々なレストランがあり楽しいと実感され、次の旅行も船でというリピーターになっていただいています。
日本のクルーズ船、飛鳥IIの場合は、ほとんどのお客様が日本人です。日本語が通じるし、和食も出るし、大浴場もあるし、チップという制度もないので、日本と同じ感覚で過ごせます。一番長いものでは、約100日間で世界一周するクルーズがあります。船は飛行機ほど速くないので時差ボケを感じることがありません。飛行機で1時間の距離を船は1日かけて移動するので、時差ボケという身体への負担がなく世界各地を回ることができます。
外国のクルーズ船は、5万トンと小型の飛鳥IIに比べると大きい船が多く、10万トン、15万トン、世界最大で22万5000トンという船もあります。大きな船内にレストランが20カ所くらいあり、1500名が入れる劇場でミュージカルを楽しむことができます。
クルーズは長くて高いので自分には縁がないと思われている方が多いのですが、期間が短く代金が安いものもありますので、一度は船旅を体験していただきたいと思います。
(クルーズ紹介映像)
映像のナレーションに「何でもできる自由」と「何もしない自由」というフレーズがありました。船旅の良いところは、ご自身のペースに合わせて旅行できることです。船の中では基本的に自由です。何かをしなければいけないという場面はほとんどありません。港に着いても、船から降りるか降りないかは自由です。
船内では日中、ダンス教室や映画の上映などのイベントが用意されています。ご夫婦で乗船されても船の中では別行動という方もいらっしゃいます。つかず離れずで、食事の時だけ合流するという過ごし方もできます。
日本では年間32万人が船旅に参加されています。10年前の倍くらいの人数になっています。いずれは50万人、100万人になると言われています。人口が日本の約半分の英国では年間150万人がクルーズに参加しています。日本では、クルーズはまだ身近な旅行ではないかもしれませんが、いずれは多くの人が参加する身近なものになるのではないかと思います。
船旅というと、タキシードやドレスが必要、晩餐会が毎日というような堅苦しいイメージがあるかもしれませんが、今のクルーズは違います。日中は普通の恰好で構いません。クイーン・エリザベスであっても飛鳥IIであっても、Tシャツや短パンのような、リゾートホテルで過ごすような服装で全く構いません。夕食の時間にはドレスコードが設けられています。しかし、毎日タキシードやドレスを着る必要はなく、普段の服装での夕食が半分以上です。1週間程度のクルーズであれば2回ほどドレスアップする夕食がありますが、男性は普通のスーツにネクタイ、女性はスーツかワンピースで構いません。思ったよりも堅苦しくなく、楽しんでいただけるのが今のクルーズです。
外国のクルーズの場合は、お客様の98%程度が外国人ですので、船の中では英語になります。英語は苦手という日本のお客様のために、各旅行会社の添乗員が色々とお手伝いいたします。今では横浜や神戸から乗船できる外国のクルーズ船が増えており、その場合は日本のお客様が多くなり、あまり言葉の心配をせずに楽しんでいただけます。
船内では、朝のラジオ体操から始まり、マッサージやクイズ大会、チェスの大会、ダンス教室など沢山のイベントが催されています。クルーズの代金には、朝昼晩の食事や船内でのイベントがすべて含まれています。クルーズは高いと思われがちですが、色々なものが代金に含まれているのでお得です。
一度ご参加いただけると、新たな旅行の選択肢の幅が広がるので、近い将来のご旅行の中に船旅を加えていただければ大変ありがたいと思います。
私からのお話は以上となります。 誠に有難うございました。
質疑応答
Q: 一人で参加しても船旅を楽しめますか?
A: おひとり様、特に女性1名での参加は多いです。女性に比べると、男性1名の参加は少ないほうです。部屋はツインを使うので少し割高の代金になります。船内では「おひとり様大集合」という出逢いの場を設けるイベントもあります。
Q: 船内でのトラブルや困ったことについてお聞かせいただけますか?
A: 日本の船では高齢のお客様が多いため、自分の部屋がわからなくなって夜中に徘徊されたり、最後の夜に荷物を全部入れてスーツケースを出して、翌朝、着替えがないことに気づいて、パジャマのまま下船される方が時々いらっしゃいます。事前にきちんとご案内しなくてはと思います。
Q: 瀬戸内海のクルーズについて話を聞かせてください。
A: 風光明媚な瀬戸内海ですが、以前は夜しか通れませんでした。今は日中も通れるようになり、外の景色をご覧いただけます。ただ、狭いところに定置網などが張られているので、船が通れる時間は厳しく制限されています。瀬戸内海に限らず、船が通れる道や時間はかなり制限があります。船長や乗組員に話を聞くと色々教えてくれるので、それも船の楽しみの一つかと思います。
【卓話編集後記】
今回の卓話では、クルーズの旅の魅力を、映像を交えてご紹介いただきました。クルーズの過ごし方には「何でもできる自由」と「何もしない自由」があり、各人が自分らしい旅を楽しめること、特に、時差ボケに悩まされずに各地を回ることができるのは、とても魅力的だと思いました。幅広い人々のニーズに応えて、高齢者も独身者も楽しめるイベントが用意されており、家族や友人と一緒に参加しても、一人で参加しても十分に楽しめるというクルーズの旅に、出席された会員の方々も大いに関心を持たれたようでした。
卓話 「病は気からを科学する」
NPO法人医療制度研究会副理事長 本田宏様
2019年11月21日

 皆さん、今日は歴史ある東京山の手ロータリークラブでお話させていただけるということで、短い時間ですが頑張ってお話したいと思います。
私は福島県で生まれ、父が開業した小さな洋品店の息子として育ちました。高校3年生の秋まで、将来の夢はパイロットでしたが、母に反対され、泣く泣く夢をあきらめて、青森県の弘前大学を卒業して医師になり、東京女子医大、その後埼玉県の病院でも勤務をし、現在に至っております。
私は2002年7月から医療再生の活動をしてきました。日本では、医師不足と病院の赤字を理由に公的病院の再編統合が進められようとしています。日本の医師不足を、国は医師の偏在が問題だと言っていますが、日本の医師数はOECD加盟国平均を大きく下回っています。それにもかかわらず、厚労省は、医師が将来余ると言って医学部の定員を削減してきました。私は非常に理不尽だと思ってこの活動を続けています。
それでは、今日のテーマ、精神神経免疫学のお話に入ります。
私たちはストレスを脳で感じます。常に目から入る情報や、暑い寒い痛いといったストレスが脳に入ってくると、自然と内分泌、ホルモンや免疫が作動します。分かりやすい例をご紹介します。1995年の阪神大震災の際には心筋梗塞で亡くなった人がたくさんおられました。震災で亡くなる方の中には、火事とか家屋の倒壊だけでなく、ストレスによる心筋梗塞という方も少なくなかったのです。 私はこの当時、埼玉県の済生会栗橋病院で外科医として働いていましたが、「仮設住宅孤独死、83人」という新聞記事を見て、恐らく高齢の方が亡くなっているのだろうと思って読み驚きました。働き盛りの男性が多かったのです。男性はどうしても孤独になりがちです。 社会からの孤立は、肥満、運動不足、喫煙と同じくらい健康に害を及ぼし死亡のリスクが2倍になる、群衆の中の「孤独」が人をむしばむと言われています。ちなみに貧しくても健康長寿のコスタリカには、強い社会的な絆があるそうです。
今日は、私の話に笑いが少なくて申し訳ないのですが、いつもは冗談を言いながらお話しています。 というのも、笑いは免疫に直接影響するというデータが数多く出ているからです。
私たちの体の中では毎日がん細胞が生まれていますが、がん細胞を殺す免疫細胞であるナチュラルキラーが夜寝ている間にがん細胞をやっつけてくれます。このナチュラルキラーは笑うと活性化するのです。「なんばグランド花月」でお笑いを聞いた癌の患者さんの、笑う前と笑った後のナチュラルキラー細胞を調べたところ、笑った後で機能が上がったという研究結果は有名です。
また、林家木久蔵さんの落語をリウマチの患者さんに聞いてもらい、前後で痛みのチェックをしたところ、落語を聞いた時の方が、鎮痛剤服用後よりも痛みが軽減し長く持続したという研究結果も出ています。「楽しい笑いは副作用のない薬」です。林家木久蔵さんの色紙に「よく笑うヒト 人生の達人」とありますが、健康に生きるためには笑って生活した方が良いのです。
何故私がこのようなことに興味を持ったのかと言うと、医師不足が関係しています。私は東京女子医大で腎移植、肝臓移植を研究して、移植外科医になりたかったのですが、日本は先進国の中で臓器提供が一番少ない国なので、臓器移植で貢献したいと思ってもできない。それで埼玉県の病院で、一般外科で多くの患者さんを治療するようになりました。医師不足ですから、外科医は乳癌の疑いのある患者さんのしこりの診察をすると、そのあと細胞診、手術、術後の抗がん剤投与、万が一再発した時には鎮痛剤の投与、そして最後のお見送りまで担当するということが普通だったのです。一人一人の患者さんに向き合いながら、あるとき、乳癌の患者さんの気持ちと病気の進行に関係があるのではないかと思うようになりました。ある時、1985年の『Lancet』という権威ある医学雑誌で、乳癌の患者さんの術後3か月の心理状態によって長期生存率が異なるというデータを見つけました。5年、10年、13年の生存率で見ると、一番早く亡くなるのは絶望する人、二番目は受け入れる人、素直な人、三番目は否定する人、そして一番長生きできたのはファイティングスピリットがある人でした。そしてこの生存率の差は、抗がん剤治療によるものよりも大きかったのです。私は、患者さんが前向きになれるように協力をして治療にあたることができれば、副作用もお金も少なくて済むかも知れないと考えて勉強を始めました。ただ、患者さんの精神状態は血液検査やレントゲンと違って、簡単には確認できないので、一般の医学界ではほとんど無視され、関心も持たれませんでした。
しかし、2002年に、世界的に有名な腫瘍内科医の上野直人さんが、「〇〇癌センター等、名前に癌がつく病院の治療成績が、全国平均より良いのは、始めから患者さん自身が癌と知り、強い意欲と希望をもって治療を受けていることが影響していると考えられる」ということを日本の学界で指摘され、私はとても勇気づけられました。 さらに、2008年の『Cancer』という医学雑誌に、「心理学的介入は乳がん患者の生存を改善する」という研究結果が掲載されました。さらに、今年(2019年)岡山大学の神谷先生は、ストレスと乳がんの関係について研究をされ、交感神経の密度の高い人、すなわち緊張状態にある人は、「術後の再発や死亡率が高いことを確認した」、「交感神経を刺激すると、がん細胞が増殖し、転移も増え、交感神経を除去すると抑制」という内容のデータを発表されています。つまり私が長年考えてきたことが証明されつつあるのです。
長生きする方法、健康に生きる方法は男と女で微妙に異なるようです。和歌山県立医大循環器内科の先生が調べたところ、循環器疾患で死亡率が上昇する危険性が高まるのは、男性の場合は「生きがいの欠如」、女性の場合は「人に頼りにされないこと」でした。
また、人間の追及する二つの幸福と健康の関係を示す、大変興味深いデータを見つけました。一つは「生きがい追求型幸福」、もう一つは「快楽追及型幸福」です。 大好きな人のためにケーキを作るのが前者で、大好きなケーキをお腹いっぱい食べるのが後者で、本人にとってはどちらも幸せです。しかし、精神神経免疫学的な調査の結果、後者の幸せは、身体がストレスを感じているときと同じ反応を示すことが判明しました。まさにアリストテレスが残した「最高善こそが幸福」という言葉が近代科学で証明されたのです。
乳癌を患いながら映画『ゴルダと呼ばれた女』に出演し女優賞を取ったイングリッド・バーグマンも手記に「最後まで闘うことをやめません」と書いています。レオナルド・ダヴィンチの言葉にも「充実した一日が幸せな眠りをもたらすように、充実した一生は幸福な死をもたらす」とあります。法然上人の「知足」、足るを知る。中国のことわざには、「一生の幸福が欲しいなら人を助けなさい」という言葉があり、ジェラール・シャンドリの言葉に「一生を終えてのちに残るものは、われわれが集めたものではなく、われわれが与えたものである」とあります。まさに、ロータリークラブの皆さまの活動にぴったりだと感じております。
ご清聴ありがとうございました。
【卓話編集後記】
本田先生には、免疫機能に対する笑いの影響を医学的なデータに基づいてご説明いただき、日常生活に笑いを取り入れることが健康維持のために大切であることを痛感しました。ユーモアあるジョークを交えた本田先生の卓話で、大いに笑った会員の免疫機能はきっと向上したに違いないと感じた卓話でした。
また、医師不足という日本が抱える問題についてもお話いただき、日本の医療について考えるきっかけにもなりました。
皆さん、今日は歴史ある東京山の手ロータリークラブでお話させていただけるということで、短い時間ですが頑張ってお話したいと思います。
私は福島県で生まれ、父が開業した小さな洋品店の息子として育ちました。高校3年生の秋まで、将来の夢はパイロットでしたが、母に反対され、泣く泣く夢をあきらめて、青森県の弘前大学を卒業して医師になり、東京女子医大、その後埼玉県の病院でも勤務をし、現在に至っております。
私は2002年7月から医療再生の活動をしてきました。日本では、医師不足と病院の赤字を理由に公的病院の再編統合が進められようとしています。日本の医師不足を、国は医師の偏在が問題だと言っていますが、日本の医師数はOECD加盟国平均を大きく下回っています。それにもかかわらず、厚労省は、医師が将来余ると言って医学部の定員を削減してきました。私は非常に理不尽だと思ってこの活動を続けています。
それでは、今日のテーマ、精神神経免疫学のお話に入ります。
私たちはストレスを脳で感じます。常に目から入る情報や、暑い寒い痛いといったストレスが脳に入ってくると、自然と内分泌、ホルモンや免疫が作動します。分かりやすい例をご紹介します。1995年の阪神大震災の際には心筋梗塞で亡くなった人がたくさんおられました。震災で亡くなる方の中には、火事とか家屋の倒壊だけでなく、ストレスによる心筋梗塞という方も少なくなかったのです。 私はこの当時、埼玉県の済生会栗橋病院で外科医として働いていましたが、「仮設住宅孤独死、83人」という新聞記事を見て、恐らく高齢の方が亡くなっているのだろうと思って読み驚きました。働き盛りの男性が多かったのです。男性はどうしても孤独になりがちです。 社会からの孤立は、肥満、運動不足、喫煙と同じくらい健康に害を及ぼし死亡のリスクが2倍になる、群衆の中の「孤独」が人をむしばむと言われています。ちなみに貧しくても健康長寿のコスタリカには、強い社会的な絆があるそうです。
今日は、私の話に笑いが少なくて申し訳ないのですが、いつもは冗談を言いながらお話しています。 というのも、笑いは免疫に直接影響するというデータが数多く出ているからです。
私たちの体の中では毎日がん細胞が生まれていますが、がん細胞を殺す免疫細胞であるナチュラルキラーが夜寝ている間にがん細胞をやっつけてくれます。このナチュラルキラーは笑うと活性化するのです。「なんばグランド花月」でお笑いを聞いた癌の患者さんの、笑う前と笑った後のナチュラルキラー細胞を調べたところ、笑った後で機能が上がったという研究結果は有名です。
また、林家木久蔵さんの落語をリウマチの患者さんに聞いてもらい、前後で痛みのチェックをしたところ、落語を聞いた時の方が、鎮痛剤服用後よりも痛みが軽減し長く持続したという研究結果も出ています。「楽しい笑いは副作用のない薬」です。林家木久蔵さんの色紙に「よく笑うヒト 人生の達人」とありますが、健康に生きるためには笑って生活した方が良いのです。
何故私がこのようなことに興味を持ったのかと言うと、医師不足が関係しています。私は東京女子医大で腎移植、肝臓移植を研究して、移植外科医になりたかったのですが、日本は先進国の中で臓器提供が一番少ない国なので、臓器移植で貢献したいと思ってもできない。それで埼玉県の病院で、一般外科で多くの患者さんを治療するようになりました。医師不足ですから、外科医は乳癌の疑いのある患者さんのしこりの診察をすると、そのあと細胞診、手術、術後の抗がん剤投与、万が一再発した時には鎮痛剤の投与、そして最後のお見送りまで担当するということが普通だったのです。一人一人の患者さんに向き合いながら、あるとき、乳癌の患者さんの気持ちと病気の進行に関係があるのではないかと思うようになりました。ある時、1985年の『Lancet』という権威ある医学雑誌で、乳癌の患者さんの術後3か月の心理状態によって長期生存率が異なるというデータを見つけました。5年、10年、13年の生存率で見ると、一番早く亡くなるのは絶望する人、二番目は受け入れる人、素直な人、三番目は否定する人、そして一番長生きできたのはファイティングスピリットがある人でした。そしてこの生存率の差は、抗がん剤治療によるものよりも大きかったのです。私は、患者さんが前向きになれるように協力をして治療にあたることができれば、副作用もお金も少なくて済むかも知れないと考えて勉強を始めました。ただ、患者さんの精神状態は血液検査やレントゲンと違って、簡単には確認できないので、一般の医学界ではほとんど無視され、関心も持たれませんでした。
しかし、2002年に、世界的に有名な腫瘍内科医の上野直人さんが、「〇〇癌センター等、名前に癌がつく病院の治療成績が、全国平均より良いのは、始めから患者さん自身が癌と知り、強い意欲と希望をもって治療を受けていることが影響していると考えられる」ということを日本の学界で指摘され、私はとても勇気づけられました。 さらに、2008年の『Cancer』という医学雑誌に、「心理学的介入は乳がん患者の生存を改善する」という研究結果が掲載されました。さらに、今年(2019年)岡山大学の神谷先生は、ストレスと乳がんの関係について研究をされ、交感神経の密度の高い人、すなわち緊張状態にある人は、「術後の再発や死亡率が高いことを確認した」、「交感神経を刺激すると、がん細胞が増殖し、転移も増え、交感神経を除去すると抑制」という内容のデータを発表されています。つまり私が長年考えてきたことが証明されつつあるのです。
長生きする方法、健康に生きる方法は男と女で微妙に異なるようです。和歌山県立医大循環器内科の先生が調べたところ、循環器疾患で死亡率が上昇する危険性が高まるのは、男性の場合は「生きがいの欠如」、女性の場合は「人に頼りにされないこと」でした。
また、人間の追及する二つの幸福と健康の関係を示す、大変興味深いデータを見つけました。一つは「生きがい追求型幸福」、もう一つは「快楽追及型幸福」です。 大好きな人のためにケーキを作るのが前者で、大好きなケーキをお腹いっぱい食べるのが後者で、本人にとってはどちらも幸せです。しかし、精神神経免疫学的な調査の結果、後者の幸せは、身体がストレスを感じているときと同じ反応を示すことが判明しました。まさにアリストテレスが残した「最高善こそが幸福」という言葉が近代科学で証明されたのです。
乳癌を患いながら映画『ゴルダと呼ばれた女』に出演し女優賞を取ったイングリッド・バーグマンも手記に「最後まで闘うことをやめません」と書いています。レオナルド・ダヴィンチの言葉にも「充実した一日が幸せな眠りをもたらすように、充実した一生は幸福な死をもたらす」とあります。法然上人の「知足」、足るを知る。中国のことわざには、「一生の幸福が欲しいなら人を助けなさい」という言葉があり、ジェラール・シャンドリの言葉に「一生を終えてのちに残るものは、われわれが集めたものではなく、われわれが与えたものである」とあります。まさに、ロータリークラブの皆さまの活動にぴったりだと感じております。
ご清聴ありがとうございました。
【卓話編集後記】
本田先生には、免疫機能に対する笑いの影響を医学的なデータに基づいてご説明いただき、日常生活に笑いを取り入れることが健康維持のために大切であることを痛感しました。ユーモアあるジョークを交えた本田先生の卓話で、大いに笑った会員の免疫機能はきっと向上したに違いないと感じた卓話でした。
また、医師不足という日本が抱える問題についてもお話いただき、日本の医療について考えるきっかけにもなりました。
卓話 「出逢い・感謝 ボクシングのおかげで」
日本ボクシングコミッション試合役員会 会長 吉田和敏様
2019年10月17日

 本日はお招きくださいましてありがとうございます。
只今レフェリーの資格でご紹介いただきました。レフェリーのシャツの色は白ですが、太めの僕は昔の青いシャツを着てきました。靴は選手と同じゴム底のリングシューズです。選手と接触して怪我をしないように金属類のベルトや眼鏡をつけてリングには上がれません。結婚指輪が抜けなかったために、僕はレフェリーの資格をとってもリングの下で採点するジャッジばかりしていました。減量して指輪が抜けてレフェリーもできるようになりましたが、それ以来結婚指輪は外したままです。
本日は、ボクシングをしていた現役時代を中心にお話しいたします。
高校生の時は何日も学校をさぼり、両親に心配をかけました。せっかく入った硬式野球部も退部して、充実感のない高校生活を送りました。大学生になって、もう一度運動部に入ろうと思いボクシング部を選びました。2年生まで勝てなかったのですが、人と同じことをしていたら人と同じだ、人が一やるところを二やれという父の教えに奮起して人の三倍やりました。名選手の本を何冊も読んで研究しました。「どんなボクサーも長所を持っている。その長所を伸ばせ」という僕にぴったりの言葉がありました。僕はスタミナとパワーが人より優っているので、毎日30キロ走りこみました。さらにラッキーな出来事は、誉め上手の親友との出逢いでした。彼の誉め言葉のおかげで試合に勝てる自信がどんどん膨らんでいきました。
大学3年の時の決勝戦はちょうど父の日でした。一生懸命頑張っている姿を、それ以上に優勝する息子の姿をどうしても見せたいと思い父を招待しました。相手から顎を2か所も骨折するほどの強烈な右アッパーカットを食らいましたが、歯を食いしばって打ち返し2ラウンドで相手をノックアウトしました。試合後にリングを下りて父の元に駆け寄ると、父は嬉しそうに最高の笑顔を見せてくれました。
大学3年の秋にボクシング部のキャプテンになり、誰よりも一生懸命練習して部員を引っ張っていきました。そのおかげでボクシング部はまとまっていましたが、僕自身は学生の本分である学業に問題を抱えていました。大学に入った時に父と二つの約束をしていました。一つは大学を4年間で卒業すること、もう一つは卒業までに日商簿記検定二級を取ることでした。そこで、大学4年の時は練習を1日おきに途中で切り上げて神保町の簿記学校に通い、父との約束を果たしました。
大学4年の時の決勝戦の相手は東京大学の選手でした。当時の東大は赤門パワーと言われてスポーツが強かったのです。僕の対戦相手は20戦以上無敗の早稲田君、「東京大学の早稲田君のケーオー勝ち」というアナウンスが当時話題になった選手でした。僕はボクシング部のキャプテンとして先頭に立って練習がしたいと思い、決勝戦の10日前に簿記学校の欠席届の用紙を父に差し出しました。「どっちが大事なんだ!」を怒鳴られるのを覚悟していたのですが、父は引き出しの中から初めて見るハンコを取り出し、「これが一番縁起がいいハンコなんだぞ」と言いながら欠席届に押してくれました。早稲田君との決勝戦には自分の持っている最大のエネルギーでぶつかり2ランドKO勝ちで優勝しました。
大学卒業後、大きなグループ企業に就職してレストラン部門に配属されました。ボクシングは学生時代の良い思い出として終えたつもりでした。しかし、友達からのプロボクサーへの誘いに少しずつ気持ちが動き、ただ一度きりの人生で自分の可能性に挑戦したいと思いました。プロボクサーを目指してもう一度身体を鍛え直しました。でも、仕事を続けながらプロボクサーとして成功するのは無理でした。すると父から家に帰ってくるならボクシングをやってもいいぞと言われました。但し、25歳になるまでという条件付きでした。
こうして僕は、日本で一番古い名門の帝拳ジムに入りました。このジムには23歳の若さで亡くなった世界チャンピオン大場政夫を母親のように厳しく温かく育て上げたマネージャーの長野ハルさんがいました。長野さんはみんなからお姉さんと呼ばれていてプロボクサーになった僕のマネージャーでもありました。
23歳の6月4日、僕はプロデビュー戦を迎えました。応援に来てくれた両親や恩師をはじめとする50人以上の人たちの前で、相手をノックアウトするはずでした。しかし、1分46秒でノックアウトされたのは僕でした。試合後真っ先に長野さんの元へ行き「お姉さん、すみませんでした」と謝りました。すると、長野さんは一言だけ「今日はなかったことにしましょう」と言ってくれました。この言葉に救われました。恩師の宮崎先生からは「吉田君、逆境にあったときに本当の人間性がわかるんだよ」と言われて、思わず涙をこぼしました。
その後、しばらくは、朝はロードワーク、夕方まで仕事、夕方からボクシングジムで汗を流し、夜は本社で仕事という元の生活に戻りました。でも時間が経つにつれ、だんだんさぼるようになり、朝は走らなくなり、夕方はスポーツバッグを持って家を出てもジムには行かず、時には一杯飲んで帰るようになりました。こんな姿の僕に、ある朝母が大きな声で「走らないのか!負けたままで悔しくないのか!」と叱りました。この一言で僕は生まれ変わりました。そして屈辱の敗戦から8か月後24歳の時、僕はプロ第二戦目の1ラウンド1分4秒で相手をノックアウトしました。この試合には誰も呼ばなかったのですが、父が一人で後楽園ホールに見に来ていました。家に帰ると母が笑顔で出迎えてくれました。父も、かつての父の日と同じ最高の笑顔でした。
三戦目からは学生時代と同じ快活な自分に戻り、「必ず勝つから見に来いよ、試合の後はみんなで飲み会だ」と決まり文句で友達を誘って足を運んでもらいました。自分自身にプレッシャーをかけて負けられない状況を作り、有言実行しました。しかし、10月10日の東日本新人王選手権準々決勝で、ゼロ対2の判定で負けてしまいました。3日後に僕は25歳になりました。もし勝っていたら、頑固な父を説得してもう少しボクシングを続けていたでしょう。でも今は、これで良かったのだと思います。
ボクシングを離れてしばらくして、あの朝母が僕を叱りつけたのは、ボクシングで得た自信や信念をボクシングで失わせてはいけないという親心からだとわかりました。あのときは厳しい母だと思いましたが、今は心から感謝しています。
そして、今、ボクシングに対する感謝の気持ちを込めてJBCレフェリーとしてリングに立っています。試合前にレフェリーがリング中央で選手に何を話しているか知っていますか。決まり文句はありません。細かい注意は選手の耳に入りません。ですから大切にしている気持ちを言います。「JBCルールを守り、ベストを尽くして、悔いを残さないように頑張って」と。
最後に大好きな相田みつをさんの言葉を聞いてください。「人の世の幸不幸は人と人が逢うことから始まる よき出逢いを」
ありがとうございました。
【卓話編集後記】
東京足立ロータリークラブの会員でいらっしゃる吉田和敏様に、ボクシングを通して経験されたこと、学ばれたこと、家族とのつながり、いろいろな人との出逢いなど、心温まるお話をしていただきました。卓話の途中、ジャブやストレートのポーズを教えていただくなど、みんなで体を動かしながらの楽しいひとときとなりました。ご一緒に参加してくださった奥様の優しい笑顔、仲睦まじいお二人のお姿もとても印象的でした。
本日はお招きくださいましてありがとうございます。
只今レフェリーの資格でご紹介いただきました。レフェリーのシャツの色は白ですが、太めの僕は昔の青いシャツを着てきました。靴は選手と同じゴム底のリングシューズです。選手と接触して怪我をしないように金属類のベルトや眼鏡をつけてリングには上がれません。結婚指輪が抜けなかったために、僕はレフェリーの資格をとってもリングの下で採点するジャッジばかりしていました。減量して指輪が抜けてレフェリーもできるようになりましたが、それ以来結婚指輪は外したままです。
本日は、ボクシングをしていた現役時代を中心にお話しいたします。
高校生の時は何日も学校をさぼり、両親に心配をかけました。せっかく入った硬式野球部も退部して、充実感のない高校生活を送りました。大学生になって、もう一度運動部に入ろうと思いボクシング部を選びました。2年生まで勝てなかったのですが、人と同じことをしていたら人と同じだ、人が一やるところを二やれという父の教えに奮起して人の三倍やりました。名選手の本を何冊も読んで研究しました。「どんなボクサーも長所を持っている。その長所を伸ばせ」という僕にぴったりの言葉がありました。僕はスタミナとパワーが人より優っているので、毎日30キロ走りこみました。さらにラッキーな出来事は、誉め上手の親友との出逢いでした。彼の誉め言葉のおかげで試合に勝てる自信がどんどん膨らんでいきました。
大学3年の時の決勝戦はちょうど父の日でした。一生懸命頑張っている姿を、それ以上に優勝する息子の姿をどうしても見せたいと思い父を招待しました。相手から顎を2か所も骨折するほどの強烈な右アッパーカットを食らいましたが、歯を食いしばって打ち返し2ラウンドで相手をノックアウトしました。試合後にリングを下りて父の元に駆け寄ると、父は嬉しそうに最高の笑顔を見せてくれました。
大学3年の秋にボクシング部のキャプテンになり、誰よりも一生懸命練習して部員を引っ張っていきました。そのおかげでボクシング部はまとまっていましたが、僕自身は学生の本分である学業に問題を抱えていました。大学に入った時に父と二つの約束をしていました。一つは大学を4年間で卒業すること、もう一つは卒業までに日商簿記検定二級を取ることでした。そこで、大学4年の時は練習を1日おきに途中で切り上げて神保町の簿記学校に通い、父との約束を果たしました。
大学4年の時の決勝戦の相手は東京大学の選手でした。当時の東大は赤門パワーと言われてスポーツが強かったのです。僕の対戦相手は20戦以上無敗の早稲田君、「東京大学の早稲田君のケーオー勝ち」というアナウンスが当時話題になった選手でした。僕はボクシング部のキャプテンとして先頭に立って練習がしたいと思い、決勝戦の10日前に簿記学校の欠席届の用紙を父に差し出しました。「どっちが大事なんだ!」を怒鳴られるのを覚悟していたのですが、父は引き出しの中から初めて見るハンコを取り出し、「これが一番縁起がいいハンコなんだぞ」と言いながら欠席届に押してくれました。早稲田君との決勝戦には自分の持っている最大のエネルギーでぶつかり2ランドKO勝ちで優勝しました。
大学卒業後、大きなグループ企業に就職してレストラン部門に配属されました。ボクシングは学生時代の良い思い出として終えたつもりでした。しかし、友達からのプロボクサーへの誘いに少しずつ気持ちが動き、ただ一度きりの人生で自分の可能性に挑戦したいと思いました。プロボクサーを目指してもう一度身体を鍛え直しました。でも、仕事を続けながらプロボクサーとして成功するのは無理でした。すると父から家に帰ってくるならボクシングをやってもいいぞと言われました。但し、25歳になるまでという条件付きでした。
こうして僕は、日本で一番古い名門の帝拳ジムに入りました。このジムには23歳の若さで亡くなった世界チャンピオン大場政夫を母親のように厳しく温かく育て上げたマネージャーの長野ハルさんがいました。長野さんはみんなからお姉さんと呼ばれていてプロボクサーになった僕のマネージャーでもありました。
23歳の6月4日、僕はプロデビュー戦を迎えました。応援に来てくれた両親や恩師をはじめとする50人以上の人たちの前で、相手をノックアウトするはずでした。しかし、1分46秒でノックアウトされたのは僕でした。試合後真っ先に長野さんの元へ行き「お姉さん、すみませんでした」と謝りました。すると、長野さんは一言だけ「今日はなかったことにしましょう」と言ってくれました。この言葉に救われました。恩師の宮崎先生からは「吉田君、逆境にあったときに本当の人間性がわかるんだよ」と言われて、思わず涙をこぼしました。
その後、しばらくは、朝はロードワーク、夕方まで仕事、夕方からボクシングジムで汗を流し、夜は本社で仕事という元の生活に戻りました。でも時間が経つにつれ、だんだんさぼるようになり、朝は走らなくなり、夕方はスポーツバッグを持って家を出てもジムには行かず、時には一杯飲んで帰るようになりました。こんな姿の僕に、ある朝母が大きな声で「走らないのか!負けたままで悔しくないのか!」と叱りました。この一言で僕は生まれ変わりました。そして屈辱の敗戦から8か月後24歳の時、僕はプロ第二戦目の1ラウンド1分4秒で相手をノックアウトしました。この試合には誰も呼ばなかったのですが、父が一人で後楽園ホールに見に来ていました。家に帰ると母が笑顔で出迎えてくれました。父も、かつての父の日と同じ最高の笑顔でした。
三戦目からは学生時代と同じ快活な自分に戻り、「必ず勝つから見に来いよ、試合の後はみんなで飲み会だ」と決まり文句で友達を誘って足を運んでもらいました。自分自身にプレッシャーをかけて負けられない状況を作り、有言実行しました。しかし、10月10日の東日本新人王選手権準々決勝で、ゼロ対2の判定で負けてしまいました。3日後に僕は25歳になりました。もし勝っていたら、頑固な父を説得してもう少しボクシングを続けていたでしょう。でも今は、これで良かったのだと思います。
ボクシングを離れてしばらくして、あの朝母が僕を叱りつけたのは、ボクシングで得た自信や信念をボクシングで失わせてはいけないという親心からだとわかりました。あのときは厳しい母だと思いましたが、今は心から感謝しています。
そして、今、ボクシングに対する感謝の気持ちを込めてJBCレフェリーとしてリングに立っています。試合前にレフェリーがリング中央で選手に何を話しているか知っていますか。決まり文句はありません。細かい注意は選手の耳に入りません。ですから大切にしている気持ちを言います。「JBCルールを守り、ベストを尽くして、悔いを残さないように頑張って」と。
最後に大好きな相田みつをさんの言葉を聞いてください。「人の世の幸不幸は人と人が逢うことから始まる よき出逢いを」
ありがとうございました。
【卓話編集後記】
東京足立ロータリークラブの会員でいらっしゃる吉田和敏様に、ボクシングを通して経験されたこと、学ばれたこと、家族とのつながり、いろいろな人との出逢いなど、心温まるお話をしていただきました。卓話の途中、ジャブやストレートのポーズを教えていただくなど、みんなで体を動かしながらの楽しいひとときとなりました。ご一緒に参加してくださった奥様の優しい笑顔、仲睦まじいお二人のお姿もとても印象的でした。
卓話 「輝く瞳に会いに行こう」
タイ王国立ダムロンラドソンクロ高校日本語教師 原田義之様
2019年9月26日

 皆さんこんにちは。 只今ご紹介いただきました原田義之です。
私は現在、タイ王国立ダムロンラドソンクロ高校で日本語教師を12年間続けておりま
す。 教壇に立つ傍ら、休日にはミャンマー・ラオス・タイの国境地域のアカ族の子ど
も寮「夢の家」ほか4つの寮において識字向上支援をしております。
現在、アカ族が住む北タイのチェンライロータリークラブの会員でもあり、2013年7月から1年間第47代会長を務めました。会員全員が現地のタイ人のクラブで日本在住の日本人が会長になったのは、タイのロータリー史上、私が初めてです。
私がアカ族の子どもと出会ったのは、25年前に遡ります。私が勤務していた神戸の会社がタイに工場を作ることになり、訪問したバンコックのホテルのテレビで、北タイ、チェンライの子どもたちがバンコックのNPOから図書を受け取る姿を見ました。引率の先生も子どもたちも粗末な服装でしたが、図書を受け取る子供の瞳は輝いていました。当時私が国際奉仕委員長を務めていた2680地区高砂青松ロータリークラブの国際奉仕予算は10万円、この10万円でタイの図書を買えば、貨幣価値の違いから、50万、60万円相当の図書が買える。そう考えて早速830キロ離れたチェンライに飛びました。
情報もなく、タイ語の読み書きや会話ができない私は、空港でタクシーの運転手に一番古くて有名なホテルに連れて行くように頼みました。到着したワンカムホテルでロータリアンであることを伝え、社長に面談を求めました。初対面のウン社長は、私を10年来の既知の友であるかのように迎えてくれ、その日の夜には7名のロータリアンに紹介され、私のアカ族子ども支援が始まりました。私は、ロータリー入会30年ですが、あの時ほど、直径1センチ、重さ20グラムに満たないこのロータリーバッチが持つ重みを感じたことはありません。
15年間に北タイの36の小学校に図書寄贈を行いました。北タイには様々な民族を抱える学校が多数あります。 図書寄贈の会場でアカ族の青年アリヤさんから、識字のないアカ族の子どもは重労働や麻薬の運び屋、売春といった職につけられている、どうか識字向上支援をしてほしいと懇願されました。
当時64歳の私はロータリーの奉仕の心、奉仕の行動で貧しいアカ族を助けてあげようと決断しました。 早速、週末には、兵庫県国際協会主催の外国人向け日本語講座に通って全課程を終了し、三宮のタイ語教室でタイ文字を覚えました。
そして、北タイ、チェンライの国立ダムロンラドソンクロ高校に行き、この学校で子どもたちに日本語をタイ語で教えさせてほしいと校長に直訴しました。 以来12年間無報酬でボランティア教師として今も教壇に立っています。国立ダムロンラドソンクロ高校は、私の長年の奉仕に対してダムロン日本文化センター原田義之記念室を開設してくれました。
アカ族は、800年前は中国平野部に住んでいましたが、蒙古の襲撃を受けてチベット山中を移動する回遊民族と化して南下を続け、400年前には中国雲南省、100年前に北タイに達しました。 第二次世界大戦の終結によって国境が定まり、それまでの焼き畑農業と母国語のアカ語を禁じられました。生活手段と言語手段を奪われるという最も深刻な差別を受けたのです。
アカ族の月収は1万円、学校は彼らが住む山岳地帯から20キロも30キロも離れていて、子供に識字教育ができない状況です。 国連が規定する識字率は、その国の15歳以上の婦女子が母国語を使える割合です。タイの識字率は92.8%と非常に高いのですが、アカ族の識字率を調べると56%でした。この識字率の低さからアカ族の子どもは、低賃金の労働に従事するか、麻薬の運び屋になるか、売春するかといった現実に直面しています。
ロータリークラブの識字向上支援の重要性、必要性をご理解いただけるでしょうか。教育こそがただ一つの解決策なのです。私にとって、識字向上支援とは単に母国語であるタイ語を学ぶだけではありません。さらに学び続けて優秀な人材に育て上げることが、識字向上支援です。
ダムロン高校の私の教え子であるアカ族の子どもフレンドさんは、高校3年間日本語でトップの成績を修めました。しかし、それ以上の進学を考えていませんでした。 私は彼女を日本に留学させたいと思い、親を説得し、日本各地で彼女の留学引受先を探し求めました。いわき平中央ロータリークラブのロータリアンの支援で、その夢は実現し、フレンドさんは10か月間日本に留学し、日本語検定3級を取って帰国しました。帰国後、日本で私の奉仕を支える「アカ族子供支援基金」の奨学金を受けてラチバット大学日本語科4年で学業トップを修めています。そして、この度日本政府招聘留学生として、国立愛知教育大学に1年間留学することになりました。
このような私の奉仕を見守ってくれた全国のロータリアンが原田を支える会が「アカ族子ども就学支援基金」です。私の著書『輝く瞳に会いに行こう』と1年前に書いた『続・輝く瞳に会いに行こう』の印税をこの基金に入れております。 この基金は里親制度も設けています。
衛生面での支援としては、アカ族の子ども寮にトイレ設置の支援を行い、15の村に浄水器を設置して水支援を行ってきました。 この浄水器の支援によって、水源を巡る民族の争いが解決されました。
私の活動に対して批判や中傷もありました。 しかし、小さな奉仕の心でロータリアン活動をしていきたいと考えて、行動する奉仕として全国で講演しています。
私は再び今月末からアカ族の子ども支援でタイに入ります。 私の目の前のアカ族の子どもたちが、麻薬の運び屋や、売春、そしてエイズを患うような、悪の予備軍になってほしくないからです。
ロータリークラブに入って、奉仕の大切さとすばらしさを教えていただき目覚めることができました。 これからも、日本人、一人のロータリアンとして、北タイの貧困最前線に身を置いて、微力ながら役立って参りたいと考えています。
ご清聴ありがとうございました。
【卓話編集後記】
25年前に出会ったアカ族の子供たちを支援し続ける原田先生から、「アイ サーブ」のモデルと言える国際奉仕の実例をご紹介いただきました。原田先生の卓話を聞くために、アカ族支援活動を応援されている20名以上のロータリアンの方々が福島、京都、岡山など各地から参加してくださり、数多くのクラブとバナー交換ができました。例会場は、奉仕の大切さを再確認するロータリアンの温かいつながりに包まれました。
皆さんこんにちは。 只今ご紹介いただきました原田義之です。
私は現在、タイ王国立ダムロンラドソンクロ高校で日本語教師を12年間続けておりま
す。 教壇に立つ傍ら、休日にはミャンマー・ラオス・タイの国境地域のアカ族の子ど
も寮「夢の家」ほか4つの寮において識字向上支援をしております。
現在、アカ族が住む北タイのチェンライロータリークラブの会員でもあり、2013年7月から1年間第47代会長を務めました。会員全員が現地のタイ人のクラブで日本在住の日本人が会長になったのは、タイのロータリー史上、私が初めてです。
私がアカ族の子どもと出会ったのは、25年前に遡ります。私が勤務していた神戸の会社がタイに工場を作ることになり、訪問したバンコックのホテルのテレビで、北タイ、チェンライの子どもたちがバンコックのNPOから図書を受け取る姿を見ました。引率の先生も子どもたちも粗末な服装でしたが、図書を受け取る子供の瞳は輝いていました。当時私が国際奉仕委員長を務めていた2680地区高砂青松ロータリークラブの国際奉仕予算は10万円、この10万円でタイの図書を買えば、貨幣価値の違いから、50万、60万円相当の図書が買える。そう考えて早速830キロ離れたチェンライに飛びました。
情報もなく、タイ語の読み書きや会話ができない私は、空港でタクシーの運転手に一番古くて有名なホテルに連れて行くように頼みました。到着したワンカムホテルでロータリアンであることを伝え、社長に面談を求めました。初対面のウン社長は、私を10年来の既知の友であるかのように迎えてくれ、その日の夜には7名のロータリアンに紹介され、私のアカ族子ども支援が始まりました。私は、ロータリー入会30年ですが、あの時ほど、直径1センチ、重さ20グラムに満たないこのロータリーバッチが持つ重みを感じたことはありません。
15年間に北タイの36の小学校に図書寄贈を行いました。北タイには様々な民族を抱える学校が多数あります。 図書寄贈の会場でアカ族の青年アリヤさんから、識字のないアカ族の子どもは重労働や麻薬の運び屋、売春といった職につけられている、どうか識字向上支援をしてほしいと懇願されました。
当時64歳の私はロータリーの奉仕の心、奉仕の行動で貧しいアカ族を助けてあげようと決断しました。 早速、週末には、兵庫県国際協会主催の外国人向け日本語講座に通って全課程を終了し、三宮のタイ語教室でタイ文字を覚えました。
そして、北タイ、チェンライの国立ダムロンラドソンクロ高校に行き、この学校で子どもたちに日本語をタイ語で教えさせてほしいと校長に直訴しました。 以来12年間無報酬でボランティア教師として今も教壇に立っています。国立ダムロンラドソンクロ高校は、私の長年の奉仕に対してダムロン日本文化センター原田義之記念室を開設してくれました。
アカ族は、800年前は中国平野部に住んでいましたが、蒙古の襲撃を受けてチベット山中を移動する回遊民族と化して南下を続け、400年前には中国雲南省、100年前に北タイに達しました。 第二次世界大戦の終結によって国境が定まり、それまでの焼き畑農業と母国語のアカ語を禁じられました。生活手段と言語手段を奪われるという最も深刻な差別を受けたのです。
アカ族の月収は1万円、学校は彼らが住む山岳地帯から20キロも30キロも離れていて、子供に識字教育ができない状況です。 国連が規定する識字率は、その国の15歳以上の婦女子が母国語を使える割合です。タイの識字率は92.8%と非常に高いのですが、アカ族の識字率を調べると56%でした。この識字率の低さからアカ族の子どもは、低賃金の労働に従事するか、麻薬の運び屋になるか、売春するかといった現実に直面しています。
ロータリークラブの識字向上支援の重要性、必要性をご理解いただけるでしょうか。教育こそがただ一つの解決策なのです。私にとって、識字向上支援とは単に母国語であるタイ語を学ぶだけではありません。さらに学び続けて優秀な人材に育て上げることが、識字向上支援です。
ダムロン高校の私の教え子であるアカ族の子どもフレンドさんは、高校3年間日本語でトップの成績を修めました。しかし、それ以上の進学を考えていませんでした。 私は彼女を日本に留学させたいと思い、親を説得し、日本各地で彼女の留学引受先を探し求めました。いわき平中央ロータリークラブのロータリアンの支援で、その夢は実現し、フレンドさんは10か月間日本に留学し、日本語検定3級を取って帰国しました。帰国後、日本で私の奉仕を支える「アカ族子供支援基金」の奨学金を受けてラチバット大学日本語科4年で学業トップを修めています。そして、この度日本政府招聘留学生として、国立愛知教育大学に1年間留学することになりました。
このような私の奉仕を見守ってくれた全国のロータリアンが原田を支える会が「アカ族子ども就学支援基金」です。私の著書『輝く瞳に会いに行こう』と1年前に書いた『続・輝く瞳に会いに行こう』の印税をこの基金に入れております。 この基金は里親制度も設けています。
衛生面での支援としては、アカ族の子ども寮にトイレ設置の支援を行い、15の村に浄水器を設置して水支援を行ってきました。 この浄水器の支援によって、水源を巡る民族の争いが解決されました。
私の活動に対して批判や中傷もありました。 しかし、小さな奉仕の心でロータリアン活動をしていきたいと考えて、行動する奉仕として全国で講演しています。
私は再び今月末からアカ族の子ども支援でタイに入ります。 私の目の前のアカ族の子どもたちが、麻薬の運び屋や、売春、そしてエイズを患うような、悪の予備軍になってほしくないからです。
ロータリークラブに入って、奉仕の大切さとすばらしさを教えていただき目覚めることができました。 これからも、日本人、一人のロータリアンとして、北タイの貧困最前線に身を置いて、微力ながら役立って参りたいと考えています。
ご清聴ありがとうございました。
【卓話編集後記】
25年前に出会ったアカ族の子供たちを支援し続ける原田先生から、「アイ サーブ」のモデルと言える国際奉仕の実例をご紹介いただきました。原田先生の卓話を聞くために、アカ族支援活動を応援されている20名以上のロータリアンの方々が福島、京都、岡山など各地から参加してくださり、数多くのクラブとバナー交換ができました。例会場は、奉仕の大切さを再確認するロータリアンの温かいつながりに包まれました。
卓話 「言語と文化―日本語の特徴―」
東北大学大学院教授 江藤裕之様
2019年9月5日

 皆さん、初めまして。江藤と申します。
今日は、日本語の特徴、言語と文化というお話をさせていただきます。
少なからずの日本の大学、特に大学院では、少子化の影響を受けて学生の募集に苦労しています。そこで頼みの綱となるのが留学生です。私は、大学院で「言語と文化」という演習を担当しており、受講生には留学生も多数います。日本語は難しいかと尋ねると、ほとんどの留学生は、話すことはさほど難しくないが、漢字や色々な表記法があるので書くことは難しいと答えます。また、同意語が非常に多いことも日本語を難しくしているようです。
例えば、「私は( )を食べた」のカッコに入るのは「イネ」「コメ」「ゴハン」のどれでしょうか。正解は「ゴハン」です。ところが「私は( )を植えた」になると、正解は「イネ」になります。でも、「パンばかり食べないで、コメを食えよ」と言ったりしませんか。英語ではいずれもriceでよいのですが、日本語では「イネ」「コメ」「ゴハン」と区別されるのです。日本語を勉強している外国人にとって難しいのが、このような単語の選び方です。もちろん、逆のことが英語を勉強している我々にも言えますね。
中国人が悩むのは漢字の読み方です。中国では一つの漢字には基本的に一つの読み方しかありませんが、日本では多くの読み方があります。例えば、「生」という漢字には、「生の肉」「楽しく生きる」「草が生える」「子が生まれた」「人の一生」「生活が苦しい」「生糸」といった読み方があります。中国人留学生に、これらをどう区別するのかと尋ねたところ、そのまま、このコンテキストの中ではこう読むという風に覚えるのだそうです。
日本語の漢字の読み方には音読みと訓読みがあります。この二つを我々はなんとなく微妙に使い分けています。
例えば、「草原」は、「そうげん」とも読めるし「くさはら」とも読めます。この二つの読み方にはニュアンスの違いがあります。「そうげん」は雄大な広さを感じ、「くさはら」だと近所のコオロギやバッタがいる空き地が思い浮かびます。「市場」を「しじょう」と読むと大きな青果市場や株式市場、「いちば」と読むと買い物かごを下げて出かけていく八百屋とか果物屋、魚屋、スーパーマーケットになります。
「そうげん」や「しじょう」という読み方と「くさはら」や「いちば」という読み方に、どのような違いがあるかを考えてみると、大和言葉である「くさはら」や「いちば」は生活に身近なものであり、「そうげん」や「しじょう」は漢字が頭に浮かばないと分からない、少し離れた遠い感じがあります。
このように、まず大和言葉があり、次に漢語があり、明治以降にはおしゃれな響きのあるヨーロッパの言葉が入ってきました。
私が学生の頃に住んでいたところは、「〇〇荘」というような名前がついていました。ずいぶん前から市民権を得ている言葉のひとつが、「マンション」ですが、このマンションという言葉が大きな誤解をもたらすことがあります。アメリカ人にマンションと言うと豪華な邸宅を思い浮かべます。「マンションを買ったよ」と言うと「おお、すごいな!」というわけです。私たちの住んでいるようなマンションは英語ではコンドミニアムやフラットという言い方をします。さらに、マンションではあきたらず、最近では、メゾン、カーサ、ハイムというような英語以外の言葉も使われるようになってきました。なんとなくおしゃれな感じがするからです。
また、アジェンダ、アセスメント、アカウンタビリティ、スキームなどの言葉が使われるようになり、カタカナ語が氾濫して由々しきことだと嘆く方もいるようですが、このような語彙の流入は、その国語を豊かにするので、文法が変わらなければ、さほど嘆くことではないでしょう。
日本語の三層の同意語、すなわち、大和言葉、漢語、西洋語と分けて考えると、大和言葉は心に響く言葉で、話し言葉でよく使われます。漢語には形式ばったところがあり、レポートなんか書くときはこちらを使います。西洋語はおしゃれな感じがしますが、少し突き放したような感じがあり、さっきあげた「アジェンダ」のように仲間内だけで専門用語のように使われることが多いかもしれません。
日本語と日本文化の特徴の一つは、大和言葉には語彙が少ないことです。例えば、自分が回転するのも、何かの周囲を動くのも「まわる」です。それを「回る」や「周る」のように漢字を使って区別します。語彙が少ないため同音異義語が多く、造語力が豊かです。すなわち、漢字や西洋の言葉から多くの言葉を取り入れることによって語彙を豊かにしてきたのです。
語彙が少ない日本人について、谷崎潤一郎が『文章読本』の中で、次のような考察をしています。
・国語は国民性と切っても切れない関係にあり、日本語の語彙が乏しいのは、我等 の国民性がおしゃべりでない証拠である。
・国民性を変えないで、国語だけを改良しようとしても無理である。
・漢語や西洋語の語彙を取り入れて国語の不足を補うことは結構だが、それにも自 ずから程度がある。
日本人は人前で自分の意見を述べるのに慣れておらず、人前でしゃべることを良しとしない気風があるのではないでしょうか。日本人が英語を勉強してもベラベラしゃべることはできないのです。寡黙で、黙っていても通じる、相手が察してくれるというのが日本の文化です。日本語の構造は少ない言葉で多くの意味を伝える、つまり、沢山の言葉を積み重ねることはせず、察する、沈黙の文化なのです。
これを端的に表すキャッチコピ―を最後にご紹介します。
「男は黙ってサッポロビール」
母語を振り返るというお話でした。 ありがとうございました。
【卓話編集後記】
江藤教授の卓話を通して、留学生の視点からの日本語の特徴や難しさに気づかされ、普段私たちが意識せずに何となく使い分けている言葉の区別について認識することができました。グローバル化が進む社会の中で、言葉にも様々な影響が出ていることや、言葉と文化のつながりの深さを考えさせられ、私たちの母語である日本語を改めて見直す機会になりました。江藤教授のテンポのよい卓話に例会場は笑いに包まれ通しの楽しいひと時でした。
皆さん、初めまして。江藤と申します。
今日は、日本語の特徴、言語と文化というお話をさせていただきます。
少なからずの日本の大学、特に大学院では、少子化の影響を受けて学生の募集に苦労しています。そこで頼みの綱となるのが留学生です。私は、大学院で「言語と文化」という演習を担当しており、受講生には留学生も多数います。日本語は難しいかと尋ねると、ほとんどの留学生は、話すことはさほど難しくないが、漢字や色々な表記法があるので書くことは難しいと答えます。また、同意語が非常に多いことも日本語を難しくしているようです。
例えば、「私は( )を食べた」のカッコに入るのは「イネ」「コメ」「ゴハン」のどれでしょうか。正解は「ゴハン」です。ところが「私は( )を植えた」になると、正解は「イネ」になります。でも、「パンばかり食べないで、コメを食えよ」と言ったりしませんか。英語ではいずれもriceでよいのですが、日本語では「イネ」「コメ」「ゴハン」と区別されるのです。日本語を勉強している外国人にとって難しいのが、このような単語の選び方です。もちろん、逆のことが英語を勉強している我々にも言えますね。
中国人が悩むのは漢字の読み方です。中国では一つの漢字には基本的に一つの読み方しかありませんが、日本では多くの読み方があります。例えば、「生」という漢字には、「生の肉」「楽しく生きる」「草が生える」「子が生まれた」「人の一生」「生活が苦しい」「生糸」といった読み方があります。中国人留学生に、これらをどう区別するのかと尋ねたところ、そのまま、このコンテキストの中ではこう読むという風に覚えるのだそうです。
日本語の漢字の読み方には音読みと訓読みがあります。この二つを我々はなんとなく微妙に使い分けています。
例えば、「草原」は、「そうげん」とも読めるし「くさはら」とも読めます。この二つの読み方にはニュアンスの違いがあります。「そうげん」は雄大な広さを感じ、「くさはら」だと近所のコオロギやバッタがいる空き地が思い浮かびます。「市場」を「しじょう」と読むと大きな青果市場や株式市場、「いちば」と読むと買い物かごを下げて出かけていく八百屋とか果物屋、魚屋、スーパーマーケットになります。
「そうげん」や「しじょう」という読み方と「くさはら」や「いちば」という読み方に、どのような違いがあるかを考えてみると、大和言葉である「くさはら」や「いちば」は生活に身近なものであり、「そうげん」や「しじょう」は漢字が頭に浮かばないと分からない、少し離れた遠い感じがあります。
このように、まず大和言葉があり、次に漢語があり、明治以降にはおしゃれな響きのあるヨーロッパの言葉が入ってきました。
私が学生の頃に住んでいたところは、「〇〇荘」というような名前がついていました。ずいぶん前から市民権を得ている言葉のひとつが、「マンション」ですが、このマンションという言葉が大きな誤解をもたらすことがあります。アメリカ人にマンションと言うと豪華な邸宅を思い浮かべます。「マンションを買ったよ」と言うと「おお、すごいな!」というわけです。私たちの住んでいるようなマンションは英語ではコンドミニアムやフラットという言い方をします。さらに、マンションではあきたらず、最近では、メゾン、カーサ、ハイムというような英語以外の言葉も使われるようになってきました。なんとなくおしゃれな感じがするからです。
また、アジェンダ、アセスメント、アカウンタビリティ、スキームなどの言葉が使われるようになり、カタカナ語が氾濫して由々しきことだと嘆く方もいるようですが、このような語彙の流入は、その国語を豊かにするので、文法が変わらなければ、さほど嘆くことではないでしょう。
日本語の三層の同意語、すなわち、大和言葉、漢語、西洋語と分けて考えると、大和言葉は心に響く言葉で、話し言葉でよく使われます。漢語には形式ばったところがあり、レポートなんか書くときはこちらを使います。西洋語はおしゃれな感じがしますが、少し突き放したような感じがあり、さっきあげた「アジェンダ」のように仲間内だけで専門用語のように使われることが多いかもしれません。
日本語と日本文化の特徴の一つは、大和言葉には語彙が少ないことです。例えば、自分が回転するのも、何かの周囲を動くのも「まわる」です。それを「回る」や「周る」のように漢字を使って区別します。語彙が少ないため同音異義語が多く、造語力が豊かです。すなわち、漢字や西洋の言葉から多くの言葉を取り入れることによって語彙を豊かにしてきたのです。
語彙が少ない日本人について、谷崎潤一郎が『文章読本』の中で、次のような考察をしています。
・国語は国民性と切っても切れない関係にあり、日本語の語彙が乏しいのは、我等 の国民性がおしゃべりでない証拠である。
・国民性を変えないで、国語だけを改良しようとしても無理である。
・漢語や西洋語の語彙を取り入れて国語の不足を補うことは結構だが、それにも自 ずから程度がある。
日本人は人前で自分の意見を述べるのに慣れておらず、人前でしゃべることを良しとしない気風があるのではないでしょうか。日本人が英語を勉強してもベラベラしゃべることはできないのです。寡黙で、黙っていても通じる、相手が察してくれるというのが日本の文化です。日本語の構造は少ない言葉で多くの意味を伝える、つまり、沢山の言葉を積み重ねることはせず、察する、沈黙の文化なのです。
これを端的に表すキャッチコピ―を最後にご紹介します。
「男は黙ってサッポロビール」
母語を振り返るというお話でした。 ありがとうございました。
【卓話編集後記】
江藤教授の卓話を通して、留学生の視点からの日本語の特徴や難しさに気づかされ、普段私たちが意識せずに何となく使い分けている言葉の区別について認識することができました。グローバル化が進む社会の中で、言葉にも様々な影響が出ていることや、言葉と文化のつながりの深さを考えさせられ、私たちの母語である日本語を改めて見直す機会になりました。江藤教授のテンポのよい卓話に例会場は笑いに包まれ通しの楽しいひと時でした。
卓話 「ポリオの会と私 今私にできること ~そして世界のポリオ根絶に向けて私にできること」
ポリオの会 世話役 丸橋達也様
2019年8月29日
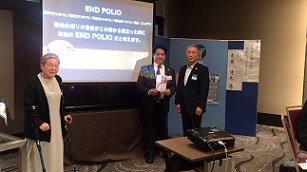
 皆さま初めまして、丸橋と申します。
本日は、卓話の機会を与えていただき本当にうれしく思います。
私は1965年昭島市に生まれ、生後7か月の時にポリオの生ワクチンの定期接種を受けました。約2週間後に高熱が出て、おむつ替えの時に左足がパタンと落ちてしまうことに気づいた母が病院に連れて行き、検査の結果、ワクチンによるポリオと診断され、隔離病棟で2カ月間の入院をすることになりました。
ポリオの生きたウィルスを弱めたものを身体に入れて抗体をつけるのが生ワクチンです。1960年頃に日本ではポリオが大流行し、母親たちがワクチンを海外から緊急輸入するように厚労省に押しかけて要請し、ポリオの流行を収めたという歴史があります。生ワクチンは有効ですが、まれにポリオの症状が出てしまうリスクがあり、それが私のような生ワクのポリオです。一方、病原性をなくした状態の不活化ワクチンというものがあり、これは麻痺を起こすことはありません。しかし、コストが高いこと、医療従事者による注射での接種、注射器の廃棄の問題がデメリットとしてあります。
母子手帳に「生ワク投与」というハンコが押してありました。これが私の運命の日となりました。母が作ったアルバムには、昭和41年5月9日から7月5日まで約2か月間入院したこと、両親にとって一生忘れることができない悲しい時期であったことが書かれていました。自分が子供を持つようになってわかるのですが、やはり親が一番辛かったと思います。
退院後、小児療育病院で補装具をつける指導を受け、リハビリをしながら松葉杖で歩けるまでに回復しました。
小学校入学の時、障害者が通う養護学校から入学通知が届いたのですが、母が教育委員会に何度も乗り込んでお願いして、普通の小学校に通うことが出来ました。
その後結婚し、子供もでき、何ともなく過ごしていたのですが、40歳の時に身体の異変が少しずつ出始めました。家で転倒して右足を骨折しました。左足は麻痺があるため装具をはめていますが、右足はポリオではない普通の足だと思っていました。しかし、右足も力が入りにくくなってよろけて転んだのです。。
その後、インターネットを通じてポリオの会を知り、小山万里子代表と出会い、自分が生ワクチンのポリオという珍しい貴重な存在であることに気づきました。ポリオを分かってくれる先生と出会い、42歳の時にPPS、ポスト・ポリオ症候群だと診断されました。罹患してから30年後、40年後に再度症状が進行することがあるのです。
小山代表から色々と教えていただき、今でも生ワクによる同じ被害が出ていることを知り驚きました。安全な不活化ワクチンがあるのに、なぜ日本ではそちらに切り替えないのかと思いました。そこで、ポリオの会の活動に一生懸命参加するようになり、厚労省にも不活化ワクチンへの切り替え運動で何回も行きました。メディアにもいろいろと出演しました。
私が訴えたいことは、国が指導しているワクチン行政では、なぜ安全なものがあるのに切り替えないのかということです。私のような生ワクによるポリオが珍しい存在ならば、自分が前面に出たら説得力があるのではないかと思い、さまざまな活動を始めました。
例えば、模擬患者として大学の授業に参加したり、理学療法士の学校でポリオのことを伝えるなど、ポリオを知ってもらうための活動をしています。国を動かそうという思いで何度も議員会館に行きました。ユニセフ議員連盟を訪ね、日本にもポリオ患者がいることを伝えています。ワクチンメーカーの社内研修でも話をさせていただいています。厚生労働省が主体となって3都市で開催される「シーズ・ニーズマッチング交流会」にポリオの会のブースを出して、より良い福祉機器を製作してもらうための活動もしています。明日からは福岡で開催される外来小児学会に行ってブースを出します。リハビリテーション科の先生がたくさんいらっしゃる義肢装具学会にも参加しています。
こうした活動が認められ、先日、社会貢献支援財団から「ポリオの会」が表彰を受けました。式典では、財団の会長安倍昭恵夫人と写真を撮らせていただいたり、とても光栄な賞をいただき、良い思い出になりました。
生ワクチンによる健康被害を受けた人たちの写真に小さな女の子が写っています。この子もポリオですが、症状が重くて色々な障害が出ていて、かわいそうな女の子です。
この子が成長して、今私がお話ししたすべてのことを知った時に、なぜもっと早くこの活動を始めて、もっと早く不活化ワクチンに切り替えてくれなかったのかと言われたら、どうしようと思いました。早くに気づいていたらポリオにならずに済んだかもしれない。そんな子供たちが、まだまだいると思います。ですから、私はこの活動を続けて、伝え続けるということを決めました。
ロータリーがポリオ撲滅を目指して進めているEND POLIOの活動は本当に素晴らしく、世界からポリオをなくすことはとても大切だと思って参加しています。今でも世界では生ワクが使われている国があり、生ワク由来の患者が出ているということも聞いています。
私たちが考えるEND POLIOとは、最後のポリオ患者がこの世から消えたとき、亡くなったときだと考えています。その時には私たちはもういないかもしれない。でも私が伝え続けていけば、その先の人たちが伝えていってくれると考えて、ポリオの会の活動を行っています。私たちの役目はポリオに罹患してしまった患者たちを一生守ることだと思っています。
お話ししたいことはまだまだあります。どこへでも行きます、どこででも話します、どこへでも呼んでください。今のところ私は元気で動けるので、動けるうちはどんどん出かけていって話そうと思っておりますので、是非お声がけください。
有難うございました。
【卓話編集後記】
丸橋様ご自身の幼少期からの体験、活動に対する熱い想い、そして明るいお人柄があふれるお話を聴きながら、例会会場は深い感動に包まれました。また、ロータリーはポリオ撲滅を最優先課題として取り組んでいますが、日本でも未だに解決されていない身近な問題であることを知り、驚きも覚えました。
卓話後の質疑応答では、ポリオの会の小山会長にもご参加いただき、ポリオ撲滅は、単なる病気との闘いにとどまらず、複雑な課題であるという理解も深まり、10月24日の「世界ポリオデー」を前に、とても有意義な卓話となりました。
皆さま初めまして、丸橋と申します。
本日は、卓話の機会を与えていただき本当にうれしく思います。
私は1965年昭島市に生まれ、生後7か月の時にポリオの生ワクチンの定期接種を受けました。約2週間後に高熱が出て、おむつ替えの時に左足がパタンと落ちてしまうことに気づいた母が病院に連れて行き、検査の結果、ワクチンによるポリオと診断され、隔離病棟で2カ月間の入院をすることになりました。
ポリオの生きたウィルスを弱めたものを身体に入れて抗体をつけるのが生ワクチンです。1960年頃に日本ではポリオが大流行し、母親たちがワクチンを海外から緊急輸入するように厚労省に押しかけて要請し、ポリオの流行を収めたという歴史があります。生ワクチンは有効ですが、まれにポリオの症状が出てしまうリスクがあり、それが私のような生ワクのポリオです。一方、病原性をなくした状態の不活化ワクチンというものがあり、これは麻痺を起こすことはありません。しかし、コストが高いこと、医療従事者による注射での接種、注射器の廃棄の問題がデメリットとしてあります。
母子手帳に「生ワク投与」というハンコが押してありました。これが私の運命の日となりました。母が作ったアルバムには、昭和41年5月9日から7月5日まで約2か月間入院したこと、両親にとって一生忘れることができない悲しい時期であったことが書かれていました。自分が子供を持つようになってわかるのですが、やはり親が一番辛かったと思います。
退院後、小児療育病院で補装具をつける指導を受け、リハビリをしながら松葉杖で歩けるまでに回復しました。
小学校入学の時、障害者が通う養護学校から入学通知が届いたのですが、母が教育委員会に何度も乗り込んでお願いして、普通の小学校に通うことが出来ました。
その後結婚し、子供もでき、何ともなく過ごしていたのですが、40歳の時に身体の異変が少しずつ出始めました。家で転倒して右足を骨折しました。左足は麻痺があるため装具をはめていますが、右足はポリオではない普通の足だと思っていました。しかし、右足も力が入りにくくなってよろけて転んだのです。。
その後、インターネットを通じてポリオの会を知り、小山万里子代表と出会い、自分が生ワクチンのポリオという珍しい貴重な存在であることに気づきました。ポリオを分かってくれる先生と出会い、42歳の時にPPS、ポスト・ポリオ症候群だと診断されました。罹患してから30年後、40年後に再度症状が進行することがあるのです。
小山代表から色々と教えていただき、今でも生ワクによる同じ被害が出ていることを知り驚きました。安全な不活化ワクチンがあるのに、なぜ日本ではそちらに切り替えないのかと思いました。そこで、ポリオの会の活動に一生懸命参加するようになり、厚労省にも不活化ワクチンへの切り替え運動で何回も行きました。メディアにもいろいろと出演しました。
私が訴えたいことは、国が指導しているワクチン行政では、なぜ安全なものがあるのに切り替えないのかということです。私のような生ワクによるポリオが珍しい存在ならば、自分が前面に出たら説得力があるのではないかと思い、さまざまな活動を始めました。
例えば、模擬患者として大学の授業に参加したり、理学療法士の学校でポリオのことを伝えるなど、ポリオを知ってもらうための活動をしています。国を動かそうという思いで何度も議員会館に行きました。ユニセフ議員連盟を訪ね、日本にもポリオ患者がいることを伝えています。ワクチンメーカーの社内研修でも話をさせていただいています。厚生労働省が主体となって3都市で開催される「シーズ・ニーズマッチング交流会」にポリオの会のブースを出して、より良い福祉機器を製作してもらうための活動もしています。明日からは福岡で開催される外来小児学会に行ってブースを出します。リハビリテーション科の先生がたくさんいらっしゃる義肢装具学会にも参加しています。
こうした活動が認められ、先日、社会貢献支援財団から「ポリオの会」が表彰を受けました。式典では、財団の会長安倍昭恵夫人と写真を撮らせていただいたり、とても光栄な賞をいただき、良い思い出になりました。
生ワクチンによる健康被害を受けた人たちの写真に小さな女の子が写っています。この子もポリオですが、症状が重くて色々な障害が出ていて、かわいそうな女の子です。
この子が成長して、今私がお話ししたすべてのことを知った時に、なぜもっと早くこの活動を始めて、もっと早く不活化ワクチンに切り替えてくれなかったのかと言われたら、どうしようと思いました。早くに気づいていたらポリオにならずに済んだかもしれない。そんな子供たちが、まだまだいると思います。ですから、私はこの活動を続けて、伝え続けるということを決めました。
ロータリーがポリオ撲滅を目指して進めているEND POLIOの活動は本当に素晴らしく、世界からポリオをなくすことはとても大切だと思って参加しています。今でも世界では生ワクが使われている国があり、生ワク由来の患者が出ているということも聞いています。
私たちが考えるEND POLIOとは、最後のポリオ患者がこの世から消えたとき、亡くなったときだと考えています。その時には私たちはもういないかもしれない。でも私が伝え続けていけば、その先の人たちが伝えていってくれると考えて、ポリオの会の活動を行っています。私たちの役目はポリオに罹患してしまった患者たちを一生守ることだと思っています。
お話ししたいことはまだまだあります。どこへでも行きます、どこででも話します、どこへでも呼んでください。今のところ私は元気で動けるので、動けるうちはどんどん出かけていって話そうと思っておりますので、是非お声がけください。
有難うございました。
【卓話編集後記】
丸橋様ご自身の幼少期からの体験、活動に対する熱い想い、そして明るいお人柄があふれるお話を聴きながら、例会会場は深い感動に包まれました。また、ロータリーはポリオ撲滅を最優先課題として取り組んでいますが、日本でも未だに解決されていない身近な問題であることを知り、驚きも覚えました。
卓話後の質疑応答では、ポリオの会の小山会長にもご参加いただき、ポリオ撲滅は、単なる病気との闘いにとどまらず、複雑な課題であるという理解も深まり、10月24日の「世界ポリオデー」を前に、とても有意義な卓話となりました。
卓話 「車いすからパラリンピック、そして2020年へ」
パラリンピック ライフル射撃 元日本代表選手 田口亜希様
2019年8月8日

 2004年アテネ、2008年北京、2012年ロンドンパラリンピックにライフル射撃競技で出場した田口亜希です。
以前は自分の足で歩き、客船「飛鳥」でパーサーとしてレセプションでの接客や入出港管理など仕事にやりがいを感じながら働いていました。25歳の時、突然身体中に激痛が走り、両足が動かなくなりました。検査の結果、脊髄の中の血管が破裂して中枢神経が傷つき、一生車いす生活だと宣告されました。もう一生働けず、家の中で暮らすのだろう、脊髄の神経をつなぐ手術法が見つかるまで病院のベッドで暮らせばよいと思ったこともありました。
でも、見舞いに来た友人や同僚、上司のキラキラした姿を見て、私も何かしなければと思い直し、車いすでの生活に向けたリハビリに励むようになり、発病から2年半後にバリアフリーの整った会社で仕事に復帰しました。
その一方、同じ病院に入院していた知人に誘われて、趣味としてビームライフル(光線銃)の練習を始めました。実弾の銃は日本の銃刀法の制限がありますが、ビームライフルは銃刀法に関係ありません。そのビームライフルで成績を上げて大会で優勝し続けたところ、コーチに勧められ、所持許可を取って実銃を持つようになりました。
当時は、パラリンピックを目指していたわけではありませんが、色々な大会で好成績を出して、2年後の2004年アテネパラリンピックを意識するようになりました。2年間でランキングを上げてアテネパラリンピック、さらに、その4年後の北京パラリンピックと、2年先、6年先を考えていました。射撃でアテネパラリンピックを意識したときに、いつの間にか、目標を立てている自分に驚きました。射撃を始めて目標ができ、目標のために努力して、前進できました。自分一人の努力だけでなく、支えてくれたコーチや家族、友人、同僚のおかげです。
私の出場種目は、10メートル先の標的を狙うエアライフルと、50メートル先の標的を22口径の火薬銃で撃つライフルでエアライフルは10点圏は0.5ミリの点です。ファイナルに残るためにはメンタルの強さも必要となります。
私の現在の勤務先は日本郵船東京本社で、とても恵まれていると思います。日本では働きたくても働けない障害者がたくさんいます。障害の度合いによりますが、環境さえ整えば普通に働けることを知らない方々がたくさんいます。だからこそ、私たち障害者が、環境が整えば働けることを証明しなければなりません。そのために、私は手を抜かないことを心がけています。障害者には権利と共に義務があります。そして私は、権利や義務よりも自分で出来ることが嬉しく、心地よく感じています。
次にパラリンピックについてお話します。パラリンピックの原点は、英国のストーク・マンデビル病院のルートヴィヒ・グットマン博士が、第二次世界大戦で脊髄を損傷した兵士の治療とリハビリの一環として、また手術よりもスポーツをという理念で、1948年ロンドンオリンピックの年に開催した車いすスポーツ競技大会だとされています。グッドマン博士の「失ったものを数えるな、残されたものを最大限に生かせ」という言葉はパラリンピアンや障害者にとって非常に大切な言葉ですが、この言葉はどなたにもそして様々なシチュエーションで大切な言葉ではないでしょうか。
この大会の最初の競技は、足が不自由でも手で弓を引けるアーチェリーでした。当初は、入院患者の競技大会でしたが、その後毎年開催されて国際大会となり、1960年、オリンピックが開催されたローマで、国際ストーク・マンデビル競技会が行われ、それを現在第1回パラリンピックと呼んでいます。
その4年後、1964年東京オリンピックの後に開催された「第13回国際ストーク・マンデビル車いす競技大会」が、世界で初めて愛称として「パラリンピック」を公式に用い、第2回パラリンピックとなります。
2016年リオデジャネイロ・パラリンピックには159の国・地域・難民選手団、約4300名の選手が参加し、1964年と比べると参加国は7倍、選手は10倍以上となりました。
オリンピックには、Excellence(卓越)、Friendship(友情)、Respect(尊敬)という3つのValue(価値)があり、パラリンピックには、Courage(勇気)、Determination(強い意志)、Inspiration(感動)、Equality(公平)という4つのValue(価値)があります。
東京2020大会には、オリンピック・パラリンピック共通の3つのコンセプト、「全員が自己ベスト」、「多様性と調和」、「未来への継承」があります。
パラリンピックはスポーツ以外にも考えたり、気づかせてくれるものがあります。その中でも多様性と調和につながるのはAccessibilityです。Accessibilityとは、誰もがアクセス可能な快適な世界を作るということです。
WHOの調査では、障害者は世界の全人口の10%、妊婦や怪我をしている人、高齢者を含めると、全人口の20%がAccessibilityを必要としています。こうした人たちが、ご家族や友人にいるかもしれないと思うと、自分のこととして考えてもらえるでしょう。
2020年、それ以降に向けて、東京そして日本ではハード面のバリアフリー化が進みますが、使うのは人です。日本では、障害者用の駐車場やお手洗いを使う健常者が少なくない状況です。これは、悪意があるのではなく、知らないからです。周りに障害者がいない、障害者と共に勉強したり、働いたりする環境ではない、Accessibilityが進んでいないことが問題かと思います。
一方、障害者自身もきちんと意見を言うこと、これ不便だ、これがあると助かる、使いやすかったと伝えることが大切です。昔は言えなかったのかもしれませんが、2020年東京パラリンピック開催を契機に日本でも変わってくるでしょう。
パラリンピックの開会式8月25日まであと383日です。是非、皆様には日本各地で開催されるテストイベント大会と2020年パラリンピックにお越しいただき、選手にエールを送ってください。
2020年パラリンピックは、アスリートや障害者だけでなく、日本国民全員がチームジャパンとして一つになれる機会です。是非、ボランティアや観客として皆様に関わっていただければと思います。
そして、2020年で終わりではありません。1964年のパラリンピックでは障害者の自立や社会参加、社会貢献が考えられるようになりました。2020年東京では、2020年以降のレガシーとして様々なものが残っていくように、そして共生社会の実現に向けて、私たちも意見や思いを伝えていきます。是非皆様にもご協力いただけると嬉しいです。
【卓話編集後記】
2020年東京オリンピック・パラリンピック大会招致では、IOC委員会の前でプレゼンターを務め、現在は組織委員会のアスリート委員、聖火リレー公式アンバサダーなど数多くの役職で活躍中の田口亜希さん。25歳の時に車いす生活になっても、仕事に復帰し、パラリンピック出場という目標を持ったというお話に、勇気と元気をいただきました。来年のパラリンピック開催を待つことなく、誰もが公平にアクセスできる共生社会の実現に近づけるよう、今日からできることに取り組もうという気づきも与えていただいた卓話でした。
2004年アテネ、2008年北京、2012年ロンドンパラリンピックにライフル射撃競技で出場した田口亜希です。
以前は自分の足で歩き、客船「飛鳥」でパーサーとしてレセプションでの接客や入出港管理など仕事にやりがいを感じながら働いていました。25歳の時、突然身体中に激痛が走り、両足が動かなくなりました。検査の結果、脊髄の中の血管が破裂して中枢神経が傷つき、一生車いす生活だと宣告されました。もう一生働けず、家の中で暮らすのだろう、脊髄の神経をつなぐ手術法が見つかるまで病院のベッドで暮らせばよいと思ったこともありました。
でも、見舞いに来た友人や同僚、上司のキラキラした姿を見て、私も何かしなければと思い直し、車いすでの生活に向けたリハビリに励むようになり、発病から2年半後にバリアフリーの整った会社で仕事に復帰しました。
その一方、同じ病院に入院していた知人に誘われて、趣味としてビームライフル(光線銃)の練習を始めました。実弾の銃は日本の銃刀法の制限がありますが、ビームライフルは銃刀法に関係ありません。そのビームライフルで成績を上げて大会で優勝し続けたところ、コーチに勧められ、所持許可を取って実銃を持つようになりました。
当時は、パラリンピックを目指していたわけではありませんが、色々な大会で好成績を出して、2年後の2004年アテネパラリンピックを意識するようになりました。2年間でランキングを上げてアテネパラリンピック、さらに、その4年後の北京パラリンピックと、2年先、6年先を考えていました。射撃でアテネパラリンピックを意識したときに、いつの間にか、目標を立てている自分に驚きました。射撃を始めて目標ができ、目標のために努力して、前進できました。自分一人の努力だけでなく、支えてくれたコーチや家族、友人、同僚のおかげです。
私の出場種目は、10メートル先の標的を狙うエアライフルと、50メートル先の標的を22口径の火薬銃で撃つライフルでエアライフルは10点圏は0.5ミリの点です。ファイナルに残るためにはメンタルの強さも必要となります。
私の現在の勤務先は日本郵船東京本社で、とても恵まれていると思います。日本では働きたくても働けない障害者がたくさんいます。障害の度合いによりますが、環境さえ整えば普通に働けることを知らない方々がたくさんいます。だからこそ、私たち障害者が、環境が整えば働けることを証明しなければなりません。そのために、私は手を抜かないことを心がけています。障害者には権利と共に義務があります。そして私は、権利や義務よりも自分で出来ることが嬉しく、心地よく感じています。
次にパラリンピックについてお話します。パラリンピックの原点は、英国のストーク・マンデビル病院のルートヴィヒ・グットマン博士が、第二次世界大戦で脊髄を損傷した兵士の治療とリハビリの一環として、また手術よりもスポーツをという理念で、1948年ロンドンオリンピックの年に開催した車いすスポーツ競技大会だとされています。グッドマン博士の「失ったものを数えるな、残されたものを最大限に生かせ」という言葉はパラリンピアンや障害者にとって非常に大切な言葉ですが、この言葉はどなたにもそして様々なシチュエーションで大切な言葉ではないでしょうか。
この大会の最初の競技は、足が不自由でも手で弓を引けるアーチェリーでした。当初は、入院患者の競技大会でしたが、その後毎年開催されて国際大会となり、1960年、オリンピックが開催されたローマで、国際ストーク・マンデビル競技会が行われ、それを現在第1回パラリンピックと呼んでいます。
その4年後、1964年東京オリンピックの後に開催された「第13回国際ストーク・マンデビル車いす競技大会」が、世界で初めて愛称として「パラリンピック」を公式に用い、第2回パラリンピックとなります。
2016年リオデジャネイロ・パラリンピックには159の国・地域・難民選手団、約4300名の選手が参加し、1964年と比べると参加国は7倍、選手は10倍以上となりました。
オリンピックには、Excellence(卓越)、Friendship(友情)、Respect(尊敬)という3つのValue(価値)があり、パラリンピックには、Courage(勇気)、Determination(強い意志)、Inspiration(感動)、Equality(公平)という4つのValue(価値)があります。
東京2020大会には、オリンピック・パラリンピック共通の3つのコンセプト、「全員が自己ベスト」、「多様性と調和」、「未来への継承」があります。
パラリンピックはスポーツ以外にも考えたり、気づかせてくれるものがあります。その中でも多様性と調和につながるのはAccessibilityです。Accessibilityとは、誰もがアクセス可能な快適な世界を作るということです。
WHOの調査では、障害者は世界の全人口の10%、妊婦や怪我をしている人、高齢者を含めると、全人口の20%がAccessibilityを必要としています。こうした人たちが、ご家族や友人にいるかもしれないと思うと、自分のこととして考えてもらえるでしょう。
2020年、それ以降に向けて、東京そして日本ではハード面のバリアフリー化が進みますが、使うのは人です。日本では、障害者用の駐車場やお手洗いを使う健常者が少なくない状況です。これは、悪意があるのではなく、知らないからです。周りに障害者がいない、障害者と共に勉強したり、働いたりする環境ではない、Accessibilityが進んでいないことが問題かと思います。
一方、障害者自身もきちんと意見を言うこと、これ不便だ、これがあると助かる、使いやすかったと伝えることが大切です。昔は言えなかったのかもしれませんが、2020年東京パラリンピック開催を契機に日本でも変わってくるでしょう。
パラリンピックの開会式8月25日まであと383日です。是非、皆様には日本各地で開催されるテストイベント大会と2020年パラリンピックにお越しいただき、選手にエールを送ってください。
2020年パラリンピックは、アスリートや障害者だけでなく、日本国民全員がチームジャパンとして一つになれる機会です。是非、ボランティアや観客として皆様に関わっていただければと思います。
そして、2020年で終わりではありません。1964年のパラリンピックでは障害者の自立や社会参加、社会貢献が考えられるようになりました。2020年東京では、2020年以降のレガシーとして様々なものが残っていくように、そして共生社会の実現に向けて、私たちも意見や思いを伝えていきます。是非皆様にもご協力いただけると嬉しいです。
【卓話編集後記】
2020年東京オリンピック・パラリンピック大会招致では、IOC委員会の前でプレゼンターを務め、現在は組織委員会のアスリート委員、聖火リレー公式アンバサダーなど数多くの役職で活躍中の田口亜希さん。25歳の時に車いす生活になっても、仕事に復帰し、パラリンピック出場という目標を持ったというお話に、勇気と元気をいただきました。来年のパラリンピック開催を待つことなく、誰もが公平にアクセスできる共生社会の実現に近づけるよう、今日からできることに取り組もうという気づきも与えていただいた卓話でした。
卓話 「世界で一つのオーケストラ ~オーケストラ・アジアのお話~」
東京ユニバーサルフィルハーモニー管弦楽団専任指揮者 稲田康様
2019年7月25日

 本日は指揮とオーケストラ・アジアという世界にひとつしかないオーケストラの話をします。
コンダクターは何をしているのかというと、おそらく音楽に合わせて踊っている、私も時々踊っています。基本的には、踊りで音楽を作って発信しているのです。音楽を誘い込むと言うか、英語のinvite 招き入れる、それが指揮の極意です。無理やり音を出すのではなくて、音を聞きながら誘い込んでいます。
指揮者の勉強は楽器演奏者の勉強とほぼ変わりません。ひとつ違うのは、作曲、和声学とか音を積み重ねる学問を勉強します。和音をどう繋げるかという学問と、バッハが確立した対位法、ベートーベンが完成させたソナタ形式など、時代による作曲の変遷などを勉強します。
お手元にある「運命」の譜面は、上からフルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン、トランペット、打楽器、第1バイオリン、第2バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスという配列になっています。指揮者はこのスコアを頭に叩き込みます。どこに何が載っているか、どういう音が書いてあるかを、時間をかけて覚えます。譜面を見て、ピアノで弾いて、歌って、叩いて、時間をかけて全部覚えこみます。普通のシンフォニーは、1曲35分くらいですが、最初はテンポ通りには譜面は見られません。ちょっと見ては考え、ちょっと見ては覚え、ということを100回も、何日もかけて繰り返します。スコアを全部覚えて、初めてオーケストラの前に立ち、この音はこうしよう、その音は素晴らしいというように、曲をinvite引き込んでいきます。そして何回も演奏し、譜面を見ていると、内容の捉え方、感じ方が変わり、譜面の中から発酵してくるような、新しい発想が浮かんできます。
コンピューターでも音を出せます。譜面を打ち込んで、楽器を選択すると、オーケストラの音が出るのですが、そこには何の感情もありません。人間は呼吸をする。その呼吸と一緒に音楽が流れていきます。歌も、吹奏楽、木管楽器、金管楽器の人たちも息を吸わないと次の音を出せません。ですから、指揮者はどういう息をさせるかが勝負です。指揮棒を速く上げると早い息になり、ゆっくり上げてゆっくり降ろすと、フーっとした音楽を出すことができる。それが、指揮者の動いている意味なのです。たくさん勉強をして、作曲家の背景、どういう時代に生きていたか、こんなテンポだということを調べて、オーケストラの前に立ちます。
「アンダンテ」というスピード記号は、「歩く速さで」という意味ですが、16世紀や17世紀と比べたら現代の歩く速さの方が速いでしょう。ですから、「アンダンテ」という記号も今の時代に合っているかを考えなければなりません。時代とともに、譜面は同じでもクラシック音楽も変わっていく、それが生きた音楽ということです。そのようにして、この指揮者は良い棒を振る、すごい音楽を作るということになります。
ベートーベンの時代には指揮法は確立されていませんでしたが、19世紀の後半に指揮法の基礎が確立され専門職の指揮者が活躍し始めました。日本では齊藤秀雄の齊藤メソードという指揮法があり、私も18才の頃に齊藤メソードを始めました。
ベートーベンの時代の音楽は35人くらいで演奏されていましたが、今は、60人、70人、あるいは100人という大きなオーケストラで演奏します。その大勢の人たちをどのようにひとつの音に呼び込んでいくか、指揮者が勉強したことをオーケストラにどう伝えて、音として出してもらうか、それが一番難しいことです。棒一つを振った時に同じ音を出せるかどうか、どういう発想で、オーケストラにどんな話をして、どんな振り方をするか、それはもう「人間力」で引っ張っていくしかありません。演奏後にブラボー!となるのを狙うのですが、色々なテクニック、技、マジック、色々な手を使うわけです。
「運命」の譜面を見ていただくと分かりますが、最初の音は休符です。八分休符がついています。それがなければ、最初から、タ・タ・タ・ターン、と振ればよいのですが、そうではなくて、ン・タ・タ・タ・ターンなのです。それをどう合わせるのかはとても難しいことです。
リハーサルの時に研究発表をしてしまう指揮者がたくさんいます。 指揮者はものすごく勉強するので、勉強したことをしゃべりたくて仕方なくなる。そうすると、肝心の練習が半分くらいになって、本番で失敗してしまいます。どういう言葉を選んで、何を言えば一番相手に伝わるかという、言葉のセレクトをしなければなりません。
ベートーベンの音「運命」を聴いてみましょう(CD演奏)。弦楽器の音しか聞こえませんが、譜面を見るとクラリネットの音があるのがわかります。こういうのは、譜面を見ないと絶対にわかりませんし、なぜクラリネットが入るのかを考えなければいけない。弦楽器だけでは、どうしても出発点の音が甘くなります。そこにクラリネットが入ると、クリアになり、輪郭がはっきりするので、そのために入れてあるのです。そういうことを発見するとすごく嬉しいですね。
最後に、世界で一つのオーケストラ、オーケストラ・アジアについてお話します。日本の伝統楽器の尺八、お琴、琵琶、三味線に、韓国の伝統楽器、中国の伝統楽器、合わせて72人の編成です。第1二胡、第2二胡、管楽器、太鼓と30種類以上の伝統楽器の編成ですが、把握するのはとても大変なことです。また、マッチングがとても難しい。どの楽器とどの楽器を合わせたらどういう効果が出るかというのは、世界で初めてなので、ものすごく苦労し、難しいことです。
オーケストラ・アジアは、20年ほど前は、年に1回、3カ国を1ヶ月程かけて回っていましたが、最近は情勢が悪く、集まることができません。ただ、オーケストラ・アジアの指揮を通じて経験したことは、やはり本気で向き合わないといけない、ということです。「本気」というのが一番大切なことで、どういう方法で相手に伝わるかはわかりませんが、中途半端では絶対に負けますから、本気で戦っていかないと、音も変わらないし、言うことも聞いてくれません。 あいつは本気だと、言わさなければなりません。
オーケストラ・アジアの音をお聞きください(CD演奏)。農耕民族の音楽です。ベートーベンの「運命」などは騎馬民族の音楽なので、私たちが聞く時はどこか緊張しています。でも、農耕の音楽では、ゆったりできます。この音楽をもっと世界に広げたいと思っています。
もう少しお話したいのですが、時間が来てしまいました。有難うございました。
【卓話編集後記】
稲田様は、2016年ロータリー国際大会がソウルで開催され、2750地区ガバナーナイトに於いて韓国の国楽管弦楽団(通常、国賓来訪時などの公式行事のみで演奏する韓国で最も権威ある楽団)の演奏、舞踏などをプロデュースされました。また、お嬢様がロータリーの青少年交換留学生としてアメリカに留学されるなど、ロータリーとは深いつながりのある方です。
卓話の締めくくりとして、ロータリーソング「四つのテスト」で、ソングリーダーに指揮の指導をしてくださり、例会会場は大いに盛り上がりました。
本日は指揮とオーケストラ・アジアという世界にひとつしかないオーケストラの話をします。
コンダクターは何をしているのかというと、おそらく音楽に合わせて踊っている、私も時々踊っています。基本的には、踊りで音楽を作って発信しているのです。音楽を誘い込むと言うか、英語のinvite 招き入れる、それが指揮の極意です。無理やり音を出すのではなくて、音を聞きながら誘い込んでいます。
指揮者の勉強は楽器演奏者の勉強とほぼ変わりません。ひとつ違うのは、作曲、和声学とか音を積み重ねる学問を勉強します。和音をどう繋げるかという学問と、バッハが確立した対位法、ベートーベンが完成させたソナタ形式など、時代による作曲の変遷などを勉強します。
お手元にある「運命」の譜面は、上からフルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン、トランペット、打楽器、第1バイオリン、第2バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスという配列になっています。指揮者はこのスコアを頭に叩き込みます。どこに何が載っているか、どういう音が書いてあるかを、時間をかけて覚えます。譜面を見て、ピアノで弾いて、歌って、叩いて、時間をかけて全部覚えこみます。普通のシンフォニーは、1曲35分くらいですが、最初はテンポ通りには譜面は見られません。ちょっと見ては考え、ちょっと見ては覚え、ということを100回も、何日もかけて繰り返します。スコアを全部覚えて、初めてオーケストラの前に立ち、この音はこうしよう、その音は素晴らしいというように、曲をinvite引き込んでいきます。そして何回も演奏し、譜面を見ていると、内容の捉え方、感じ方が変わり、譜面の中から発酵してくるような、新しい発想が浮かんできます。
コンピューターでも音を出せます。譜面を打ち込んで、楽器を選択すると、オーケストラの音が出るのですが、そこには何の感情もありません。人間は呼吸をする。その呼吸と一緒に音楽が流れていきます。歌も、吹奏楽、木管楽器、金管楽器の人たちも息を吸わないと次の音を出せません。ですから、指揮者はどういう息をさせるかが勝負です。指揮棒を速く上げると早い息になり、ゆっくり上げてゆっくり降ろすと、フーっとした音楽を出すことができる。それが、指揮者の動いている意味なのです。たくさん勉強をして、作曲家の背景、どういう時代に生きていたか、こんなテンポだということを調べて、オーケストラの前に立ちます。
「アンダンテ」というスピード記号は、「歩く速さで」という意味ですが、16世紀や17世紀と比べたら現代の歩く速さの方が速いでしょう。ですから、「アンダンテ」という記号も今の時代に合っているかを考えなければなりません。時代とともに、譜面は同じでもクラシック音楽も変わっていく、それが生きた音楽ということです。そのようにして、この指揮者は良い棒を振る、すごい音楽を作るということになります。
ベートーベンの時代には指揮法は確立されていませんでしたが、19世紀の後半に指揮法の基礎が確立され専門職の指揮者が活躍し始めました。日本では齊藤秀雄の齊藤メソードという指揮法があり、私も18才の頃に齊藤メソードを始めました。
ベートーベンの時代の音楽は35人くらいで演奏されていましたが、今は、60人、70人、あるいは100人という大きなオーケストラで演奏します。その大勢の人たちをどのようにひとつの音に呼び込んでいくか、指揮者が勉強したことをオーケストラにどう伝えて、音として出してもらうか、それが一番難しいことです。棒一つを振った時に同じ音を出せるかどうか、どういう発想で、オーケストラにどんな話をして、どんな振り方をするか、それはもう「人間力」で引っ張っていくしかありません。演奏後にブラボー!となるのを狙うのですが、色々なテクニック、技、マジック、色々な手を使うわけです。
「運命」の譜面を見ていただくと分かりますが、最初の音は休符です。八分休符がついています。それがなければ、最初から、タ・タ・タ・ターン、と振ればよいのですが、そうではなくて、ン・タ・タ・タ・ターンなのです。それをどう合わせるのかはとても難しいことです。
リハーサルの時に研究発表をしてしまう指揮者がたくさんいます。 指揮者はものすごく勉強するので、勉強したことをしゃべりたくて仕方なくなる。そうすると、肝心の練習が半分くらいになって、本番で失敗してしまいます。どういう言葉を選んで、何を言えば一番相手に伝わるかという、言葉のセレクトをしなければなりません。
ベートーベンの音「運命」を聴いてみましょう(CD演奏)。弦楽器の音しか聞こえませんが、譜面を見るとクラリネットの音があるのがわかります。こういうのは、譜面を見ないと絶対にわかりませんし、なぜクラリネットが入るのかを考えなければいけない。弦楽器だけでは、どうしても出発点の音が甘くなります。そこにクラリネットが入ると、クリアになり、輪郭がはっきりするので、そのために入れてあるのです。そういうことを発見するとすごく嬉しいですね。
最後に、世界で一つのオーケストラ、オーケストラ・アジアについてお話します。日本の伝統楽器の尺八、お琴、琵琶、三味線に、韓国の伝統楽器、中国の伝統楽器、合わせて72人の編成です。第1二胡、第2二胡、管楽器、太鼓と30種類以上の伝統楽器の編成ですが、把握するのはとても大変なことです。また、マッチングがとても難しい。どの楽器とどの楽器を合わせたらどういう効果が出るかというのは、世界で初めてなので、ものすごく苦労し、難しいことです。
オーケストラ・アジアは、20年ほど前は、年に1回、3カ国を1ヶ月程かけて回っていましたが、最近は情勢が悪く、集まることができません。ただ、オーケストラ・アジアの指揮を通じて経験したことは、やはり本気で向き合わないといけない、ということです。「本気」というのが一番大切なことで、どういう方法で相手に伝わるかはわかりませんが、中途半端では絶対に負けますから、本気で戦っていかないと、音も変わらないし、言うことも聞いてくれません。 あいつは本気だと、言わさなければなりません。
オーケストラ・アジアの音をお聞きください(CD演奏)。農耕民族の音楽です。ベートーベンの「運命」などは騎馬民族の音楽なので、私たちが聞く時はどこか緊張しています。でも、農耕の音楽では、ゆったりできます。この音楽をもっと世界に広げたいと思っています。
もう少しお話したいのですが、時間が来てしまいました。有難うございました。
【卓話編集後記】
稲田様は、2016年ロータリー国際大会がソウルで開催され、2750地区ガバナーナイトに於いて韓国の国楽管弦楽団(通常、国賓来訪時などの公式行事のみで演奏する韓国で最も権威ある楽団)の演奏、舞踏などをプロデュースされました。また、お嬢様がロータリーの青少年交換留学生としてアメリカに留学されるなど、ロータリーとは深いつながりのある方です。
卓話の締めくくりとして、ロータリーソング「四つのテスト」で、ソングリーダーに指揮の指導をしてくださり、例会会場は大いに盛り上がりました。